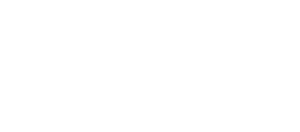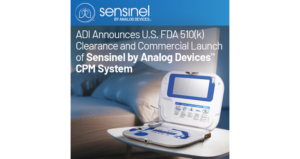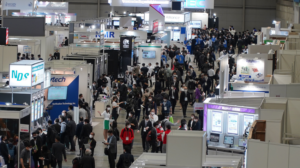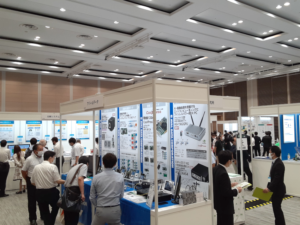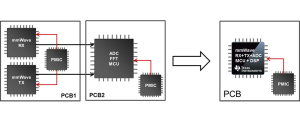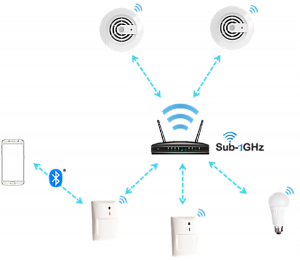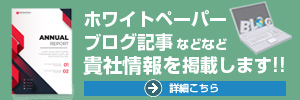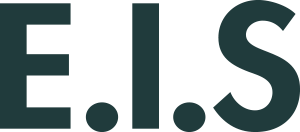横田英史の読書コーナー
コロナ対策の政策評価〜日本は合理的に対応したのか〜
岩本康志、慶應義塾大学出版会
2025.8.16 6:49 am
新型コロナ対策として打ち出された「接触8割削減政策」が、Evidence-Based Policy Making(エビデンスに基づく政策立案)として妥当だったかを経済学者が検証した書。接触を8割削減しなくても、新規感染者数を目標通りに抑制できた可能性が高いとする。新型コロナ蔓延時にポンコツぶりを発揮した政策や行政機関は多いが、同じ過ちを次のパンデミックに繰り返さないためには検証が欠かせない。本書はシミュレーションに基づいたと言われた「接触8割削減」に的を絞り、科学的根拠があったのかを明らかにする。喉元過ぎても熱さを忘れてはいけない政策過程の問題点を的確に指摘しており、お薦めの1冊である。
筆者が問題視するのは、①科学的根拠に基づく対策が選択されたのか、②経済学の視点から「対策の効果と費用」が考慮されたのか、の2点である。
①については、疫学分野において数理モデル研究者の層が薄く、検証が不十分だったと指摘する。驚くのは、公表されたシミュレーションの説明や結果に多くの瑕疵があったことだ。政策担当者に示された助言で「新規感染者」と「感染者」が取り違えられていたり、グラフが歪んでいたり、誤りの数々に唖然とさせられる。
②については、医学以外の専門的知見が政策に反映しにくい意思決定上の歪みを指摘する。例えば経済学的知見を取り入れ、社会経済活動とのバランスを考慮すべきだと訴える。新型コロナ対策は効果に見合わない巨費を投じた。「費用度外視で対策をすることが科学的とは言えない」と断言する。
オミクロン以降にとられた新型コロナ対策は、「公衆衛生的児童虐待」だったという指摘は興味深い。高齢者の命を救うために、若い人の日常を奪うことになった。新型コロナが性質を変えているにもかかわらず、政策が変化についていけなかった。手段が目的化して、本来の目的を忘れ同じ政策を漫然と続けた。既得権が生まれ、政策の変更を阻む抵抗勢力とななった。高齢者の利益のために、若者が負担を負う構造ができあがったと断じる。
書籍情報
コロナ対策の政策評価〜日本は合理的に対応したのか〜
岩本康志、慶應義塾大学出版会、p.280、¥3300