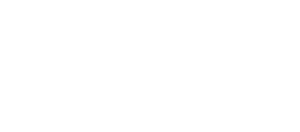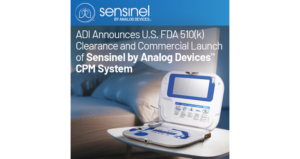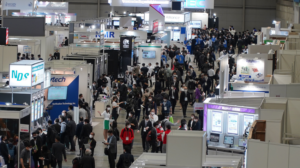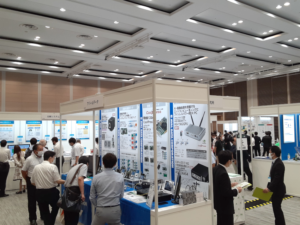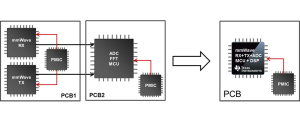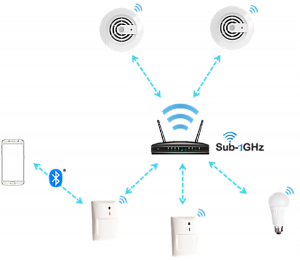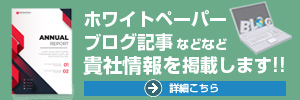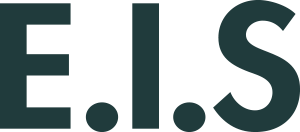横田英史の読書コーナー
修理する権利〜使いつづける自由へ〜
アーロン・パーザナウスキー、西村伸泰・訳、青土社
2025.7.31 8:22 am
スマホやパソコン、医療機器、家電製品を修理しながら使い続けられない現状を問題視し、その原因を分析するとともに在るべき姿を探った書。法律や社会的規範、市場など多角的な視点から問題点を明らかにする。また保証期間を過ぎると急激に劣化したり、壊れやすくなるように設計する「計画的陳腐化」も俎上に上げる。
こうしたなか、使用済みの製品を修理する「リマニュファクチャリング」は新たな潮流になっている。筆者が厳しい視線を送る米アップルも、こうした状況に対応する姿勢を見せる。さらにEUが2024年1月に「修理する権利」を法制化したり、ニューヨーク州が23年2月に「Digital Fair Repair Act」を制定するなど、法的規制の動きも着実に広がっている。本書は時宜にかなった内容であり、今読むべき本の一つだろう。著者は法律の専門家で少々理屈っぽいが、決して読みづらくはない。400ページを超える大著だが、強くお薦めしたい。
評者にとって、実は“身につまされる”内容が満載である。つい先日のことである。バリバリ現役で活躍していたアップル製ノートパソコン「MacBook Pro」が文鎮化した。しかし2016年製で、すでにサポート対象外(アップルではビンテージと呼ぶ)。アップルの担当者は在庫部品を探してくれたが、結局のところ修理は不可能だった。結局この原稿は、バッテリーやHDDを自分で取り替えて使い続けている2009年製MacBook Pro(通常のプラスネジだけで簡単に交換可能)で書いている。ユーザーが修理する(部品を交換する)権利の重要さを痛感している今日このごろである。
本書が問題視するのは、短い保証期間や高額な修理費用、交換のできない部品などである。こうしたメーカーが企てる修理を妨げる取り組みを、著作権や特許、商標といった法体系が巧妙に支えているという。筆者は、まず修理の歴史を振り返る。修理をめぐる闘いが法廷や議会、行政機関で繰り広げられてきたことを示し、その経緯を明らかにする。「修理する権利」を取り巻く不透明で複雑な法的状況を解説し、その権利を取り戻す方策を提示する。
書籍情報
修理する権利〜使いつづける自由へ〜
アーロン・パーザナウスキー、西村伸泰・訳、青土社、p.464、¥4840