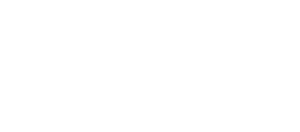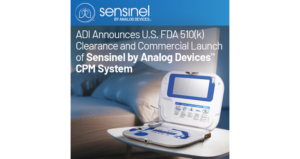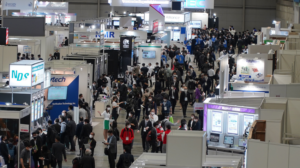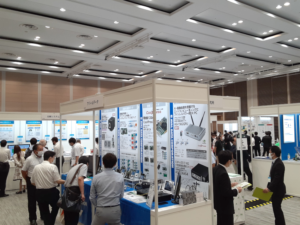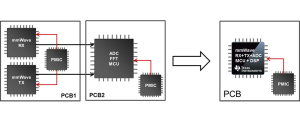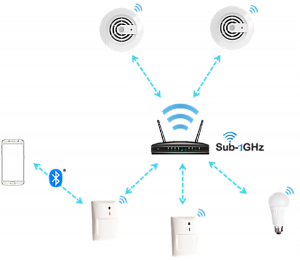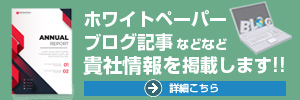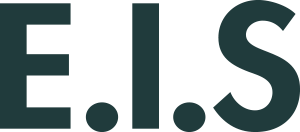横田英史の読書コーナー
書くことのメディア史〜AIは人間の言語能力に何をもたらすのか〜
ナオミ・S・バロン、古屋美登里・訳、山口真果・訳、亜紀書房
2025.7.16 8:18 am
AI(生成AI)をはじめとする情報技術が、人間の言語能力や言語活動に与える影響について論じた書。社会や文化、生活、学校教育など多角的な切り口で考察する。筆者が焦点を当てる一つが「書くこと」である。手で書くことが読み書き能力の向上や学習において有益であり、知能や精神に好ましい影響を与えることを忘れてはならないと説く。AIについては、人間の知能に対抗できる仕組みの構築ではなく、人間の取り組みを拡張することが肝要だとする。
本書はまず、文字を「書くこと」と「書き直す」ことの重要さを歴史を踏まえて考察する。同時に、「AIが書く」ことによって、人間の役割が変わりつつあることを明らかにする。次に、AIによる自然言語処理の歴史を振り返り、歴史の中でAIを位置づける。エニグマ暗号機やチューリング、ダートマス会議、機械学習、ニューラルネットワーク、トランスフォーマーにまで言及して持論を展開する。
さらに事例を挙げて、人間が文章を書く環境をAIが侵食しつつある現状を明らかにする。ジャーナリスト、法律家、翻訳家への影響に言及する。最後に述べるのは、スペルチェックや入力予測、校正、文法チェックなど、コンピュータと人間の当たり前になっている現状である。今後はAIエージェントの登場で、人間とAIのチームワークが進展し、「ヒューマン・イン・ザループ」が重要になるとする。
480ページと大著だが、明快な書き口と翻訳の良さで長さを感じさせない。チューリングやダートマス会議に遡って論じるなど、米国の書籍らしくカバー範囲が広く頭の整理に役に立つ。
書籍情報
書くことのメディア史〜AIは人間の言語能力に何をもたらすのか〜
ナオミ・S・バロン、古屋美登里・訳、山口真果・訳、亜紀書房、p.536、¥3960

横田 英史 (yokota@et-lab.biz)
1956年大阪生まれ。1980年京都大学工学部電気工学科卒。1982年京都大学工学研究科修了。
川崎重工業技術開発本部でのエンジニア経験を経て、1986年日経マグロウヒル(現日経BP社)に入社。日経エレクトロニクス記者、同副編集長、BizIT(現ITPro)編集長を経て、2001年11月日経コンピュータ編集長に就任。2003年3月発行人を兼務。
2004年11月、日経バイト発行人兼編集長。その後、日経BP社執行役員を経て、 2013年1月、日経BPコンサルティング取締役、2016年日経BPソリューションズ代表取締役に就任。2018年3月退任。
2018年4月から日経BP社に戻り、 日経BP総合研究所 グリーンテックラボ 主席研究員、2018年10月退社。2018年11月ETラボ代表、2019年6月一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)理事、現在に至る。
記者時代の専門分野は、コンピュータ・アーキテクチャ、コンピュータ・ハードウエア、OS、ハードディスク装置、組込み制御、知的財産権、環境問題など。
*本書評の内容は横田個人の意見であり、所属する企業の見解とは関係がありません。
新着記事
-

脳・心・人工知能〈増補版〉〜数理で脳を解き明かす〜
2025.9.19 7:01 am
-

となりの史学〜戦前の日本と世界〜
2025.9.13 7:00 am
-

勝負師 孫正義の冒険(下)
2025.9.8 6:59 am
-

日本終戦史1944-1945〜和平工作から昭和天皇の「聖断」まで〜
2025.9.5 6:56 am
-

勝負師 孫正義の冒険(上)
2025.8.31 6:55 am
-

琉球処分-「沖縄問題」の原点
2025.8.26 6:53 am
-

国家にモラルはあるか?〜戦後アメリカ大統領の外交政策を採点する〜
2025.8.23 6:51 am
-

コロナ対策の政策評価〜日本は合理的に対応したのか〜
2025.8.16 6:49 am
SOLUTION
REPORT
横田英史の 読書コーナー
お薦めセミナー・イベント情報
-
9月3日~5日 幕張メッセ
JASIS 2025
-
9月10日~12日 東京ビッグサイト
センサエキスポジャパン 2025
-
9月17日~18日 大阪・関西万博EXPOメッセ
Global Startup EXPO 2025
-
9月17日~19日 幕張メッセ
オートモーティブ ワールド[秋]
-
9月17日~19日 幕張メッセ
ネプコン ジャパン [秋]
-
9月17日~19日 幕張メッセ
SMART ENERGY WEEK 秋
-
10月1日~3日 インテックス大阪
ものづくり ワールド [大阪]
-
10月8日~9日 マリンメッセ福岡
[九州]半導体産業展
-
10月14日~17日 幕張メッセ
CEATEC 2025
-
10月23日~24日 パシフィコ横浜
ロボットワールド
-
10月29日~31日 ポートメッセなごや
[名古屋] オートモーティブ ワールド
-
10月29日~31日 ポートメッセなごや
[名古屋] ネプコン ジャパン
-
10月29日~31日 ポートメッセなごや
[名古屋] ロボデックス
-
11月19日~21日 パシフィコ横浜
EdgeTech+ 2025
-
12月3日~5日 マリンメッセ福岡
ものづくり ワールド福岡
-
12月17日~19日 東京ビッグサイト
SEMICON JAPAN
ET/IoT Technology Show
Back Number
Pick Up Site
運営

株式会社ピーアンドピービューロゥ
〒102-0074
東京都千代田区九段南4-7-22
メゾン・ド・シャルー3F
TEL. 03-3261-8981
FAX. 03-3261-8983