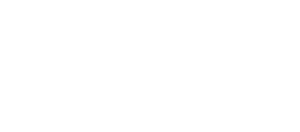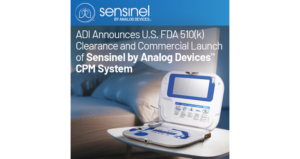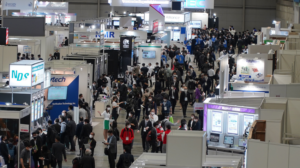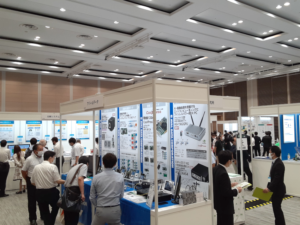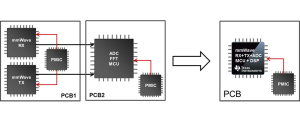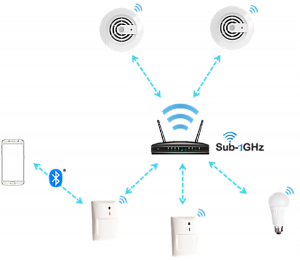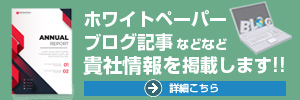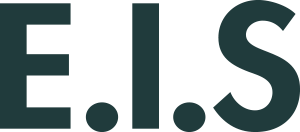横田英史の読書コーナー
コロナ禍と出会い直す〜不要不急の人類学ノート〜
磯野真穂、柏書房
2024.10.17 11:54 am
新型コロナ禍における日本社会や日本人の行動パターンを人類学の視点から分析・検証した書。東京工業大学教授で人類学者が、「和をもって極端をなす」や「走り出したら止まらない」といった日本社会の思考の癖を明らかにする。パニックを沈静化するためにとられた極端な対策が、科学的な根拠なしにダラダラと続いた。真剣に現状を問い直す機構が日本社会に備わっていないと批判する。具体的な事例を挙げた分析は説得力がある。
筆者はコロナ禍に出会い直さなければならない理由について、「同じ社会を未来に残したくないから」と語る。コロナ禍は壮大な社会実験であり、パンデミックに対する日本のヒト・カネ・モノや社会システム(医療システム、行政システムなど)の動作検証になった。ポンコツぶりを露呈した社会システムの詳細な検証は、今後の社会を設計する上で不可欠な情報となる。次のパンデミックのときに、日本社会が同じ間違いを繰り返さないために必要な情報を本書は含んでおり、お薦めである。
筆者は、「県をまたぐ移動の自粛」や「感染者が増えるたびに原因を“気の緩み”に求める精神論」などを取り上げ、コロナ禍における社会現象を分析する。福井県や介護施設の事例は興味深い。自治体や報道機関、はては専門家までが科学的でない恣意的な情報発信によって国民を操作し、意図した方向に誘導したと断じる。政治や行政が気の緩みに原因を求める姿勢は、責任を国民に押しつけ、本来行うべき社会体制や医療体制の変革をなおざりにした。
本書を読んで思い出すのは、日本軍の敗北を組織論的に分析し「失敗の本質」である。失敗の本質で指摘された日本軍の問題点が、相似形で日本社会でも露呈した格好である。
書籍情報
コロナ禍と出会い直す〜不要不急の人類学ノート〜
磯野真穂、柏書房、p.232、¥1980

横田 英史 (yokota@et-lab.biz)
1956年大阪生まれ。1980年京都大学工学部電気工学科卒。1982年京都大学工学研究科修了。
川崎重工業技術開発本部でのエンジニア経験を経て、1986年日経マグロウヒル(現日経BP社)に入社。日経エレクトロニクス記者、同副編集長、BizIT(現ITPro)編集長を経て、2001年11月日経コンピュータ編集長に就任。2003年3月発行人を兼務。
2004年11月、日経バイト発行人兼編集長。その後、日経BP社執行役員を経て、 2013年1月、日経BPコンサルティング取締役、2016年日経BPソリューションズ代表取締役に就任。2018年3月退任。
2018年4月から日経BP社に戻り、 日経BP総合研究所 グリーンテックラボ 主席研究員、2018年10月退社。2018年11月ETラボ代表、2019年6月一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)理事、現在に至る。
記者時代の専門分野は、コンピュータ・アーキテクチャ、コンピュータ・ハードウエア、OS、ハードディスク装置、組込み制御、知的財産権、環境問題など。
*本書評の内容は横田個人の意見であり、所属する企業の見解とは関係がありません。
新着記事
-

The Nvidia Way エヌビディアの流儀
2025.5.22 12:24 pm
-

日本史 敗者の条件
2025.5.12 12:22 pm
-

続・日本軍兵士〜帝国陸海軍の現実〜
2025.5.8 12:21 pm
-

シンギュラリティはより近く〜人類がAIと融合するとき〜
2025.5.3 12:19 pm
-

世界秩序が変わるとき〜新自由主義からのゲームチェンジ〜
2025.4.30 12:18 pm
-

移民は世界をどう変えてきたか〜文化移植の経済学〜
2025.4.26 12:16 pm
-

論点・西洋史学
2025.4.22 12:15 pm
-

日本軍兵士〜アジア・太平洋戦争の現実〜
2025.4.17 12:12 pm
SOLUTION
REPORT
横田英史の 読書コーナー
お薦めセミナー・イベント情報
-
2月19日~21日 東京ビッグサイト
スマートエネルギーWEEK 春
-
3月5日 ウインクあいち
Security Days 名古屋
-
3月11日~13日 柘植大学 文京キャンパス
エレクトロニクス実装学会春季講演大会
-
3月11日~14日 JPタワー
Security Days 東京
-
3月13日~15日 立命館大学 大阪いばらきキャンパス
情報処理学会 第87回全国大会
-
3月19日 グランフロント大阪
Security Days 大阪
-
4月9日~11日 ポートメッセなごや
ものづくりワールド名古屋
-
4月9日~11日 東京ビッグサイト
ジャパンライフサイエンスウィーク2025
-
4月15日~17日 東京ビッグサイト
NexTech Week【春】
-
4月23日~25日 東京ビッグサイト
Japan IT Week
ET/IoT Technology Show
Back Number
Pick Up Site
運営

株式会社ピーアンドピービューロゥ
〒102-0074
東京都千代田区九段南4-7-22
メゾン・ド・シャルー3F
TEL. 03-3261-8981
FAX. 03-3261-8983