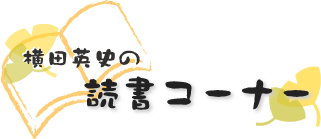|
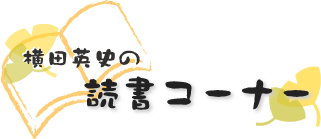 |
|
|
|

|
2014年4月 |
人間と動物の病気を一緒にみる~医療を変える汎動物学の発想~
バーバラ・N・ホロウィッツ、キャスリン・バウアーズ、土屋晶子・訳、インターシフト、p,408、¥2484 |
2014.4.29 |
|
 |
人間と動物の垣根を越えて病気の治療法を考える統合進化医学「汎動物学(Zoobiquity)」を紹介した書。人間がかかる病気の原因や症状を、動物の病気から解き明かす。なるほどとヒザを打つ事例を数多く挙げる。動物がどのように病気になり、治っていくかを理解すれば、あらゆる種の動物の健康度を改善できると、筆者は確信する。400ページと分量があるので読み終えるのは大変だが、それだけの価値がある。医学、進化学、人類学、動物学が融合した新たな学問の動向と知見を取り上げており、知的好奇心を満足させられる良書だ。
筆者は多角的に人間と動物の病気を論じる。がん、中毒や依存症、肥満、自傷行為、過食と拒食、性感染症の知られざる力、思春期に危険な行動をとる理由などをテーマとして取り上げる。興味のあるテーマの章をだけを拾い読みするのも悪くない。
例えばがんについては、野生生物学、(ヒト)腫瘍学、獣医学の専門家たちが一緒に集まれば、がんそのものへの理解は格段に広がると予測する。2章の「なぜ気絶するのか」では、失神するメリットを水中生物から受け継がれた防衛力と位置づける。5章の「中毒や依存症から抜け出す」では、麻薬でハイになるワラビーや酔っ払う動物たちを紹介する。そして依存症から抜け出す一つの方法は、別の依存症に切り替えることだという。6章の「死ぬほどこわい」を読むと、警察に取り押さえられる過程で死亡する事件が起こる理由が分かる。肥満を扱う7章では、へ~っと驚く事実を明らかにしている。
|
| |
申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。~コンサルタントはこうして組織をぐちゃぐちゃにする~
カレン・フェラン著、神崎朗子・訳、大和書房、p.328、¥1728 |
2014.4.23 |
|
 |
「皆さんの生活に無関係な用語や、誤解を招くモデルを氾濫させた、すべての経営コンサルタントを代表して心から深くお詫びします」。ベテラン・コンサルタントが、自らの足跡をたどり、クライアント企業でおかしたミスの数々を“ざんげ”した書。実社会での経験に乏しいコンサルタントが唱える戦略計画、最適化プロセス、業務管理システムといった言葉に惑わされるのは愚の骨頂。モデルや理論は明快で論理的だが鵜呑みしてはいけないと警告を発する。タイトル一発の感もあるが、コンサルティング業界の仕事の実態を明らかにしており実像を知る上で読んで損はない1冊だ。
筆者の筆鋒は鋭い。例えば、コンサルタントは芝居で商売をしている、ビジネスは数字では管理できない、数人のコンサルタントが歪んだ流れを作った、確実に間違っている理論の数々、戦略計画は何の役にも立たない、コンサルタントが去ったあとに残るのは大量の資料だけ、最適化プロセスは机上の空論、業績管理システムで士気はガタ落ち、人材開発プログラムには絶対に参加するな、とコンサルティングへの疑問が次から次へと登場する。身も蓋もない指摘だが、だから貴重とも言える。。
|
| |
辞書になった男~ケンボー先生と山田先生~
佐々木健一、文藝春秋、p.347、¥1944 |
2014.4.21 |
|
 |
三省堂が出版する2冊の国語辞典「三省堂国語辞典」と「新明解国語辞典」を執筆した二人の編纂者、見坊豪紀(けんぼう ひでとし)と山田忠雄に焦点を当てたノンフィクション。四角四面と思いがちな国語辞書だが、これほど個性豊かだとは知らなかった。少し前に赤瀬川原平の『新解さんの謎』がベストセラーになったが、本書はその舞台裏を明らかにしている。言葉好き、日本語好きにはたまらない一冊である。ちなみに本書は、2013年にNHKのBSで放映された「ケンボー先生と山田先生~辞書に人生を捧げた二人の男~」を書籍化したもの。番組を見逃したのが悔やまれる。
二人の編纂者のなかでも、とりわけ見坊は凄い。145万例という桁外れの用例を収集したという。この用例の数は人類史上最大ともいわれ、見坊は戦後最大の辞書編纂者と呼ばれる。ちなみに見坊と山田は、東京大学の同期生である。二人で一冊の辞書「明解国語辞典」を編纂していたが、あるとき袂を分かつ。見坊は三省堂国語辞典、山田は新明解国語辞典を担当することになる。この2冊で累計4000万部と、いずれも国民的な国語辞典である。二人の辞書編纂者の歩みと愛憎は、新明解国語辞典の語釈に反映されている。筆者は足を使った取材でその謎を1つずつ解いている。その執念に感服する。帯に「字引は小説より奇なり」とあるが、本書の価値を見事に言い当てている。
新明解国語辞典には変わった語釈と用例が数多く存在する。なかでも筆者が注目するのが「時点」の用例。具体的には、「1月9日の時点では、その事実は変名していなかった」である。ここに二人の辞書編集者をめぐる謎を解く鍵が隠されているという。
|
| |
ファミコンとその時代~テレビゲームの誕生~
上村雅之、細井浩一、中村彰憲、NTT出版、p.279、¥2808 |
2014.4.18 |
|
 |
任天堂のファミリーコンピュータ(ファミコン)の設計思想と開発、発売までの経緯、その後の爆発的ブームと終焉を、ビジネスモデルや社会的インパクトを絡めながら学術的に論じた書。昔懐かしいゲーム機やソフト、世相が次々と登場する。最大のポイントは、開発責任者だった上村雅之(立命館大学客員教授)が執筆に加わっているところ。上村は第Ⅰ部「テレビゲームの誕生」で、数々の資料を使いながら開発秘話などを紹介している。6502をCPUとして選んだ理由やファミコン回収の経緯など興味深い話が満載である。ファミコンだけではなく、ゲーム&ウォッチの開発物語やゲーム機の開発体制の変遷といった話も悪くない。上村が執筆した100ページあまりを読むだけでも価値がある。組み込み技術者にお薦めの1冊である。
上村の論考では、「アタリショック」やファミコンで起こった数々のトラブルの分析も面白い。アタリショックは粗悪なゲームソフトが横行した結果、販売不振に陥ったという理解が一般的だ。しかし上村は、グラフィックス性能という技術面の問題を指摘する。技術者としての上村の面目躍如である。トラブルの話には技術の香りして面白い。トラブルに見舞われたのは入力用コントローラと表示用LSIである。前者はユーザーの想定外の“押し方”が原因でボタンに不具合が頻発した。後者はNMOSの発熱による“消える白線”問題で、全量を回収することになったという。
後半の第Ⅱ部では立命館大学教授が、産業論「ファミコンとゲーム産業の確立」と文化論「ファミコンの社会的影響と需要」を展開する。産業論ではファミコン成功の要因を分析。任天堂の成功は、「サードパーティがプラットフォームメーカー認証によりゲームを開発する」というエコシステムを図らずも構築したことによると指摘。文化論ではゲームが社会にどのように受け入れられていったかを明らかにする。例えば、ゲーム専門誌の創刊、ドラクエ攻略本の大ヒット、ゲーム・クリーエーターやゲーム音楽作曲者への社会的評価、“ゲーム名人(例えば高橋名人)”の登場など、あの時代を思い出せてくれる話題に溢れている。
|
| |
第五の権力~Googleには見えている未来~
エリック・シュミット著、ジャレッド・コーエン著、櫻井祐子・訳、ダイヤモンド社、p.424、¥1944 |
2014.4.15 |
|
 |
米Googleのエリック・シュミット会長によるIT未来論。原書「The New Digital Age」が出たときにKindle版を購入し読み始めたが、マスメディアやプライバシーを論じる章で挫折した。ありがちな議論が展開されており退屈で中断したのだが、これが大失敗だった。もう少し読み進まないと、本書の良さは分からない。最後まで通読すると、筆者の視野の広さ、全体を俯瞰する能力の高さを知ることができる。刺激的な議論を期待すると失望するかもしれないが、淡々とした指摘に重要な意味が含まれている。今後の世界を垣間見ることができる良書で、読んで損はない。
本書は7章から成る。報道とプライバシーの未来、国家の未来、革命の未来、テロリスムの未来、紛争と戦争の未来、復興の未来などについて、確かな技術的バックグラウンドに基づき論じる。現在の状況を考えると、本書の指摘の的確さと奥の深さには驚かされる。国家、革命、テロリズムといったテーマの選定に米国らしさを感じるし、中国や中東といった地域、ビットコインやロボット兵士などの新技術、サイバー攻撃に代表されるインターネット時代の問題に目を向けて議論を進めるところはさすがである。
|
| |
記憶のしくみ(上)
エリック・R・カンデル著、ラリー・R・スクワイア著、小西史朗・監修、桐野豊・監修、ブルーバックス、p.304、¥1728 |
2014.4.9 |
|
 |
「記憶するとはどういうことなのか」について、ノーベル賞生理学・医学賞受賞者らが過去の研究成果と最新の知見に基づき解説した書。記憶はどこに、どのようにして保存されるのか、記憶の保存に特化した分子は存在するのか、記憶はどのようにして安定化されるのかといった疑問に答える。豊富な図版を駆使して、記憶の種類、記憶を司る分子、学習とシナプス可塑性など、記憶の仕組みを分かりやすく解説している。脳や記憶に興味をもつ方にお薦めの1冊である。
筆者によると、分子的生物学的なアプローチが、システム神経科学や認知心理学と結びついて記憶の解明は進んでいる。神経回路内で神経細胞同士がどのように働くのか、学習プロセスと記憶のシステムはどのように組織化され、それらが相互にどう作動するかが明らかになりつつある。学習に関する研究では、神経細胞同士の結合が学習中にどのように変化するか、その変化が時間とともに記憶としてどのように維持されるのかを説明できるようになっているという。
我々は特定のことを忘れるが、この忘却によって、抽象化したり、主要な点だけを覚えることができる。詳細を忘れることができるおかげで、異なる種類の経験から教訓を加えていって、概念を形成したり徐々に知識を吸収することができるようになる。ある程度の物忘れは、記憶を正常に機能させるために重要かつ必要な一部だという。なんとも魅力的な話の数々である。
|
| |
国際メディア情報戦
高木 徹著、講談社現代新書、p.264、¥864 |
2014.4.4 |
|
 |
NHKのディレクターで「戦争広告代理店」の著者が12年ぶりに上梓したノンフィクション。国際政治の世界で繰り広げられる虚々実々の駆け引きを取り上げる。自らの主張を認めさせるために、どういった手段を用い演出を凝らすかを、オバマ大統領やビンラディンのメディア操縦法、ソチ・オリンピックに込めたロシアの意図、日本が東京五輪の招致で勝てた理由など、具体的な事例を挙げて紹介する。現代社会のメカニズムや常識を知る上で多くの方に読んでほしい良書である。
筆者は、現代の国際政治のリアリティは、自らの倫理的優位性をメガメディアを通じて世界に広めた者が勝つことだと断じる。「民主主義を大切にする世界では、情報は外に出すもの、秘密であってもいずれ出てくるというのが基本である。国民も政府も、それらの情報とどう向き合うかが問われる。テレビ、インターネットなどメディアが発達する現代においては、重要な情報こそ外部に発信し、それを武器として自らを有利に導くことが、国際社会で生き残るうえで不可欠」と語る。
本書は、こうした情報戦の裏側を、マスメディアやPR会社、代理人の活動を通して描き切っている。冒頭で紹介するのはボスニア紛争。ボスニア・ヘルツェゴビナ政府がどのように国際社会に訴え、ボスニア政府に対して有利な状況に持ち込んだかを詳述する。ここで登場するキーワードがサウンドバイト、バズワード、サダマイズ。これらは、現在の国際メディア戦の基本テクニックだという
|
| |
仕事に効く 教養としての「世界史」
出口治明著、祥伝社、p.344、¥1890 |
2014.4.2 |
|
 |
「先人に学べ、そして歴史を自分の武器とせよ」「歴史を学ぶことは、楽しいことであり仕事に効く」。冒頭で筆者は、本書に込める思いをこう紹介する。ライフネット生命保険の代表取締役会長兼CEOで、読者家として知られる筆者が、自らの世界史観を開陳した書である。世界史を単発の出来事の集合ととらえるのではなく、相互に関連付けて鳥瞰的に世界の動きを解釈する。語り口は平易だが説得力がある。学生時代に“暗記科目”だった世界史が魅力的に見えてくる。歴史に興味をもつ方が、取っ掛かりに読むと勉強のモチベーションが高まりそうだ。
本書は10の視点から世界史を読み解く。例えば第1章は「世界史から日本史だけを切り出せるだろうか」と題し、奈良時代に相次ぐ女帝と中国との関係、鉄砲伝来と欧州での宗教革命や世界交易との関係などを解釈する。このほか「歴史は、なぜ中国で発達したのか」「神は、なぜ生まれたのか。なぜ宗教はできたのか」「中国を理解する四つの鍵」「キリスト教とローマ教会、ローマ教皇について」などについて筆者の見解を明らかにする。
|
| |
|
|

|
2014年3月 |
記者たちは海に向かった 津波と放射能と福島民友新聞
門田隆将著、角川書店、p.339、¥1680 |
2014.3.28 |
|
 |
いま旬のノンフィクション作家・門田隆将が東日本大震災の折に起こった人間ドラマを描いた書。地元の人間を助ける代わりに津波にさらわれて亡くなった福島民友新聞の熊田記者を核に、3.11の際に地元記者たちがとった行動を克明に追う。津波が迫るなかで身の危険を顧みず写真撮影する記者の姿、取材中に地元の人を助けられなかった記者の悔恨、震災翌日に宅配しただけではなく避難所にも新聞を配った販売店の奮闘などを紹介する。あのとき何が起こったかを知るうえで貴重な情報を提供してくれる1冊である。
もう一つの見所は、休刊の危機に瀕した福島民友新聞の執念だ。福島民友新聞は、震災による停電、非常用発電機のトラブルなどに見舞われ、100年以上の歴史で初めて新聞を出せない状況に直面する。創刊以来の通算号数を表す「紙齢(しれい)」が3万8340で途絶えかなねい。この状況から、どのような手を打って脱したのか。同業者として興味深い情報が満載である。
|
| |
グローバル・ガバナンスと日本(歴史のなかの日本政治4)
細谷雄一・編、中央公論新社、p.302、¥2940 |
2014.3.26 |
|
 |
国際連盟の創設から現在に至る、国際関係の組織化の歩みと日本との関係について論じた書。国際関係の組織化とは、政治を介さずに国家間の摩擦を緩和し、日常的な国際協力を遂行をする仕組みを指している。国際組織が国家間の問題を解決することが期待されている国際政治の現状を理解するのに役立つ。このほか、満洲事変の時期における対中技術協力から現在の国連外交まで、日本の外交戦略を検証している点も興味深い。
少々学術的で読みやすいとは言えないが、日本外交に関して示唆に富む指摘が多い書である。例えばエイズ・結核・マラリア対策基金への資金提供、上下水道と給水設備の整備といった国際保健事業は、歴史的に日本が深く関与し、貢献してきた分野である。国際社会の平和と安全のために、日本はこの領域で今後大いに力を発揮できると言い切る。
国連を舞台にしたアジア・アフリカ諸国(AA諸国)と日本との関係を、歴史的に振り返る第6章も興味深い。国連では1950年代末に、相次いで独立したAAの新興国が欧米の超大国の特権に挑戦する構図が生まれた。こうした状況のなか日本は、AA諸国と西側陣営の架け橋役を果たした。このバランスのとれた姿勢によって、国連におけるAA諸国の態度の軟化に寄与し、米国やカナダなどの西側諸国からも期待を寄せられる立場を確立したという。もっとも、日本の是々非々の中立的な外交姿勢は逆効果を生んだことも本書は明らかにする。
|
| |
チャーチル~不屈のリーダーシップ~
ポール・ジョンソン著、山岡洋一・訳、 高遠裕子・訳、日経BP社、p.325、¥1890 |
2014.3.21 |
|
 |
チャーチルといえば、第2次世界対戦でドイツ軍が迫るなか行った演説「わたしが提供できるのは血と労苦と涙と汗、これら以外に何もない」である。小学生のころに伝記を読み、ボーア戦争に従軍し捕虜となったチャーチルが、収容所を脱走する下りにワクワクした記憶がある。本書は英国屈指といわれる歴史家が、チャーチルの波乱にとんだ一生を追った評伝である。抑揚を付けない淡々とした書き口なので、子供向けの冒険物語が頭の片隅に残る評者には、正直なところ少々物足りなかった。評伝のインパクトとしてはニクソンの著書「指導者とは」、チャーチルの生涯を概観する教科書的価値では本書といったところだろうか。
筆者はチャーチルの人生からは多くのことが学べると冒頭で語る。具体的には、(1)身体面、精神面、知識面のあらゆる機会をどん欲につかむ方法、(2)大胆に行動し、成功すれば追撃し、いずれ避けがたい失敗に陥っても後に引きずらないようにする方法、(3)精力を注ぎ込み、楽しみながら強烈な野心を追求すると同時に、友情や寛大さ、思いやり、品位を養っていく方法の3つである。さらに付け加えるとすれば、ニクソンが著書「指導者とは」で言及してる、「指導者は明日の一歩先を考える」「指導者は歴史の針路を扱う」の具体例を学ぶこともできる。
本書で特筆すべきは、野中郁次郎・一橋大学名誉教授による解説である。「チャーチルの『ウォー・リーダーシップ』から何を学ぶか」と題された解説は実に50ページ超。この部分だけでも、本書を読む価値がある。野中はこう書く。環境の不確実性、複雑性、多様性が高まり、予測困難な時代において、いかにして千変万化する状況に応じて、適時に最適最善の判断を行っていくか。その実践知のモデルを、われわらはウィンストン・チャーチルに求める、と。そしてチャーチルから、有事におけるリーダーシップには6つの能力が求められることを明らかにする。善悪の判断基準を持ち、「善い」目的を作る能力や「場」をタイムリーに作る能力などだ。リーダーシップに興味のある方は、野中の解説とニクソンの「指導者とは」とを併せて読むことをお薦めする。
|
| |
セラピスト
最相葉月、新潮社、p.345、¥1890 |
2014.3.18 |
|
 |
最相葉月は、出版されたら買わずにはいられないノンフィクション作家の一人である。「絶対音感」「青いバラ」「あのころの未来 星新一の預言」と評者の本棚には最相の著作がずらりと並ぶ。次々と対象を変えて、ディープな取材をこなしていく才能には舌を巻く。その最相が今回焦点を当てたのがセラピスト。箱庭療法の河合隼雄と風景構成法の中井久夫を中核に据えながら、セラピストの実像に迫る。自らも中井のカウンセリングを受けた過程を克明に記す逐語録にはつい引き込まれる。心理療法とは何かに興味のある方にお薦めの1冊である。
箱庭療法と風景構成法は、いずれも患者の心の奥底にあるものを明らかにする手法だ。本書は箱庭療法と風景構成法の手順を解説するとともに、反発にあいながら臨床の現場に受け入れられるまでの過程を克明に記している。これらの手法を使うことで、時間をかけてセラピストと患者の心が通い、快癒へと向かう過程は感動的である。
|
| |
「一体感」が会社を潰す~異質と一流を排除する<子ども病>の正体~
秋山進、PHPビジネス新書、p.224、¥882 |
2014.3.15 |
|
 |
タイトルが秀抜な新書。つい手が出て購入したが、タイトルがすべてを物語っており、想像通りの内容が綴られている。筆者はこのように問う。一流の人材になるために不可欠なのは自律期間。しかし日本の組織では、自律すると反抗的な変わり者と扱われる。筆者は、一体感や仲間意識が組織や会社の成長を妨げているのではないかと危機感を抱く。コドモの組織は、生産規模と効率が重要だった高度経済成長の時代には、同じ方向を向いて、同じ時に同じやり方で、同じことをするほうが効率的で大きな成果につながった。しかし現在の経営環境はそれを許さない。
では、どうすればいいのか。経営・組織コンサルタントとして25年間で30社以上で働いた経験をもとに、この答えを探る。画期的な指摘をしている訳ではないが、全体に役立ち感のある経営書である。
筆者は、個人がコドモの組織、組織文化がコドモの組織、マネジメントがコドモの組織を解説するとともに、コドモ組織から大人の組織への戦略、コドモの組織で大人になる戦略、グローバル化と大人の組織といった観点で組織と人材育成の手法を論じる。批評家ばかりの組織、空気に支配されている人たちの組織、稼ぐことを忘れた人たちの組織、仲間としか仕事をしない組織など、15のパターンに分けてコドモの組織を具体的に紹介する。
例えば仲間としか仕事をしない組織では、どんなに論理的に説明しても、データを示しても、「でも、うち違うから」の一言に勝てないという。コドモの組織の競争力の源泉は「標準化と同質性」だったが、大人の組織では「専門技術力と異質性」がモノを言う。コドモの組織は一体感や仲間意識でつながっていたが、大人の組織を結びつけるのはビジョンや目的、理念だと指摘する。つい膝を打つ合点のいく指摘が多い。
|
| |
指導者とは
リチャード・ニクソン著、徳岡孝夫・訳、文春学藝ライブラリー、p.473、¥1743 |
推薦! 2014.3.10 |
|
 |
ニクソンという政治家を見直した。本書の紹介に「20世紀最高の『リーダー論』、ついに復刊!」とあるが、読み終わると納得できる。ニクソンといえばウォーターゲート事件がすぐに思い浮かぶ。どうも悪役のイメージが強い。しかし本書で登場するニクソンは、会談を重ねた首脳たちと当意即妙なやりとりを行うと同時に、その人物を冷静に分析する教養にあふれた政治家である。視野の広さと文章の明晰さには驚かされる。ニクソンは本書で、指導者がいかに出来事を作ったかの背景を追うとともに、彼らがどれだけ常人と異なるか、彼らの間でもいかに違っているか、彼らに力を振るわせた性格、いかに権力を振るったかを紹介する。切り口は鮮やかである。元毎日新聞記者の徳岡の翻訳も優れており、緊張感のある評伝に仕上がっている。秀抜なリーダー論であり、多くの方に読んでほしい1冊である。
ニクソンは経営力と指導力は別物だと主張する。経営者は今日と明日を考える。指導者は明日の一歩先を考えねければならない。経営者はプロセスを扱うが、指導者は歴史の針路を扱う。だから、経営する客体を失った経営者は無に等しいが、指導者は権力を失っても人々を惹きつける。腑に落ちる指摘である。
本書でニクソンは、チャーチル、ド・ゴール、マッカーサー、吉田茂、アデナウアー、フルシチョフ、周恩来を俎上に上げる。いずれ劣らぬ魅力的な人物たちである。直接会い、話し合い、緊張感の中で腹を探りあった同士にしか分からない部分に踏み込む。それが本書の価値を高めている。一番バッターはウィンストン・チャーチル。肝っ玉、直感、決断力の観点からチャーチルの魅力を描き出す。チャーチルは、時代の危機を処理する能力と性格、勇気をもつのは自分一人だと信じ、その信念は正しかったとニクソンは断じる。
ちなみに本書で最も魅力的に描かれているのはフルシチョフだ。ド・ゴールやマッカーサーの評伝も素晴らしいが、それに優っている。猛烈なユーモアのセンス、知的柔軟さ、粘り強い目的意識、権力へのあくなき意志において、フルシチョフに匹敵するものは1人もいないとお墨付きを与える。時に応じてフルシチョフが吐く名句、絶妙の言葉の応酬は、おそらく全盛期のチャーチルでなければ張り合えなかったと評価する。権力を追われた後のフルシチョフにも言及し、その人物像を余すとこなく描く。
|
| |
不安定化する国際金融システム(世界のなかの日本経済:不確実性を超えて9)
翁百合、NTT出版、p.284、¥2520 |
2014.3.6 |
|
 |
リーマン・ショック前と後における国際金融市場が抱える諸問題を俯瞰的した書。現在の国際金融システムが不安定性を高めている理由を探るとともに、どういった対応が可能かについて考察する。特筆すべきは解説の分かり易さだ。リーマン関係の書籍を何冊も読んだ。しかし筆者の説明ほどス~ッと腑に落ちる書は多くない。この書評でビジネス書・経済書を紹介したが、行きつ戻りつしながら筆者の意図を汲み取るケースが多く、本書は珍しい部類に入る。評者のような理科系の人間が、国際金融市場の過去・現在・未来をざっと知る上で最適な書である。
本書のカバー範囲は広い。第1部と第2部では1980年代からリーマン・ショックまでの間に、金融システムがどのような変化を遂げたかを概観する。金融自由化や金融工学の進展、グローバル化が、先進国の低成長と長期的な金融緩和とあいまって、国際金融システムの不安定性を徐々に高めていったことを明らかにする。
第3部で扱うのはリーマン・ショックと、それに伴う規制強化である。規制監督当局は、個々の金融機関の破綻を防ぐミクロな対策に加え、グローバルな金融システムへの影響を考慮するマクロの視点が求められていると主張する。カナダがリーマン・ショックで大きな打撃を受けなかった理由や、存在感が増している影の銀行への対処など、興味深い分析を行う。第4部ではギリシアに始まる欧州の債務危機や米国の金融緩和の出口戦略、財政問題が深刻化する日本の課題など、直近の話題を扱う。
|
| |
血族の王~松下幸之助とナショナルの世紀~
岩瀬達哉、新潮文庫、p.394、¥662 |
2014.3.4 |
|
 |
松下幸之助と本田宗一郎----多くの日本人が好む最強の二人である。最近では稲盛和夫を加えた三人衆かもしれない。本書は、日本人が愛する松下幸之助の足跡をたどる評伝である。筆者はパナソニックの協力をあえて断り、自らの足で稼いだ取材と新たな資料をもとに松下幸之助の実像を描き出す。感情移入が激しい佐野眞一の評伝を読み慣れていると、気負いが感じられな筆者の書き口に物足りなさを感じるかもしれない。しかし、事実に物語らさせている本書の読後感は決して悪くない。
|
| |
|
|

|
2014年2月 |
しんがりしんがり~山一證券 最後の12人~
清武英利、講談社、p.362、¥1890 |
2014.2.27 |
|
 |
2600億円の債務を隠蔽し続けたあげく、1997年に自主廃業した山一證券。当時の社長が記者会見で号泣した場面を記憶している方も多いだろう。本書は、破綻後も会社に残り、その原因究明と清算業務を行う“殿(しんがり)戦”を務めた12人にスポットライトを当たノンフィクションである。元凶だった人物を含め幹部の多くを実名で取り上げている。迫力満点で読み応えがある。会社とは何か、社会人とは何か、人間の生き様とは何かを感じさせる良書。ベストセラーで長く上位にランキングされているのも納得できる。
筆者は読売新聞の社会部で敏腕記者と呼ばれ、後に読売巨人の球団代表に就任したものの渡邉恒雄を告発して球団を追われた清武英利。本書では約17年前に起きた出来事を丹念な取材で活写しており、長めのノンフィクションだが一気に読ませる。ブランクを感じさせない出来である。
本書には大きく二つの見どころがある。一つは企業が倒産したときの人間模様。殿戦という損な役回りを引き受けた12人のメンバーの揺れ動く心情を描くとともに、早々に逃げ出した役員たちの保身と責任転嫁、沈黙、大蔵省の責任にもページを割く。もう一つは、2600億円という債務が生まれた経緯である。関連会社や海外支店を使った飛ばしの実態と、巨額の債務が生まれた原因を明らかにする。
|
| |
ネットで「つながる」ことの耐えられない軽さ
藤原智美、文藝春秋、p.231、¥1155 |
2014.2.24 |
|
 |
従来の“書きことば”ではなく、“ネットことば”が幅を利かせようとしている現状を憂えた書。筆者は、インターネットがことばを変え、それが国あり方まで変えようとしていると危機感を募らせる。ネットことばは、話しことばのように書いて瞬時に多くの人に届けられるが、熟慮とは縁遠い。ネットことばが主流になり、紙とインクの書きことば終わるとき、同時に何が終わり、何が始まるかを本書を通じて明らかにする。一般受けする書ではないが、インターネットが言葉に与える影響やメディア論に興味をお持ちの方にお薦めしたい1冊である。
筆者は、日本はことばから狂い始め、今や政治や司法、教育が揺らいでいると訴える。書きことばの信頼性失墜が、検察官による証拠改竄、政治家のことばの幼稚化、暴言・失言につながり、その結果、書きことばで成立している憲法は危機に瀕していると分析する。書きことばがネット言葉に移行することで、プロフェッショナルな書き手が不必要になっていることへの危機意識も強い。書く力や文章への責任よりも、テーマや企画、ネタをいち早くネットことばにできるかが重視されていると嘆く。
筆者は、対話やコミュニケーションを重視する社会のあり方に懐疑的である。対話力やコミュニケーション力が幸福や豊かな人生につながるという見方には偽りが隠れていると主張する。書くことは思考であり、その思考を深め継続することで、生き延びる力が得られることをアンネ・フランクを引き合いに出して明らかにする。インターネット社会やSNSで喧伝される「絆」や「つながる」ことに筆者は欺瞞の匂いを感じるという。
|
| |
「知恵」の発見
山本七平、さくら舎、p.196、¥1470 |
2014.2.21 |
|
 |
1977年の「実業の日本」に掲載された山本七平の著作を再構成した書。もはや加筆や追加できない状況なので、構成が水増し気味になっているのは致し方ないだろう。30年以上も前の著作とあって古さを感じさせる記述が少なくないが、山本らしいユダヤ文化や西洋文化、聖書についての薀蓄に触れられる。米国では、セールスマンの一番の参考書が聖書という見方も興味深い。学生時代に影響を受けた名著「空気の研究」のバックグラウンドを知る意味でも貴重な1冊である。
山本の真骨頂は日本文化と西洋文化との比較だ。特に聖書に基づく西洋文化の解釈は独特で、本書でも「日本人の空想力の乏しさ」を新約聖書と関連付けて論じている。平等の概念を日本と西洋を比べる手際も鮮やか。日本社会では、お互いに人間だから平等だとされる。西欧では、法律と規約と各人が契約を結ぶ。その契約が同じだから平等だと解釈する。
本書の今日的な価値は、論争における日本の異質性についての論考だろう。西欧人の論争の手段は、引用であり、事実の提示である。論争は事実によって解決するもの。相手の言葉への言い負かし的な反論は意味をなさない。日本の論争では、敗北主義者的とか右翼的といったレッテルが貼られ、倫理的な糾弾が始まる。言って言って言いまくって、ワーワー言って、何だか分からなくして、相手を言い負かす。どこかで見た風景である。
|
| |
日本のエネルギー問題(世界のなかの日本経済:不確実性を超えて2)
橘川武郎、NTT出版、p.241、¥2415 |
2014.2.18 |
|
 |
ゼロイチになりやすい日本のエネルギー政策について、定量的なデータに基づいた議論を展開し、現実的な解決策を模索した書。東日本大震災と福島原発事故後の日本のエネルギー政策について、示唆に富む提言が多くなされており役立ち感がある。筆者は2012年に「リアルでポジティブな原発のたたみ方」を提唱したが、本書はその後の状況を踏まえて執筆している。今後の日本を考える上で避けては通れないエネルギー問題に興味をお持ちの方にお薦めの1冊である。
筆者はエネルギー問題の見直しには、四つの視点が肝要だと主張する。現実性、総合性、国際性、地域性である。この四つの視点から、原子力発電問題、電力改革、再生可能エネルギーの課題、省エネ、天然ガス、LPガス、石油、石炭について現状と今後を幅広く分析している。
例えば原子力発電所の停止によってブラックアウトの危険が3回あり、電力供給のリスクはまさに「今そこにある危機」であることを明らかにする。しかし原発問題への対応は遅々として進まない。この点について筆者は、東京目線や大阪目線だけではなく、原発の地元の目線を取り入れない限り解決はありえないと主張する。さらに中長期的には原発事業を電力会社の経営から切り離し、国と民間電力会社の間の「もたれ合い」を解消すべきだという。電力改革については、発送電分離が有力な選択肢という立場をとる。
個人的には天然ガスとLPガスについての論考が興味深かった。日本を含む東アジアの天然ガス調達コストが高い理由を、欧州とは異なりパイプライン網が整備されていないことに求める。国際標準に比べて二周遅れという。しかも日本の場合、パイプラインが寸断されており、天然ガスを柔軟に融通できない。LPガスの強みは分散型エネルギーであること。電気や都市ガスは、地震などによってラインが破損することで供給が止まる。しかしLPガスは、各家庭には使用中のボンベのほかに予備ボンベが備えられている。いわゆる「軒下在庫」が確保されているのだ。都市ガス普及地域である大都市が直下型地震等の災害に備えるために、あえて地域内でLPガスを部分的に使っておくべきだという主張は面白い。
|
| |
にわかには信じられない遺伝子の不思議な物語
サム・キーン、大田直子・訳、朝日新聞出版社、p.416、¥2520 |
2014.2.13 |
|
 |
DNAに残された痕跡をもとに、人類や生物の歴史を解明する書。タイトルの「にわかには信じられない」とは少々大げさだが、知的好奇心をくすぐる良書であるのは確かだ。冒頭部分は数々の発見物語を中心にDNAや遺伝子の研究にまつわる逸話を紹介する。個性豊かな科学者たちのエピソードは楽しく読めるが、専門的な内容も多くやや退屈かもしれない。だが、後半になると俄然面白くなり、読むペースが上がる。
例えば人間とチンパンジーの違い、ヒトとチンパンジーを交配させようとする科学者、人間の脳(例えばアインシュタインの脳)の大きさ、著名人の偉業と遺伝病との関係、ツタンカーメンのミイラのDNAが明かす王族の秘密といった話を、下世話な話題を織り交ぜながら筆を進める。なかなかの手際である。最初の部分が退屈だからといって投げ出さずに読み続けていただきたい。
|
| |
政権交代と政党政治(歴史のなかの日本政治6)
飯尾潤編、中央公論新社、p.278、¥2940 |
2014.2.7 |
|
 |
民主党政権の誕生と下野の経緯と背景を主に分析しているが、英国との比較などカバー範囲は広い。首相の面会データから政権の運用手法を分析するといった斬新な切り口を提示している点が興味深い。学者が中心になっている割に堅苦しさが気にならず読みやすい。7章に分かれ、それぞれ異なる著者が担当する。この手の本には珍しく著者のレベルが比較的合っていて、違和感なく読む進むことができる。あの政権交代が何だったのかを知りたい方にお薦めの1冊である。
章立てはなかなか魅力的。例えば第1章「自民党政治と政権交代」で注目するのは、議員数に比べて異様なほど高い影響力をもった新党さきがけ。民主党政権の中核人材を輩出するとともに、自民党を弱体化させる役割を担ったと分析する。しかも交渉のプロセスをメディアを見せることで、多数党のなかで埋没せず、存在感を際立たせた。日本政治における連立政権形成の範型を示したと評価する。
第2章では、自民党と民主党の党首の属性を分析することで、政権交代期における最高指導者像を描く。自民党の指導者に求められる素質は明らかに変化している。候補者の選挙区が都市型になるとともに、当選回数と党役職経験者が少なくなっているという。しかも変化をもたらす候補者が派閥のリーダーでなくなっている。また第4章では、民主党政権の何が問題だったかを、政党ガバナンスの側面から分析する。
最後の第7章は、マスメディアの問題を取り上げる。民主党への政権交代によって、自民党の有力者としか付き合ってこなかった大新聞の有力記者の人脈はあまり意味をもたなくなった。政治記者が語る「いまどきの政治家」に対する慨嘆は、民主党の経験不足や人材難だけではなく、自らの無力さを表していると見る。政治報道をはじめとする報道の質を上げることには困難だと予測する。
|
| |
かたき討ち:復讐の作法
氏家幹人、草思社文庫、p.314、¥819 |
2014.2.5 |
|
 |
色物っぽいタイトルだが、豊富な史料に基づいた論考を中心としており、きわめて真面目な内容である。戦国期から江戸時代の人々がどういった形で恨みを晴らしたのか、武士の世界の慣行や法の在り方、江戸幕府が敵討ち管理のためにどういった制度を整えたのか、敵討ちの時代による変遷を明らかにする。知られざる近世の制度や法、習俗を知ることができ、知的好奇心を満足させてくれる。もともとは中公新書で出版されたが、草思社文庫として復刻した。ちょっと時間があるときの気晴らしに向く書である。
本書は敵討ちを14の側面から紹介する。先妻による後妻の襲撃「うわなり打」、みずから腹を割き遺書で敵に切腹を迫る「さし腹」、敵の死刑執行人を願い出る「太刀取」、密通した妻と間男を殺害する「妻敵討」、男色の愛と絆の証「衆道敵討」などに、それぞれ1章を割いて説明を加える。将軍吉宗と中国人の敵討ちをめぐる問答、敵討ちの許可を書面に記す手続き「帳付」、見世物化する敵討ちの話も興味深い。
|
| |
経済学は人びとを幸福にできるか
宇沢弘文、東洋経済新報社、p.273、¥1680 |
2014.2.3 |
|
 |
「経済学に人間の心を持ち込みたい」という経済学者・宇沢弘文が自らの人生哲学を開陳した書。現在の貧困を解決するキーワードとしての社会的共通資本を紹介するとともに、ミルトン・フリードマン流の市場原理主義を徹底的に批判している。リベラルな論客としての宇沢の考え方がよく分かる。本書は2003年に刊行された「経済学と人間の心」に、二つの未公表講演録と池上彰の解説を追加した新装版である。池上の解説がコンパクトでよく出来ている。
第1部「市場原理主義の末路」は経済倶楽部での2本の講演で構成する。2009年の「社会的資本と市場原理」と2010年の「平成大恐慌~パックス・アメリカーナの崩壊の始まりか」である。質疑応答も収録しており、新自由主義や市場原理主義に対する宇沢のスタンスだけではなく、人柄が伝わってくる。もし東日本大震災や原子力発電所の事故後に宇沢が講演していれば、どういった内容になったのか興味のあるところだ。第2部以降は、思想や歴史観、官僚観、教育観を宇沢自らが語るエッセイである。右傾化する日本への危惧、60年代のアメリカ、学の場の再生、地球環境問題への視座という構成をとる。
|
| |
|
|

|
2014年1月 |
現場主義の競争戦略~次代への日本産業論~
藤本隆宏、新潮新書、p.221、¥756 |
2014.1.30 |
|
 |
製造現場の視点から日本の産業と競争力を論じた書。筆者は、日本経済は「夜明け前」の状態にあり、悲観する必要はまったくないと断言する。数字だけの経営分析やマスメディアの「産業悲観論」は、日本の製造現場の実力を正しく評価できていない。現場は沈黙の臓器であり、会社にも社会にも自己主張しないから、本社もマスコミも官界も政界もこれを軽視する。日本社会は目を覚まさなければならない。本社は有能なグローバル人材を集めた J リーグ方式、現場は国別対抗戦のオリンピック型 。本書には、実証経営学の第一人者の藤本東京大学教授らしい主張が並ぶ。
「現場の匂いがしない日本経済再生策は本物ではない」「良い現場は国内に残すべき」「現場がよい設計の流れを作らない限り、政府の投資奨励も助成も期待した付加価値を産まない」といった傾聴すべき指摘が多い。組み込み業界の読者の方々に向く1冊である。擦り合わせ型、能力構築競争、トヨタの現場といった藤本節にどっぷり浸ることもできる。ちなみに本書は、2010年、2012年、2013年に行った経済倶楽部での講演をベースにしたこともあって読みやすい反面、論理の展開に荒っぽさを感じさせる部分も残っている。
筆者は2013年の講演で、次の20年をこう予測する。日本の優良現場にとって、最もハンデの厳しい最悪の時期は終わりつつある。第1の理由は、新興国と先進国の賃金格差が縮小しつつあり潮目がかわったから。第2は、日本の国内工場の多くが、まだ生産性を上げる伸び代を残している。むしろ、良い現場は逆境と戦ってきた結果、生産性やリードタイム、製造品質といった競争力は以前よりも強くなっている。現在は夜明け前であり、それを永久に続く暗闇だと見誤っている本社は覚醒しなければならないと檄を飛ばす。
|
| |
劣化国家
ニーアル・ファーガソン、櫻井祐子・訳、東洋経済新報社、p.201、¥1680 |
2014.1.29 |
|
 |
ハーバード大学の歴史学教授が、「なぜ豊かな欧米諸国が貧困へと逆戻りするのか? 」という命題に対して、政治、経済、法律、社会の角度か衰退の原因と先進国の将来像に迫った書。切り口が鋭く、なかなか刺激的な内容である。例えば、政府の複雑すぎる規制が治療法を装っているものの、じつは病そのものであり、おろしく長く入り組んだ法を作る者たちが危険なのだと主張する。中国との対比も興味深い。いったん衰退した中国が急成長している状況を、西洋と東洋の再収斂の始まりと表現する。中国は、西洋文化の「キラー・アプリケーション」のほとんど(経済競争、科学革命、現代医学、消費者社会、労働倫理)をダンロードしたことが、躍進の原動力になっていると見る。
本書は BBC ラジオ の番組「リースレクチャー(Reith Lecture)」が2012年に著者を招いた際の講義をベースに書籍化したもので、ハードな内容を平易に解説している。ちなみに、この番組にはこれまで、バートランド・ラッセル、ロバート・オッペンハイマー、ジョン・ガルブレイスなど、そうそうたる面々が登場しているという。
序章で筆者はこう述べている。停滞も成長も、その大部分が「法と制度」が招いた結果だというアダム・スミスの洞察にひらめきを得て、本書を執筆した。スミスの時代の中国についていえたことが、いまの時代の西洋世界の大部分に当てはまるというのが、本書の中心的主張だ。問題は、西洋の法と制度にある。目下の不況は、より深刻な「大いなる衰退」の一症状でしかない、と。筆者は、アダム・スミスの『国富論』をはじめとして、多くの知識人の主張を織り交ぜて主張を肉付けする。
|
| |
司法権力の内幕
森炎、ちくま新書、p.222、¥798 |
2014.1.27 |
|
 |
裁判官経験者の筆者が体験を基に、日本の裁判所の組織的な歪みと司法制度の問題を糾弾した書。裁判官たちが、どういったプレッシャーにさらされながら判決文を書いているのかについて、筆者自身のエピソードを交えながら紹介する。裁判所内の内実が分かり唖然とする場面が少なくない。異端とされた判決を下した裁判官たちのその後を追ったエピソードはなかなか興味深い。司法の世界で異端児が生きにくいことがよく分かる。新書らしくコンパクトにまとまっており、人質司法、冤罪、不当判決、形式的な死刑基準といった、日本の司法制度の問題点をざっと知るのに向く。ただし少し気取った感じの文章は好き嫌いが分かれるかもしれない。
自ら体験しただけあって、裁判所の組織や人事制度への批判は鋭い。筆者自身に対する不可解な配属に始まり、下克上の組織、バラバラな人間関係、検察との腐れ縁、形骸化する裁判官の独立、服従のメカニズムなど具体的に問題点を一つひとつ指摘する。さらに、冤罪を生み出す組織的欠陥や法律無視の身柄拘束が起こる背景といった、読者の関心が高そうな話題を次々に取り上げる。新書としてやむを得ないところは理解するが、いくつか取り上げている冤罪事件などの判例が表面的すぎるので、少し物足りなさが残る。もう少し突っ込んでも良かったのではないか。
|
| |
ジェフ・ベゾス~果てなき野望~
日経BP社、ブラッド・ストーン、井口耕二・訳、p.504、¥1890 |
推薦! 2014.1.24 |
|
 |
Amazon.comのアイデアがウォール・ストリートで生まれた1990年代から現在に至るまでを、創設者のジェフ・ベゾスの人生と意思決定を軸に描いたノンフィクション。アマゾンの成功と失敗、成長の歴史が克明に描かれている。「どんなものでも買える店(Everything Store:原書のタイトル)を作る」という野望の実現に向けて突き進むベゾスを活写しており面白く読める。500ページ超とそれなりに分量があるが、翻訳がこなれていることもあって、あっという間に読み終えることができる。
フィナンシャル・タイムズ紙の選ぶビジネスブック・オブ・ザ・イヤー2013を受賞したのもうなずける充実したビジネス書である。赤字を垂れ流しながらも高成長を続け、最近は新聞社事業や宇宙事業にまで乗り出すアマゾンの行動原理を知ることのできる1冊であり、多くの方にお薦めしたい。
筆者はこのように述べる。「我々が目にしているのは、実は、アマゾンが自ら演出している神話だけ。プレスリリースや講演、取材対応などの原稿のうち、ベゾスが赤ペンで消さなかった部分だけなのだ」。まさに本書は、この知られざるアマゾンの実像を白日のもとに晒している。例えば、今ではすっかり身近になったサービス誕生の裏側で、どういったことが起こっていたかを克明に描き出す。過大とも思える物流システム、9ドル99セントの電子書籍、無料通信サービス付きのKindle、クラウド時代を切り開いたAWS(Amazon Web Services)などを巡るドタバタ劇は興味深い。ベゾスの先見性、意思決定の早さ、経営者としての冷酷さなど、アマゾン成功の秘訣を余すことなく描き出している。
|
| |
新しい国際通貨制度に向けて
高木信二、エヌティティ出版、p.275、¥2520 |
2014.1.21 |
|
 |
NTT 出版が始めた企画「世界のなかの日本経済ー不確実性を超えて」の初回に配本された書である。世界経済を支える金融システムについて、わかりやすく解説している。筆者は第1章「国際通貨エイドとは何か」で、新興国の台頭を背景として変貌する国際通貨制度の枠組みと、グローバル金融危機を踏まえた国際金融アーキテクチャーの改革について論じると、執筆の意図を述べている。また国際金融の制度改革に向けて日本なし得る貢献と、日本が国際通貨制度に関わる意思決定における影響力を維持するための方策を提示することも本書の狙いだという。これだけ読むと少々堅苦しい印象を受けるが、意外に読みやすく、国際金融の仕組みをざっと知るには好適な書に仕上がっている。
筆者は、為替政策に関する行動規範、世界経済の相互依存とリスク、経済危機のメカニズム、揺らいでいる既存パラダイムなどについて、それぞれ章を設けて論じる。例えば為替政策に関する行動規範では、資本自由化、変動相場制、中央銀行によるインフレ目標制を歴史を踏まえ解説してる。このほか、 IMF などの多国間主義、G20といった政府間主義、EU 等の地域主義について重点的に説明を加える。
全体に比較的抑え気味の筆致で持論を展開しているが、日本の財政・金融政策、国際金融における日本のプレゼンスのなさ(知的能力の不足)、筆者が7年間勤務したIMF への批判は手厳しい。特に英国やフランスが日本より経済力が小さいにもかかわらず、国際通貨制度の意思決定において、圧倒的な影響力を行使してきたことに比べ、日本の存在感のなさを嘆く。オランダーやベルギーでさえ、日本以上のプレゼンスを示しているという。ちなみに本書は大阪大学経済学部での講義がベースになっている。そのため学生に向けたメッセージといった趣もある。これが筆者の熱いメッセージにつながっているともいえそうだ。
|
| |
精神医療ダークサイド
佐藤 光展、講談社現代新書、p.336、¥903 |
2014.1.16 |
|
 |
読売新聞で取り上げた、精神医療の現場の記事をまとめて新書化したもの。誤診の数々、誤った投薬や過剰投薬で廃人状態にする、強制入院制度の悪用による拉致・監禁など、精神医療の現場がこれほどまで酷いとは寡聞にして知らなかった。患者に対する高圧的で差別的な医者や裁判官の態度と言動、拉致され10年以上も監禁生活をおくった人の証言など、これが日本の話なのか信じがたいほどだ。医療現場だけではなく社会全体で考える問題だと筆者は訴える。知られざる闇を知ることができる一冊である。
本書は7章に分けて、精神医療現場の実態を白日のもとに晒す。誤診、拉致・監禁、過剰診断、過剰投薬、処方箋依存、離脱症状との闘い、暴言面接である。「通院歴もないのに突然、精神科病院に拉致監禁」「薬漬けで廃人状態にして18年間の監禁生活を強要」「自殺願望に悩む患者に首つり自殺の方法を教える」「大量の薬物投与と電気ショックで26歳男性の言葉を失わせる」など、凄まじい実態を明らかにする。
|
| |
メルトダウン 連鎖の真相
NHKスペシャル『メルトダウン』取材班、講談社、p.296,¥1955 |
推薦! 2014.1.13 |
|
 |
400人を超える関係者への取材をもとに、福島第一原発事故の真相に迫るノンフィクション。掛け値なしに素晴らしい本である。NHKスペシャルの取材班が書き下ろしたもので、2011年12月から2013年3月に放送した3本の番組がベースになっている。福島原発であのときに何が起こったを知る上で貴重な情報が数多く含まれており、多くの方にぜひ読んでもらいたい。B5判と大型の本のうえに重いので持ち運びに難があるが、迫力のある写真や詳細な図を掲載するには、これくらいのサイズが必要だろう。我慢しても読むだけの価値はある。
本書の特徴の一つは、福島原発事故の経過を時間軸にそって、現場関係者・東電社員の証言を交えながら克明に追っているところにある。三つの原子炉がほぼ同時にメルトダウンを起こし、しかも“想定外”の事態が次々に起こる現場を活写する。とにかく迫真の度合いが半端ではない。もう一つの特徴は、迫力満点の写真と技術的な詳細を分かりやすく解説した図の数々である。いずれも効果的に使われており、紙の書籍の良さを満喫できる。
|
| |
採用基準
伊賀泰代、ダイヤモンド社、p.248、¥1575 |
2014.1.12 |
|
 |
タイトルを見て就活関連の書籍だと勘違いし敬遠していたが、実は非常に優れた人材論・リーダーシップ論である。日本社会論や日本企業論、大学教育論(これが秀抜)といった面も備えている。日本企業の人材育成の問題点に鋭く切り込み、的を射た指摘が多い。全体に役立ち感がある。ハーバード・ビジネス・レビュー読者が選ぶベスト経営書2013の第2位に選ばれたのも納得できる。人材育成を考えている方にお薦めしたい。
筆者は、マッキンゼーの採用マネジャーを12年務めた人材コンサルタント。マッキンゼー(あるいは米国企業)が考える優れた人材像を詳細に解説し、世間一般の認識との乖離を明確にする。例えば、地頭信仰を重視する、分析な得意な人を求めている、優等生を求めている、優秀な日本人を求めているという見方に反論している。コンサルティングの仕事は、多くの場合に正しい答えが存在しない。こうしたなかで求められるのは、とことん考え抜く力であり、独自性があり実現した時のインパクトが大きい仮説を立てる構築力、ゼロから新しい提案の全体像を描く構想力や設計力だと強調する。
筆者は本書を通して、「これからのグローバスビジネスの前線で求められるのは、どのような資質をもった人なのか」「日本ではなぜそれらの資質が正しく理解されていないのか」「それらの資質やスキルを身につけることによって、世の中はどう変わるのか」「それらを身につければ、どのような人生を歩むことが可能になるのか」といった問いに答えている。とりわけ強調するのがリーダーシップの重要性である。日本はそもそもリーダーシップを履き違えており、組織的な育成システムが皆無で、リーダーとなる人材の総量が決定的に不足していると嘆く。
|
| |
発明家に学ぶ発想戦略~イノベーションを導くひらめきとブレークスルー~
エヴァン・I・シュワルツ、桃井緑美子・訳、翔泳社、p.312、¥2100 |
2014.1.8 |
|
 |
この書評で2010年に取り上げた「Juice: The Creative Fuel That Drives World-Class Inventors」の日本語訳。日本語版はかつて、「発明家たちの思考回路」(2006年)と題されてランダムハウス講談社から出版されたものの絶版状態になっていた。復刻されたので改めて読んでみた。発明とは一連の発想戦略をツールとして生まれるもので、料理や演技、セーリングなどのスキルと同じように、教え、学び、実行できると筆者は強調する。本書は発明について示唆に富む内容を含んでおり、お薦めの1冊である。
筆者は発明家に共通する11の特徴を挙げる。可能性を創出する、問題をつきとめる、パターンを認識する、チャンスを引き寄せる、境界を横断する、障害を見極める、アナロジーを応用する、完成図を視覚化する、失敗を糧にする、アイデアを積み重ねる、システムとして考える、である。
本書は、11の要因にそれぞれ1章を充て、発明家と言われる人が、どういった思考プロセスを経て発明に至ったか、どんな経験(失敗)をしてきたのか、学問的なバックグラウンドはどうなのかなどを紹介する。エジソンやベル、ニコ・テスラ、ライト兄弟、グッドイヤー(この逸話は面白い)といった過去の偉人のほか、Holonyak(LEDの発明者)、Kamen(セグェイの発明者)、Katz(コールセンター・システムの発明者) など存命している発明家もカバーする。もちろん本書を読んですぐに発明家になれる訳ではないが、示唆に富む指摘が多い。実生活でも役立ちそうである。
|
| |
|
|

|
2013年12月 |
理系のための交渉学入門
一色正彦、田上正範、佐藤裕一、東京大学出版会、p.142、¥2700 |
2013.12.28 |
|
 |
著者が東京大学工学部で行った、技術をベースに起業を目指す学生に向け授業を単行本化したもの。年末の日経コンピュータで書評が出ていたのを見て購入。Win-Winの関係に交渉を導く理論と実践を紹介する。コンパクトかつ実践的な書に仕上がっている。理系だけでなく、文系の方が読んでも十分に役立つ。とりわけ最後の「演習問題:ストーリーで学ぶ逆引き理論解説」が秀抜である。多くの方に一読をお薦めする。
本書は、「理系が交渉を学ぶ意義」に始まり、「交渉の理論」「意思決定」「行動科学に基づくコミュニケーション」「交渉の成功確率を上げる方法」について順々に紹介する。ダラダラと理論を展開するのではなく、実践例の提示と解説に重きを置いているところに特徴がある。取材先とのコミュニケーションを生業とする評者から見ても、的を射た指摘が多くなかなか役立つ。
筆者は、理系人間が苦手としていると言われるコミュニケーション力は、行動科学の研究に基づく理論を学び、トレーニングを積めば、能力向上を期待できると断言する。むしろ、論理的な思考力が重要となる交渉では、理系人間のほうが高い潜在能力があると見る。
|
| |
倫理の死角~なぜ人と企業は判断を誤るのか~
マックス・H・ベイザーマン、アン・E・テンブランセル、池村千秋・訳、NTT出版、p.297、¥2940 |
2013.12.27 |
|
 |
人間の意思決定プロセスをミクロの視点から実証的に分析し、人や組織が不祥事を引き起こすメカニズムを解明するとともに、健全な企業組織を構築する方法を提示した書。倫理上のジレンマに直面した人間が、個人の心理や組織との関係の中でどのように行動するのかを解明する学問「行動倫理学」にもとづいている。興味深い視点を提供してくれる刺激的な書である。
筆者の問題意識は、人間はなぜ自分の倫理観に反した行動を取るのか、なぜ思っているほど倫理的に行動できないのか、なぜ他人の非倫理的行動に気づけないのか、なぜ倫理的な組織を築けないのか、なぜ改革が実現しないのかといった点にある。ポイントは「限定された倫理性」にあるというのが筆者の見立てである。ここでいう限定された倫理性とは、最も検討すべきデータは何かを考えることをせず、目前の簡単に手の入るデータに基いて性急に分析する性癖を意味する。平常心を失った結果、倫理上の問題を生じてしまう。筆者は行動倫理学の知見に基づき、意思決定の事前と最中、事後の三段階で倫理的意思決定を妨げる心理プロセスを提示する。それぞれの指摘は的確で納得できるところが多い。
|
| |
5年後、メディアは稼げるか
佐々木紀彦、東洋経済新報社、p.204、¥1260 |
2013.12.22 |
|
 |
東洋経済オンラインの編集長が、これからのメディアの在り方について持論を展開した書。欧米の事例を取り上げながら、日本にあったビジネスモデルやこれからのジャーナリストの生き方、ウェブメディアにおける広告コンテンツのあるべき姿を提示している。かつてオンラインの編集長を務めた評者から見て、共感する指摘が少なくない。新聞社や雑誌社、オンライン・メディアの今後に興味をお持ちの方にお薦めの1冊である。ちなみに東洋経済オンラインは、リニューアルから4カ月たった2013年3月にビジネス誌系サイトで1位(ページビューベース)になったという。それもあって、本書の書き口は自信満々である。日経BPをはじめとする日経グループが褒め殺しにあっているのが少々気になるが・・・。
筆者のメディア業界を見る目は、「メディア人の多くは、目先の仕事や古い慣習にとらわれ、メディアの未来について考えていない」「紙は主に高齢者をターゲットとした媒体となりブランディング、若手の人材育成などが主な役割になる」「一刻も早くウェブ時代の新しい稼ぎ方を見出さないとメディア業界が焼け野原になる」と厳しい。テクノロジー音痴のメディア人は2流という指摘も興味深い。
|
| |
関わりあう職場のマネジメント
鈴木竜太、有斐閣、p.260、¥2625 |
2013.12.19 |
|
 |
社員同士が関わりあいながら仕事を進めることが多い職場は、お互いに助け合い、勤勉で組織のルールややるべきことをきっちりこなし、自律的な創意工夫を促す。職場の強化によってこそ組織が強くなる。これが本書の趣旨だ。この仮説を証明するために、企業へのヒアリングや調査を駆使する。経営層や部課長クラスのマネジャーの方にとって、一読に値する書である。今年の日経・経済図書文化賞を受賞したのも納得できる。
本書で出色なのはタマノイ酢のケーススタディである。300人規模の企業だが、その組織が実にユニークである。筆者は1章を割いてタマノイ酢における「関わりあう職場」を紹介する。本書の中盤に経営学での位置づけを行っている。この部分はアカデミックで少々読みづらいが、飛ばしてしまっても本書の価値に影響を及ぼさない。
|
| |
原発ホワイトアウト
若杉冽、講談社、p.322、¥1680 |
2013.12.17 |
|
 |
現役のキャリア官僚が、原発をめぐる政官財の利権の構造を暴いたとして話題を呼んだ小説。クライマックス部分が駆け足で小説としての出来は今一歩だが、原発ムラのカラクリなど、日本社会の仕組みを知る上では役立ちそうだ。肩のこらない本なので、正月休みにリラックスして読むのに向く。
|
| |
アルゴリズムが世界を支配する
クリストファー・スタイナー著、永峯涼・訳、角川EPUB選書、p.374、¥1680 |
2013.12.12 |
|
 |
タイトルの「世界を支配する」は少々大げさだが、金融市場を左右するなど存在感を増すアルゴリズムの実像を紹介した書。理系の人間にとってアルゴリズムは馴染み深いが、文系の方にもぜひ読んでいただきたいノンフィクションである。情報技術が進んだ現代社会や経済がどのような仕組みで動いており、将来的にどういった方向に進もうとしているのかが分かる。洋書が出た時に購入しようと思ったが、思いとどまって正解だった。こなれた翻訳なので、すいすい読める。
アルゴリズムの歴史は古い。筆者はその歴史を丹念にたどっているが、科学史関連の書籍を読むことの多い評者には少々冗長に感じられた。アルゴリズムが脚光を浴びるようになったのは、ウォール街で金融商品の開発に応用されるようになってからである。本書はその辺りの経緯を詳細に描く。いまや全米の取引の60%がアルゴリズムによって導き出されたものという。エンジニアの学位もないハンガリー移民の成功物語など、人間臭いエピソードが多く楽しめる。
アルゴリズムが幅を利かせているのは金融商品だけではない。しかし、アルゴリズムに対する拒否反応は根強い。アルゴリズムで作曲した楽曲の栄光と挫折について筆者は詳細に紹介しているが、これが実に面白く示唆的でもある。このほかチェスの世界チャンピオンと対決したディープブルー、CIAが関与した軍事的・政治的な予測、医療診断と投薬の判断など、アルゴリズムの応用の数々を本書は紹介する。その広がりには驚かされる。ちなみに筆者は、将来的に医者や弁護士の仕事の一部がアルゴリズムに取って代わられる可能性を示唆している。
|
| |
狼の牙を折れ:史上最大の爆破テロに挑んだ警視庁公安部
門田隆将、小学館、¥1785 |
2013.12.9 |
|
 |
公安警察が、三菱重工ビル爆破など連続企業爆破事件の犯人たちを、どうやって追い詰めていったのかを克明に追った書。公安警察の捜査員が実名で登場するなど、臨場感にあふれている。捜査員や新聞記者、カメラマン、妻を小包爆弾で亡くした土田國保警視総監の人間模様も詳細に書き込んでいる。企業連続爆破事件が起こったのは30年ほど前なのでご存じない方も多いかもしれないが、一級のノンフィクションとしてお薦めである。当時をご存じの方にとっても、知られざる内容がてんこ盛りなので十分楽しめる。
三菱重工ビル爆破事件が起こったのは1974年(昭和49年)7月。その後も三井物産、帝人、大成建設、鹿島建設、間組などが狙われた。今では考えられないほど騒然とした時代だった。犯行声明を出したのは、公安が把握していない、東アジア反日武装戦線“狼”、東アジア反日武装戦線“大地の牙”、東アジア反日武装戦線“さそり”という正体不明の過激派だ。彼らを爆弾教本「腹腹時計」と犯行声明を詳細に分析して突き止める。筆者が書き込んだ、捜査における数々の失敗と幸運が本書に奥行きを与えている。
|
| |
「曖昧な制度」としての中国型資本主義
加藤弘之、NTT出版、p.291、¥2625 |
2013.12.5 |
|
 |
「曖昧な制度」が中国の経済発展の背景にあると論じた書。筆者の問題意識は、「市場経済システムは先進国に比べて劣っているのに、なぜうまく機能しているのか」にある。この疑問を、歴史的な視点や多角的な比較、グローバルの観点から解明する。制度に組み込まれた曖昧さがポイントだと著者は見る。内容はなかなか刺激的。中国型資本主義の強さと弱さ、欧米諸国やロシアの資本主義との違いを詳細に分析しており説得力に富む。中国の経済と社会の仕組みを理解するのに役立つ一冊である。難儀な隣人に興味をもつ方にお薦めしたい。
筆者はまず中国史を紐解く。官と民を明確に分けるのではなく、両者が曖昧に併存する制度は中国の歴史的伝統に根ざしている。また国有企業や地方政府といった、本来なら市場経済の担い手になりえない組織が、激しい市場競争を繰り広げているところにも中国型資本主義の特徴を見る。中央政府が地方政府に財政上の自主権を与えたことによって地方政府のあいだに競争が起こり、経済発展しつながった。中国といえば汚職などの腐敗のイメージがあるが、一定の腐敗官僚が出現するリスクを織り込んで、民営企業家や官僚に自由な経済活動を行わせるのが中国のやり方という。地方官僚の昇進競争も、汚職などの腐敗によって非効率に陥ることにつながったと著者は論じる。
次に取り上げるのが中国が起こしている国際摩擦。国際ルールに対して、国内ルールを使って挑戦しているように見える中国だが、中国のルールがグローバルのルールに取って代わることはないというのが著者の見立てである。ただし、中国を含む新興国が先進国と同レベルの経済水準に達した時の、新たな世界秩序が再編されることは否定しない。最後が、中国経済の成長の持続性である。筆者は以下のように論じる。イノベーションを伴わない成長は持続可能ではない。現在の中国は体制移行の罠と中所得国の罠に陥っており、持続可能な成長には成長体験から決別し、新たな発展モデルへの転換が欠かせない。しかし相当の摩擦と抵抗が予想され容易ではないと著者はみる。
|
| |
かつお節と日本人
宮内泰介、藤林泰、岩波新書、p.240、¥798 |
2013.12.2 |
|
 |
「かつお節」という身近で魅力的な題材を扱った書。朝の連ドラ「ごちそうさん」で、かつお節削り(カンナ)が登場する場面があり、懐かしい思いでつい購入してしまった。かつお節の生産方法や生産者の生活の変化など、興味深い内容が満載の新書である。
かつお節には300年の歴史があり、関連する地域は約4000キロに及ぶ。しかも明治から現在にいたるまで一貫して消費を伸ばし続け、いまブームが到来しているという。かつお節は日本の軍事進出に密接に関係し、台湾やミクロネシア、インドネシアで生産されていたというのは驚きだ。沖縄との関わりも興味深い。ちなみに沖縄は、日本で最もかつお節の消費が多い地域という。かつお節パックを売りだした老舗・にんべんのエピソードも悪くない。新書らしい内容なので、ちょっとした暇つぶしにお薦めである。
|
| |
|
|

|
2013年11月 |
自殺のない社会へ~経済学・政治学からのエビデンスに基づくアプローチ~
有斐閣、澤田康幸、上田路子、松林哲也、p.238、¥2415 |
2013.11.29 |
|
 |
日本では毎年約3万人が自殺で亡くなる。1997年以降、年間3万人を超え続け、2012年にようやく3万人は切った状態だ。男性の自殺率はOECD加盟国で3番目、女性は2番目に多い。本書は、こうした状況を解決するにはどういった政治的・経済的政策を打てばよいのかを、調査データに基づき論じた書。画期的な結論を導いている訳ではないが、定量的な数字を押さえているので説得力に富む。今年の日経・経済図書賞を受賞したのも理解できる。多くの方に知ってもらいたい自殺の実態と政策の問題点を明らかにした良書である。
本書はまず、自殺の与える社会的な影響について考察する。遺族だけではなく、鉄道の遅延などの社会的な損失、著名人の自殺がさらなる自殺につながる問題などを明らかにしている。次に論じるのが、自殺と経済的要因との関係である。日本の自殺率は他の国と比べて所得格差や景気後退、失業率による影響が大きく、とりわけ所得格差との相関が特に高いという。
このほか自然災害や政治イデオロギーと自殺との関係を明らかにする。前者では、死者数が自殺率を増加させるのは、大規模な自然災害に限定される。しかも災害が発生した年の自殺率には影響を与えず、1年後、2年後に高まる傾向がある。これは災害の発生直後には地域住民の社会的つながりが一時的の高まり、社会的孤立が薄まることに原因があると推測する。後者については、左派政党ほと自殺率が減少する傾向がある。
最後に筆者は、公共事業や失業対策、生活保護といった政策と自殺率の関係を検証する。公共事業や失業対策が65歳未満の男性、生活保護が65歳以上の自殺率の減少につながることを明らかにする。政策の有効性が明確な自殺対策だが、問題は十分な手当がなされていないこと。死亡者数が6分の1以下の交通事故に対する安全対策事業費(2980億円)に比べ、予算は20分の1以下の130億円に過ぎないという。
|
| |
縄文人に学ぶ
上田篤、新潮新書、p.223、¥756 |
2013.11.25 |
|
 |
タイトルに惹かれて購入したが、評者の求めていた内容とは異なっていた。帯の説明は「神棚、ベランダ付き2DK、高級懐石、家計簿、鍋物のルーツは縄文だ」と魅力的。このほかにも南向きの部屋を好むこと、主婦が家計を預かること、玄関で靴をぬぐことなど、著者はこれらのルーツを縄文に見る。建築学者でありながら30年にわたって進めた縄文研究の結果を開陳したのが本書である。筆者の縄文によせる強い思いがひしひしと伝わってくるが、多くの議論が推測で成り立っていることに違和感を感じる。全体に説得力に乏しいのが残念である。
|
| |
~果てしない孤独~独身・無職者のリアル
藤原宏美、関水徹平、扶桑社新書、p.179、¥798 |
2013.11.22 |
|
 |
スネップ(SNEP:Solitary Non-Employed Persons)と呼ばれる独身・無職者の置かれた現状を解説した書。スネップとは、20~59歳の結婚したことがなく、学生でもなく、家族以外との人付き合いがない孤立状態にある無業者を指す。その人口は現時点で約160万人だが、今後さらに増加する可能性が高い。なんとも生きにくくなっている時代を本書はインタビューを中心に明らかにする。書き込み不足を感じる部分があるが、日本社会の現状を知ることのできる新書である。
ちなみに同様の用語にニート(NEET:Not in Education,Employment or Training, NEET)がある。ニートは就学、就労、職業訓練のいずれも行っていない15~34歳の若年無業者を指しており、社会的に孤立しているスネップの方が深刻度は大きい。
筆者は、日本社会が育んできた「学校・企業・家族の三位一体」が崩れたことにスネップの原因を見る。崩れたのは安定した雇用。非正規雇用の増加につながり、未婚率を高めた。すなわち企業社会の崩壊が学校、家族に波及し、孤立無援のスネップを生み出したと筆者は分析する。
|
| |
病の皇帝「がん」に挑む~人類4000年の苦闘~ 下
シッダールタ・ムカジー、田中文・訳、早川書房、p.402、¥2205 |
推薦! 2013.11.20 |
|
 |
人類とガンとの闘いを描くノンフィクション巨編の下巻。禁煙などガン予防の話で始まり、分子生物学の進歩によるガンの原因究明にいたる長いの道のりを描いている。上巻に負けず劣らず興味深い話が満載である。ガンの根治に向けた医者や研究者の野心と一縷の望みを託す患者の思いが織りなす物語を、筆者はときに厳しく、ときに抑え気味に描いている。多くの方にお薦めできる1冊である。
ガンの根本的な原因が突き止められるまで、人類はガン細胞を理解しないまま闘っていた。結果として、外科手術も化学療法も、やみくもに極限まで進んでしまったというのが著者の見立てである。外科医はぞっとするようなレベルにまで手術を徹底したし、化学療法家は、「結局のところ毒である抗ガン剤の投与を増やし、ガン細胞を知らなくても毒殺できる」レベルに到達してしまった。
本書を読むと、人類は試行錯誤の末にガンの原因にたどり着いたことがよく分かる。何度も行き詰まりながら、ときには捏造事件も起こしながら、英雄的な活躍をする研究者に支えられ少しずつ歩を進めていった。最終的には分子生物学によって、遺伝子の突然変異の蓄積が原因だったことが明らかになった。原ガン遺伝子の活性化とガン抑制遺伝子の不活性化が起こり、正常細胞から悪性細胞まで段階的にステップを踏んで移行する過程を、著者は分かりやすく書き切っている。
|
| |
病の皇帝「がん」に挑む~人類4000年の苦闘~ 上
シッダールタ・ムカジー、田中文・訳、早川書房、p.418、¥2205 |
推薦! 2013.11.14 |
|
 |
現役の腫瘍内科医/ガン研究者が、ガンとは何か、人類はガンとどう戦ってきたかを綴ったノンフィクション。文句なく面白い。ガンの起源にさかのぼり、歴史を通してガンという病気がどのように変化してきたかを描く。筆者は本書を「ガンの伝記」と呼んでいる。ガン研究者や医者の人間臭さが書き込まれており、フィクションのような面白さがある。
上下2巻の大著なので引いてしまうかもしれないが、多くの方にお薦めしたい良書である。ピュリッツァー賞やガーディアン賞を受賞したのもうなづける。翻訳も悪くないので、分量が気にならないくらいスイスイ読める。上巻の最後に筆者に対するインタビューを収録していることも理解を助けてくれる。
上巻は小児がん(白血病)と乳がんを中心に、外科治療、X線治療、化学療法の歴史を、ガンと戦いに試行錯誤を続けた研究者たちを活写する。特に、抗癌作用をもつ物質・葉酸類似体を偶然発見し、普遍的な治療法への道を拓いたシドニー・ファーバーには多くのページを割いている。上巻の終盤では、終末医療(ホスピス)やガン予防にも言及する。がん予防の章で描く、タバコ業界との攻防はスリリングで、読み手を飽きさせない。
|
| |
「幸せ」の経済学
橘木俊詔、岩波現代全書、p.184、¥1785 |
2013.11.8 |
|
 |
何冊も読んだので少し飽きてきた「幸福の経済学」関連の本だが、新刊本が出るとやはり手にしてしまう。本書は、「日本の経済格差」「家計から見る日本経済」「女女格差」などで知られる橘木俊詔が著者とあって、安定感のある啓蒙書に出来上がっている。古典派に始まり現代まで、経済学が幸せをどのように捉えてきたかを知ることができる。「幸福の経済学」の入門書としては悪くない。ただし類書に比べて特段のアドバンテージが感じられないのも事実である。
著者は、各種の調査・分析結果を用いて、幸せは必ずしも消費の最大化、あるいは所得の最大化だけで得られるものではないと主張する。本書の特徴は日本国内だけではなく、世界各国のデータに基づいて議論を進めているところ。日本と世界各国の幸福感の違いを、統計データを駆使して論じており説得力がある。
幸福な国とされるデンマークとブータンについては1章を割いている。社会保障制度の重要さ、人々の平等意識の大切さ、人々の心や精神、家族やコミュニティにおける絆の重要さを具体的に論じているのも悪くない。もっともブータンは、2005年の時点では国民の97%が幸福だと感じている国だったが、2010年には41%まで急落した。国民が外国の豊かな生活を知るようになったことや、経済の果たす役割が人生では大きいと国民が思うようになったことが原因だと著者は分析する。なんとも幸福感は移ろいやすい。
|
| |
脳と機械をつないでみたら~BMIから見えてきた~
櫻井芳雄、岩波現代全書、p.224、¥1995 |
2013.11.6 |
|
 |
動物が思い通りに機械を動かすことができる仕組み「BMI(Brain-Machine Interface)」について、最新の研究成果や知見を紹介した入門書。BMIの研究が現時点でどこまで進んでおり、どういった治験を神経科学にもたらしているのか、BMI研究がぶつかっている壁とは何か、今後の展望、社会にどのような影響を与えているかなど、広範な話題を扱う。著者は「BMIは21世紀の月面着陸である」という研究者のコメントを引用しているが、本書を読むとナルホドと得心がいく。図やイラストを多用し分かりやすく解説しており、BMIや神経科学に興味をもっている方はもちろん、そうでない方が読まれても損はない1冊である。
興味深いのは、BMIが脳の活性化に一役買っているところ。筆者は、「まるで自分の身体を動かすように、思った通りに機械が動く」のが真のBMIだと定義する。このためには動物(ヒトやラット、サルなど)側の学習が不可欠となる。BMIにつながった脳は、機械がうまく動くように学習を繰り返し、操作に習熟していく。この学習がニューロンの新生を促し、電極の周辺に新しい神経回路を作り出す。この神経回路が活動することでBMIの習熟がさらに進むといったループを描いて、思い通りに機械が動く状態に近づいていく。クモ膜下出血や脳梗塞などのリハビルに活かせそうである。
|
| |
科学者が人間であること
中村桂子、岩波新書、p.256、¥840 |
2013.11.5 |
|
 |
生命科学者・生命誌研究者の筆者が「科学者のあるべき姿」「科学のあるべき姿」を考察した書。東日本大震災のときに、国民の期待に応えられなかった科学者の姿が本書執筆のキッカケとなっている。宮沢賢治や南方熊楠を引き合いに出しながら、自然や生命と科学者との関わり方を論じる。洒脱なエッセイで知られる筆者だが、本書はかなり内省的かつ哲学的である。肩に力が入り過ぎのきらいもあり、好き嫌いが分かれそうだ。
東日本大震災や原発事故について語る科学者や技術者に、多くの人が不信感を抱き、その不信感は日を追うにしたがって強まっていったと著者は当時を振り返る。専門家が生活者の感覚を失い、閉じられた集団の価値観だけを指針に行動していることが露見し、多くの人が不信感を募らす結果につながったと分析する。
では、科学者や技術者はどうすればいいのか。筆者は、人間を機械として見て、その故障を治す技術を開発し、お金を儲けることに価値を見出す「機械論的世界観」からの決別を提言する。その代わりに、生きるものとして人間を知り、そこから新しい生き方を探る「生命論的世界観」に変わるべきだと主張する。その具体的な方法を、ミクロを探求する科学とマクロの自然を同時にとらえる「重ね描き」に求めている。
|
| |
|
|

|
2013年10月 |
日本の「情報と外交」
孫崎享、PHP新書、p.269、\819 |
2013.10.31 |
|
 |
外務省情報局分析課長や国際情報局長を歴任した筆者が、CIA やMI6、旧KGB といった各国の情報機関との交流や外交官としての経験にもとづき、日本外交におけるインテリジェンス不在を指摘した書。今も昔も“空気”に左右され、情報を的確に分析して適切な行動につなげることのできない日本の政治・外交・社会を痛烈に批判している。英国のしたたかな交渉術など、仕事の役立ちそうなヒントが散りばめられており、ビジネス書として読むこともできる。多くの人にお薦めの1冊である。
筆者は日本の外交をこう分析する。「政策決定において、論理よりも空気が重んじられる傾向は戦艦大和の最後の出撃と重なる」「願望が先行し、都合の良い情報ばかりが集められる政策立案が繰り返された」「相手の脅威を過小評価して自己の能力を課題に評価する傾向がある」など。いずれも的確な指摘で、納得性が高く読み応えがある。事例はいずれも具体的。例えば、石油危機やニクソン訪中(キッシンジャー外交)、中東問題、イスラム革命などで、日本外交はどう判断を誤ったのかを説いている。このほか、ベルリンの壁崩壊のキッカケを作ったハンガリー政府、ゴルバチョフ政権崩壊の裏に米国の盗聴といった知られざる裏話も多い。エンターテインメントとしても楽しめる1冊である。
|
| |
岐路に立つ精神医学~精神疾患解明へのロードマップ~
加藤忠史、勁草書房、p.222、¥2730 |
2013.10.25 |
|
 |
精神医学の置かれた現状を分析し、あるべき姿を提案した書。この書評で以前紹介した「クレイジー・ライク・アメリカ:心の病はいかに輸出されたか」と共通している部分もあるが、精神疾患についてより広範に扱っており提言色が濃くなっている。「新型うつ病」など、精神疾患への関心が高まっているなか、精神医学の歴史と現状、今後をざっと知ることのできる良書である。後半部分が駆け足になっている感があるのは少し残念だが、多くの方にお薦めしたい。
著者はまえがきで、精神疾患に現在用いられている治療法は50年ほど前から画期的な進歩がないと語る。国際的診断基準や治療アルゴリズムが作られたものの、それが画一的な治療と批判されるとともに、「とりあえず抗うつ薬」と揶揄される現状を生んだと嘆く。脳科学が進歩した現在でも、診断法といえば、面接をして、症状を話し、病歴を聞くといった方法しかない。精神疾患に特化した検査法が存在しない。本書では、精神疾患の原因を解明して、生物学的な診断法を確立し、その原因を直接治すような、根本的な治療法を開発することが必要であり、そのために何をすべきかについて持論を展開している。
|
| |
流星ひとつ
沢木耕太郎、新潮社、p.323、\1575 |
推薦! 2013.10.22 |
|
 |
すごい本である。電車で読んでいて鳥肌が立ってしまった。本書は、1979年に引退を発表した藤圭子に、筆者・沢木耕太郎がホテル・ニューオータニで行ったロング・インタビューを基に構成したノンフィクション。地の文が存在せず、藤圭子と沢木の会話だけで構成されている。二人の言葉のやりとりが実に素晴らしいし、子供時代、両親、流しの時代、デビュー、前川清との結婚・離婚、そして引退と、藤圭子という女性の実像をあますところなく描き出している。当時、藤は28歳、沢木は31歳。28歳の藤の人間性に驚かされる。評者は藤の歌をリアルタイムで聞いているが、その人となりを完全に誤解していたことを本書を読んで初めて知った。こんなに思慮深く、賢明でピュアだったというのは驚きである。藤を知る方も知らない方も読んで損はない。
沢木は藤の了解を得ていた本書の出版を、いったん蔵入りにした。藤があまりにプライベートな話を率直に語っており、関係者への影響を慮ったからである。ジャーナリストとして、この決断はすごい。同業者として、沢木の葛藤は想像するに余りある。しかしこの8月に藤が自殺。娘の宇多田ヒカルが病んだ母親の姿しか見ていないことを知り、母親の実像を伝えるために緊急出版を決意する。本書を読むと、沢木の気持ちが十分理解できる。
|
| |
雑誌の王様~評伝・清水達夫と平凡出版とマガジンハウス~
塩澤幸登、河出書房新社、p.544、¥3150 |
2013.10.20 |
|
 |
平凡出版(現マガジンハウス)の創業者の一人・清水達夫の評伝。評伝とはいうものの、全編を通して筆者の雑誌作りへの情熱や古巣・マガジンハウスへの愛情が感じられる。「平凡」「平凡パンチ」「アンアン」「ポパイ」といった雑誌を創刊した清水を通して、雑誌づくりの面白さ・醍醐味を伝えている。マーケティングに基づくのではなく、“思い”を実現した雑誌づくりという良き時代を詳細に描く。筆者は愛情があるが故に、マガジンハウスの現状を手厳しく批判する。ちなみに筆者自身、「平凡」「週刊平凡」「平凡パンチ」などの編集を担当した人物である。万人向けの本ではないが、雑誌好きの方や「平凡パンチ」「ポパイ」全盛期の時代を懐かしく思い出したい方に向く。
評者は日経コンピュータ編集長だった時に、こんな文章を書いたことがある。「雑という言葉がちょっと気に入っている。力強い響きがいいし、漢字の格好も悪くないと思っている。雑が入っている言葉というと、雑踏、猥雑、雑然、雑談、雑草、そして雑誌…。何となくグチャグチャしているが、しぶとく生き抜くバイタリティが感じられる。現場のにおいや生活感が漂う素敵な言葉でもある」。本書を読み、10年以上も前に書いたこの文章を思い出した。やはり雑誌はいいし、清水の人生が羨ましい。
|
| |
消費税 政と官との「十年戦争」
清水真人、p.320、新潮社、¥1680 |
推薦! 2013.10.15 |
|
 |
小泉政権から現在の安倍政権まで、消費税増税の決定にいたる10年にわたる道のりを丹念な取材で追った力作である。政権交代やリーマン・ショック、東日本大震災などと並行して、与野党の政治家と財務官僚、学者が入り乱れて虚々実々の駆け引きを繰り広げるさまを、多くの人物を登場させて活写している。帯には「死屍累々の舞台裏を追った政界ドキュメント」とあるが的を射た紹介である。
登場人物は多彩。筆者は、「俺は上げない」と宣言した小泉純一郎にはじまり、福田康夫、麻生太郎、菅直人、野田佳彦といった歴代首相はもちろんのこと、竹中平蔵や与謝野馨、園田博之、吉岡洋、亀井静香といった面々が、場面場面でどのように登場し、どのような役割を果たしたかを詳細に書き込む。一寸先は闇を地でいく内容は読み応え十分で、つい引き込まれる。多くの方にお薦めの1冊である。
|
| |
CIA極秘マニュアル~日本人だけが知らないスパイの技術~
H・キース・メルトン、ロバート・ウォレス、北川玲・訳、創元社、p.224、\1470 |
2013.10.9 |
|
 |
タイトルにつられて、スパイ教本だと思って買うと後悔するかもしれない。007に登場するようなスパイの技術や仕掛けといたった話題はほとんど登場しない。本書のメインは、マジシャンの技術を応用した“騙しのテクニック”である。これ自体はCIAの活動の一端が分かり興味深いが、さすがに全体の3分の2を占めと延々と続くので最後は飽きてしまう。認識不能バイオ銃や歯磨きチューブに隠した単発銃、毒入りペンといった話もあるので、スパイ活動に興味のある方がざっと目を通すのに向く書である。
本書の背景には1950年代における共産主義台頭の脅威がある。アイゼンハワー大統領の時代には「平和な時代には認可されないような防衛的かつ攻撃的な諜報活動」が求められた。こうした考えのもとに、「MKウルトラ」と呼ぶ149の冷戦対応プログラムが策定された。KGBによる活動から米国民や友好国の国民を守るための対抗策が中心だったが、このなかに当時有名だったマジシャンの技術をスパイ活動に役立てるプログラムが含まれていた。MKウルトラのマニュアルのなかで破棄を免れたのが本書である。
本書の紹介するマジシャンの技術は、ステージマネジメントや手さばき、変装、替え玉(アイデンティティ・トランスファー)、脱出術、錠剤・液体・粉末をこっそり飲ませる方法、モノを隠せる小道具の数々である。とりわけ小道具の数々の紹介は挿絵付きで楽しく読める。
|
| |
リ・インベンション:概念のブレークスルーをどう生み出すか
三品和広、三品ゼミ、東洋経済新報社、p.285、\2100 |
2013.10.6 |
|
 |
イノベーション、ストラテジー、テクノロジーは、ビジネス書やビジネス雑誌が好んで使う言葉である。とりわけイノベーションの影響力は強い。筆者は、この状況に警鐘を鳴らす。イノベーションは儲からない、儲かるのはリ・インベンションだと主張する。日本企業の生きる道はイノベーションではなくリ・インベンション(再発明)にあると説く。新鮮な視点を提供してくれる書である。少し気になるのは本書がイノベーションをかなり狭く定義している点だ。一般的にはイノベーションに分類される事例がリ・インベンションとされており、少し違和感を感じる部分も少なくない。一般的なイノベーションをリ・インベンションとイノベーションに区別すべきというのが著者の主張ともいえる。
リ・インベンションとは何か。筆者は、携帯電話やキッチン用品といった製品を特徴づけると長らく考えれてきた評価基準を無視して、パラメータを作り変えることと定義する。要するに同じ土俵で戦うのでなく、ルール自体を変えるわけだ。したがってリ・インベンションでは必ずしも技術力は必要なく、構想力が重要になる。リ・インベンションによって、現状の技術なら解消できるにもかかわらず放置されている不合理を解決することも可能になる。一方イノベーションの源泉は部品や製造装置にあり、その成果は独り占めできない。抜本的に製品のあり方を見直すことによって、競合をダントツに引き離すことできる点がリ・インベンションの要諦である。
ちなみに本書はリ・インベンションの事例を9つ取り上げる。自転車用の見えないヘルメット、スマートペン、キッチン用品を作りなおすOXO(オクソー)、ダイソンの羽根のない扇風機「エアマルチプライアー」、手書きと音声を連動させたペンなどである。
|
| |
避難弱者:あの日、福島原発間近の老人ホームで何が起きたのか?
相川祐里奈、東洋経済新報社、p.285ページ、\1890 |
2013.10.2 |
|
 |
福島原発事故の際に、周辺にある9つの老人ホームで起こったことを、職員たちへの丹念な取材をもとに綴ったルポルタージュ。自ら避難できない老人を被った被害や職員たちの葛藤が描かれている。不安に苛まれながらも奮闘した職員や介護士たちの仕事ぶりは感動的である。筆者は読売新聞を退職し、国会の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会に参加した。委員会の解散後、フリージャーナリストとして現地を歩いて著したのが本書だ。被災者たちへの思いがぎっしり詰まった良書である。
身体が不自由だったり、病気だったり、体力がなかったりする老人を多く抱える老人ホーム。福島第1原発から30キロ圏内の老人ホームに、政府から退去命令が出される。通信手段は断たれ、道路は渋滞し、県市町村の命令系統はズタズタ。こうした状態のなか老人や老人ホームの職員は、行くあてもなく、乗るクルマの手配が十分でない状態で放り出される。食料や水がない、寝る場所もないといった状態で、老人ホームによっては福島県だけではなく県外までさまよった。当時の混乱ぶりを本書は克明に描く。
|
| |
|
|

|
2013年9月 |
技術者たちの敗戦
前間孝則、草思社文庫、p.313、\861 |
推薦! 2013.9.30 |
|
 |
昭和史に名を残した6人の名技術者が戦時中どのように過ごし、敗戦をどのように受け止め戦後活躍したのかを描くノンフィクション。風立ちぬの堀越二郎を取り上げていることもあって脚光を浴びているが、それ以外の技術者たちの話も興味深い。単純な評伝に終わるのではなく、彼らの技術思想や哲学にも迫っている。筆者は石川島播磨重工でジェットエンジンの設計に20年あまり従事した後にノンフィクション作家に転身した。著者の技術者への愛情が感じられる良書である。多くの方に強くお薦めしたい。
本書が取り上げるのは、ゼロ戦の設計主務者・堀越二郎のほか、新幹線の生みの親・島秀雄、造船日本を生んだ合理化の鬼・真藤亘、レーダー開発の緒方研二、ホンダF1の立役者・中村良夫。伝説ともいえる製品やシステムを開発した技術者たちだが、全員が必ずしも正当に評価されていなかったり、不幸な晩年だったりする。例えば島は新幹線の開業式典に招待されていない。合理化の鬼と呼ばれた真藤は、田中角栄や後藤田正晴とわたりあった剛毅な性格だが、リクルート事件に足をすくわれた。筆者は名技術者の人物像を浮き彫りにすることで、これらの原因を明らかにする。
|
| |
スポーツ・インテリジェンス~オリンピックの勝敗は情報戦で決まる~
和久貴洋、NHK出版新書、p.200、\777 |
2013.9.26 |
|
 |
オリンピックでの競争力向上やメダル獲得の裏舞台を、情報戦の側面から明らかにした書。戦略性に疑問が投げかけられること多い日本だが、スポーツに関しては意外にちゃんとやっていることが分かる。金メダリストを生む具体的なプロセスなど、知られざる話が多く楽しめる新書である。スポーツ好きの方にぜひお薦めしたい。ちなみに日本にスポーツ・インテリジェンスの専門組織ができたのは2001年のこと。国立スポーツ科学センターに情報戦略部門が設置されたのが最初で、現在は日本スポーツ振興センターの情報・国際部に引き継がれている。
国家の諜報(インテリジェンス)と同じで、スポーツ・インテリジェンスの大半は公開情報に基いている。外国人選手やチーム、器具を徹底的に調べあげる。最近は選手のブログの分析までも行うという。例えば何気ないオーストラリア選手のブログから、チームビルディングのノウハウを突き止めるあたりの記述は興味深い。
スポーツ・インテリジェンスの先進国はオーストラリアとイギリスである。オーストラリアは2000年のシドニーオリンピックに向けて、戦略的にトップアスリートの発掘と育成を行った。そのなかにはトレーニングと医学・科学のサポート体制の整備が含まれる。これらは「オーストラリアモデル」として世界中に広まった。そのオーストラリアの勢いが落ちている中で台頭めざましいのが、2012年にロンドン・オリンピックを開催したイギリスという。
|
| |
ロスト・インタビュー~スティーブ・ジョブズ 1995~
「スティーブ・ジョブズ 1995」MOVIE PROJECT、講談社、p.242、¥1050 |
2013.9.25 |
|
 |
米Appleを追われ、米NeXTを設立した当時のSteve Jobsへのインタビューを単行本化したもの。1995年にTV局が行った69分のインタビューだったが、オンエアで使われたのはわずか数分。録画したテープは英国から米国に送られる途中で行方不明になり「ロスト・インタビュー」と呼ばれるようになった。ところがJobsの死後、2011年に担当者のガレージで発見される。本書は、Appleへの復帰の2年前にJobsが何を考えていたかを知ることができる貴重なインタビューのテープ起こしである。Jobs好きだけではなく、多くの方にお薦めの1冊だ。
本書でJobsは、コンピュータと出会った12歳の夏休みに始まり、Appleの創設時の思い出、Mac誕生秘話、Appleを離れた理由、Microsoftへの批判、10年後のコンピュータ像のほか、ベンチャー観、マネジメント論、人材論、人生論を展開する。Appleに戻ってiMacやiPod、iPhoneを生み出す原点となる考え方を披露する下りもあり興味深い。ちなみに242ページの単行本だが、実は読むべきは100ページに満たない。残りの半分以上はJobsのインタビューを英文で起こしたものとその対訳である。
|
| |
「ものづくり」の科学史~世界を変えた《標準革命》~
橋本毅彦、講談社学術文庫、p.288、\1008 |
2013.9.20 |
|
 |
“標準”について誕生の経緯から現状までの3世紀を扱った書。技術者にとって無視できない標準について体系的に論じている。情報技術(IT)についての記述に物足りなさが残るが、多くの技術者の方にお薦めしたい。講談社学術文庫の面目躍如といった感がある良書だ。
標準化の歴史は18世紀のフランスに始まる。フランスの技術者が互換性のある部品から成る銃の製造法を開発したのが端緒である。この技術を米国に輸入したのが、後に米国大統領となるトマス・ジェファーソン。米国に上陸した標準化技術はいっきょに花開く。当初の目的は修理を容易にすることで、互換性部品で量産しコストを下げて製品価格の低減につなげるといった発想はなかった。互換性技術は、コルトなどの拳銃の製造から始まり、ミシン、自転車、自動車、コンテナとその適用範囲を広げる。筆者は数々のエピソードを盛り込みながら発展過程を丹念にたどっている。この辺りは読み応えがある。
19世紀になると互換性は標準化・規格化へと進展する。企業ごとの互換性は、業界全体をカバーする標準化に姿を変えていく。筆者はまずネジを例示して、標準化にいたる道程を明らかにする。本書の特徴は具体的な事例を挙げて議論を進めるところである。コルトの拳銃、シンガーのミシン、T型フォード、紙のサイズ(A/B判、レターサイズなど)、キーボード(QWERTY配列とドボラク配列)、ARPANETなど興味深い話が盛り沢山である。
|
| |
気骨:経営者 土光敏夫の闘い
山岡淳一郎、平凡社、p.352、¥1890 |
2013.9.17 |
|
 |
石川島播磨重工や東芝の社長を経て、第2次臨時行政調査会(第二臨調)会長を務めた土光敏夫の評伝。生い立ちから始まり、社会人・経済人、財界人、家庭人、教育者としての足跡を丹念に追う。清廉や質実剛健といったイメージの強い土光の実像を明らかにしている。読みやすいノンフィクションなので、日本の高度成長期にいたる道程や明治生まれの気骨を知りたい方にはお薦めだ。それにしても本田宗一郎や松下幸之助、井深大、盛田昭夫、土光たちの生き様には痺れるものがある。なお注意して欲しいのは評者のようにリアルタイムに土光を知る人間には、想定通りで驚きが少ない内容なのも事実である。
|
| |
経営センスの論理
楠木建、新潮新書、p.235、¥777 |
2013.9.12 |
|
 |
この書評でお薦めの経営書として取り上げた「ストーリーとしての競争戦略」の著者によるエッセイ。オンラインメディアに執筆した記事をベースに新書化したもの。「スキルだけでは経営はできない」「優れた会社にはセンスがある」といった経営の要諦を、独特の洒脱な語り口で論じる。エッセイなので雑音が多く含まれるが、その分だけ読みやすい書に仕上がっている。肩の力を抜き、オフの時間に読むのに向く書である。
本書は、経営者・戦略・グローバル化・日本・よい会社・思考と六つの切り口から経営について持論を展開する。例えば経営者の章では、センスを磨くにはどうすればよいのか、センスが良い企業の特徴などについて、具体例を挙げながら説明を加える。筆者が力を入れているのが第2章「戦略の論理」だろう。イノベーションについての誤解、「できる」と「する」の違いなどについて多くのページを割いている。残念なのは、後半部に前半ほどの切れ味がみえないところ。筆の勢いが失速気味でワクワク感に乏しい。
|
| |
検証・学歴の効用
濱中淳子、勁草書房、p.256、¥2940 |
2013.9.9 |
|
 |
統計データにもとづいて、学歴の効用の“現在”を説得力をもって論じた書。大学、大学院、短大、専門学校、高専などについて漠然と感じていたことが数字で裏付けられたり、逆に先入観を覆されたりと読み応えのある書に仕上がっている。例えば効用で見ると、大卒の有利性が際立っている一方で、効用の面で高専・短大卒は高卒と同レベルになっているという。このほか女性の方が男性よりも学歴の効用がかなり大きい、女性の学歴の結婚市場における価値、専門書を読む習慣は所得にプラスの影響を及ぼすといった考察は興味深い。学歴や家族の教育に興味をもっている方に強くお薦めしたい書である。
なお大学入試センター准教授の筆者は、本書を執筆した理由をこう述べる。先行き不透明な時代に突入して、自らの努力で学歴を高める意義が以前よりも増している。個人の力でなんとかコントロールできる数少ない地位達成手段が、教育訓練、教育投資、学歴なのであれば、いまこそ実態を見直すべきではないか、と。
本書は大きく3部構成をとる。第1部は「大学という学歴を問い直す」と題して、高卒との違い、出世する大学と出世しない大学、大卒人材の価値といった切り口で話をすすめる。次に焦点を当てるのは女性教育と専門学校、大学院。最後に学歴不信を形成した社会的な要因、どうすれば学歴と健全に向き合う社会を築けるかについての提言を示している。
筆者は、自律的に学び、自ら成長するところに大卒の価値があると繰り返し述べる。この自己学習の姿勢を培うのが大学教育の意義だと断じる。一方で高卒は、他者との関わり、上司やロールモデルのなかで成長する。転職前の経験といったキャリアパスを有効に活用できるのが大卒の特徴だと論じる。ちなみにリクルートワークス研究所の調査によると、自己学習をしている人は、していない人に比べて、およそ3%所得が高い結果が出ているという。
|
| |
アップル帝国の正体
後藤直義、森川潤、文藝春秋、p.212、¥1365 |
2013.9.5 |
|
 |
類書と異なる切り口で米Appleのビジネスに迫った書。Appleといえば、報道管制が厳しい秘密主義の企業として有名である。米国のジャーナリストさえAppleに直接アクセスするのが難しい状況にあって、日本人の著作には自ずと限界があり、期待ハズレの書が少なくなかった。本書は週刊ダイヤモンド記者という立場を逆に利用し、日本の部品メーカーや家電量販店、レコード会社、家電メーカー(特にソニー)、通信キャリアを丹念に取材することで、Appleビジネスの実情を明らかにする。Appleの経済圏に飲み込まれた日本企業の実情を炙りだしており興味深い。
iPhone5やPhone5S/5Cの状況を見るとピークを打った感があり出版のタイミングを逸した気がするが、本書が一時代を築いたAppleの動きを知る上で役立つ情報を盛り込んでいるのも確か。身近で身につまされる話も多く、EISの読者の皆さんにお薦めの書である。
本書はAppleからの発注が止まったシャープの亀山工場の話で始まる。シャープとAppleとの関係を歴史を踏まえながら紹介する。Appleとビジネスをすることが部品メーカーにとってどのような意味を持つのか、Appleは下請けメーカーにどのような態度をとるのかを現場担当者への取材をもとに掘り下げている。知られざるエピソードも多く、読み応え十分である。
このほか倒産に追い込まれた小型モーター・メーカーの話、iPodのステンレスケースを磨いて一躍有名になった業者の話など、興味深いエピソードがてんこ盛りである。下請けメーカーの原価を丸裸にする購買部門の力量、1~2カ月先の生産予定を1日単位で立てるサプライチェーンの威力などAppleの凄さを感じさせる話が多い。
|
| |
エンジェルフライト~国際霊柩送還士~
佐々涼子、集英社、p.288、¥1575 |
2013.9.3 |
|
 |
海外で亡くなった邦人の遺体や遺骨を日本に搬送したり、海外から運ばれてきた遺体に防腐処理などの適切な措置を施し遺族のもとに送り届ける会社「エアハース・インターナショナル」の活動を追ったノンフィクション。2012年の開高健ノンフィクション賞を受賞しているが、その理由がよく分かる良書である。ノンフィクション好きの方に強くお薦めしたい。そうでない方も読んで損はない。
知られざる国際霊柩送還士と呼ぶ職業自体も興味深いが、本書が取り上げるエアハースの社員たちも実に魅力的である。エアハース設立までの経緯、社員が国際霊柩送還という職業を選んだ理由、社員それぞれが背負った人生を筆者は丹念な取材で明らかにする。ノンフィクションらしいノンフィクションで読み応え十分だ。
もう一つの読みどころは日本人の死生観である。身近な人間の突然の死に対する日本人の反応や遺体に対する思いを、本書はエアハースの仕事ぶりを通して明らかにする。感動的なエピソードが多く、不覚にも涙ぐむことになりかねない。電車のなかで読むのは要注意である。
|
| |
|
|

|
2013年8月 |
インテルの製品開発を支える
ブライアン・デイビッド・ジョンソン、細谷功・監修、島本範之・訳、亜紀書房、p.336、\2310 |
2013.8.31 |
|
 |
タイトルと内容に少々ギャップがある。筆者は米Intelのフューチャリスト(未来研究員)で、SF小説や映画、コミックを使って「10年後」を予測している。ただし、その予測がIntelの製品開発にどのように生かされているかについて、本書ではほとんど言及していない。評者同様に「Intelの製品開発」というタイトルにひかれて本書に興味をもつ方は少なくないと思うが、その期待にダイレクトに応えてくれる内容ではないことに注意が必要である。
フューチャリストは「未来予測とは、未来を予言することではない。われわれの日々の判断や行動から、未来は作られていく」というスタンスに立って消費や事業を企画する。そのときのツールがSFプロトタイピングであり、未来を予測するときに、現実の科学技術に基いた小説や映画、コミックを駆使する。小説や映画、コミックが展開する想像の世界を足がかりに、未来と対話することで将来起こることを予測する。人間が想像力を縦横無尽に展開できるメディアを活用するSFプロトタイプは実に興味深い。
筆者は本書で、SF小説、映画、コミックを手がける作家、科学の専門家へのインタビューによって、SFプロトタイピングの効用を明らかにする。巻末には、実際のSF小説とコミックを掲載して読者の理解を助けている。興味深いのはSF小説「ブレイン・マシーン」に登場するジミーと呼ばれるロボット。この召使いロボットは、主人の状況に合わせてジントニックを作る。これが、周辺の環境に適応し、複数の人格を切り替えて動作する人工知能の研究につながることを本書は明らかにする。
|
| |
世界が認めたニッポンの居眠り~通勤電車のウトウトにも意味があった!~
ブリギッテ・シテーガ、畔上司・訳、阪急コミュニケーションズ、p.256、\1785 |
2013.8.27 |
|
 |
電車や会議、授業、国会での居眠りは日本ではごく普通の風景だ。昼食後の会議の眠たさは、誰しも経験済みだろう。本書は、ケンブリッジ大学の文化人類学者が日本人の居眠りを論じた書である。日本の居眠りのほか、世界の睡眠文化についても論じている。筆者は20年を費やして、日本人がどのように眠っているのかを観察するとともに、どのような状況で居眠りをしているかを研究してきたという。ちなみに本書によって「イネムリ」という言葉がドイツ語圏で普及し、いまやドイツでも通じるという。
タイトルから下世話な内容を期待するかもしれないが、とても真面目な本である。帯の「なぜ日本人は降車駅に着くと、突然ニョキッと起き上がるのか」は少々ミスリードだろう。タイトルと帯に誘われて買うと肩透かしを食った気分になるかもしれない。読んで損のない内容だが、購入するときは勘違いしないように気をつけたほうがよい。
本書は日本人の睡眠習慣、日本の睡眠の歴史、世界と日本の睡眠、睡眠と余暇、居眠りの社会的ルール、居眠りの社会学、賢くなるための短眠法といった切り口で居眠りを論じる。立て付けは魅力的で悪くない。例えば眠りのパターンについて三つのタイプがあるという指摘は興味深い。第1は単相睡眠の文化圏。1日の睡眠が1回だけで、8時間の継続睡眠は理想とされている。第2が昼寝文化圏。第3が日本人が属する仮眠文化圏である。夜間の睡眠時間が短く、昼寝や居眠りで補っている。
残念なのは、日本社会について違和感の残る記述が散見されるところ。例えばサウナの利用について、「アポイントの場所までの距離が意外に長い場合が多いので、途中にサウナによるのだろう」とあるが、これは取材相手が悪かったのか、あるいは著者の単純な勘違いだろう。
|
| |
ディズニーリゾートの経済学 新版
粟田房穂、東洋経済新報社、p.256、\1680 |
2013.8.23 |
|
 |
この4月に30周年を迎えたディズニーリゾートのビジネスモデルを紹介した書。経済学と銘打っているがアカデミックな内容ではない。元朝日新聞の記者らしく読みやすい文章で、儲けの仕組みを説いたビジネス書である。筆者は1987年刊行の「ディズニーランドの経済学」に著しており、ディズニーランドを経済的視点から分析した草分けとして知られているという(ディズニーランドが竣工したのは1983年3月)。もっともディズニーランドについては語られつくされた部分が多く、本書で得るところはさほど多くないかもしれない。
本書はディズニーランドだけではなくディズニーシー、イクスピアリ、舞浜のホテル群に言及するとともに、大阪のユニバーサル・スタジオとの対比も行う。ディズニーランドやディズニーシーのコンセプト、優れたユーザー・エクスペリエンスを提供する仕組み、米ディズニー社との関係などについて過不足なく扱う。大きな驚きはないが、まとまりのよいビジネス書という印象だ。
なお本書は2001年に出版した同名の書籍に、日本の消費社会の成熟化、日本文化の異文化への対応などの視点を加味したもの。前者は「『成熟消費社会』の経済学」、後者は「『ディズニー』を受容する日本の異文化吸収力」と題する章を設け解説している。
|
| |
すぐれた意思決定~判断と選択の心理学~
印南一路、中公文庫、p.323、\648(ただし絶版) |
2013.8.21 |
|
 |
質の高い意思決定を行う秘訣を説いたビジネス書。ポイントは人間が陥りやすい誤りを自覚し、それを回避して意思決定を行う方法を解説しているところ。イケイケどんどんの成功体験ではなく、認知心理学や行動心理学、社会心理学、ゲーム理論などの知見に基づき、失敗を避けるところに主眼を置く。的確な数多く事例を挙げ、説得力に富む議論を展開しており読み応えがある。意思決定を日々迫られている方々にお薦めしたい。
著者は慶應義塾大学総合政策学部教授で、この書評で著書「『社会的入院』の研究~」を取り上げたこともある。Wikipediaによると専門は医療政策と意思決定・交渉領域となっているが、最近は全社に傾注しているようだ。ちなみに早稲田大学の内田和成教授がどこかの記事で本書を推薦していたが、すでに絶版になっており古本でしか入手できない。
筆者は本書で、規範的意思決定論の規範性を引き継ぎながら、これに実証的な根拠を明らかにし、実際的な立場から「すぐれた意思決定」を実現する術を追求したという。確かに本書では、人間の意思決定プロセスに関する実証研究を通じて、人間が共通して犯しやすい誤りを数多く紹介している。これがなかなか役に立チ、意思決定の際の“気付き”につながりそうだ。もともとは1997年と15年も前に出版されたビジネス書だが、議論における多様性や情報技術(IT)活用の重要性にも言及しており、筆者のセンスの良さが光っている良書である。
本書は3部構成をとっているが第1部と第2部が興味深い。第1部では「我々と意思決定」と題し、意思決定とは何かを論じると同時に、人間の認知能力の仕組みと限界を解説する。第2部「直感的意思決定のおとしあな」は読み応え十分である。情報データの罠、数値データの罠、記憶の罠、推論の罠、直感的な決定ルールの罠といった角度から、人間が陥りやすい落とし穴を論じる。
|
| |
卵子老化の真実
河合蘭、文春新書、p.253、¥893 |
2013.8.15 |
|
 |
先日の書評で取り上げた「産みたいのに産めない~卵子老化の衝撃~」と同じテーマを、“日本で唯一の出産ジャーナリスト”が扱った書。20年あまり出産を取材してきた著者らしく、取り上げる内容は的確で読み応えのある内容に仕上がっている。「産みたいのに産めない」がNHKらしく具体的事実でぐいぐい押してくるのに対して、本書は手練のジャーナリストらしくトピックスを適切に配置して読者を引き付ける。図版のよさも、本書の特徴の一つである。卵子老化に興味を持たれた方は、両方の書を読むことをお薦めする。
本社は4章構成をとる。第1章の「何歳まで産めるのか」で35歳以上の妊娠の難しさを統計データや歴史的背景に言及しながら指摘する。驚くのは明治女性の高齢出産である。45歳以上の出産数は現代の20倍を超えている(ただし明治の女性は、若いうちに最初の出産を終えている)。第2章は「妊娠を待つ」。不妊治療の現場を問題点とともに明らかにしている。第3章では「高齢出産」を扱う。特に、興味深いのが出生前診断についての記述だ。この対処が難しい問題に対して。妊婦がどのように考え、どのように行動しているのかを取材をもとに明らかにする。第4章は「高齢母の育児」で、陥りがちな問題とともに、高齢であることのメリットにも言及する。視点がユニークで思わず唸ってしまう。
|
| |
プルトニウムファイル~いま明かされる放射能人体実験の全貌~
アイリーン・ウェルサム、渡辺正・訳、翔泳社、p.600、\2625 |
2013.8.13 |
|
 |
凄まじい取材力に圧倒されるノンフィクションである。プルトニウムを人間に注射し、放射能の影響を調べる人体実験が国家の名のもとに米国で繰り返されていた事実を丹念な取材をもとに追っている。人体実験に関与した医者や科学者の行状を明らかにするとともに、実験の対象になった人たちの人生にも迫る。半世紀にわたって隠されていただけに、取材に困難が伴うのは想像に難くない。筆者は、ピューリツァー賞を受賞したこともある米国人ジャーナリストで、その力量をいかんなく発揮している。ちなみに本書は2000年に刊行された同名の書籍に加筆・修正を加えた新装版。原子力にまつわる歴史を知ることができる良書である。
本書は、冷戦時代に数千回の放射能人体実験が行われ、その被験者の大半が貧者か弱者か病人だったことを明らかにする。プルトニウムを注射されたのは18人。このほか、829人の妊婦に放射性の鉄を投与したり、74人の施設の子どもへの放射性物質投与、700人以上の患者に対する全身照射、131人の囚人の睾丸への放射線照射などやりたい放題だった。米原子力委員会は、これらの事実をひた隠しに隠した。
クリントン政権は1995年に、放射能人体実験に関する報告書を発表し謝罪した。ところが、同じ日にO.J.シンプソン裁判の無罪評決が下ったこともあり、マスコミの扱いは小さかった。恥ずかしながら評者も、この事実を本書を読むまで知らなかった。
|
| |
英国一家、日本を食べる
マイケル・ブース、寺西のぶ子・訳、亜紀書房、p.280、¥1995 |
2013.8.6 |
|
 |
英国のトラベル/フード・ジャーナリストが家族同伴で日本を食べ歩いた100日間を綴った書。東京、横浜、札幌、京都、大阪、沖縄、福岡と行動範囲は実に広い。よく知られた名店、玄人筋がひいきにする一見さんお断りの店、ごく庶民的な店と紹介される店はバラエティに富む。身近なだけに気づかない日本の食の奥深さを感じさせる書である。料理の達人で知られた服部幸應(服部栄養専門学校長)、料理研究家の辻静雄(辻調理師学校創設者)の長男・辻芳樹との交流も実に興味深い。
1日に何軒もラーメン屋をハシゴしたりと、100日間の滞在期間中の食べっぷりは凄まじい。個人的にはあまり美味しそうな感じがしないのだが、これは評者の味音痴のためだろう。食道楽の方にはたまらない1冊かも知れない。
|
| |
太陽 大異変~スーパーフレアが地球を襲う日~
柴田一成、朝日新書、p.211、\798 |
2013.8.2 |
|
 |
京都大学の天文台長で太陽物理学者の筆者が、最新の研究成果をもとに太陽の素顔に迫った書。大爆発(スーパーフレア)や黒点が生じる仕組み、地球に与える影響について論じる。新書らしい内容で、ちょっとした知識を身につけるのに役立つ。太陽の物理に関する記述は少し難解だが、そんなもんかと読み飛ばせばよいだろう。夏休みなどの生き抜きに向く書である。
筆者は冒頭で、1000年に一度の超巨大爆発「スーパーフレア」が起こったときに、地球にどんな影響を与えるかをSF仕立てで紹介する。これが、なかなか衝撃的である。大量の放射線粒子が地球に降り注ぎ、人工衛星はすべて故障し、航空機の乗客のなかには急性放射線障害を起こす人が現れ、北極圏ではオゾン層の破壊が始まり、GPSは動かなくなる。さらに大磁気嵐によって大停電が発生し、全世界の原子力発電所で電源が喪失する。まさに恐怖のストーリーである。ちなみに1989年のフレアは、ケベック州で9時間の大停電を引き起こした。600万人に影響を及ぼし、10億円の被害を与えたという。
筆者は、太陽とよく似た恒星でスーパースレアが起きていることを雑誌「Nature」で公表した。しかし査読の過程で、地球で起こる可能性を言及した箇所については、「社会を恐怖に陥れる」「太陽で起きる確証がない」との理由で掲載を拒否された。
太陽の黒点の話も興味深い。このところ太陽の黒点は少ない時期が続いているという。この結果、地球は寒冷化に向かう可能性がある。二酸化炭素が地球温暖化の元凶と吊し上げにあっているが、筆者は寒冷化の歯止めになっているのではないかと指摘する。
|
| |
鼻の先から尻尾まで~神経内科医の生物学~
岩田誠、中山書店、p.224、\2940 |
2013.8.1 |
|
 |
神経内科医が人間の体の不思議を、鼻の先から尻尾にわたって解説した書。編集者の試みは悪くないが、一つひとつの部位の説明が短いのと、専門用語を無造作に多用している面があり、素人には読みづらい。筆者は洒脱な学者のようだが、それを活かしきれていない。全体に、少々面白みに欠けているのは残念である。
本書は、鼻、目、脳、顎、背骨、首など全部で11の部位について、それぞれ数ページを割いて紹介する。神経内科医の診療は、鼻の先から尻尾までの領域に対し刺激を与え、その反応を観察することによって成り立っているという。筆者は本書で、人体の各部位をどのような観察をしてきたかを紹介するとともに、生物学的な進化の側面も論じている。研究者としての体験について力を注いで記述しているのも本書の特徴である。
興味深いのは四つの部位について「神様の失敗(設計ミス)」と称しているところ。具体的には、頸椎、鼠径輪、肛門の周りの静脈叢、腰椎だ。例えば頸椎。四足で歩いているのなら問題はなかったが、二足歩行を始め、重い頭を乗せて40年以上も歩くことは神様の想定外だった。頸椎の椎間板は擦り切れ、頸部変形性脊椎症(頸椎症)を引き起こす。鼠径輪では鼠径ヘルニア、肛門の周りの静脈叢では痔核、腰椎では腰椎症が人間を悩ませる。確かに、こうした症状を訴える方は少なくない。
|
| |
|
|

|
2013年7月 |
クレイジー・ライク・アメリカ:心の病はいかに輸出されたか
イーサン・ウォッターズ、阿部宏美・訳、紀伊國屋書店、p.342、\2100 |
2013.7.29 |
|
 |
米国が心の病気を輸出していることを、香港の「拒食症」、スリランカの「PTSD」、ザンジバルの「統合失調症」、日本の「うつ病」を例に挙げて論じたもの。うつ病の話はなかなか衝撃的だ。米国人は精神疾患の概念を輸出し、その疾病分類や治療法を世界標準にしてしまう。その結果、地域固有の多様な疾患や民族特有の治療法を席巻した。都合の良い事例を取捨選択した気もするが、筆者の主張には耳を傾ける価値がある。知的好奇心を満足させられる良書なので、精神疾患に興味をお持ちの方に薦めたい。
筆者によると、米国で認識され社会に広められたいくつかの精神疾患が、文化の壁を越えて伝染病のように広がっている。例えば香港における拒食症。香港の拒食症には従来、肥満への恐怖はみられなかったし、痩せているのに太りすぎだという間違った思い込みもなかった。ところが米国流の価値観と診断法が入った結果、香港の文化と精神疾患はすっかり姿を変えてしまったという。
日本のうつ病は、製薬会社のマーケティングに大きな影響を受けたと筆者は主張する。日本では元来、憂鬱や愁い、悲しみは辛くても個人の性格を作り上げる要素だとみなされていた。米国なら病的とされる抑うつ感情は、道徳的な意義を持つとともに、自己認識のキッカケだという認識を多くの日本人が共有していた。うつ病はまれな疾患だった。こうした悲しみや抑うつ感に関する日本人の考え方に影響を与え、治療薬を売り込むために、製薬会社はメンタルヘルスの定義を必死に作り変えようとした。その一つが、マーケティング担当者が生んだ「心の風邪」というフレーズだという。それなりに説得力をもつ内容である。
筆者によると、うつ病の根本原因はセレトニンの枯渇にあり、SSRIが脳内で「自然の分泌される」化学物質のバランスを再調整するという理論には科学的根拠がない。科学的事実というよりも文化的に共有されている物語であり、マーケティングが奏功した結果だという。
|
| |
産みたいのに産めない~卵子老化の衝撃~
文藝春秋、p.259、\1470 |
推薦! 2013.7.23 |
|
 |
2012年6月放送のNHKスペシャルを単行本化したもの。リアルタイムで番組を見られなかったのが残念である。本書は読むと切なくなると同時に、不妊に関する知識の欠如を思い知らされる。英国の大学教授は、「日本は不妊についての正しい知識が不足しているうえに、不妊について話すことを避けてきた。そのことが新たな不妊を次々に生んでいる。このままでは日本は次の世紀を生き延びることができない」と警鐘を鳴らす。この発言がけっして大げさでないことが本書を読むとよく分かる。日本社会の問題点に鋭く切り込んだ良書であり、多くの方に読んでもらいたい。
日本は世界一の不妊治療大国である。しかし不妊治療の成功率は突出して低く、世界最低レベルである。原因は治療を受ける女性の年齢の高さと、どんな患者も断らない日本の医師の特質にあるという。卵子は30代後半から確実に老化する。しかも老化を止める方法はない。例えば企業でキャリアを積んで、「そろそろ子どもを」と考え30代後半に不妊治療クリニックの扉を叩いても、「すでに卵子が老化していて、治療をしても妊娠が難しい」ことが多いという。「もっと若いうちに正しい知識がちょっとでもあったら、今は隣に子どもがいたんじゃないかなって・・・」という発言は辛い。
男性にも苦言を呈している。WHOによると不妊の原因の約半分は男性によるもの。しかしプライドが邪魔をし、検査を受けることを先延ばしにする。その間に卵子の老化が進み、妊娠のチャンスを逃すといった事態が続出する。考えさせられる内容が満載の書である。
|
| |
のめりこませる技術~誰が物語を操るのか~
フランク・ローズ、島内哲朗・訳、フィルムアート社、p.439、¥2310 |
2013.7.19 |
|
 |
さほど期待せずに読み始めた本が、意外にも“当たり”だった経験が1年に何回かある。本書はそんな1冊だ。米WIRED誌の編集者兼ライターでIT業界に詳しい筆者らしく、テレビや映画といったエンタテインメントのほか、広告、ゲームなどの製作者が、どのような工夫や仕掛けによってユーザーがのめり込むコンテンツを作り出してきたかを、ソーシャルメディア論や脳神経科学の知見を交えながら論じている。ユーザーはコンテンツの物語に参加し、コンテンツの世界で居場所を見つけ行動を始める。そして次第に深くのめり込んでいく。ここでのポイントは、いかに参加させ、共感を生み、楽しませるかである。事例が具体的かつ身近で、説得力に富んだ良書である。
本書の魅力は映画、TV、広告、本、ゲームなどの具体的コンテンツをピックアップして、詳細に分析していることろ。例えば映画では『アバター』『スター・ウォーズ』『ダークナイト』『A.I.』。ゲームでは『シムピープル』『ミスト』、TVでは『ロスト』『ヒーローズ』、マーケティングでは『Nike+』などを取り上げる。これらが消費者を引きつけた理由を、歴史的背景とソーシャル化の進むトレンドを踏まえ論じる。内容が多様で気づきが多い。ちなみに筆者は、日本のオタク文化とそれを育てた日本の出版社(メディア)に高い評価を与えており興味深い。
|
| |
Slingshot: AMD's Fight to Free an Industry from the Ruthless Grip of Intel
Hector Ruiz、Greenleaf Book Group Llc、p.200、¥2426(原書)/¥644(Kindle版) |
2013.7.16 |
|
 |
米AMDでCEOを務めたHector Ruizが、米Intelとのバトル、提訴までの経緯、パソコン・メーカーとの駆け引き、製造部門の分離など在職中の出来事を振り返った書。出色なのは、やはりライバルIntelを巡る話。IntelがAMDの追い上げをかわすために、パソコン・メーカーにどのような条件を提示したかを微に入り細をうがって記述する。Intelとの係争中に法廷で明らかになった証言・証拠に基づいているのだろうが、「ここまでやるか」といった秘密交渉が明かされている。このほかAMD社内の経営会議やパソコン・メーカーとの交渉、製造部門売却先との会談の内容を詳細に書き込んでおり、半導体ビジネスの裏側を知る上で役に立つ。一般向けの書ではないが、IntelとAMDのバトルが繰り広げられた昔を思い出すには最適だ。ちなみにタイトルのSlingshotとは、Y字形の棒にゴムひもをつけたパチンコを意味する。
Ruizは米Motorola出身である。Sandersに口説かれAMD入りする。背中を押したのは「チャレンジ」である。この辺りのくだりは、Jobsに口説かれたJohn Sculleyの米Apple入りを彷彿とさせる。Ruizは入社当時に感じた、Sandersの2番手商法の限界など、AMDの経営戦略の問題点も指摘する。こうなるとSandersの自伝も読みたくなる。
RuizがCEOに就いたとき、マイクロプロセサ市場におけるAMDのシェアは15%だった。x86を64ビット化したOpteronなど、Intelを上回る商品力をもったマイクロプロセサを抱えていたにも関わらずシェアは落ちていったと、Ruizは悔しさをにじませながら筆をすすめる。米IBMや米HP、米Dellといった大手パソコン・メーカーから色よい返事をもらっていたものの、Intelは“market development fund”とよぶ資金をテコに商談を最終的にひっくり返した。例えばAMDは、HPが3年契約を結べば、初年度に100万個のAthlonを実質無料で提供するといった条件を出したにもかかわらず、契約に至らなかった。本書は数々のAMD失注の経緯を白日のもとに晒している。1億3000万ドル、60億ドルといった現ナマの話は生々しい。この辺りを読むだけでも価値がある。
ちなみにIntelとの係争は2009年にAMD勝訴で決着がついた。IntelはAMDに12億5000万ドルを支払うことになった。しかしAMDは体力をすっかりすり減らし、製造部門は2009年にGLOBAL FOUNDRIESとして分社化された。Ruizは10年間にAMDに被った損害を20億ドルから30億ドルと見積もっている。
|
| |
「フクシマ」論~原子力ムラはなぜ生まれたのか~
開沼博、青土社、p.412、\2310 |
2013.7.11 |
|
 |
このところ集中的に読んでいる社会学者・開沼博のデビュー作。3.11直前に行った福島原発の周辺地域のフィールドワークがベースになっている。筆者が前書きで書いているように、2011年3月11日以前の福島原発について書かれた最後の学術論文である。本書を読むと、3.11後に学者や知識人たちが訳知り顔で垂れ流した、原発の地元をめぐる論説の浅薄さがよく分かる。ノンフィクション作家の佐野眞一は、「“大文字”言葉で書かれたものばかりの原発本の中で、福島生まれの 著者による本書は、郷土への愛という神が細部に宿っている」と本書を評しているが同感である。ちなみに本書は筆者が2011年1月14日に提出した東京大学の修士論文。その質の高さに舌を巻く。
筆者は福島原発がなぜあの地域にでき、いかに3.11に向かって進んでいったのかを、原子力、地方、戦後、高度経済成長、エネルギー、政治といった観点から多角的・体系的に明らかにしていく。地域の視点から原子力ムラの成立と発展を解き明かす手際は鮮やかである。筆者は自らの視点を以下のように表現する。「ムラの状況に軸をおきながら、そこに地方と中央がどのように関わってきたのかを見る。水面を見ることによって得られた認識とは違った、水底の位置に身をおき周囲に目を配りながら、水面と水面下双方の動きを見定めることによって新しい認識を得る」。表面をなぞるだけで本質に迫れないマスメディアに警鐘を鳴らす。
筆者は、原発・原子力施設の維持という点で原子力ムラでは特異な「安定状態」ができていると主張する。原発は運命共同体であり、原子力ムラのシステムをより強固なものにするメディアである。原子力は押し付けられたものではなく、原子力ムラが能動的に求めた結果であることを足で稼いだ取材で明らかにしている。つまり、原子力政策の推進を指向する中央の原子力ムラと、原子力を自らの維持・再生産のために必要とする地方側の原子力ムラが互いに依存しあった結果が現在の状況という。
|
| |
習慣の力
チャールズ・デュヒッグ、渡会圭子・訳、講談社、p.394、\1995 |
2013.7.9 |
|
 |
ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー欄にずっと居座っている書。気になっていたが、ようやく日本語訳が出たので購入。「キーストーン・ハビット(要となる習慣)」と呼ぶ良い習慣を増やせば、人生や生活、ビジネス、社会は劇的に改善することを、豊富な事例と最新の研究成果に基づいて論じている。当初は単純なノウハウ本かと思ったが、意外に底が深く役立ち感がある。翻訳も悪くないのでスイスイ読める。部課長クラスの方々にお薦めの1冊である。
米デューク大学の研究によると、人の行動の40%以上がその場の決定ではなく習慣によるものだという。しかも、脳はよい習慣と悪い習慣の区別をつけられない。悪い習慣が一度身につくと、何かのキッカケでそれがすぐに現れてしまう。逆も同様だ。それだけ習慣の行動に与える影響は大きい。では、どうすればキーストーン・ハビットは身につくのか。筆者はキーストーン・ハビットを身につけたくなるような、ある種のキッカケと報酬を見つけ出すことがポイントという。そして、そのキッカケと報酬に結びつく“欲求”によって習慣を長続きさせることができる。
本書は「個人の習慣」「成功する企業の習慣」「社会の習慣」と3部構成で、習慣の威力について解説する。米国の本らしく、読み応えがあるのは事例の数々。例えば「消臭剤のファブリーズがヒット商品になった理由」「大手アルミ・メーカーのアルコアはダメ会社から優良企業になった理由」「スターバックスのスタッフを一流に育てるプログラム」などは、いずれも“習慣づけ”がポイントだったことを明らかにする。特にアルコアとファビリースの話は興味深い。
|
| |
「空気」の研究
山本七平、文春文庫、p.237、\490 |
推薦! 2013.7 |
|
 |
やはり名著だった。「空気」の研究は、大学生のときに月刊文藝春秋で読んで切り口の鋭さと説得力に感銘を受けた記憶がある。それから35年。文庫本で再読したが、まったく古びていない。むしろ東日本大震災以降の状況を見事に言い当てている。読むほどに凄みが伝わってくる。もちろん、日中国交正常化などの事例に時代を感じさせる部分もあるが、論考はいまでも十分通じる。名著「失敗の本質」と同様に、日本の組織の問題点を知る上で必読の1冊だろう。多くの方に一読をお薦めする。
ちなみに本書は、「「空気」の研究」「「水=通常性」の研究」「日本的根本主義について」の3部構成をとるが、お急ぎの方は最初の「空気」の研究を読むだけで十分である。
|
| |
センス入門
松浦弥太郎、筑摩書房、p.159、\1365 |
2013.7.3 |
|
 |
暮しの手帖編集長が考える、センスよく生きるための書。「センスのいい人とは?」「センスを磨くアイデア」「センスの手本」について持論を展開する。筆者の趣味が装丁やイラストなど本全体に反映されており、紙ならではの趣をもつ書籍に仕上がっている。肩のこらない書き口なので、夏休みなどオフのときにお薦めの書である。
心を開くことがセンスのよさへの最初の一歩、友だちはたくさんいらない、あいさつ上手になる、すすめられたことを試してみるなど、筆者の経験をもとに「センスをよくするコツ」の数々を伝授する。洒脱な語り口で嫌味を感じさせないところは、さすが暮しの手帖編集長である。センスを磨くことにお金を惜しまないのも筆者流だ。人に教えてもらってセンスを磨くときに筆者が推すのが、京都の高級旅館(俵屋か柊家?)に泊まること。言われてみれば納得なのだが、暮しの手帖のイメージとのギャップがあり意外性がある。
雑誌編集長の経験者として、評者には筆者の主張に共感できるところが多い。例えば記事のリード部分の書き方。収まりのよい常套句があり、もっともらしいリードを作ることはできるが、それでは読者の心に届かない。上手に書こうとしないで、取材で感動したこと、心に残ったことを素直に綴った方が読者に迫れると筆者は述べる。この気持はよくわかる。
素敵なものは“変なもの”という考え方も理解できる。創刊者の花森安治がいなくなったことで、暮しの手帖の誌面は“変なもの”から“正しいもの”に変わった。その結果、暮しの手帖は元気がなくなった。「言葉にできないけれど、なぜか惹かれる」には、変であることが重要だと筆者は気づいたという。予定調和ではなく、違和感や引っ掛かりのあるところに記事の価値があるというのは雑誌共通だろう。
|
| |
プライドの社会学~自己をデザインする夢~
奥井智之、筑摩選書、p.256、\1680 |
2013.7.2 |
|
 |
「プライドとは何か」について、自己、家族、地域、階級、用紙、学歴、教養、宗教、職業、国家と10の切り口から解き明かした社会学の書。プライドといえば心理学的な側面から語られることが多いが、実は「社会的な事象なのではないか」というが本書の出発点である。悪くない建てつけだが、10の切り口と六つの素材、全部で60の独立した小話というのは、どう考えても多すぎる。細切れの話が連続し、全体に散漫な印象を受ける。文章も社会学の大学教授らしく分かりづらい。話が行きつ戻りつし、筆者の主張が迫力を持って伝わってこない。狙いが悪くないだけに残念である。
|
| |
|
|

|
2013年6月 |
反省させると犯罪者になります
岡本茂樹、新潮新書、p.220、\756 |
2013.6.28 |
|
 |
悪いことをした人間を“反省”させても更生にはつながらないことを力説した書。筆者は立命館大学教授として教壇に立つとともに、刑務所で累犯受刑者の更生支援にも携わっている。刑務所や教育現場での体験に基づき、「犯罪者に反省させるな」「子どもに反省文を書かせるな」と訴える。興味深い事例がてんこ盛りである。タイトルも秀抜である。内容を的確に表すとともに、読者の関心をぐっと引き寄せる力をもっている。「我が子と自分を犯罪者にしないために」と題した章も用意しており、子育てにも生かせる。多くの方にお薦めの1冊である。
筆者は、問題行動が起きたとき、厳しく反省させればさせるほど、その人は後々大きな問題を引き起こす可能性が高まると強調する。反省するのは表面上だけで、世間向けに体裁を整える偽善が身についてしまう。あるいは反省文ばかりが上手になってしまい、心からの反省につながらない。犯罪者に対して筆者は、被害者や裁判、家族に対して不満があるのなら、まずその不満を語らせる。不満を語るなかで、なぜ犯罪を犯さなければならなかったのか、自分自身にどういった内面の問題があるのかが少しずつ見えてくるという。そこが更生の出発点だと強調する。
|
| |
内向型人間の時代~社会を変える静かな人の力~
スーザン・ケイン著、古草秀子・訳、講談社、p.360、\1890 |
2013.6.26 |
|
 |
ビジネスパーソンとしては損な性格と思われる内向型。筆者は、この俗説を事例や最新の知見に基づき覆す。内向型だからといって成功するわけではないが、ビジネスに成功するための資質として優れた面が少ないことを説得力をもって論じる。ここでいう内向型人間とは、喋るよりも他人の話を聞き、パーティで騒ぐよりも一人で読書をし、自分を誇示するよりも研究することを好む人間を指す。本書では、ビル・ゲイツやガンジー、アインシュタイン、ラリー・ペイジ、バフェット、ゴアなどを内向型人間として挙げる。
筆者は、誰からも好かれる人が理想像になり、カリスマ的なリーダーシップという神話が生まれた経緯を明らかにする。神話が流布して、外向型人間が“成功”に結びつき、内向型人間が“失敗”につながるというハーバード・ビジネススクール的な価値観が世の中を席巻してしまった。しかし筆者は、カリスマ的だとみなされている人物は、そうでない人物と比べて給料は多いが経営手腕は優れていないという調査結果を披露し、神話を否定する。
ちなみに米国は一般的に外向型人間の国家だと思われているし、米国人(特にビジネスパーソン)はそうした期待を背負わされている。しかし米国人の3分の1から2分の1は内向型だという。一方で外向型が重視される米国では内向型の存在感は大きくない。出世競争でも不利になる。本書は、内向型が直面する問題を明らかにすると同時に、創造性に飛んだ人間は内向的という調査結果などをもとに、内向型のメリットを明らかにする。
|
| |
「空気」の構造: 日本人はなぜ決められないのか
池田信夫、白水社、p.240、\1680 |
2013.6.24 |
|
 |
日本人の意思決定の構造を、山本七平の「空気の研究」や丸山眞男の言説にもとづいて論じた書。日本の企業や政治の「決められない」「変革できない」症候群の根本原因を探っている。名著「失敗の本質」を現代に当てはめて解説している感がある。精神主義が跋扈し兵站を無視した日本軍の犯した失敗を繰り返している日本の姿を浮き彫りにしている。事例は満州事変から福島原発事故までと広範だが、著者のブログ同様に切り口が鮮明で読みやすい。一読をお薦めする。
筆者は、毎年のように首相が代わり、歳出が際限なく膨張する日本の政治と、グローバル資本主義のなかで大胆な事業再構築ができない日本企業とのあいだに共通の欠陥を見る。具体的には、責任の所在が曖昧で中枢機能が弱い。そのため利害の対立する問題を先送しがちになる。現場が強く部分最適に陥り、放置すると破綻が目に見えているのに変えられない。全体最適の視点がスッポリ抜け落ちる。本書はこうした状況を、これまでに書かれた「日本人論」から探る。
|
| |
量子革命:アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突
マンジット・クマール、青木薫・訳、新潮社、p.527、\2800 |
2013.6 |
|
 |
本書を開いてすぐに目に飛び込んでくるのが、1927年に開かれた第5回ソヴェイ会議の写真である。アインシュタインやキュリー夫人を含め、錚々たる物理学者29人が居並ぶ。なんと29人のうち17人がノーベル賞を受賞する。本書は量子論100年を振り返る物理学者列伝である。アインシュタインやボーア、マックス・プランク、ハイゼンベルク、シュレーディンガー、オッペンハイマー、フォン・ノイマンといった物理学者の逸話をふんだんに盛り込む。天才たちの知的ゲームの数々を人間味たっぷりに描かれている。特にアインシュタインの実像は興味深い。
本書のクライマックスはアインシュタインとボーアの論争である。量子物理学が腑に落ちないアインシュタインはボーアに何度も論争を挑む。その都度、ボーアと弟子たちは反論に成功する。一連の論争を通してアインシュタインの人となりが伺えて興味深い。
かなりディープな内容なので万人向けとはいえないが読み応え十分である。科学史好きにお薦めしたい。驚くのは翻訳者の力量だ。量子力学についての専門知識が必要な内容だが、こなれた日本語でこの手の書籍としては分かりやすく仕上がっている。
|
| |
幸福の計算式~結婚初年度の「幸福」の値段は2500万円! ?~
ニック・ポータヴィー、阿部直子・訳、阪急コミュニケーションズ、p.304、\1680 |
2013.6.17 |
|
 |
幸福とは定量化できるものであり、測定されなければならないという信念のもと「幸せや不幸の値段」を探った経済書。結婚、離婚、子ども、友情、仕事、死別、失業、障害など、人生における数々の出来事の経済価値を論じている。例えば結婚初年度の幸福は2500万円と弾き出す(独身者が既婚者と同じレベルの幸福を感じるには2500万円が必要と言い換えることもできる)。しかし幸福を扱う経済学は歴史が短いこともあって、学問的な蓄積が進んでいないようだ。再年来、この書評で「幸福」を扱った書籍を集中的に取り上げてきたが、さすがに内容のダブリ感が強くなってきた。このところ増加傾向の幸福本のなかで、本書は最も楽しく読める1冊である。
金持ちが貧乏人よりもすっと幸せである。これは当然だろう。しかし、収入が増えたからといって、すべての人が幸せになるとは限らない。むしろ身近な人の収入より多いか少ないかによって幸福感は左右される。なんとなく説得力のある話だ。宝くじの話は笑える。宝くじで12万円以上当たった人の精神状態を調べると、当たった年はストレスを抱えた状態になって幸福度は下がる。幸福になるのはやっと3年後だという。子供の価値は、なぜかとても低い。子供が生まれた最初の年の幸福度の上昇は31万円にすぎない。
それにしても人間とは面白いものである。人は離婚や配偶者の死の悲しみから意外に早く回復する。結婚や子供の誕生の喜びは数年後には消えてしまう。喜びにも悲しみにも意外なほど早く順応するのだ。しかも過去の経験に対する印象は、楽しかったことも不愉快だったことも、そのピーク時と終了時の様子によって左右される(ピーク・エンドの法則)。例えば大腸の内視鏡検査では、検査に長い時間をかかるよりも、途中でとても強い痛みがあったり、終わり近くになってもまだ痛みがあったりする方が、辛い経験として思い出す傾向があるという。
|
| |
フクシマの正義~「日本の変わらなさ」との闘い~
開沼博、幻冬舎、p.380、¥1890 |
2013.6.15 |
|
 |
この書評でも取り上げた「漂白される社会」で今注目の若手社会学者・開沼博の前著である評論集。雑誌や新聞などで発表した福島原発事故関連の原稿を集めたものなので、ダブり感や整合性の面で気になる所が散見される。しかし筆者の地に足の着いた社会観、問題意識の確かさがよく分かる内容になっており悪くない。知識人・識者と呼ばれる人たちが、傷つかないポジションから上からものを言う言説への違和感、原発事故で浮き彫りになった都会で論じられる“フクシマ”と実際の“福島”との乖離などを鋭い切り口で論じている。評者には共感できる観点が多く、筆者の処女作(出世作)『「フクシマ」論~原子力ムラはなぜ生まれたのか』をさっそく発注してしまった。
筆者は原発事故後に急に原発を語り出した識者たちの姿に、善意同士のぶつかり合いを見る。他者の苦痛に対して「善意」を装うが、自分の身に降り掛かってくると善意は分裂する。識者たちは一枚岩でなくなる。例えば異なる主張を持つ者が、互いにカルト団体のごとく罵倒しあう。「被害者」や「弱者」を見出し、鬼の首を取ったように大騒ぎするが、根無し草のパフォーマンスに過ぎない。エンターテイメント化したTV番組や週刊誌で見た風景だろう。言説の軽さにウンザリした方も少なくないのではないか。
筆者の目は原発事故を超え、「変わる変わる詐欺」を繰り返した日本の戦後社会を見据える。日本の知識人は問題の原因を「悪」のせいにし、自分を安全地帯(筆者は後出しジャンケンと表現する)に置いて免責された気分になり、解決すべき問題の放置を繰り返した。当事者を振り回すだけ振り回して、結局何も解決していない。沖縄しかり、福島しかりである。瞬間的に大騒ぎをするが何も変わらない。しょせんは他人ごとでしかない識者たちによる忘却の反復運動が延々と繰り広げられているというのが、戦後社会に対する筆者の見立てである。辛く厳しい指摘だが、頷けざるを得ない。
|
| |
歴史を変えた外交交渉
フレドリック・スタントン、佐藤友紀・訳、原書房、p.339、\2940 |
推薦! 2013.6.12 |
|
 |
米国の独立交渉やナポレオン戦争後のウィーン会議、日露戦争のポーツマス講和条約など、歴史の教科書で取り上げられている外交交渉の舞台裏を、臨場感タップリに活写した書。事実は小説より奇なりを地で行ったような興味深い内容の連続で、つい引き込まれて読み進んでしまう。駆け引きの数々はビジネスでも応用できそうである。非常に優れた歴史書であると同時に国際政治学の書でもあり、多くの方にお薦めしたい。
本書が取り上げる交渉は八つ。独立戦争の裏で進んでいた米国とフランスの同盟交渉、米国のルイジアナ買収交渉、ナポレオン戦争後のウィーン会議、日露戦争のポーツマス講和条約、第1次世界大戦後のパリ講和会議、第1次中東戦争後のエジプト・イスラエル休戦協定、キューバ・ミサイル危機、レーガンとゴルバチョフの日米首脳によるレイキャヴィク会談だ。いずれの交渉も劇的だが、評者の印象に残ったのは米国の独立交渉とウィーン会議、そしてキューバ危機である。
米国の独立交渉の主役はベンジャミン・フランクリン。フランクリンは、フランスとイギリスの利害関係を巧みに利用し、米国を独立に導く。その粘り強さと信念を、本書は余すところなく伝えている。ナポレオン戦争の後始末で開かれたウィーン会議では、フランスの外交官タレーランが絶妙な舞台回しをみせる。戦勝4大国の分裂を利用し、敗戦国でありながらフランスを会議の中心に据えることに成功。そして欧州の国境線が引き直されたときに、フランスの国益を守りぬいた。本書のハイライトは、核戦争一歩手前の緊張感が伝わってくるキューバ危機だろう。いろいろな書籍を通してキューバ危機についてはそれなりに知っているつもりだったが、いかに浅い知識だったかを本書で思い知らされた。ケネディとフルシチョフの緊迫した駆け引き、米国政権内の緊迫した状況、軍部の想定外の暴走などを、筆者は克明に記している。
|
| |
鳩居堂の日本のしきたり 豆知識
鳩居堂・監修、マガジンハウス、p.208、\1575 |
2013.6.6 |
|
 |
鳩居堂といえば、路線価日本一の場所に店を構える和文具の老舗である。てっきり東京の店だと思い込んでいたが、創業の地は京都の本能寺門前。今年の京都マラソンの前日に京都・寺町をブラブラしていたときに、初めてこの事実を知り非常に驚いた。本書は、創業350年の鳩居堂が約90のしきたりの来歴や背景について、それぞれ見開き2ページでコンパクトにまとめたもの。蘊蓄本としての内容も悪くないが、デザイン、写真、装丁、紙に凝っており、紙の書籍の良さを味わえる。
本書は7章から成る。第一章:季節の歳時、第二章:祝い寿ぐ、第三章 :親しむ、遊ぶ、第四章:弔いごと、第五章:人生の節目、第六章:贈答の心、第七章:手紙、たよりと続く。例えば季節の歳時では、干支、正月飾り、初詣、左義長。祝い寿ぐでは、熨斗鮑、結納などについて解説を加える。評者としては第四章:弔いごとが勉強になった。ふくさ、不祝儀、御霊前・御仏前、香典返しなどといった項目が並ぶ。
冠婚葬祭のノウハウ本としても使えるし、和文具の選び方の優れたガイドブックにもなっている。一家に1冊置いても悪くない。
|
| |
イノベーションを実行する~挑戦的アイデアを実現するマネジメントから
ビジャイ・ゴビンダラジャン、クリス・トリンブル、吉田利子・訳、NTT出版、p.348、\2730 |
2013.6.3 |
|
 |
イノベーションを組織として成功させるためのノウハウを紹介した経営書。類書が多く競争の激しい分野だが、本書は豊富な事例を含め実践的で読み応えがある。ダートマス大学の教授2人が10年をかけて行った調査研究をもとに、イノベーションを生み出す組織の在り方を論じている。アイデアを実現するマネジメントのスキルだと語る。原書が出たときに話題を呼んでいたので気になっていたが、ぐずぐずしているうちに半年前に翻訳本が出てしまった。米国で評価が高かったのも頷ける内容である。主に幹部クラスのマネジメント層にお薦めしたい。
筆者はほとんどの企業には豊かな創造力と高い技術がある。しかしイノベーションを生み出せないのは、そもそも企業はイノベーション向きにできていないからだ。反復が基本の既存事業と反復できないイノベーションは相容れない。企業を存続させるためには、確実に収益を生む既存事業を大切にせざるを得ない。未知数のイノベーションに人・カネ・モノを割くモチベーションは働かない。しかし筆者は、イノベーションと既存事業を適切に分離し、イノベーションの専任チームを外部人材を中心に構成し、マネジメントすれば企業内で併存できると主張する。「組織の記憶」を消し去ることが、イノベーションを生む秘訣だというのが筆者の見立てである。組織の記憶とは言い得て妙だ。
|
| |
|
|

|
2013年5月 |
素晴らしきラジオ体操
高橋秀実、草思社文庫、p.250、\714 |
2013.5.31 |
|
 |
ラジオ体操といえば思い出すのが小学生の夏休み。眠い目をこすりながら、6時30分に近所の公園に集まった記憶をお持ちの方は多いだろう。最近では、公園で日常的にラジオ体操をしている高齢者の姿を見ることが多くなった。本書は、そんなラジオ体操の誕生と発展、現状をとことん追ったノンフィクションである。実は米国が発祥だったという歴史も面白いが、読み応えがあるのはラジオ体操会場における人間模様だろう。筆者はラジオ体操会場に3年通い、メンバー(多くは高齢者)へのインタビューによって真髄を浮き彫りにしている。書き口は軽妙でつい引き込まれる。肩の凝らない内容なので、出張のときや旅のお供にお薦めの1冊である。
世界初のラジオ体操は、米国のメトロポリタン生命保険の発案によるもの。1925年(大正14年)に自社ビルのスタジオからラジオ体操の放送を早朝6時45分から20分間に流した。「死の換金」「死を待つ不吉な商売」といった暗いイメージの生命保険を、明るく生き生きしたものにするというのがメトロポリタン生命保険の戦略だったという。この米国初のラジオ体操を日本に紹介したのは逓信省の役人。昭和3年に日本でのラジオ体操の放送が始まった。ちなみに当時の体操の図解と録音が残っており、今でも復元できるのは凄い。
本書で秀抜なのはラジオ体操会場で繰り広げられている老人たちの生態を生き生きと描いているところ。縄張り争いやハイアラキー、ほとんど信仰と化したラジオ体操への思いなど面白い話題がてんこ盛りである。
|
| |
増補新版 霊柩車の誕生
井上章一、朝日文庫、p.288、\756 |
2013.5.27 |
|
 |
霊柩車の歴史を扱ったマニアックな書だが、中身はきわめてまじめ。霊柩車の誕生や変遷に始まり、葬送などの日本風俗史にまで言及する。難点は内容が古いこと。初版は1984年だが、内容はもっと古びた感じだ。とくに写真が粗く汚いのは残念である。文庫化にあわせて加筆し、昔懐かしい宮型がなくなり、洋型が主流になった背景を解説している。確かに装飾をほどこした霊柩車はとんと見なくなり、黒塗りの地味なタイプが主流になっているのは確か。全体に不思議な雰囲気をもった珍書といえる。
筆者は三つの視点から執筆したことを巻頭で明らかにしている。霊柩車はいつごろどこで使用されるようになったのか、どのような経緯と背景のもとに生み出されたのか、なぜあのようなデザインの車になったのか、である。このなかで興味を引かれるのは、宮型霊柩車の特異なデザインの話だろう。筆者は「平安宮型二方破風標準仕上げ」や「神宮寺型四方破風総黄金造り」といった数々の霊柩車の外観とともに内部を写真で紹介する。写真を見るだけでも結構楽しい。このほか、台数の推移や外装の値段などのデータもなかなか興味深い。
霊柩車誕生と葬送(葬列)の関係も面白い。葬送は明治時代に、世間に見栄を張るための儀式で、派手さを増していった。ところが大人数で長時間にわたって道路を占拠するため、モータリゼーションの興隆と相容れなくなった。大正時代に葬列は、デモ行進なみの扱いになってしまった。こうした状況から生まれたのが霊柩車という。珍しい話がてんこ盛りなので、暇つぶしにお薦めできる書である。
|
| |
インフォメーション:情報技術の人類史~
ジェイムズ・グリック、楡井浩一・訳、新潮社、p.589、\3360 |
2013.5.23 |
|
 |
情報技術の歴史を壮大なスケールで描いた書。訳者が後書きに書いているように叙情詩という表現がピッタリである。600ページに迫るページ数にも驚くが、生物学、言語学、遺伝子学、脳科学に言及し、学問の枠を超えて縦横無尽に持論を展開する筆者の筆力も大したものである。あまりのスケールに付いて行けないところもあるが、仕方ないと諦めるしかない。残念なのは原書にはKindle版があるのに、日本語の電子版が存在しないこと。分厚く重い書籍を持ちは運ぶのはできれば避けたいし、参考文献の多い本書のような本こそ電子版の本領を発揮できる。
本書のカバー範囲はとにかく広い。もちろんチューリングやシャノン、バベッジ、フォン・ノイマン、ウィナーといったお馴染みの面々は登場する。本書の特徴はシャノンの情報理論を起点に、情報を伝達するアフリカのトーキング・ドラムや辞書編纂、電信・電話、暗号、遺伝子解読、ミーム、量子コンピュータ、Wikipediaなどにまで言及しているところである。万人にお薦めできる書ではないが、いつかは読もうと本棚の片隅に置くのも悪くない。
|
| |
Lean In: Women, Work, and the Will to Lead
Sheryl Sandberg、W H Allen、p.256、¥1990(ペーパーバック版)/¥1377(Kindle版) |
2013.5.12 |
|
 |
このところ日本のメディアでさかんに取り上げられている、米Facebook COOのシェリー・サンドバーグの書。女性の社会進出の難しさ、ガラスの天井、仕事と家庭の両立問題を、自らの体験やIT業界の著名人のコメント、各種の調査を駆使して論じている。世界銀行やMcKinsey 、Googleといったエリート街道を歩いているサンドバーグだけあって、説得力のある論理展開はさすがである。本書は出版以来、米国でトップ・セラーになっているだけではなく、賛否両論を巻き起こし社会的現象になっている。万人向けではなく、けっして面白い本ではないが、女性の上司・同僚・部下をお持ちの方が読んで損はない。英語は平易で読みやすい。日本語版が出ていないのは不思議だが、これだけ話題を呼んでいるので、そのうちに出るのだろう。
タイトルの“Lean In”は「一歩踏み出す」の意味である。サンドバーグは、世間の目を気にして社会進出や出世に消極的で尻込みしている女性の背中を押し、一歩踏み出すことを促している。年俸3000万ドル(30億円)のサンドバーグの主張は、一般的な女性には当てはまらないとの批判が多いが、超エリートで超リッチという面を考慮しても傾聴すべき指摘が少なくない。米国は女性の進出が進んでいるというイメージだが、現実はかなり異なることが本書を読むとよく分かる(それでも日本よりも数段進んでいる)。子育ての問題、企業における微妙な立場、女性同士の問題など、日米で共通する課題は驚くほど多い。
サンドバーグは、人生訓やビジネス体験、本書を上梓する決断をするまでの過程を率直に披露している。女性から「メンターになってくれ」と頻繁に言われる話や、キャリア形成は階段を上り下りではなくジャングルジムという人生観、パーフェクトではなくベターを目指すモットーなど、興味深い話が盛りだくさんである。夫の話もしきりに出てくる。夫ができた人間なのも、本書が批判にさらされる一因かもしれない。
|
| |
藤原道長の日常生活
倉本一宏、講談社現代新書、p.288、\840 |
2013.5.10 |
|
 |
藤原道長が綴った日記「御堂関白記」(世界最古の自筆日記)に基づき、道長や平安貴族の日常生活、平安時代の風習・風俗などを解説した書。筆者は、自筆日記の書き方や書き換え、抹消、誤字などから道長の心象風景を推察する。このあたりの手法はなかなか面白い。道長といえば有名な短歌「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたる事も無しと思へば」である。栄華を極めた権力者というイメージが強いが、筆者は傲慢さと小心さが同居する人間・道長を明らかにする。教科書の登場人物の実像を知ることができるので歴史好きの方にお薦めの1冊である。
本書は、感情表現、宮廷生活、妻・倫子の素顔、次々に中宮にした娘たちとの関係、自宅や御所といった生活環境、宗教や禁忌などの精神生活といった角度から道長の人間像を描く。泣き虫だが怒りっぽい道長の人間像も興味深いが、評者の興味を引いたのは平安貴族の生活。徹夜で短歌を競い合ったあとに、そのまま仕事場に向かうなど実にタフである。平安貴族というとナヨナヨしたイメージをもっていたが、先入観を覆された。本書には京都事件帳といった趣もある。京都で起こった喧嘩や殺人、火事、天災なども紹介する。
|
| |
レジリエンス 復活力~あらゆるシステムの破綻と回復を分けるものは何か~
アンドリュー・ゾッリ、アン・マリー・ヒーリー、須川綾子・訳、ダイヤモンド社、p.416、\2520 |
推薦! 2013.5.5 |
|
 |
災害や事故・事件のような急激な状況変化に適応できる組織や機関、システムをどうすれば構築できるのか。本書はレジリエンス(resilience)と呼ぶ研究分野をキーワードに、適応力の高い社会の在り方と構築の仕方を論じている。示唆に富む議論の展開と豊富な事例は非常に読み応えがある。今年読んだ書籍ではNo.1だ。ちなみにレジリエンスは辞書的には、「(元気の)回復力・復元力」「障害や誤りが存在しても、要求された機能を遂行し続けることのできる能力」である。
筆者は冒頭でレジリエンスについてこう述べる。「レジリエントなシステムはいさぎよく失敗する。危険な状況を避け、侵入を察知し、部分的な被害を分離して最小化し、資源の供給源を多様化する。必要とあれば縮小した態勢で稼働し、破壊されると自ら再構築して回復を図る。レジリエントなシステムはけっして完璧ではない。現実はむしろその反対だ。一見完璧なシステムはきわめて脆弱であることが多く、ときとして失敗を伴うダイナミックなシステムはこのうえなく頑強になりうるのだ」。約30ページの序章を読むだけでも価値がある。
本書の特徴は、自然環境、都市環境、金融システム、個人(脳)、結核菌、テロ組織、電力網など幅広い分野についてレジリエンスに言及している点。例えば第1章では、インターネットや金融市場などを「頑強だが脆弱な(RYF:robust-yet-fragile)」なシステムと位置づける。予測される危険に対してはレジリエントだが、予期せぬ脅威にはきわめて弱い。これらのシステムの脆弱性を増幅するのは複雑さ、集中度、同質性であり、レジリエントを高めるのは適正な単純さ、局所性、多様性、透明性だと筆者は主張する。なかなか含蓄のある指摘だ。
クライマックスはハイチ大地震の救援プラットフォーム「ミッション4636」。インターネット、ボランティア、オープン・システムがグローバルに機能し、ハイチ大地震の被災者を世界規模で支援した組織だ。筆者はミッション4636が構築される過程を克明に描いている。ここで登場するリーダーは、従来型の豪腕タイプとはまったく異なっているのが興味深い。組織の各階層に自由自在に働きかけ、蚊帳の外におかれたグループを引き込み、関係者が互いに理解し合うための通訳を務めるリーダーという。いろいろと考えさせられる書である。
|
| |
|
|

|
2013年4月 |
漂白される社会
開沼博、ダイヤモンド社、p.488、\1890 |
2013.4.29 |
|
 |
元ライターで現在は東大の博士課程に在籍する社会学者の書。さすがにAERAや文芸春秋などで鍛えられただけあって、地に足の着いた社会論になっている。理屈をこねくり回し、すんなり理解できない内容の社会学の書籍とは一線を画している。教えられることの多い良書である。寡聞にして著者が『「フクシマ」論』で脚光を浴びたことを知らなかった。ちょっと楽しみな社会学者の登場である。
筆者は、人々が抱く個人的感覚と社会の実態に乖離が生じていることに着目する。現在の日本は社会の周縁部を「漂白」し、一般人の目から隔離する力が働いていると分析。つまり社会の至る所で、「周縁的な存在」から何らかの偏りや猥雑さ、すなわち「色」が取り除かれている。その結果として、本当は厳然と存在するにもかかわらず、社会的には「無いもの」「あってはならないもの」として隠蔽され、一般人は一見、平和で自由な生活を営んでいるというのが筆者の見立てである。漂白という表現は言えて妙で、社会の実態をうまく表現している。
筆者がフィールドワークの対象にしたのは、売春島、偽装結婚、ホームレスギャル、シェアハウス、違法ギャンブル、脱法ドラッグ、フィリピン人偽装結婚ブローカー、、高学歴の「中国エステ」経営者など12のテーマ。いずれも知られざる日本社会の裏側(貧困)を、足を使った取材で明らかにしている。しかも図を挿入して自らの見立てを分かりやすく解説しており、読者の理解を助けてくれる。
|
| |
鳥類学者 無謀にも恐竜を語る
川上和人、技術評論社、p.272、\1974 |
推薦! 2013.4.24 |
|
 |
文句なく楽しめる恐竜学の啓蒙書。ここ10年ほどの恐竜学の進展は目覚ましく、鳥類と恐竜の関係に対する見直しが進んでいるという。本書は鳥類学者である著者が、最新の研究成果とともに鳥類の祖先に当たる恐竜について縦横無尽に語る。軽妙な語り口も良いアクセントになっている。そもそも化石しか残っていてないので、筆者は想像力を大きく膨らませて恐竜の姿に迫っている。考古学と同様の楽しさがある。豊富なイラストとともに気軽に読める書なので、リラックスした休日にお薦めである。
鳥と恐竜の関係が科学的に裏付けられたのは2007年のこと。ティラノサウルスの骨から抽出したコラーゲンのアミノ酸の配列を分析した結果、分子生物学的に恐竜と鳥の類縁性が示唆されたという。このほか「恐竜の体の色は」「恐竜の歩き方は」「恐竜は鳴いたのか」「毒をもつ恐竜は存在したのか」「恐竜はなぜ絶滅したのか」などなど知的好奇心をくすぐる話題を次々に示しながら話を進める。なかなかの手練れである。注目したい研究者が表れた。
|
| |
赤塚不二夫のことを書いたのだ!!
武居俊樹、文春文庫、p.367、\650 |
2013.4.22 |
|
 |
赤塚不二夫の担当を35年にわたって務めた小学館の元編集者が、赤塚の日々のハチャメチャな生活やマンガにまつわる裏話、少年マンガの変遷などを紹介した書。古き良き編集者と作家の関係が描かれている。著者の赤塚への愛情があふれた1冊である。昭和30年代生まれの評者にとって懐かしいマンガ家とマンガが続々登場する。それだけでも本書は十分に楽しめるし、読む価値がある。ちなみに解説はやまさき十三が書いている。これも、なかなか味わい深い内容である。
筆者は小学館に入社し少年サンデーの編集部に配属になる。最初に赤塚の「お松くん」の担当になる。当時のサンデーでは、おそ松くんと藤子不二雄の「おばQ」、つのだじろうの「ブラック団」が看板連載だった。この下りを読むだけで、懐かしさでいっぱいになる。赤塚と寝食を共にした筆者だけに、本書では赤塚のさまざまなエピソードがてんこ盛りになって語られる。それに、高井研一郎(総務部総務課 山口六平太)、北見けんいち(釣バカ日誌)、古谷三敏(ダメおやじ)と並ぶアシスタントもすごい。
エピソードもすごい。小柄な赤塚が巨漢の梶原一騎を腕相撲で負かした話し、少年マガジンの「天才バカボン」をサンデーに引き抜いた事件、ヤクザに追われた逃亡生活などすさまじい。最後は崩れていく赤塚を、筆者は優しいまなざしで描いている。ちなみに筆者は、赤塚のほかにも古谷三敏、石井いさみ、あだち充などの担当編集者を務め、多くのヒットを飛ばした敏腕編集者である。
|
| |
リーダーを目指す人の心得
コリン・パウエル、トニー・コルツ、井口耕二・訳、飛鳥新社、p.349、\1785 |
2013.4.19 |
|
 |
ノウハウ本っぽいビジネス書にはさほど興味はないのだが、著者の名前に惹かれて購入。コリン・パウエルといえば、湾岸戦争で米統合参謀本部議長、ブッシュ政権で国務長官などを歴任し、1996年の大統領選挙に出馬していれば当選確実とも言われた人物である。人望や見識に優れているといわれるパウエルが、どういったリーダー論を展開するのか興味津々で買い求めた。有名な「13カ条のルール」は粒度に差があり今一歩だが、興味深いのは経験談の数々。パウエルが感情をあらわにしている部分が登場し興味深い。万人向けの書とはいえないが、米国のベスト・アンド・ブライテストを知るうえで貴重な情報を与えてくれる。
パウエルは本書で6章に分けて仕事論と人生論を披露する。「コリン・パウエルの13カ条のルール」「己を知り、自分らしく生きる」「人を動かす」「情報戦を制する」「150%の力を組織から引き出す」「人生をふりかえって」だ。これらの章で貫かれてるのは、多くの人との関わりである。特にレーガン大統領やダイアナ妃とのエピソードもなかなかいい。
冷静な印象が強いパウエルだが、本書には怒りをぶつける個所がある。国務長官として2003年2月に行った「イラクの大量破壊兵器保有」を指摘した国連演説の関する下りだ。こう安全保障委員会で演説したものの、大量破壊兵器はいっこうに見つからない。そもそも証拠をよく調べてみれば、信頼できない情報源に基づいたCIAからの報告をはじめ、信憑性に問題があった。満天下に向かって嘘をついたことになったのだ。パウエルは、嘘つき呼ばわりするブロガには心穏やかでないことを明らかにするとともに、問題に気づかなかった自らに怒りをぶつけている。
|
| |
完全なるチェス~天才ボビー・フィッシャーの生涯~
フランク・ブレイディー、佐藤耕士・訳、文藝春秋、p.525、\2625 |
2013.4.16 |
|
 |
チェスに詳しくないので、本書の主人公で元世界チャンピオンのボビー・フィッシャーについてはまったく知らなかった。本書は、そのフィッシャーが波乱に富んだ人生を丹念に追った評伝。日本との関係をはじめ、へ~っという逸話がてんこ盛りで実に面白い。フィッシャーがIQ180の天才であると同時に変わり者だったのは間違いないところだが、マスメディアによって誇張されていたのも事実である。筆者はKGBやFBIのファイル、手紙などを読み込むとともに数百人にのぼる関係者に取材することで実像を描いている。500ページを超える大著なので、さすがに一気に読み通す訳にはいかないだろう。ゴールデンウィークなど比較的長く休めるときお薦めしたい。
フィッシャーの生涯は波瀾万丈である。13歳で米国チャンピオンになり、さらに冷戦下で国家の威信をかけたソ連のチェスプレイヤーとの闘いに勝ち世界チャンピオンになったものの、奇行や反米・反ユダヤ的な言動、失踪、極貧の生活、日本での潜伏生活と逮捕、法改正まで行ったアイスランドへの移住など後半生の転落は凄まじい。
チャンピオン後に10億円超のファイトマネーを提示された防衛戦を拒否し失踪する。再び姿を現すまでに20年の空白期間がある。1992年に姿をみせ宿敵と対局し勝利をおさめたものの、再び失踪。次に登場するのは何と成田空港である。米国が経済制裁を行っていたヘルツェゴビナで対局したことが原因で、米国政府の要請によって逮捕されたのだ。常人には理解しがたい行動の数々だ。ちなみに、フィッシャーを「チェスの世界のモーツアルト」にたとえる羽生善治の解説が巻末に掲載されているが、これがなかなかな秀抜である。
|
| |
統計学が最強の学問である~データ社会を生き抜くための武器と教養~
西内 啓、ダイヤモンド社、p.320、\1680 |
2013.4.15 |
|
 |
ビッグデータへの関心の高さが影響したのか、あるいは刺激的な書名や挑発的な語り口が奏功したのか分からないが、ベストセラーになっている書。統計学が最強な理由について研究成果と事例をたくみに用いながら論じている。帯には「入門書」とあるものの、ハッキリ言って難しい。評者は大学の教養で統計学を履修したが、それでも後半部は少々辛い。統計学について何の知識もないと、読みこなすのは骨だろう。もっとも前半を読むだけでも、十分に読者と筆者の目的は達せられるように思う。時代が要請した書籍なのは間違いないので、進めるとこころまで読み、分からなくなったら諦めることをお勧めする。
前半部では威勢のいい文言がぽんぽん飛び出す。「統計学を制する者が世界を制する」「統計学は最善最速の正解を出す」「すべての学問は統計学のもとに」「これから10年で最もセクシーな職業」などと筆者は自信満々だ。本書の読むことの意義や重要性を読者に徹底的に刷り込む。紅茶やコレラの話など、事例の使い方も秀逸である。ビッグデータがもて囃されるなか、何が知りたいかを明確にすればスモールデータで十分と言い放つ切れのよさも筆者の持ち味である。
ちなみに本書が扱うのは大きく六つの分野。具体的には、社会調査法、疫学・生物統計学、心理統計学、データマイニング、テキストマイニング、計量経済学について解説している。
|
| |
焼かれる前に語れ~司法解剖医が聴いた、哀しき「遺体の声」~
岩瀬博太郎、柳原三佳、WAVE出版、p.240、\1575 |
2013.4.9 |
|
 |
千葉大学 法医学教授の司法解剖医とノンフィクション作家が日本における検死制度の問題を告発した書。日本で発生する年間15万体の「変死体」のなかで、司法解剖されるのはわずか5000体に過ぎない。変死体は多くの場合、病死で片づけられてしまう。暴行死や保険金殺人、子供の虐待死、医療ミスによる死亡なのに病死で済まされることが少なくないことを、誤認の事例を数多く挙げて明らかにする。教えられることの多い書である。
日本の検死体制はあまりにも貧弱というのが著者の主張だ。人員や予算、施設の不足、法整備が遅れおり、検死や解剖現場は崩壊寸前だと警鐘を鳴らす。死体解剖に対する国家予算は貧弱で実費さえ出ない。この結果、薬物・毒物の検査ができない、鑑定書が書けない、すべての部位を解剖したことにしたり臓器を保管せずに採算を合わせる、鑑定医が少なく鑑定の質を担保できないといった事態を招いている。日本の現状は惨憺たる状況である。
しかも都道府県によって法医解剖の比率に大差がある。県に行政解剖の予算がないという理由から、死因究明のための検査を経ず荼毘に付されてしまう。死者の人権はすっかり無視される。筆者は、国家や法制度、警察といった権力だけではなく、遺族への思いやりに欠け傷つけている、自らが属する司法解剖医の問題点も指摘する。
|
| |
言語の社会心理学~伝えたいことは伝わるのか~
岡本真一郎、中公新書、p.277、\924 |
2013.4.7 |
|
 |
話し言葉は「文字通り」には伝わらないことを、具体的な事例を挙げながら社会心理学の観点から論じた新書。親しい間柄では話していないのに真意が伝わることや、逆に親しくないと丁寧に説明しているのに誤解されるといったことは、多くの方が体験しているだろう。本書は、こうした言葉にまつわる日常的な体験を社会心理学の知見や実験結果をもとに解き明かす。ごく日常的は話なので目から鱗が落ちるといった驚きはないが、言葉の面白さを感じさせてくれる1冊なのは間違いない。
全体に驚きの少ない書だが、対人関係と言葉についての考察はなかなか読ませる。特に盛り上がるのは終章「伝えたいことを伝えるには」である。たとえば、フィードバックに非言語的チャネルを利用する、日常語に専門の意味がある語には誤解のおそれがある、ことさら易しく言うのも混乱の元になる、謝罪はまとめて行う、余計な弁解は印象を悪くするだけ、などなどだ。会話の勘所を押さえており、この部分を読むだけでも価値がある。
|
| |
リスク化される身体~現代医学と統治のテクノロジー~
美馬達哉、青土社、p.252、\2520 |
2013.4.4 |
|
 |
タイトルと中身に少しギャップがある書。なぜ「リスク」という言葉がさまざまな領域で使われ注目されるようになったのかを、医療・医学領域の状況から解き明かそうと試みた書。なかなかチャレンジングなテーマ設定であるし、ある程度は成功している。例えば筆者の本職である医療・医学分野に関する考察はなかなか鋭く読み応えがある。その一方で、医療・医学以外にまでスコープを広げた議論は、残念だが著者の思い入れが空回りしている。地に足が着いていない議論が多く、説得力が今一歩だ。
筆者の言う「リスク化される身体」とは、物理的な人間の身体ではなく、検査数値や行動パターン、心理学的特性、ライフスタイルなどのリスクによって数値化された心身情報の集合体を指す。病気や健康への対処方法が原因を取り除く臨床的なアプローチから、確率論的な予防医学(リスクの医学)へとシフトしているという現状認識を示す。従来の臨床医学とリスクの医学を対比した議論は切れ味が鋭く読み応えがある。
筆者はリスクの医学に懐疑的なスタンスをとる。リスクの医学では、症状や病気の有無とは無関係に、公衆衛生的な疫学研究によって見出されたリスクやリスクの組み合わせが、将来の疾病発生と関連するかどうかが重要になる。代表例がメタボリックシンドロームだ。国によってメタボリックの基準が異なっており、リスクの設定が恣意的になっていると指摘する。
|
| |
|
|

|
2013年3月 |
日本人のための世界史入門
小谷野敦、新潮新書、p.271、\819 |
2013.3.28 |
|
 |
ちょっと変わった世界史読本。“暗記”教科になっている世界史教育の現状を嘆く筆者は、世界史を物語として縦横無尽に展開する。評者のような歴史好きが空き時間に気軽に読むのに向くである。
筆者は、古代ギリシアから現代までの3000年を対象に蘊蓄を傾けながら語る。新書なので深さはないが、世界史をざっと知ることができる。ある意味で言いたい放題であり、筆者の思想や思い入れが強く出ている。「浮世絵は低俗文化」「小乗仏教ではなく上座部仏教だと教える学者に我慢ならない」「スイスは、スイス銀行を使って世界の裏金を預かるなど、国際倫理を顧みないことで成り立っている」といったフレーズがあちらこちらに登場する。ちなみに本書の特徴の一つが、筆者による書評と映画評になっていることだ。お薦めの書籍や映画、テレビドラマを世界史と関連付けながら論じている。筆者の博覧強記ぶりがよく分かる。
|
| |
ディジタル作法~カーニハン先生の「情報」教室~
ブライアン・カーニハン、久野靖・訳、オーム社、p.288、\2310 |
2013.3.26 |
|
 |
ブライアン・カーニハンとデニス・リッチーといえば「プログラミング言語C」である。評者が組み込みエンジニアだったころ、C言語の教科書といえばこれだった。本書は、カーニハンがディジタル社会と情報技術について最低限知っておくべき事柄を分かりやすく解説する。プリンストン大学の講義「Computers in Our World」がベースになっており、文系の学生がコンピューティングに関する新聞記事を読んで理解し、新聞記事が正しくなければ指摘できるレベルを目指したという。
本書は3部構成をとる。ハードウエア、ソフトウエア、コミュニケーションである。ハードウエアの章では、コンピュータの構造、ビットとバイト、CPUの中身について解説する。過不足なく説明しており、頭の中の整理に役立つ。ソフトウエアについては、アルゴリズム、プログラミングとプログラミング言語、OSとファイルシステムなどをカバーする。プログラミング言語では、JavaScriptについて説明を加える。コミュニケーションの章では、ネットワーク(モデム、DSL、無線LAN、携帯電話など)、インターネット、WWWについて解説する。
|
| |
調理場という戦場~「コート・ドール」斉須政雄の仕事論~
斉須政雄、幻冬舎文庫、p.283、\630 |
2013.3.15 |
|
 |
三田にある有名フレンチ・レストラン「コート・ドール」のオーナーシェフ・斉須政雄が、フランスでの修行時代の思い出や料理哲学を綴った書。料理哲学は人生哲学につながっており、含蓄のある内容が豊富で読み応えがある。エピソードの一つひとつが味わい深く、読み終わったあとに満足感が残る。万人向けの内容だが、とりわけ若い方にお薦めしたい。ちなみに本書を推薦してくれたのは、京都・三条京阪近くの中華レストランのシェフ。もともと東京で自動車のセールスマンをしていた彼が料理の道に進んだのは、本書から影響を受けたからという。確かに、それだけのパワーを秘めた良書である。
筆者の斉須は23歳でフランスに渡る。来日したフランス人シェフに誘われて修行に出るのだが、選ばれたキッカケについてのエピソードが“ちょっといい話”である。フランスに行くものの、フランス語は話せず、最初の住まいは屋根裏部屋。厳しい環境からスタートするが、数軒のレストランで修行し腕を磨く。食はもちろん“住”についての考え方は少々ユニークで興味深い。レストランの個性的なオーナーたちの仕事ぶりやビジネス観、同じ職場で働く料理人たちとの確執など楽しめる。本書を読むと、会社の近くにあるコート・ドールの厨房をちょっとのぞいて見たくなってしまう。
|
| |
エリア51~世界でもっとも有名な秘密基地の真実~
アニー・ジェイコブセン、田口俊樹・訳、太田出版、p.536、\2520 |
2013.3.15 |
|
 |
ラスベガスの北120kmにある軍事施設エリア51の謎に、ジャーナリストが迫ったノンフィクション。エリア51の存在を米政府は認めておらず、地図にも載っていないという。このエリア51をめぐる最大の話題は、UFOの墜落と宇宙人の遺体回収で知られる「ロズウェル事件」。筆者は、エリア51近郊に住んだり、勤務していた関係者、エリア51で進めされたプロジェクトに参加した科学者たちの証言をもとに、ロズウェル事件だけではなく数々の謎を解明していく。
本書の取り上げる話題は豊富である。特に1947年に起こったロズウェル事件の謎解きは刺激的で、この部分だけでも本書を読む価値はある。そのほか、スチルス偵察機、無人偵察機、大気圏核実験、ミグ戦闘機のリバースエンジニアリングと墜落、プルトニウムを使った人体実験、月面着陸捏造など、東スポ的な話題は尽きない。米ソ冷戦時代の米国とソ連の駆け引きがよく分かるし、ナチスドイツの技術の高さを改めて知らされる内容になっている。
ちなみに米国政府は軍事施設エリア51について、ほとんど情報を公開しない。公開しても黒塗りの場合が多く、得られる情報は限られている。米国大統領さえ「情報適格性がない」として拒絶されるなど、情報管理は徹底していえる。その黒幕は、原子力委員会というのが筆者の見立てだ。
牽強付会な部分もあるが、ゴシップ記事を読むのと同様の楽しさを味わえる書である。暇つぶしにピッタリだが、行間が狭く1ページにぎっしり文字が詰まっているし500ページを超える分量があるので、新幹線で東京-大阪間で読み終えるのは辛いかもしれない。
|
| |
オープン・サービス・イノベーション~生活者視点から、成長と競争力のあるビジネスを創造する~
ヘンリー・チェスブロウ、博報堂大学 ヒューマンセンタード・オープンイノベーションラボ・監修、TBWA博報堂・監修、阪急コミュニケーションズ、p.304、\2310 |
2013.3.7 |
|
 |
サービスをオープン化してイノベーションにつなげ、コモディティ化による価格競争に陥らないための方策と事例を紹介した書。オープン・イノベーション研究の第一人者の筆者が、対象をモノからサービスに広げ論考を加えている。オープン・イノベーションによって顧客とサービスを共創することで、持続可能なビジネスモデルが生まれ、コモディティ化の陥穽から脱出が可能になるというのが筆者の主張。経済がサービス化を強めるなか、示唆に富む指摘が多い書である。
筆者はオープン・サービス・イノベーションの位置づけと必要性から説き始める。コンセプトを明らかにするとともに、フレームワークについて論じる。モノは使われることで消耗し価値が下がるが、知識(サービス)は使われることによって知見がたまり価値は高まる。社外を巻き込むことで、社内では得られなかった知見がたまりイノベーションにつなげられる。このあたりの議論は説得力がある。
米国の書らしく、米Xeroxや米GEアビエーション、米メリスリンチ、オランダのKLMオランダ航空、米Amazonなど事例が豊富。ピックアップしているのは先進国の大企業ばかりではない。新興国や中小企業も事例として挙げる。例えばスペインのレストラン「エル・ブリ」の事例も興味深い。1年の半分しか店を開かない。残りはレシピ開発に費やす。しかもレシピのアイデア外部研究機関から得ている。
|
| |
昭和という時代を生きて
氏家齊一郎、塩野米松(聞き手)、岩波書店、p.304、\2520 |
2013.3.5 |
|
 |
日本テレビの前会長・氏家齊一郎のオーラルヒストリー。本書は、渡邉恒雄や網野善彦、石原慎太郎らとの交遊、共産党や演劇との関わり、歴史観、朝日新聞と読売新聞との対比などを語っている。ちなみにナベツネは、高校時代から友人で読売新聞の記者としても同じ釜の飯を食った間柄である。本書はスタジオジブリ発行の小冊子に掲載されていた連載記事がベースになっており、内容の冗長さと繰り返しが少々気になる。
本書を読み始めて辟易とさせられるのが氏家のエリート意識。ここで嫌になって止めてしまう方も多そうだが、もう少し我慢して読んでも損はない。インタビュイーである氏家の人柄がストレートに表れており、ある意味で貴重である。聞き書きの効果とインタビュアーである作家・塩野米松の力量が発揮された書ともいえる。読み進んでいくと、人物評や歴史観など得るところもある。
|
| |
デフレーション~日本の慢性病"の全貌を解明する~
吉川洋、日本経済新聞出版社、p.236、\1890 |
2013.3.1 |
|
 |
デフレーションの多角的に論じた書。最近話題のアベノミクスだが、肝はデフレ経済を克服するための金融緩和措置である。本書はアベノミクスの理論的裏付けとなる貨幣数量説を歴史を踏まえ徹底的に批判している。時宜を得た書といえる。本書を読むと、「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という格言をつい思い起こしてしまう。
評者は中学校時代に、デフレは起こらないと習った覚えがある。そのデフレに日本は陥った。筆者は冒頭でデフレについての問題意識についてこう述べる。「戦後、先進国が経験したことにないデフレーションに、なぜ日本は陥ったのか。田の国々では低インフレとはいえデフレではないのに、なぜ日本だけがデフレなのか。デフレを止めるには何をなすべきなのか、するべきだったのか。ゼロ金利の下でも、貨幣数量を増やせば、デフレは止まるのか」。本書は専門的な部分もあるが、全体的には平易に経済学を解説している。数式を使った理論の部分は読み飛ばしても支障はない。
|
| |
|
|

|
2013年2月 |
機械との競争
エリク・ブリニョルフソン、アンドリュー・マカフィー、村井章子・訳、日経BP社、p.176、\1680 |
推薦! 2013.2.26 |
|
 |
日経の朝刊や東洋経済などに取り上げられ、ちょっと話題になっている書。テクノロジー(主に情報技術)が雇用、技能、賃金、経済に及ぼす影響を、米MITスローン・スクールの教授と研究者が論じている。そもそも2011年に自費出版された200ページに満たない本だが、中身は濃い。すでに多方面で論じられている内容も含まれているものの、まとめて読むと情報技術の雇用や経済に及ぼすインパクトの大きさがよく分かる。多くの技術者の方にお薦めした1冊である。
人間はすでに技術に後れをとっている。コンピュータとの競争に人間が負け始めており、これが雇用が回復しない原因だと著者は主張する。確かに米Googleの技術は週百kmの自動運転を可能にしているし、米IBMの機械翻訳ソフトはリアルタイムで正確な応対を実現する。いつのまにか技術は不可能だと思われていたタスクをこなすようになっている。では、これからの労働はどうなるのか。筆者はスキルの高い層と低い層が生き残ると断じる。高い層は分かるが、低い層(肉体労働)は体の動きと知覚を上手くこなす必要があり機械には真似ができない。職を奪われるのは中間層の人材である。
筆者は本書の最後に、技術の後れをとらないための19か条を挙げる。教育、起業家精神、投資、法規制・税制といった視点から論じており、示唆に富む指摘が多い。
|
| |
幸福度をはかる経済学
ブルーノ・S・フライ、白石小百合・訳、エヌティティ出版、p.290、\3570 |
2013.2.25 |
|
 |
幸福関連は評者が好んで読むジャンルである。この書評でも、「幸福の方程式」「日本の幸福度」「幸福の研究」などを取り上げた。本書は、これらのなかで最もアカデミックな1冊である。幸福度を測る研究の成果と新たな展開をまとめるとともに、政策との兼ね合いに言及している。センセーショナルに幸福度を扱うのではなく、調査データや学術論文を用いながら慎重に議論を進めているところに好感が持てる。内容的に一般向けとは言えないし日本語訳も少々堅いが、編集者によってシッカリ作られた良書といえる。
幸福度の経済学は、標準的な経済学の理論と大きく異なっている。定量化(計測)の方法が違うし、家族など社会的な関係や自立の有無といった要素を織り込んでいる。筆者は、「標準的な経済学の理論では、人間の幸福への理解が不足している」と所長する。例えば、標準的な経済学は所得を重視した政策を推しがちなのに対し、幸福度を加味した政策では雇用(労働)と余暇に重きを置くことになると筆者は主張する。幸福経済学はまだ発展途上だが、今後の発展と実際の政策への適用が期待されるところだ。
筆者は、失業やインフレ、格差、民主主義、結婚、離婚、テレビ、テロなどについて幸福度の研究成果を披露する。例えば所得の増加が幸福度に与える影響は限定的で、幸福感はすぐに醒める。これに対して失業による影響はより大きく、しかも持続的。自営業者と被雇用者では前者の方が幸福という指摘は分かる気がするが、ボランティアが人間を幸福にするという視点は新鮮である。
|
| |
ぼくらの近代建築デラックス !
万城目学、門井慶喜、文藝春秋、p.197、\1628 |
2013.2.20 |
|
 |
2人の作家が大阪、京都、神戸、横浜、東京の5都市の近代建築を訪ね、思い思いに批評した書。来歴や建築家などについて数々の蘊蓄が語られ、読んで楽しい。建築物好きで、5都市のうち大阪、京都、横浜、東京の四つに住んだことのある評者にはたまらない。残る一つの神戸には住んだことこそないが、お隣の明石で4年半過ごしたので馴染みの土地である。建築物好きにお薦めしたい。
それぞれの建築物について住所と地図を掲載されおり、訪ね歩くときのガイドブックとして使える。残念なのは、判型を小さく、写真の扱いが中途半端なのこと。写真集にする手もあったと思うが、価格を考えると仕方がないのかもしれない。
大阪城の天守閣や京大の時計台、東京駅など、多くの方が知っている近代建築もあれば、知る人ぞ知るといったものもある。住んだことのある土地が多いので、評者がよく知る建物がずらり並び実に懐かしい。行ったことのない建物では神戸の御影公会堂が魅力的。でぜ訪ねてみたい。
|
| |
さらば国策産業~「電力改革」450日の迷走と失われた60年~
安西巧、日本経済新聞出版社、p.286、\1680 |
2013.2.18 |
|
 |
新聞記者らし丹念な取材で、日本の電力会社と原子力政策を徹底的に批判した書。「既得権益を守る」体制の強固さを浮き彫りにしている。歴史的な背景を明らかにしたり、海外の電力事情を紹介したりと、バランスのよい構成になっている。全体に考えさせられる指摘が多いので、原発問題や電力問題に関心のある方にお薦めである。
|
| |
訣別 ゴールドマン・サックス
グレッグ・スミス、徳川家広・訳、講談社、p.458、\1995 |
2013.2.7 |
|
 |
筆者は、20代後半でバイス・プレジデントに就くなど、若くしてゴールドマン・サックスの幹部に昇進したエリート。本書は、筆者がスタンフォード大学在学時代のインターン経験から、リーマンショック以降に拝金主義がはびこるようになった社風に疑問を抱いて退社するまでを詳細に描いた手記である。ウォルストリートの住人たちの生態を余すことなく描いており、米国の金融業界に関心のある方には必読の1冊といえる。特に上司との関係やオフタイムの生活の描写は興味深い。逆にウォールストリートに関心がない方には、400ページを超える大著なので読み進むのが苦痛かもしれない。
筆者が入社したのは同時多発テロ発生直前の2001年。当時のゴールドマン・サックスには、「長期的に貪欲であれ」と、顧客の利益を優先することが長期的には会社のためになるという考え方が残っていたという。ところがリーマンショック以降は、ボーナス至上主義が蔓延し、短期的な利益に飛びつく社風に変わっていった。社員は上層部から新入社員まで顧客を食い物にする状態だった。例えば新人アナリストが顧客を「マペット」と呼び、好きかってに操れる対象と見くびり、自分よりも知性の劣った人間として扱うまでになる。顧客の世話を焼く受託者責任感の強い営業マンは絶命危惧種だと、筆者は言い切る。
こうした状況に筆者は12年間勤めたゴールドマン・サックスを辞めることを決意する。同時に、退社するまでの経緯を綴った手記「Why I Left Goldman Sachs」(タイトルは本書と同じ)を米ニューヨークタイムズ紙に寄せる。この手記は、筆者の退社直後の2012年3月14日に掲載される。この手記に大幅に加筆したのが本書である。
|
| |
秋葉原、内田ラジオでございます。
内田久子、廣済堂出版、p.183、\1365 |
2013.2.7 |
|
 |
本書に触発され、この日曜日に秋葉原ラジオセンター2階「内田ラジオ」に立ち寄った。ラジオセンターにはそこそこお客さんはいたものの、内田ラジオに人影はない。店内に並ぶクラシカルなラジオやパーツは興味深く拝見したが、残念ながら筆者である店主・内田久子さんの姿は見えなかった。本書は大正15年生まれの内田さんの自伝だが、ラジオパーツの店主にこんな人生があったとは驚愕だ。電気街全盛の古き秋葉原を懐かしく思い出す方は必読である。ただし秋葉原の昔話だけを期待しては失望するかもしれない。「そんなこともあったなぁ」と昭和という時代全体を懐かしむのに向く。
慶長5年が開湯した箱根・塔ノ沢の温泉旅館「環翠楼」に生まれた筆者。環翠楼の名前は伊藤博文がつけるなど由緒ある名旅館である。子供時代の思い出に始まり、パイロットだった父親の教え、2.26事件の記憶、東京裁判の傍聴、連合赤軍が起こしたダッカ事件の飛行機のパイロットだった長兄から聞いた裏話、ナムジュン・パイクら文化人との交流など、興味深い話が次々に登場する。波乱の人生といった感じではないが、深みを感じる逸話が多い。
夫の内田秀男の話も実に面白い。NHK技研の技師だった内田は根っからのラジオ技術者で発明家。その縁が秋葉原の内田ラジオへと続く。ちなみに内田は超常現象に興味を持ち、「オーラメーター」や「イオンクラフト円盤」といった研究でTVにも頻繁に出演していたという。
|
| |
ニュートンと贋金づくり~天才科学者が追った世紀の大犯罪~
トマス・レヴェンソン著、寺西のぶ子・訳、白揚社、p.336、\2625 |
2013.2.5 |
|
 |
アイザック・ニュートンといえば古典力学。科学者としての突出した業績がすぐに頭に浮かぶ。そのニュートンの王立造幣局官僚としての知られざる姿を紹介したノンフィクション。ミステリー仕立てで、贋金づくりの主犯ウィリアム・チャロナーとニュートンとの虚々実々の駆け引きを、膨大な資料と調査に基づいて詳細に描いている。17世紀のロンドンを中心とした時代背景を含め、興味深い話が満載でわくわくしながら読める。まさに「事実は小説より奇なり」である。
本書が扱うのは17世紀の英国を揺るがした贋金事件。粗悪な銀貨が流通し、英国の貨幣制度の信用は地に落ちた。この状況を打開することに手腕を発揮したのが、大学教授を経て王立造幣局監事に就いたニュートンだ。大学時代に錬金術に精力的に取り組んだニュートンも意外だが、行政に辣腕を振るう姿も想像しづらい。ニュートンがまず取り組んだのが粗悪な銀貨を駆逐するために改鋳。これが奏効し、瞬く間に悪貨を駆逐した。
次が贋金づくりの主犯チャロナーとの闘いである。当局の必死の捜査を巧みにくぐり抜けていたチャロナーを追いつめていく過程は読み応え十分。いかにも科学者らしい綿密な戦略を実践し、包囲網を狭めていく。そして、ついにチャロナーを刑場に送る。この功績が認められニュートンは造幣局長官にまで登り詰め、その後27年間にわたってその地位にとどまり巨額の資産を築く。ニュートンの知られざる実像を本書は描いている。
|
| |
|
|

|
2013年1月 |
アナタはなぜチェックリストを使わないのか?~ミスを最大限に減らしベストの決断力を持つ!~
アトゥール・ガワンデ著、吉田竜・訳、晋遊舎、p.239、\1680 |
2013.1.31 |
|
 |
ミスを減らす上でのチェックリストの重要さを、医師でありジャーナリストの筆者が自らの体験も含め具体例を用いて説いた書。本書が挙げる事例は多彩である。パイロット、医者、建築家、料理人、などなど。チェックリスト作成時の勘所も伝授する。さほど特異な内容ではないが、事例に説得力があり全米で30万部を超えるベストセラーになったのも頷ける。危機管理に興味のある方にお薦めである。
筆者は知識の量と複雑性は、一個人が安全かつ確実に活用できるレベルを超えているという。この結果として、大半の失敗は怠惰のせいではなく、必死の努力にもかかわらず発生する。人間の記憶力と注意力には限界がある。しかも人間には手順を省く誘惑がつきまとう。ずっとこの手順を省いてきたけれど一度も問題が起きたことはない、と。でも、いつかは問題が生じる。こうした状況に対処し、適切な判断を確実に下す方法がチェクリストだと断言する。
|
| |
幸福の方程式~新しい消費のカタチを探る~
山田昌弘、ディスカヴァー・トゥエンティワン、p.238、\1050 |
2013.1.29 |
|
 |
パラサイト・シングルや格差社会を提唱した社会学者と電通のチームハピネスが見出した「成熟社会における幸福の条件」。高度成長期からバブル期までは、幸福というものが、物質的豊かさを求める消費活動と結びついてきた。モノを買うことに幸せを見出してきたのだ。しかし成熟時代に至り、日本は消費不況の時代を迎えた。今の時代に消費と幸福の関係はどうなっていくのか。物質的な豊かさを超えた幸福の形があり得るのか。あり得るとしたら、それはどのようなものなのか。本書はこうした問題意識のもと、新たな幸福の物語を説いた示唆に富んだ書である。コンパクトにまとまっており、多くの方にお薦めしたい。
|
| |
秘密戦争の司令官オバマ~CIAと特殊部隊の隠された戦争~
菅原出、並木書房、p.263、\1680 |
2013.1.28 |
|
 |
ノーベル平和賞を受賞したバラク・オバマが率いる政権が繰り広げる特殊部隊を使った対テロ対策、無人機を使った暗殺作戦、サーバー攻撃による敵の重要施設の破壊・妨害工作などを暴いたノンフィクション。この書評で取り上げた「外注される戦争―民間軍事会社の正体」「戦争詐欺師」の著者・菅原出の最新刊である。戦争専門のジャーナリストの手によるノンフィクションとあって読み応え十分だ。
筆者は、ブッシュ政権時代に始められた多くの政策を引き継ぎ、さらに攻撃的に拡大、発展させたのがオバマ政権だと位置づける。ブッシュの秘密作戦のプログラムを劇的に拡大させ、秘密の戦争をエスカレートさせたという。本書はまず、オサマ・ビン・ラディン暗殺計画を詳細に紹介する。オバマの居場所を捕捉するまでの過程や、どのように暗殺が実行されたのかを明らかにしている。
さらにアフガニスタンの占領政策とその失敗について、アフガニスタンの国内事情とともに詳細な説明を加える。中国やパキスタン、アフガニスタンの複雑に絡まった裏事情に触れることができ、なかなか刺激的である。本書で出色なのは、アフガニスタンやパキスタンの事情通やキーマンへのインタビューである。けっして新聞には登場しない面々であり、戦争ジャーナリストとしての面目躍如といったところだ。
|
| |
2050 老人大国の現実~超高齢化・人口減少社会での社会システムデザインを考える~
小笠原泰、渡辺智之、東洋経済新報社、p.289、\1890 |
2013.1.24 |
|
 |
高齢者が1000万人を超える2050年の日本。団塊ジュニアが後期高齢者期に入り終える時期である。実質GDPは現在より4割落ち込む。団塊ジュニアは団塊とそれ以前の世代の資産を食いつぶし貧困に陥る。その結果、2050年には国税収入のほとんどを貧しい高齢者の生活保護で使い切ってしまう。こうした否応なくやってくる2050年を想定したときに、在るべき社会保障制度の姿を大胆に論じた書である。
筆者が展開する社会保障制度はあまりにドラスチック。劇薬だし、議論に粗さが目立つのも確かである。筆者のプランが実行される可能性はきわめて小さい。しかし、劇薬を処方しなくてはならないほど今の日本が罹っている病は重い。筆者の危機感がびしびし伝わってくる警世の書であり、筆者の意見に耳を傾けるのは悪くない。
本書はまず現在の社会保障制度を槍玉に挙げる。持続的な経済成長を前提にした楽観的議論に終始している政治家と官僚のまやかしを批判する。甘言を弄しながら、昔と同じことを手を替え品を替え「緊急経済対策」として繰り返し財政赤字を積み上げる政策を、雨乞いをする祈祷師と同じだと語る。この辺りの議論の展開はなかなか鋭い。
筆者は、福祉国家からナショナルミニマル国家への転換が不可欠だと断じ、在るべき社会保障システムのアウトラインを描いている。ナショナルミニマルとは、各人が幸せになるための最低限のサービスを提供・維持する社会である。つまり最大公約数的なレベルにまで国家の役割を絞り込む。これまでの最小公倍数的な政策とは真逆であり、現在の公的年金制度を清算し、生活保護を見直すことが欠かせないと筆者は主張する。
|
| |
ファスト&スロー(下)~あなたの意思はどのように決まるか?~
ダニエル・カーネマン、村井章子・訳、早川書房、p.350ページ、¥2205 |
2013.1.22 |
|
 |
行動経済学を日常生活に則して解説した書の下巻。「損失は同等の利得よりも強く感じる」というプロスペクト理論だけではなく、つい頷きたくなる事例が多く、上巻に負けず劣らず興味深い内容である。意思決定の際に、我々が陥りやすい罠の数々を紹介し、懸命な選択をするためのヒントを与えてくれる。もっとも、頭で分かっていても落とし穴にはまるのが人間なので、本書を読んでも即効性はないかもしれない。しかし頭の片隅に入れておくのは悪くないだろう。上下2巻の大著だが、行動経済学に興味のある方々に強くお薦めしたい。
本書を読むと、我々の意思決定が認知バイアスに左右され、いい加減で誤りがちになるのがよく分かる。たとえば、一度立てた計画に引きずられ(アンカーになり)、正常な判断ができない。自分がしたいことやできることばかりを見て、他人の意図や能力を無視する。幸運がもたらす役割を無視し、自分の能力で結果を左右できると思い込む。自分の知っていることを強調し、知らないことを無視する。その結果、自分の意見に自信過剰になる。自らを省みたり周囲を見渡すと、思い当たる節が多くありそうだ。
著者は長期的な結果を伴う決定を下す際の心がけを披露する。「徹底的に考え抜くか、でなければいい加減にざっくり決める」というのが筆者の流儀だ。中途半端に考えるのはいけない。ことが起きたときに「あのときもう少し考えれば、もっといい決断を下せたのに」と後悔する。人間は実際に感じる以上に深い後悔を予測しがちである。実際は後悔するにしても、いま考えるほど酷くないという。
|
| |
レッドアローとスターハウス~もうひとつの戦後思想史~
原武史、新潮社、p.396、\2100 |
2013.1.18 |
|
 |
この書評で2008年に取り上げた「滝山コミューン 1974~戦後とは何か? 自由とは何か?~」の著者が、対象を同じく西武沿線のひばりが丘団地に移して戦後の政治社会を追った書。西武沿線、東急沿線、中央線沿線を随時比較しながら話を進める。滝山コミューンの主役は全共闘世代の教員と滝山団地に住む児童、その母親たちが中心となって作った地域共同体だったが、本書は共産党と堤康次郎、住民運動を軸に当時の世相を描いている。「滝山コミューン」と同様、「そんなこともあったねぇ」と右肩上がりでバイタリティにあふれていたあの頃を思い出したい方にお薦めである。
タイトルになっているレッドアローとスターハウスとは何か。前者は西武鉄道が池袋-秩父間を走らせた特急電車の名称である。後者は日本住宅公団が作った星型(Y字型)の外見を持つ住宅のこと。いずれも乗客や応募者があふれるほど人気を博したという。この二つを象徴に、西武沿線の戦後思想史を浮き彫りにする。
本書が扱う世相は多岐にわたるが、大きく西武鉄道(堤康次郎)と東急電鉄(五島慶太)の対比、共産党の興隆と衰退、住民運動、反米活動、モータリゼーション、流通(デパートやスーパー)の進展、レクリエーションといったところである。いずれもあの時代を感じさせ懐かしい。
|
| |
Imagine: How Creativity Works
Jonah Lehrer、Houghton Mifflin、p.279、$26 |
2013.1.14 |
|
 |
集中して読む時間がとれなかったこともあり、読了するまで半年もかかってしまった。WIREDの編集者である筆者は、イマジネーションとは何か、どこから生まれるかについて、古今東西の事例をひきながら論じる。この手のビジネス書の常連である米3Mや米P&G、米Pixarといった企業だけではなく、音楽家や作家、起業家など事例は多岐にわたり読み応えがある。Nikeの有名なスローガン“Jus Do It”や I・NY キャンペーンのアイデアが生まれたキッカケなど、興味深い話が満載である。2012年春にNew York Timesのベストセラー欄に数週間にわたって顔を見せていたのが納得できる良書だ。日本語訳が出ていないのが、少々不思議に思えてくる。
イマジネーションは必然であり、けっして偶然ではないというのが筆者の基本的な考えである。イマジネーションにつながる環境を作ることは可能だし、病気やドラッグ、スランプ、執着心といった要因もキッカケになるという。例えば筆者は、音楽活動から一度引退し新境地を見つけたBob Dylanを例に、「創造性は手錠をされた状態から解き放たれることから生まれる。イマジネーションには制約と解放が不可欠」と結論づける。オープンなコミュニケーションの重要性にも言及する。例として挙げるのが米Pixarのトイレ。従業員が自然に集まる場所に配置され、何気ない会話が交わされる場となっている。これが、自由闊達なブレインストーミングとともにPixarのイマジネーションを支えていると筆者は語る。
大都市の効用という視点も興味深い。多くの人間が集まり、互いに触発し合う大都市はイマジネーションに最適な場所で、「都市は人類最大の発明」と言い切る。
|
| |
デジタルネイティブの時代~なぜメールをせずに「つぶやく」のか~
木村忠正、平凡社新書、p.256、\800 |
2013.1.8 |
|
 |
ブロードバンドの常時接続やモバイル・インターネットなどが当たり前の「デジタルネイティブ世代」の生態や、この世代の台頭に伴う社会的コミュニケーションの変容を文化人類学の手法を使って明らかにした書。メールやSNSの使い方、コミュニケーションの在り方など、彼ら・彼女らの流儀、悩みを著者が15年かけて収集した調査データを使いながら探り、日本社会の抱える問題点を浮き彫りにする。“目から鱗”というほどの驚きは感じないが、新書らしくコンパクトにまとまっている。出張のおりに気軽に読むのに向くだろう。
筆者は1980年代前後以降に生まれた世代をデジタルネイティブと定義し、四つの世代に分けて分析する。第1世代は1982年以降でポケベルやPHSに触れ、第2世代は1983-1987年生まれでパケット代を気にしながらネットアクセスを体験し、第3世代は1988-1990年生まれでパケット定額に慣れ、第4世代は1991年以降に生まれブロードバンドの常時接続当たり前に経験している世代である。
こう見ると、この30年でネットアクセスの環境が大きく変わったことがよく分かる。デジタルネイティブ世代は2010年時点で全人口の30%を占めており、確実に社会的なインパクトを与え始めている。彼ら・彼女らには四つの特徴があると筆者は論じる。一つは空気を読むことを強いる圧力。二つ目は親密さを伴わないテンション共有。第3はコミュニティ、ソーシャルとは異なるコネクションという社会原理の拡大。ちなみに著者はミクシィはコミュニティ、フェイスブックをソサエティ、ツイッターをコネクションに分類する。第4がサイバースペースに対する不信感と強い不確実性回避傾向。これらに現代社会の生態と問題点を筆者は見出し、丹念に論考を加えている。
|
| |
ファスト&スロー(上)~あなたの意思はどのように決まるか?~
ダニエル・カーネマン、村井章子・訳、早川書房、p.370ページ、¥2205 |
2013.1.3 |
|
 |
「意思はどのように決まるのか」「直感はどれほど正しいか」など、人間の意思決定の仕組みを解き明かした書。我々の常識や経済学が前提としている合理的人間像を否定するを覆していくさまは、実に小気味いい。筆者は心理学者で、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン。この書評で紹介した行動心理学の書と内容的にダブり感はあるものの、本書の物量と説得力はピカイチである。決定版といえるだろう。上下巻だが上巻だけでも読み応え十分だ。この分野に興味のある方だけではなく、多くのビジネスパーソンにお薦めしたい。
筆者は意思決定は二つの仕組みで成り立っているとする。直感的で感情的な「システム1」と意識的で論理的な「システム2」である。しかし多くの場合にシステム1が前面に出る。そのために、数々の錯覚や誤解、判断ミスが生じる。本書を読むと、システム1に影響された直感がどれだけ当てにならないかがよく分かる。
筆者は、自らの信念を肯定する証拠を意図的に探す「確証バイアス」、事前に提示された数字の影響を強く受ける「アンカリング効果」、慣れ親しんだものを信じる「認知容易性」、先行して受けた刺激に影響される「プライミング効果」のほか、「ハロー効果」「後知恵バイアス」など心理学の知見を次々と解説する。そこそこアカデミックな内容だが、事例が具体的なので興味深く読み進むことができる。
未知の出来事に出会うと現実以上に筋の通った理屈を無理矢理作ってしまったり、偶然の事象を因果関係で説明したりすることは、誰しも思い当たる節があるだろう。そして、いずれの判断も必ず間違っていると筆者は指摘する。こうした観点から槍玉に挙げるのが専門家とビジネス書である。誰もが知る著名なビジネス書を、「ほとんど役に立たない」と手厳しく批判している。
|
| |
|
|

|
2012年12月 |
日本型リーダーはなぜ失敗するのか
半藤一利、文春新書、p.262、\819 |
2012.12.28 |
|
 |
「日本のいちばん長い日」「昭和史」「幕末史」などで知られる半藤一利が、太平洋戦争時の陸海軍の軍人たちを俎上にあげ指導者論を展開した書。名著「失敗の本質」や「大本営参謀の情報戦記~情報なき国家の悲劇」と共通する個所が少なくないが、歴史探偵を自任する筆者らしい切り口で説得力のあるビジネス書に仕上がっている。決断できない、現場を知らない、責任を取らないなど、昭和期の陸海軍の指導者に対するコメントは手厳しい。教訓に満ち、示唆に富む指摘が多い書である。お薦めの1冊だ。
筆者は東日本大震災で起こった原発事故への対応に、太平洋戦争時と変わらないリーダー不在ぶりをみる。政府や東電幹部の当事者能力の欠如。ヘリコプターや機動隊の放水車で原子炉を懸命に冷やすさまは、ガダルカナル島における「戦力の逐次投入」とそっくりだと嘆く。もっとも半藤は、日本にこれというリーダーがいないのは日本人そのものが劣化している証左であり、国民のレベルにふさわしいリーダーしか持てないのは歴史の原則だと指摘することも忘れない。認めざるを得ないところだ。
筆者は、日本型リーダーが生まれた過程を日本の陸海軍の人事制度や教育制度、歴史を丹念にたどることで明らかにする。歴史探偵の面目躍如である。御神輿に担がれるだけの日本型リーダーが、それを補う参謀の必要性と地位を高めた。さらに日本陸軍の教育制度の欠陥が加わり、リーダーの権威を笠に着て権限を振り回す参謀を生んだ。本書が挙げるダメ参謀たちの行状は実に情けない。
本書はリーダーに必要な条件を六つ挙げる。「最大の仕事は決断にあり」「明確な目標を示せ」「焦点に位置せよ」「情報は確実に捉えよ」「規格化された理論にすがるな」「部下には最大限の任務の遂行を求めよ」である。それぞれの条件を具体的な事例を用いて裏付けている。ちなみに筆者は日本海軍の名将を4人挙げている。阿南惟幾、寺内正造、山口多門、栗林忠道である。
|
| |
間抜けの構造
ビートたけし、新潮新書、p.187、\714 |
2012.12.26 |
|
 |
鶴保征城氏のFacebook投稿を読んで購入。ビートたけしが人生論を交えながら“間”を論じている。「間とは何かを考えることは日本人を考えることにつながる」と指摘し、どうすれば間をコントロールできるか、人生において間をどう生かすかについて持論を展開する。間の対象は、芸能、芸術、スポーツなど幅広く、含蓄の深い話と毒舌が絶妙に配合されており楽しく読める。肩の凝らない書なので、休暇などリラックスしたいときの読書に向く。
漫才、落語、映画、絵画、野球、サッカー、相撲、踊り、茶道など、間を取り上げる範囲は広い。出色なのは漫才と映画、テレビについての考察である。間を制するもの笑いを制す、お辞儀がきれいな人に落語の下手な人はいない、映画は間の芸術、テロップがテレビから間を奪っているなど、指摘は鋭く、さすがと思わせる。
|
| |
日本農業への正しい絶望法
神門善久、新潮新書、p.237、\777 |
2012.12.23 |
|
 |
日本の農業に対する歯に衣(きぬ)着せぬ批判が持ち味の神門善久・明治学院大学教授の新著。神門教授はこの書評で何度も取り上げている、お気に入りの論客だ。今回もパワー全開で、農政・農家・農協・消費者・マスコミ・識者に次々と鉄槌を下ろす。農業ブームは虚妄とさえ言い切る。期待に違わぬ内容なので、日本の農業に関心のある方にはお薦めである。マスコミや識者の傲慢さや有害さへの批判は少々耳が痛い。
日本の農業に対する筆者の危機感はきわめて強い。それが文章を通じてビシビシ伝わってくる。例えばこうだ。日本農業は良い農産物を作る魂を失い、宣伝と演出でごまかすハリボテ農業になりつつある。「有機野菜はおいしい」「農業は成長産業」「日本人の舌は厳しい」といった言説がマスコミで飛び交うが、これらはいずれも“嘘”と断じる。例えば有機栽培は環境を悪くするし、食味も悪い。消費者は自らの味覚ではなく、能書きで農産物を評価すると手厳しい。
金儲け主義の蔓延にも警鐘を鳴らす。「農家は純朴で善良」「農家は担い手不足で困っている」というイメージは必ずしも実態を表しておらず、農家が金儲けのために都合よくでっち上げたストーリーだと断言する。大規模農家が外国人を雇うのは、日本人の肉体が農作業に耐えられないからという指摘には唖然とさせられる。
|
| |
官僚制としての日本陸軍
北岡伸一、筑摩書房、p.372、\2730 |
2012.12.17 |
|
 |
陸軍崩壊の過程や近代日本における陸軍と政治との関係を解明した書。日本軍がどのようにコントロールされてきたか、あるいはされてこなったかを、史料を丹念に読み込んで明らかにする。筆者は執筆の目的を、「現実的で有効な平和のために、日本に何ができるかを考えるうえで、明治以来の動静を単純に否定するのではなく、内在的に学び考察する」ことに置く。この視点は共感できる。もっとも学術論文がベースになっているせいか文章が少々硬く、読みやすいとはいえない。我慢して読み進むだけの価値があるので辛抱してほしい。ちなみに、この書評で取り上げた「日本はなぜ開戦に踏み切ったか」に共通する部分が少なくない。
本書が取り上げるのは、皇道派と統制派の対立、支那課官僚の動静、宇垣一成の時代観である。自制も後退もしらない自己肥大化した陸軍の姿を克明に描く。中国と泥沼の戦争を続けながら遠くのドイツと結んだだけで米英と戦争を始めるのは、いかなる軍事的合理性からも出てこないと断じる。軍国主義を軍事的価値判断が優越的地位を占める体制と定義すれば、戦前の日本は軍事主義ですらなかったと辛辣である。
このほか、取り上げられることが少ない自由主義者・宇垣一成の話は興味深く読める。宇垣に割いた章だけでも本書を読む価値がある。
|
| |
高品質日本の起源~発言する職場はこうして生まれた~
小池和男、日本経済新聞出版社、p.395、\3780 |
2012.12.14 |
|
 |
日本企業の国際競争力の起源を探った学術書。歴史的な資料に基づき、日本企業の代名詞である高品質は、現場力、具体的には「発言する職場」に支えられていると筆者は主張する。この企業の競争力の根幹にかかわる事柄に現場が積極的に発言していく方式が、いつごろから日本にみられるかを明らかにする。資料を丹念に読み込んでいるところが本書の最大の特徴である。ここで言う発言する職場とは、上流の製品設計に対して現場労働者が生産性の観点から問題点を指摘できる環境を指す。こうした環境を生み出しているのが、「共働的団体交渉モデル」と呼ぶ労使関係と日本型労働組合だと筆者は主張する。
タイトルからは、現在の現場力の強さに言及しているように見えるが、本書の議論は戦前の話に終始する。この点には注意が必要である。遠い昔のようでインパクトは限定的にならざるを得ない。クセのある筆者の文体も、好き嫌いが分かれるだろうが、我慢して読み進めばそれなりの収穫がある。万人向けではないが、現場力や労働組合に関心のある方にお薦めの書である。
筆者は戦前の綿産業の競争力は、女性労働者の低賃金に支えられたものではないことを明らかにする。品質で英国の綿業を追い越したという仮説を立て検証しようと試みる。状況証拠から低賃金ではなく品質で英国を上回ったと見なすことができるが、残念ながら積極的な証拠は見出していない。このほか定期昇給の重要性に対する指摘は示唆に富む。
|
| |
リバース・イノベーション
ビジャイ・ゴビンダラジャン、クリス・トリンブル、渡部典子・訳、ダイヤモンド社、p.408、\1890 |
推薦! 2012.12.12 |
|
 |
発展途上国で生まれたイノベーションがグローバル市場に大きな影響を及ぼすことを豊富な事例をもとに明らかにした書。「リバース・イノベーション」とは、これまでの先進国から途上国へというイノベーションが逆流することを指す。先進国向け製品の機能を省き安くしただけでは後進国が求めるニーズにマッチしない。後進国には後進国に向けたイノベーションが欠かせない著者は力説する。しかも、そのイノベーションは先進国で新たな市場を生み出す。このほかリバース・イノベーションとグローカリゼーションは同時に進行するなど、示唆に富む指摘が多くお薦めの1冊である。
頭では分かるが、体がついていかない。リバース・イノベーションには、そうした側面がある。リバース・イノベーションに立ちはだかる最大の障壁は、既存の経営者や組織だと筆者は指摘する。こうした状態を克服するには、専門の特別な組織「ローカル・グロース・チーム(LGT)」を立ち上げることが有効である。LGTによって、リバース・イノベーションとグローカリゼーションの両立が可能になる。
豊富な事例とともに実践的なアドバイスの数々が本書の特徴である。例えばマウスにおけるロジテック、生理用品でのP&G、農機具のティア・アンド・カンパニー、オーディオ製品のハーマン、心電計のGEヘルスケアなど、各社がどういった戦略で途上国市場に挑んで敗れ去り、どのように巻き返したかを詳細に紹介する。組み込み業界の方々に役立つ事例も少なくない。
|
| |
自滅する選択~先延ばしで後悔しないための新しい経済学~
池田新介、東洋経済新報社p.284、\1890 |
2012.12.6 |
|
 |
行動経済学と心理学に関する啓蒙書。「ダイエットは明日から」とか「大事な仕事なのに後回し」といった自滅する行動パターンのメカニズムを明らかにし、後悔しないための改善策と対処法を伝授する。内容はけっこう高度だが、身近で分かりやすい事例を取り上げることでアカデミック臭さを補っている。ただし、割引率や損失バイアスといった専門用語が何気なく使われているので、集中力を切らすと筋が追えなくなってしまう。要注意である。
本書の示す分析はいずれも説得力に富む。例えば夏休みの宿題を後回しにする人は、喫煙やギャンブル、飲酒の習慣があり、借金を抱え太っている確率が高いといった指摘には何となく納得させられる。このほかハトなどの動物と人間の行動パターンの比較も興味深い。気軽に読める書ではないが、示唆に富む議論が多く、行動経済学に興味のある方には一読をお薦めした。
|
| |
100のモノが語る世界の歴史3~近代への道~
ニール・マクレガー著、東郷えりか・訳、筑摩選書、p.334、\2205 |
2012.12.3 |
|
 |
大英博物館の所蔵品100点を紹介する書の最終巻。1200年から2010年までをカバーする。現代に近い時代を扱っているとはいえ、興味深い所蔵物の数々にはつい引き込まれる。冒頭は「ホーリー・ソーンの聖遺物箱」。キリストが磔になる前にかぶっていた冠から抜き出した1本のイバラがおさめられた箱だが、造形の美しさは圧巻である。
このほかインカ帝国の黄金のリャマ像(1400~1550年)、ガレオン船のからくり模型(1585年)、アステカ帝国の双頭の蛇(1400~1600年)、宗教改革100周年記念パンフレット(1617年)、ハワイの羽根の兜(1700~1800年)、ビーグル号のクロノメーターなどを解説する。滅亡した中南米の帝国の美術品は、いずれも実に美しく技術と文化の高さを今に伝えている。ちなみに日本からは柿右衛門の象と葛飾北斎の浮世絵が登場。前者は、通常思い浮かべる柿右衛門様式とは異なり意表をつかれる。後者についての解説も奥が深い。
|
| |
|
|

|
2012年11月 |
64[Kindle版]
横山秀夫、文藝春秋、999KB、\1600 |
2012.11.30 |
|
 |
評者が贔屓にする横山秀夫の新刊。期待通りの作品である。ミステリー好きだけではなく、多くの方にはお薦めだ。ベストセラーになっているのも納得できる。本書「64(ロクヨン)」は紙版だと647ページもある大著。通勤での持ち運びを考え電子版を購入した。ちょうど手元に届いたKindle PaperwhiteとGalaxy noteを行き来しながら読み終える。バックライトが均一でないのが気になったが、Kindle Paperwhiteでの読書はかなり快適。ちなみに紙版は1995円だが、電子版だと1600円と少し安い。
本書は、親子や夫婦の関係、警察における刑事課と警務課の対立、警察庁と地方の所轄の対立、主人公が所属する広報係の人間模様、広報係とマスコミの確執など、多くの関係が錯綜しながら物語は進む。複雑に絡み合っているが、それを書き分け、読者を迷路に迷い込ませない筆者の力量はさすがである。絶妙なストーリー展開で一気に読ませる。特に著者独特のテンポの良さはほれぼれする。
|
| |
外交プロに学ぶ 修羅場の交渉術
伊奈久喜、新潮新書、p.191、\714 |
2012.11.26 |
|
 |
日本経済新聞で外交・安全保障を担当してきた記者の手による、プロの外交官の交渉術と処世術。12の戦術を紹介している。外交の現場に何度も足を運んだベテラン記者らしい筆致のビジネス書である。ただし、外交交渉における丁々発止のやり取りや、知られざる裏側を期待して読むと失望する。外交交渉のエッセンスを軽いタッチで描いているのが本書の特徴である。新書らしい新書に仕上がっているものの、物足りなさも感じる。
筆者が提示するのは、交渉人は「べき」を使うな、危機管理の基本は「フルテキスト」、たった一文字が命取り、たとえ話を上手く使う、交渉決裂でも「合意」というなど12の戦術。大人のやりとりはどのようになすべきかを、外交交渉の場でのエピソードをもとに綴る。吉田茂の本音の隠し方など、微妙な言い回しの裏にある含意を解き明かす。言い回しや表現に対する配慮は、ビジネスパーソンとして身につけたいところだ。
|
| |
海賊とよばれた男(下)
百田尚樹、講談社、p.370、\1680 |
2012.11.20 |
|
 |
出光興産の創業者・出光佐三(本書では国岡鐵造という名で登場)の生涯を描いた評伝の下巻。筋を通す明治男の活躍ぶりを活写している。上巻は、国岡鐵造の生い立ちから、国岡商店の創業、戦後の再建までをカバーしていた。下巻は、事業が軌道に乗り始めてからの悪戦苦闘を紹介している。気骨あふれるスケールの大きな経営者の物語を読むのは気持ちのよいもの。上下2巻に分かれた大著だが、正月休みなどまとまった時間がとれるときにお薦めの書である。
下巻のハイライトは七人の魔女(セブン・シスターズ)と呼ばれた国際石油資本、いわゆるメジャーとの対立。メジャーはいまや懐かしい響きをもった言葉になってしまったが、当時は強力なパワーをもっていた。メジャーとの対立では、とりわけ油田の国有化を宣言したために国際的に孤立していたイランから、英国の圧力をものともせず原油を日本に運んだ「日章丸事件」が最大の見せ場である。このほか操業まで3年はかかるといわれた徳山製油所をわずか10カ月で立ち上げた話や、官僚や業界団体(石油連盟)との対立など読みどころ満載である。
|
| |
新幹線 お掃除の天使たち~「世界一の現場力」はどう生まれたか?~
遠藤功、あさ出版、p.189、\1470 |
2012.11.16 |
|
 |
JR東日本の子会社で、新幹線車両と新幹線構内の清掃を手掛けるJR東日本テクノハートTESSEI(旧社名・鉄道整備株式会社で通称テッセイで知られる)を紹介したビジネス書。多くのテレビ番組や雑誌で取り上げられたテッセイの現場と、強靭な現場力を生むまでの足跡を取材をもとに明らかにする。8月末に出版された本書はすでに14刷。ちょっとしたベストセラーである。現場でのエピソードには、ちょっといい話が多く、読み終えたときに爽やかな気分になれる。落ち込んだときに手に取ることをお薦めしたい。
本書は前半で、「お掃除の天使たち」と呼ばれる清掃スタッフの奮闘ぶりを紹介する。上司や仲間が、現場スタッフを褒める「エンジェル・リポート」をもとに、11件のエピソードを取り上げる。特に中年女性の活躍ぶりは素晴らしい。感動的な話が多いので、涙腺の弱い方は通勤電車で読むときなど要注意である(評者も困った)。
後半では、普通の企業だったテッセイが、「最強の現場」を抱える会社になるまでの2500日にわたる取り組みを振り返る。取り組みは、職場の環境整備、組織の見直し、人事制度改革など。2人の人物を軸にした成功物語はちょっと美しく描き過ぎの感もあるが、ビジネス書としては許せる範囲だろう。
|
| |
逆転無罪の事実認定
原田國男、勁草書房、p.256、\2940 |
2012.11.15 |
|
 |
8年間で24件の逆転無罪判決を言い渡した裁判官が、自らの判決を振り返った書。解説+判決文という構成で、冤罪を防いだ判決の舞台裏を明らかにする。かなり貴重な書である。被告人と初めて接する人定質問の大切さ、起訴状を読み上げるときに配慮すべき点、外国人を裁く場合の勘所、法廷で暴力団の組長を一喝したエピソード、判決を下すときの緊張感、控訴審で被告人質問をしないことが一般化している最近の裁判への疑問など、興味深い話を盛り込んでおり楽しく読める。裁判モノや刑事モノのドラマが好きな方にお薦めである。
本書を読んで驚くのは、実際の裁判が意外にドラマチックなこと。警察官や証人の偽証、狂言、誤認、判決の決め手となったビデオ映像や携帯電話の記録、足跡痕、筆跡など、TVドラマと大差ない。扱っているのが週刊誌やワイドショーなどで話題になった事件が多いのも本書の特徴である。巨乳タレントがドアの壊れた穴から通り抜けることができたかどうかが争点になった巨乳被告事件、西武新宿線の痴漢冤罪事件、調布駅南口事件など、記憶している方が多いかもしれない。
ちなみに判決文をじっくり読んだのは今回が初めてだが、いくつも発見があった。当初は解説だけ読んで、判決文は飛ばそうかとも考えた。でも読み始めると止まらない。けっして読みやすいとはいえないが、裁判官が心情を吐露していたり、思ったよりも響くものがある。論理的だし、自己陶酔に浸るタチの悪い文書よりよほどましだ。難点は、人間関係や事実関係が複雑な事件を文章だけで理解させようとする点だろう。どう考えても図示する方が正確で分かりやすいと思うのだが・・・。
|
| |
寿命1000年~長命科学の最先端~
ジョナサン・ワイナー、鍛原多惠子・訳、早川書房、p.321、\2415 |
2012.11.12 |
|
 |
人の寿命はいずれ1000歳に達する。こう語るのは、本書の主人公であるケンブリッジ大学のオーブリー・デ・グレイ教授。本書は、長寿科学研究の現状をグレイ教授の成果を中心に紹介したノンフィクションである。本書が指摘するように人生1000年を前提にすると今とは違った世界が見えてくる。奇をてらった感はあるが、たまには一風変わった書を読むのも刺激になって悪くない。
12歳ころの健康状態をずっと維持できるなら、人間は平均して1200年生きられるという。遠い祖先は2歳まで生存するのさえ難しく、12歳や20歳まで生きられるのはごく一部だった。そこで人間の体は、すべての資源を20歳までの健康維持につぎ込み、その後については知らんぷりを決め込んだ。長く生きられないことを前提にしているので、遺伝子を残すために生き急ぐ。子づくりと子育ての時期を終えると、人間の体は老化が始まり使い捨てられゴミ同然となる。
老化は大きく七つの要因で起こる。グレイ教授によると、そのうち六つについては解決のメドがたった。残りの一つは癌である。老化があらゆる発癌性物質のなかで最も強力だが、癌の撲滅にも光明が見えてきた。ただ1個の遺伝子を死滅させればよいとグレイは主張する。異端の科学者の発言は刺激的である。
|
| |
MAKERS~21世紀の産業革命が始まる~
クリス・アンダーソン、関美和・訳、NHK出版、p.320、\1995 |
推薦! 2012.11.7 |
|
 |
この書評で取り上げた「Free」「The Long Tail」の筆者クリス・アンダーソンの新著。インターネット産業から製造業へと、筆者の関心は移ったようだ。デジタル化された設計データ、インターネット環境、オープンソースの設計、3Dプリンタなどを駆使した「パーソナル・ファブリケーション(工業の個人化)」「デスクトップ・メーカーズ」について興奮気味に語る。著者の熱気がこれほど伝わってくる書は珍しい。それもそのはず。アンダーソンはパーソナル・ファブリケーションの会社「3D Robotics」を数年前に自ら立ち上げている。しかも事業に専念するために、12年間務めた雑誌「WIRED」の米国版編集長を辞めたほどだ。製造業における新しい動きを的確にとらえており、お薦めである。
筆者は、パーソナル・ファブリケーションを「新産業革命」と位置づける。頭のいいクリエーティブな人たちが、ちっぽけなビジネスチャンスを発見し儲けることができる時代がやってきたと語る。富を全員で分け合う時代というのがアンダーソンの見立てである。
この書評で先日取り上げた「FabLife」は、パーソナル・ファブリケーションを実務の面から紹介していた。現状把握には役立ったが、社会的あるいは歴史的な位置づけについての言及は少なかった。本書はさすがにWIREDの編集長らしく、背景を明確にしながら筆を進めている。事例も豊富で説得力のある書に仕上がっている。ちなみに、日経エレクトロニクスは数年前に特集を組んでいる。内容は今一歩だったが、先物買いの姿勢は評価したい。
|
| |
世にも奇妙な人体実験の歴史
トレヴァー・ノートン、赤根洋子・訳、文藝春秋、p.379、\1890 |
2012.11.2 |
|
 |
凄まじい人体実験の数々を紹介した書である。自分の理論の正しさを証明するために体を張る科学・医学者(マッド・サイエンティスト)たちの姿を取り上げている。リン病患者の膿を自らの性器に塗りつけてリン病と梅毒の感染経路を検証する、黄熱病患者のゲロを血管に注射、麻酔の効果を試しすぎて中毒患者になった医者などゲテモノ系も多いが、音速や深海への挑戦など興味深い話も続々登場する。自己を犠牲にして科学の進歩に貢献した人々の貴重な歴史を辿った書である。端座して真剣に読む本ではないが、暇つぶしには向いている。もっとも、最初は興味津々で読み始めるが、さすがに最後の方になると飽きてくるのも確かだが・・・。
本書の扱う範囲は広い。性病、麻酔、クスリ、食物、寄生虫、病原菌(コレラ)、炭疽菌、電磁波とX線、ビタミン、血液、心臓(カテーテルの話)、爆弾と疥癬、毒ガスと潜水艦、漂流、サメ、深海、成層圏と超音速などである。海水を飲みながら生き延びた漂流者の話や成層圏への気球飛行、腕に食いつかれても人食いサメの研究を続けた科学者のなど、魅力的な話題が並んでいる。
|
| |
|
|

|
2012年10月 |
海賊とよばれた男(上)
百田尚樹、講談社、p.386、\1680 |
2012.10.30 |
|
 |
出光興産の創業者・出光佐三をモデルにした小説(帯にはノンフィクション・ノベルとある)。主人公の名前は出光佐三ならぬ国岡鐵造。官僚組織との対決などヤマト運輸の小倉昌男を彷彿とさせ痛快である。もっとも、ノンフィクション好きな評者としては実名で事実をしっかり書き込んで欲しかった。どの程度まで史実に基づいて書かれているのか分からないところが辛い。出光興産といえば、かつては日本的経営の代表格と位置づけられていた。東証一部に上場するまで、タイムカードや定年制がなかったことで知られている。出光興産の秘密を知りたいと思って購入しただけに、ちょっと残念である。
小説は敗戦の日から始まる。戦争によって全てを失った出光興産ならぬ石油会社「国岡商店」だが、一人の従業員も解雇せず、石油に無関係の事業にも手を出しながら乗り切る。大手石油会社や業界団体、官僚の妨害に遭いながら会社を再建していく国岡鐵造の姿を筆者は生き生きと描いている。前編の後半は、国岡鐵造の生い立ちから、丁稚奉公、国岡商店の創業、開戦から敗戦までの活動をカバーする。
|
| |
ケータイ化する日本語~モバイル時代の“感じる"“伝える"“考える"~
佐藤健二、大修館書店、p.293、\2415 |
2012.10.29 |
|
 |
タイトルからは、携帯電話の普及が日本語にどのような影響を与えたを解き明かした書のように思えるが、そう考えて買うと落胆するかもしれない。そもそも携帯電話についての言及は多くない。著者は、電話というメディアについて、歴史的や生物学的、社会的、言語学的な観点からの論考に主眼を置いている。携帯電話だけではなく、テレビ電話、留守番電話、間違い電話なども視野に入れて“電話”について論じる。吉見俊哉や水越伸らの名著「メディアとしての電話」の延長線にある書と言える。
タイトル以上に気をつけなければならないのは文体である。もって回った冗長な書き口で、「要するに何なのか」を理解するのは大変だ。例えば「ことばは意味を保有する安定した記号の体系として、声の空間において現象し、参照できる経験として積み重ねていった」なる文章に出会うと、本を放り投げだしたくなる。本書には見るべき主張も含まれているように思うが、読み手を拒絶するような文体で損をしている。
|
| |
一揆の原理~日本中世の一揆から現代のSNSまで~
呉座勇一、洋泉社、p.237、\1680 |
2012.10.26 |
|
 |
「一揆とは何だったのか」について論じた歴史書。一揆に関して持っている常識が、いかに間違っているかを思い知らされる。もっとも、副題に「日本中世の一揆から現代の SNS まで」、帯に「一揆の思想と行動原理は、現代のソーシャル・ネットワークに通じている」とあるので、日本人の SNS に対する接し方と一揆を関連づけた書と考えて購入するとガッカリするかもしれない。SNS に言及している部分もあるがさほど多くない。しかし筆者の専門である日本中世史の歴史書としては、かなり刺激的な良書である。歴史好きにはお薦めである。
一揆というと、一向一揆や百姓一揆を思い浮かべる。数を頼んで権力と闘い要求を通す、反権力・反政府の民衆運動といったイメージだ。しかし筆者によると、一揆は常に権力と闘っていた訳ではない。むしろ体制の存続を肯定し、体制内での地位向上、待遇改善をめざして権力者に強訴を行う行為が多い。つまり一揆が階級闘争という主張は事実に基づいておらず、戦後の日本史研究者が多分にマルクス史観に影響され、そう信じたかっただけと、筆者は小気味よく断じる。
暴動や革命よりも、人のつながりの1パターンと見た方が一揆の実態に近いというのが著者の主張。この延長線上で論じることで、一揆の研究が現代日本(ソーシャル・ネットワーク)と接点を持つと持論を展開する。ちなみに本書は、一揆の最盛期だった中世を中心に扱う。江戸時代の百姓一揆は本来の一揆が変質した姿であり、中世の一揆こそがスタンダードらしい。
出色なのは、脱原発デモと一揆を関連づけて論じているところ。脱原発デモは戦後日本の諸々のデモと同様に、百姓一揆の域を出ていないと語る。百姓一揆とは「武士は百姓の生活がきちんと成り立つようによい政治を行う義務がある」という意識に基づく待遇改善要求なので、既存の社会秩序を否定するものではない。政治参加の意思は、これぽっちもない。百姓はお客様感覚で、幕府や藩のサービスの悪さにクレームをつけているだけと断言する。同様のメンタリティを筆者は脱原発デモに見出す。異論もあるだろうが、1980年生まれの若手歴史学者の観点は興味深い。
|
| |
ヒトはなぜ眠るのか
井上昌次郎、講談社学術文庫、p.208、\798 |
2012.10.23 |
|
 |
睡眠学の入門書。睡眠について網羅的に紹介しており、実によくまとまっている。もともとは1994年に出版された本だが古さを感じさせないところは、睡眠学の第一人者の手によるところが大きい。筆者は講談社学術文庫版の前書きで、「本書は睡眠学の黎明期に執筆されたため、紹介している研究成果やデータは古く、幼稚なレベルにある」と断っている。しかし、一般読者の関心が高い話題を的確にピックアップしており読み応えがある。筆者の言うように、幼稚なレベルだからこそ、眠りの本質そのものが巨視的に、また分かりやすく概観できているのは間違いない。200ページほどの文庫本なので、出張のお供にお薦めである。
本書のカバー範囲は広い。人間はなぜ眠るのかに始まり、睡眠の個人差(性差、年齢差など)、朝型と夜型の違い、睡眠の法則、不眠、睡眠中に起こる現象、睡眠にまつわる病気、睡眠学習の効果、動物の睡眠、睡眠と冬眠の違い、快眠の秘訣、睡眠は制御可能か、などについての知見を紹介する。しかも講談社学術文庫に収録するにあたって、各章の最後に最新の参考文献を載せており、初学者にはお役立ち感がある。
蘊蓄をたれるネタ本としても悪くない。具体的には以下のような話題が登場する。女性は眠りの老化が男性よりも軽い。中高年齢層では、熟睡の質は女性の方が高い。一見すると休息をとっていないようにみえる鳥類や哺乳類は、左右の大脳半球を眠らせることで休息をとっている。冬眠は寝ているのではなく、覚醒の一状態である。冬眠を続けていると睡眠不足になるので、睡眠を補給するために短い目覚めの期間が繰り返し現れる。眠ることで、神経細胞に蓄積した毒物が取り除かれ、細胞は中毒死を免れる。なかなか魅力的である。
|
| |
日本はなぜ開戦に踏み切ったか~「両論併記」と「非決定」~
森山優、新潮選書、p.223、\1260 |
2012.10.22 |
|
 |
日本社会の意思決定プロセスの致命的な欠点を鋭く突いた書。面白い。本書が取り上げるのは、第2次世界大戦の開戦プロセス。政府、陸軍、海軍、参謀本部、外務省の首脳はそれぞれに都合のよい案を併記し決定を先送りした。日本お得意の玉虫色の文章だ。矛盾だらけの文書や決められない組織など本書が描く開戦時の政治状況は、混迷する現在の政策決定にも通じている。組織的利害を国家的利害に優先させ、国家的な立場から利害得失を計算することができない体質が、対米戦という選択肢を浮上させたという指摘は身につまされる。この国の進歩のなさは、いったい何だろう。
本書を読んで痛感するのが法治国家とは思えない意思決定プロセスである。法的な基盤を欠く超法規的な調整機関の決定が、閣議を超越して日本の命運を握ってしまう。なんだかよく分からない空気が蔓延して、法的に考えると論理的とは言えない決定が下される。筆者が取り上げる典型的な国策決定の特徴は、(1)一つの国策に二つの選択肢を併記する両論併記、(2)国策の決定自体を取りやめたり、文言を削除して先送りにする非(避)決定、(3)同時に他の文章を採択することで、国策の機能を相殺する、である。公的な文書もメチャクチャだ。会議が紛糾したあげく、本文と矛盾する文章が末尾にペタペタと添付される。
本書は浮き彫りにするのは、開戦時における論理性の欠如と思考停止である。何の根拠もない希望的観測、いい加減な戦況判断と水増しされた数字。何度となく回避するチャンスがあったにもかかわらず、ずるずると開戦に至る。例えば海軍は、国運を決するぎりぎりの段階で、不都合な未来像から目をそらし、組織的利害の世界に閉じこもったと筆者は非難する。
|
| |
山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた
山中伸弥、緑慎也、講談社、p.194、\1260 |
2012.10.18 |
|
 |
帯には「祝・ノーベル賞受賞! 唯一の自伝」とある。自伝とは少々オーバーな気もするが、2012年のノーベル生理学・医学賞を受賞した山中教授自身が断片的にこれまでの人生を語っているのは事実。本書はジャーナリストの緑慎也が山中教授へのインタビューをもとに再構成しており、「iPS 細胞ができるまで」と「iPS 細胞にできること」についての説明をはじめ、分かりやすい読み物に仕上がっている。新聞・雑誌・書籍で iPS 細胞と山中教授に関する情報があふれているなか、読んで損はない1冊だろう。
山中教授は好きな言葉として「人間万事塞翁が馬」を挙げるが、本書では想定外のことが起こる研究の面白さを語っている。仮説を立て実験を繰り返すが所望の結果を得られない。場合によっては想定外の事象が発生する。そのなかから画期的な研究成果が生まれる。研究の醍醐味とそれに引かれていく様子を本書はうまく伝えている。もう一つの特徴は、共同研究者へのフェアな態度である。iPS 細胞研究に携わった研究者や学生への気配りがそこここに感じられ、さわやかな気分になる。
|
| |
毒になるテクノロジー~iDisorder~
ラリー・D・ローゼン、ナンシー・チーバー、マーク・キャリアー、児島修・訳、東洋経済新報社、p.321、\1520 |
2012.10.17 |
|
 |
評者は先日バリを旅行したが、町中のカフェやレストランは必ずと言って「Free Wi-Fi」の看板がかかっている。注文もそこそこに、まず店員にパスワードを聞きスマートフォンやタブレット PC でネットにアクセスする。Wi-Fi の調子悪いとすぐに店員にチェックを入れる。欧州からの旅行者も評者を含めたアジアからの旅行者も、皆んなそんな感じだ。本書はそうしたネット依存症について、心理学者が766人への調査に基づいて心理学と精神医学の観点から論じた書である。専門家による危険度チェックと対処策についてもページを割いているので実用性も併せ持っている。
筆者は、「あるある」とつい膝を打つ事例を次々と挙げる。ネット依存症に警鐘を鳴らす書は多いが、本書は調査結果と学術的な論考に基づいて、ソーシャルメディアやスマートフォン、ビデオゲームなどが脳や心に与える影響を論じており説得力がある。ちなみに筆者は、テクノロジやメディアの過剰な利用によって生じる様々な依存症的な精神疾患を「iDisorder」と名付けているが、残念ながら現時点では人口に膾炙しているとは言いづらい。
本書の扱う範囲は広い。Facebook などのソーシャルメディアと自己愛的な傾向との関係、メディアと摂食障害の関係、禁断書状や再発、脳の構造の変化、テクノロジー中毒と薬物中毒との類似性、メディアやテクノロジーが抑うつ症を引き出す危険性、などなどだ。牽強付会的な話も含まれており反論・反証が多そうだが、何事も行き過ぎはよくないのも確か。本書を通じて、我々が置かれた環境の危険性を認識するのも悪くないだろう。
|
| |
ネットと愛国~在特会の「闇」を追いかけて~
安田浩一、講談社、p.370、\1785 |
2012.10.11 |
|
 |
在特会(在日特権を許さない市民の会)の活動を追ったルポルタージュ。寡聞にして知らなかったが、在特会は1万人を超える会員を抱える日本最大の保守系市民団体である。「在日コリアンをはじめとする外国人が」「日本で不当な権利を得ている」と主張して勢力を広げてきたという。会員をインターネットの掲示板で募り、ニコニコ動画や USTREAM を活用してリアルタイムに街宣活動を伝える。今だからこそ生まれた右翼活動の実相を、筆者は浮き彫りにしている。日本の一面を知ることのできるノンフィクションでありお薦めである。
在特会は、朝鮮学校授業料無償化反対、外国籍住民への生活保護至急反対,、不法入国シャツ法、核兵器推進などを掲げ、各地でデモや集会を繰り返しているという。筆者の問題意識は、いったい何を目的に闘っているのか、いったい誰と闘っているのか。リーダーの桜井誠をはじめとする指導層、会員、脱会者だけではなく、支援する外部団体、反目する外部団体を丹念に取材し、在特会とは何かに迫っている。リーダーである桜井誠への体当たりの取材はなかなか読み応えがある。
筆者が明らかにするのは、在特会の活動の裏側にある日本社会の本音部分である。例えば京都市南区の朝鮮学校で在特会が起こした抗議活動。筆者は、抗議を要請した住民、抗議には参加しないものの心情として朝鮮学校を嫌悪する住民への取材を通して、日本社会の本音の部分を明らかにしてる。
|
| |
ネゴシエイター~人質救出への心理戦~
ベン・ロペス、土屋晃・訳、近藤隆文・訳、柏書房、p.380、\2310 |
2012.10.7 |
|
 |
ネゴシエーターと言われて思い出すのは、サミュエル・L・ジャクソンとケヴィン・スペイシーの映画「交渉人」。無実の罪を着せられた警察ビルに立てこもったサミュエル・ジャクソンと交渉人ケヴィン・スペイシーを中心とした映画は、最後のどんでん返しを含め見応えがあった。好きな映画の一つである。本書は実在の交渉人が、自らの体験を語ったノンフィクション。中近東や中南米でビジネスと化している身代金目的の誘拐(K&R:Kidnap and Ransomと呼ぶらしい)の実情と、金額交渉にかり出された筆者(名前は偽名)と誘拐犯との駆け引きを詳細に描いている。この書評でかつて取り上げた「人質交渉人」も面白かったが、本書も悪くない。
ちなみに、身代金目的の誘拐は1年間に2万件以上、大半がラテンアメリカで起きている。誘拐の件数はここ1年で倍増している。70%は身代金の支払いで解決し、力づくでの解決は10%に過ぎない。身代金の要求額は5000ドルから1億ドルまでとさまざま。誘拐の被害者は90%が地元の人間で、海外居住者や旅行者ではない。なかなか示唆的な数字の数々である。
筆者は、自らがかかわった数々の誘拐事件を取り上げる。金持ちの息子の誘拐、2人を間違って人質にして犯人が当惑した事件、タンカーなど船舶を襲うソマリアの海賊などなど。それぞれに実際の事件だけに緊張感にあふれていて興味深い。犯人のちょっとした仕草(例えば足の指)から心理状態を読むところなど、筆者と誘拐犯との駆け引きは小説のようで面白い。
体験から得た教訓は示唆的である。例えば、沈黙は相手の不安をかき立てる。人質の期間が長引くほど、時間は犯人に圧力をかけ生還できる可能性が高くなる。身代金を10%まで下げさせることが可能。交渉人が身代金を提示する際には、必死でかき集めた感じを出すために数字がきれいに揃わないようにする。また筆者は、誘拐は阻止できないとも断言する。しかし誘拐に対処する有効な知識を身につけることは役に立つと語る。逃げようとしてはいけない。人質になったら、少し落ち込んだ顔をする。無視するのは逆効果。自分で身代金の交渉をしない。救出活動を期待してはいけない、などなど。実際に活用する場面は少ないだろうが、頭の片隅に置いていても悪くなさそうだ。
|
| |
|
|

|
2012年9月 |
化石の分子生物学~生命進化の謎を解く~
更科功、講談社現代新書、p.240、\798 |
2012.9.30 |
|
 |
化石のDNAやタンパク質、今生きている生物のDNAを分析・解析して人類の進化史を探る「古代DNA研究」を紹介した書。研究成果だけではなく、解析法や解析ツールなども丁寧に解説している。「ネアンデルタール人は現生人類と交配したか(我々にネアンデルタール人の血が流れているか)」「ジュラシック・パークは実現するか」「縄文人はどこから来たのか」といった知的好奇心をくすぐる話題が豊富で飽きさせない。
「ネアンデルタール人は現生人類と交配したか」への回答はイエスである。ゲノムの塩基を見ると、ネアンデルタール人は現在のユーロッパ人やアジア人と共通点が多く、アフリカ人とは少ない点。この分析から人類について、以下の推論が成り立つ。現生人類がアフリカで誕生したとき、ネアンデルタール人はすでにユーロッパや西アジアで生活していた。現生人類がアフリカを出て西アジアに移住し、ネアンデルタール人と出会い交配が行われた。ただしゲノムが完全に混じった訳ではないので、交配はまれだった。一方で、アフリカに残った現生人類はネアンデルタール人と出会うこともなく、交配もなく現在にいたった。何とも壮大なストーリーである。
丁寧に解説しているとはいえ専門的な内容が多いので、集中力を切らすと話についていけなくなる。行きつ戻りつ読む羽目に陥るので注意した方がよい。新書らしくコンパクトにまとまっているので、ちょっとした空き時間ができたときの暇つぶしにお薦めする。
|
| |
工学部ヒラノ教授の事件ファイル
今野浩、新潮社、p.206、\1575 |
2012.9.27 |
|
 |
今野浩 東工大名誉教授が有名大学の内実を暴露した書。タイトルは筒井康隆の「文学部唯野教授」を意識しているが小説ではない。筆者によると、一部に仮名を使っているものの97%は真実ということなので、ノンフィクションという位置づけになる。筆者は前著「工学部ヒラノ教授」で大学の表の世界を描いたが、今回は筑波大、東工大、中央大、米パデュー大での体験に基づいて裏の世界を明らかにする。定年退職で怖いものなしということかもしれない。
筆者が白日の下にさらすのは、カラ出張、経歴詐称、服務規程違反、科研費の不正使用、セクハラ・アカハラ、単位をめぐるハニートラップ、違法コピーの数々、論文盗作やデータ捏造などなど。ザックザックと不正の数々が登場する。キャンパス殺人事件の章を設け、中大教授の刺殺事件(筆者が中大教授時代に遭遇)、広島大学・学部長刺殺事件も扱っている。
工学部らしい生真面目さや小賢しさ随所に顔をみせており、工学部出身の評者には何となく納得のいく話が多い。ベッドやソファーで寝転びながらリラクスして読むのに向く書である。
|
| |
貧乏人の経済学~もういちど貧困問題を根っこから考える~
アビジット・V・バナジー、エスター・デュフロ、山形浩生・訳、みすず書房、p.408、\3150 |
推薦! 2012.9.19 |
|
 |
貧困に対する見方が劇的に変わる書である。教えられることが実に多い。頭の中で考えた理論が実態とかけ離れており、貧困国と貧乏人に対するステレオタイプのイメージが間違っていることを、現場に根ざした精緻で定量的な研究に基づいて示している。学術的な書だが掛け値なしに面白い。本書が扱う貧困の本質を知っていて損はないだろう。タイトルの重さとみすず書房という看板に尻込みすることはない。皆さんにお薦めしたい書である。
帯には「貧困の本質への驚くほど深い洞察に満ちた本」「世界の貧困に関心のある人の必読書。こんなに多くを教えてくれる本を読んだのは久しぶりだ。経済学からの最高の贈り物だろう」といった推薦の言葉が並ぶ。本書を読むと必ずしも大げさではないことが分かる。現場に足を踏み入れることで、貧困の本質に迫った書である。
貧困と言って、まず頭に思い浮かぶのが食糧難。しかし貧困層では収入が増えても、食費は増加しないという現実を本書は突きつける。目先の豊かさ、嗜好品や娯楽といった生活費に増収分が消えてしまう。インドに至っては、実収入が増えたにもかかわらず食べなくなっているという。貧困者向けの小口金融であるマイクロファイナンスについては限界を明らかにする。マイクロファイナンスは確かに便利だが、貧困の罠にはまり中規模企業にまでは拡大しない。このほか医療や健康保険、教育など、先進国の考え方が貧困国で通用しないことを明らかにしている。
本書は貧困に対する施策が有効に機能しないのは政策立案者の三つの「I」ためだと主張する。すなわちイデオロギー(ideology)、無知(ignorance)、惰性(inertia)である。典型例としてインドのヘルスケア制度を挙げる。看護師に対するルールは、看護師という献身的なソーシャルワーカーと思いたいイデオロギーに基づくもので、現場を知らない(無知)によるものだと断じる。こうした状態が改善されないのは、紙の上だけで生き延びるのは惰性のためだという。
|
| |
図解・新幹線運行のメカニズム
川辺謙一、ブルーバックス、p.240、\924 |
2012.9.19 |
|
 |
1964年の開業以来、安全かつ大量に安定的に乗客を運んでいる新幹線。その運行の仕組みを詳細に解説した書である。運転の方法、社内検札を行う理由、列車ダイヤと時刻表、車両についてのティップス、運行管理や保守点検の仕組み、地震への備え、ミニ新幹線ついてなど、魅力的な話がテンコ盛りである。鉄道ファンでなくても十分に楽しめる。
|
| |
PlanB~不確実な世界で生きのびるための11の法則~
デイビッド・コード・マレイ、花塚恵・訳、東洋経済新報社、p.283、\2200 |
2012.9.16 |
|
 |
新しいマネジメントの在り方「適応マネジメント」を事例とともに紹介した書。変化の激しいビジネス環境のなかで、ビジネス・プランはすぐに陳腐化する。本書の帯にあるように、計画厳守は破滅への一歩である。重要なのが、状況に対して的確に適応した修正を迅速に加えた「PlanB」である。本書はPlanBを立案するための11の法則を紹介する。飛び切り面白いビジネス書とはいえないが、戦術は戦略に優先するといった現場重視の考え方には共感するし、アップル、フェイスブック、コカ・コーラ、シルク・ドゥ・ソレイユといった事例は十分に楽しめる。
ちなみに11の法則はこんな感じである。課題を特定する、戦術リストを作る、勝負の場所を選ぶ、戦略と戦術との連携をはかる、ゴールを設定する、複数の未来を予測する、指標で正否を判断する、などなど。事例を挙げながら説明しているので納得性が高い。
|
| |
コンピュータが仕事を奪う
新井紀子、日本経済新聞出版社、p.221、\1785 |
2012.9.12 |
|
 |
コンピュータに向く仕事、人間にしかできない仕事について論じた書。コンピュータの性能と機能は向上・拡大を続け、チェスの王者に勝つまでになった。人間の仕事のある部分は確実に奪われる。しかしコンピュータには得手不得手がある。コンピュータにできない仕事は確実に存在する。こうしたなか人間はどうすべきか、教育はどうあるべきかを筆者は論じる。
コンピュータの将来性と限界が本書の主題だが、もう一つ筆者が強調しているのが数学の重要性である。数学の素晴らしさと数学を学ぶことの意味を根源にさかのぼって論じている。全編にわたって、筆者の数学への愛情が伝わってくる書である。ちなみに筆者は一橋大学法学部を出てイリノイ大学数学科を修了。現在は国立情報学研究所で教授を務めている。
|
| |
ヒット商品を生む観察工学~これからのSE,開発・企画者へ~
山岡俊樹編著、共立出版、p.232、\3045 |
2012.9.10 |
|
 |
この書評で7月に取り上げた「ビジネスマンのための『行動観察』入門」が面白かったので、参考文献として挙げられていた本書を購入。タイトルから分かるように観察工学の教科書だが、教科書臭さはあまりなく実践的で好感が持てる。観察工学とは「人間に関する生理、心理、認知、行動をデザイン要件に変換し、製品企画からデザイン、評価までのプロセスに反映させ、人間優先の魅力ある商品づくりに生かす」学問を指す。本書は観察工学が基礎から体系的に学べるうえに、製品開発で実際に生かした事例が豊富に紹介されており興味深く読める。
本書が対象とするのはマンマシン・インタフェース、ユニバーサルデザインなどに関係する研究者、製品企画担当者、エンジニア、デザイナなど。しかしマンマシン・インタフェース、ユニバーサルデザインとは無関係の技術者が読んでも得るところが少なくないだろう。ちなみに編著者は和歌山大学のシステム工学部デザイン情報学科教授。執筆陣も和歌山大出身者で、パナソニックやシャープ、島津製作所といったメーカー技術者がずらりと並んでいる。
本書で役立つのは、観察工学の具体的な手法を体系的に学べるところ。しかも事例を交えて解説しているので分かりやすい。複写機のボタンの形状、操作パネルのデザイン、配食保温容器の形状などの検討過程は、なるほどと思わせる。難を言えば事例が少々古いところ。ソフトウエアの使い勝手への言及が少ないのも物足りない。
|
| |
閉じこもるインターネット~グーグル・パーソナライズ・民主主義~
イーライ・パリサー、井口耕二・訳、早川書房、p.344、\2100 |
2012.9.7 |
|
 |
原題は「The Filter Bubble(フィルター・バブル)」。インターネットが自由でパブリックでオープンな場から、カスタマイズが進み個々のユーザーに最適化されたクローズドな場へと変容している状況に警鐘を鳴らした書である。Google、Amazon、Facebookなどのインターネット・サービスを俎上に載せ、企業や個人、プログラマがフィルター・バブルから抜け出すための処方箋を書いている。
インターネットを閲覧したときに、自らの嗜好にあわせたコンテンツが表示される傾向が強まると、人間の視野はどんどん狭くなり、創造性が蝕まれていくというのが筆者の問題意識である。多様性が否定される結果、民主主義さえ危うくなると危機感を募らせる。確かにインターネットが既存のアイデアを強化するツールとしては欠かせない存在となったのは事実。しかし検索エンジンやリコメンド・エンジンが無駄だと判断した情報を切り捨てた結果、創造性を刺激する情報に遭遇する機会はめっきり減る。このままでは新しいアイデアを偶然発見する能力「セレンディピティ」が衰えると著者は嘆く。
いわゆるアンチ・グーグルという意味で類書が多い領域だが、本書の内容は可もなく不可もなくといったところ。ただし頭の整理には役立つので、この分野に興味のある方にお薦めである。
|
| |
途中下車~パニック障害になって。息子との旅と、再生の記録~
北村森、河出書房新社、p.237、\1500 |
2012.9.3 |
|
 |
筆者は日経TRENDYの前編集長。編集長として活躍していた40歳の秋に発症したパニック障害に対して、どのように向き合ったかを綴った書である。家族や会社、同僚などとの関係と、そのときどきの心の動きを詳細に描いている。実は日経ホーム出版と日経BP社が合併し、評者は筆者と僅かな期間だが同じ釜の飯を食べた。合併後しばらくして、看板雑誌の名物編集長(=筆者)が退職するという話が流れたが、理由がパニック障害だったとは知らなかった。AERAの記事で本書の存在を知り購入。いろいろ考えさせられることがギッシリ詰まった書である。
筆者のパニック障害は乗り物に乗れないという症状で表れた。地下鉄や新幹線飛行機といった空間に閉じ込められることに体が拒否反応を示す。特に地下鉄はダメ。会議も耐えられなくなってしまう。取材で飛び回ることの多い編集長・記者という職業を考えると、かなり辛い状況である。病気について会社はもちろん家族にも告げず、筆者は41歳で退職する。
無職になった筆者は6歳の息子と旅に出る。奥さんを拝み倒して出してもらった100万円を元手に、記者時代に知った旅館やホテル、飲食店を訪ね歩く。家庭を顧みず働いていた父と息子の二人旅。最初はぎこちないが、徐々に壁はなくなっていく。情景が目に浮かぶようである。親が思うよりも「子供は大人」というエピソードもいい。旅行を繰り返し軍資金が尽きかけるころ、筆者は病気を克服するキッカケをみつける。ちなみに、本書の陰の主役は奥さんである。自らの心の動きを克明に追っているのが本書の特徴だが、ときどき登場する奥さんの辛らつな発言が秀抜で笑わせる。
|
| |
|
|

|
2012年8月 |
失敗の本質~戦場のリーダーシップ篇~
野中郁次郎、杉之尾宜生、戸部良一、土居征夫、河野仁、山内昌之、菊澤研宗、ダイヤモンド社、p.336、\1890 |
2012.8.31 |
|
 |
1984年に出版された「失敗の本質」の続編。日本軍の幹部の失敗と(数少ない)成功を題材に、リーダーと組織の在るべき姿を論じる。前作同様、事例が豊富で読み応えがある。一方で「続編がベストセラーの前作を上回ることは難しい」という一般則を改めて思い出させてくれる。日本軍の失敗から組織として学べる教訓を論じた前作は、評者も何度か読み返している名著である。本書も悪い出来ではないが、さすがに前作には及ばない。前作が未読なら、併せて読むことをお薦めする。
筆者が理想とするのがフロネティック・リーダー。物事や背後にある複雑な関係性を見極めて適切なソリューションを見出すとともに、的確な判断を素早く下し行動するリーダーを指す。筆者の一人である野中郁次郎は、チャーチルにフロネティック・リーダーを見ている。フロネティック・リーダーと日本軍指導層のフィット・アンド・ギャップ分析をするために、筆者は栗林忠道、牟田口廉也、栗田健男、石原莞爾、辻政信、山口多門といった将軍・参謀や数多くの作戦を取り上げる。この辺りは手慣れており、説得力十分である。
本書の出版のキッカケとなったのが福島原発事故で露見した、首相官邸や東京電力トップのリーダーシップ不在だったのは想像に難くない。日本の指導層は、危機的状況にのぞんで日本軍と同じ轍を踏んだ。筆者が前作「失敗の本質」で挙げた「日本軍の組織的失敗」の二の舞を演じ、無様な姿をさらした。具体的には、(1)現実を直視できず、大局的な見地に基づく現場対応ができなかった、(2)多様性を排除し、同質性の高い仲間内で独善的に意思決定を行う組織だった、(3)多様性の高いタスクフォースと官僚制を生かす統制能力が欠如していた、といった問題点を筆者は取り上げる。閉鎖コミュニティの「知の劣化」がもたらした人災というのが筆者の見立てである。
|
| |
渋沢栄一〈2〉論語篇
鹿島茂、文藝春秋、p.457、¥2100 |
2012.8.29 |
|
 |
仏文学者・鹿島茂による渋沢栄一の評伝の後編。中年以降、実業家・起業家として七面六臂の活躍をし、民間外交に駆け回る財界人としての渋沢を丹念に追う。最後には艶福家と言われる私生活や家道楽といったプライベートな面にまで踏み込んで、渋沢の実像に迫っている。さすがに上下あわせて1000ページは長いが、筆者の渋沢への惚れ込みようが伝わってくる労作である。このような気骨あふれる人物を生み出す江戸時代の懐の深さに改めて驚かされる。比較的長い休みがとれるときに、上下まとめて読むことをお薦めする。
それにしても渋沢の事業意欲はすさまじい。500超の企業の創設にかかわり、日本の礎を築いた。銀行、水道、電気、鉄道、陸運、海運、紡績、鉄鋼、科学、印刷、ホテルなどなど、いまでも身近な企業の創設に関わっていたことには正直驚かされる。筆者は渋沢の事業の傾向を大きく三つに分けている。一つは資本主義のインフラにかかわる事業。銀行や証券取引所、保険などが該当する。第2は外国製品を置き換える国産品製造のための事業。紡績や毛織物、化学、製鉄といった事業である。最後が完成したインフラを活用して製品などを円滑に流通させるサービス業。勝者や通信、印刷、新聞、ホテルなどが当たる。まさに日本に尽くした人生がここにある。
|
| |
冥王星を殺したのは私です
マイク・ブラウン、梶山あゆみ・訳、飛鳥新社、p.352、\1680 |
推薦! 2012.8.23 |
|
 |
あまり期待せずに読み始めた太陽系惑星を巡るノンフィクション。よい方向に完全に裏切られた。非常に満足度が高くお薦めである。感動、ロマンス、友情、陰謀、笑い、インチキ、官僚主義などの要素がふんだんに含まれた一級のエンタテインメントに仕上がっている。小説顔負けの面白さだ。
筆者は、「冥王星を太陽系惑星の座から引き摺り下ろした」張本人の天文学者。天文学者の仕事ぶり、惑星を発見する手順といった科学的な内容もきっちり押さえられ、知的好奇心も満足させられる。翻訳の出来もいいので一気に読み進むことができる。翻訳書では今年一番である。本来なら夏休みにお薦めしたかったところだ。
太陽系惑星は、評者の時代なら水・金・地・火・木・土・天・海・冥と覚えている。最後の冥王星が惑星でなくなったのは2006年8月のこと。うっすらと記憶に残っているが、この引き金を引いたのが筆者のマイク・ブラウンである。そもそも10番目の惑星「エリス」の発見だったはずが、惑星に相応しいのか疑義を呼び、これが冥王星の降格につながった。発見から発表までの緊張感、発見者としての名誉と学者としての矜持のせめぎ合いが書き込まれていて読み応え十分である。
本書のクライマックスの一つが、惑星発見の名誉がスペインノ学者に横取りされかけたところ。どのように横取りされかけたのかの謎解きは、いかにも今風。ここを読むだけでも価値がある。天文学者の生活の一端に触れられるのも本書の魅力の一つである。天体観測の実際や私生活、冥王星を惑星のままにしておこうと国際天文学連合の画策など興味深い話が満載である。
|
| |
身につまされる江戸のお家騒動
榎本秋、朝日新書、p.264、\819 |
2012.8.20 |
|
 |
江戸時代に起こった40件のお家騒動を紹介した書。有名な伊達騒動や宇都宮釣り天井事件、佐賀鍋島藩の猫化け騒動などを冒頭で取り上げられており、ぐっと引き込まれる。大名の名前はよく似ているので登場人物が多いと頭が混乱するが、複雑なケースについて筆者は相関図を使って説明しており、これが便利。なかなか親切である。
親子・兄弟間のいさかい、バカ殿の幽閉、幕府の介入、保守派対改革派の対立など、七つのケースに分けてお家騒動の数々を紹介する。各章の最後は現在に通じる教訓で締めくくっている。ただし、お家騒動も40連発ともなると少々飽きるのも事実である。264ページに40件なので、一つのケースに割けるのは6ページあまり。人物や背景、経緯をしっかり描むには少々短い。件数を減らしてでも、もう少し人物描写や顛末を書き込んだ方が読後感は向上しただろう。筆者のサービス精神は評価するが、欲張り過ぎた感がある。
|
| |
模倣の経営学~偉大なる会社はマネから生まれる~
井上達彦、日経BP社、p.272、\1890 |
2012.8.16 |
|
 |
ヤマト運輸、スターバックス、セブン-イレブン、トヨタ自動車、グラミン銀行などの成功の原点が、既存のビジネスモデルの模倣にあったことを紹介した書。模倣からイノベーションにつなげるための作法と心得を論じる。筆者が強調するのが、製品ではなく仕組みを模倣することの重要性である。製品に比べ仕組みのキャッチアップには時間がかかり、困難を伴うことが多いからだ。ビジネス書で既出の事例が少なくないが、1冊でまとめて読めるお得感がある。ただしページ数がさほど多くないので、個々の事例に対する分析には少々物足りなさを感じる。興味のある成功例が見つかったら、参考文献にあたるのが本書の正しい使い方だろう。
筆者は模倣に四つのパターンを見る。他社の成功(単純模倣)や失敗(反面教師)、自社の成功(横展開)や失敗(自己否定)から学ぶ4パターンである。それぞれのパターンからインスピレーションを得て成功につなげる。もっとも手本を見出しても、現実とのギャップを超えないと成功はおぼつかない。そこで筆者が持ち出すのが「守破離モデリング」である。まず徹底的に倣い、その上でお手本のお教えを破り、その後に自らのモデルを確立するという手順を踏む。
|
| |
渋沢栄一〈1〉算盤篇
鹿島茂、文藝春秋、p.477、\2100 |
2012.8.15 |
|
 |
日本の資本主義の基礎を築いた渋沢栄一の評伝。上下で1000ページに迫る大著である。渋沢栄一については学生時代に城山三郎の「雄気堂々」を読んで以来なので実に久しぶり。「雄気堂々」で記憶に残っているのは、水戸の豪農出身、一橋(徳川)慶喜に仕官した、多くの企業を立ち上げたことくらい。おかげで30数年ぶりの評伝を新鮮に読めた。筆者は淡々と渋沢の人生を辿っている。エンターテインメント性が城山作品ほど高くないので、一気に読み進むといった感じではない。ドラッガー絶賛したと言われる渋沢という人物に興味を持つ方がじっくり読み込むのに向いている。
本書は上巻で500ページ弱を割いて、渋沢の生涯を詳細に描く。上巻は算盤篇と題し、ビジネスマンとしての渋沢を描いている。具体的には家庭環境や幼少時代の逸話、経済人としての思想的基盤を築いたフランス滞在時代、帰国後に通貨・円や株式会社制度の導入に奔走した時代、東京海上保険や紡績組合(東洋紡績)、抄紙会社(王子製紙)などの設立に関与した時代をカバーする。興味深いのは、明治維新で活躍した西郷隆盛や大隈重信、大久保利通、井上馨といった面々、さらには岩崎弥太郎や益田孝といった経済人との交流と彼らに対する渋沢の評価である。ここを読むだけでも価値がありそうだ。
渋沢の経済思想の原点がフランスにあるというのは寡聞にして初めて(忘れてしまた可能性も大)。渋沢は、一橋慶喜の弟の供としてパリ万博に赴いたときにサン=シモン主義に出会い、強く影響を受けた。これが経済人としての基盤になった筆者は主張している。
|
| |
重力とは何か~アインシュタインから超弦理論へ、宇宙の謎に迫る~
大栗博司、幻冬舎新書、p.289、\924 |
2012.8.8 |
|
 |
相対論や量子論、超弦理論(超ひも理論)を分かりやすく説いた啓蒙書として、書評などで取り上げられることが多い書。アインシュタインの相対論にはじまる過去100年間の研究の発展をたどり、最新の重力理論の描く宇宙論を論じている。宇宙の謎に迫る洒脱な書き口は、知的好奇心を満足させてくれる。科学の奥深さと面白さを知ることができる新書らしい新書である。
筆者は七つの視点から重力理論を紹介する。「重力の七不思議」「特殊相対論の世界」「一般相対論の世界」「アインシュタイン理論の限界」「量子力学の世界」「超弦理論」「重力のホログラフィー原理」である。超弦理論の考える宇宙は10次元、GPSは特殊相対論と一般相対論を使って誤差を補正する、光速が一定である代わりに時間や空間が変化するといったキャッチーなフレーズを織り交ぜながら筆を進める。
数式を使うことなく、身近な事象を使って説明しようとする筆者の熱意を端々に感じることができる。筆者の解説は巧みで、何となく分かった気分になる。ただし、1回読めばす~っと腑に落ちるほど最新科学は甘くないのも確か。評者の場合、行きつ戻りつ読み返すことで何とか理解することができた。それでも、ミクロ(量子論)からマクロ(相対論)、それを統合する超弦理論を、300ページそこそこで分かった気にさせる筆者の力量と努力は買える。
|
| |
直観を科学する~その見えざるメカニズム~
デヴィッド・G. マイヤーズ、岡本浩一・訳、麗澤大学出版会、p.399、\3990 |
2012.8.4 |
|
 |
身近な事例や研究成果、学術的な実験を挙げて、直感とは何か、直感の大切さ、直感に頼る危険性などを論じた社会心理学の啓蒙書。本文で350ページほどの大著だが、優れたエンタテインメントに仕上がっており楽しく読み通せる。まとまった時間がとれる夏休みに向く。
筆者は大きく三つの話題に分けて直感を論じる。「直感の力」「直感の危険」「直感の応用」である。直感を生む心理的・生理的仕組み、直感と記憶の関係、直感と専門知識の関係、直感を左右する要因などに焦点を当て、謎解きのように一つずつ解明していく。
読み応えがあるのは直感の応用を論じた第3部である。スポーツや投資、臨床心理学、面接試験、リスク、ギャンブル、心霊といった切り口で、直感がどれほど当てにならないかを示す。例えばスポーツ。よく「波に乗る」といった表現を使うが、統計的な根拠は薄い。就職や入学における面接官の直感も当てにならない。ある大学で面接に落ちた学生が他の大学で大成した例など、「面接官の目は節穴」の事例を紹介する。理由は単純だ。面接官が気にするのは入学・入社した人材のその後でしかない。面接で落とした相手を追跡調査することはない。判断力は鍛えられず、面接官の目は曇ったままになる。
|
| |
ソーシャルリスク~ビジネスで失敗しない31のルール~
小林直樹、日経BP社、p.224、\1470 |
2012.8.1 |
|
 |
企業はどのようにソーシャル・メディアを利用・活用すべきか、炎上した場合はどう対応すればいいのかなどを紹介した書。帯に「ネット護身術」とあるが、時宜にかなった内容といえる。企業の管理部門だけではなく、ソーシャルメディア時代に生きる社会人全般にお薦めの書である。
筆者は冒頭で、先進企業が策定したルールを紹介する。取り上げるのは住友スリーエム、IBM、コカ・コーラ。模範例として取り上げるだけあって、それぞれよく考えられた内容である。仕事にすぐ使えそうだ。その後に登場するのは炎上事件の数々。筆者は企業向けと個人向けの計31のルールに分類しながら、TwitterやFacebookなどで実際に起こった炎上事件を俎上に載せる。それぞれの経緯、何が問題だったか、どうすべきだったかを詳細に論じる。企業名や団体名を実名で挙げており、内容は説得力に富む。最後には理解度テストを用意している。至れり尽くせりである。
|
| |
|
|

|
2012年7月 |
英国大使の御庭番~傷ついた日本を桜で癒したい!~
濱野義弘、光文社、p.244、\1365 |
2012.7.28 |
|
 |
25年にわたって英国大使館の専属庭師を務めた著者の手記。著者が英国大使館に住み込みで働きだしたのが25歳のとき。読売新聞の三行広告を見て転職を決意する。経費削減で退職する50歳までの大使館人生を写真を交えて綴る。具体的には結婚、子育て、大使夫妻、大使館の人々との交流を活写している。知られざる世界を垣間みる楽しさに満ちた書である。ちなみに庭の見取り図と植栽の配置図が欲しいところだが、警備上の都合なのだろうか掲載されていない。ちょっと残念である。
筆者は当初1000坪、最終的には1万坪に及ぶ敷地の庭園の責任者を任された。これだけの庭を管理する大変さを筆者は語る。特に大使夫妻、特に婦人とは庭づくりについて何度も衝突する。しかし結局は使用人の身。最後は引き下がるが、庭師の矜持を造園に込める。職人としてのこだわりが本書の随所に顔を見せるのが楽しい。欲を言えば、バラづくりについての記述がもっと盛り込まれていれば、満足度はいっそう高まっただろう。
|
| |
全身がん政治家
与謝野馨、文藝春秋、p.254、\1470 |
2012.7.24 |
|
 |
壮絶なガン闘病記である。筆者は与謝野鉄幹・晶子夫妻の孫で政治家の与謝野馨。初めてガンを告知されたのが39歳。悪性リンパ腫だった。それ以降、73歳の現在までに四つの異時性多重ガン(治療後に別のガンになること)と二度の再発に見舞われ、現在も再発ガンを患っている。悪性リンパ腫に始まり、直腸、前立腺、下咽頭ガンと次から次へと病魔に教われる。にわかには信じがたいが、2006年に下喉頭ガンを公表するまで、妻や事務所の関係者に隠し闘病を続けてきたという。
「余命2年」と最初のガン告知を受けたのは、初当選から10か月あまりのとき。絶頂からの転落。残酷な告知である。その後、懸命にガンと闘った様子を本書は克明に記録する。抗がん剤治療、放射線治療、手術などを繰り返す。抗ガン剤の副作用で髪の毛が抜け、かつらも使っていたという。政党の要職や政府の重要閣僚(3大臣兼務の激務もあった)を務め、選挙戦を戦いながらの闘病は凄いの一語に尽きる。
本書は与謝野の闘病記、当時の政治状況、主治医の手記で構成する。主治医の手記がなかなかいい。専門的な立場からガンの状態、手術の詳細、患者としての与謝野の姿を綴っている。焦らず、慌てず、冷静な与謝野のガンに対峙する姿勢が印象的だ。政治的な立場はともかく一読に値する書である。
|
| |
忘れ去られたCPU黒歴史~Intel/AMDが振り返りたくない失敗作たち~
大原雄介、アスキー・メディアワークス、p.136、\1470 |
2012.7.23 |
|
 |
評者が記者として現場を走り回っていたのは約20年前。専門分野はマイクロプロセサだった。筆者の大原雄介氏と、インテルやAMDの記者会見の場でよく一緒になったのを記憶している。本書は、マイクロプロセサの失敗作(黒歴史)をその背景とともに紹介した書である。気の毒だが、必然的に米インテルと米AMDの事例が数多く登場する。失敗作だけではなく、シリーズの歴史も掲載されており、マイクロプロセサに興味のある方にお薦めの書である。逆にそうでないと、「どこが面白いの?」となるかもしれない。
取り上げられているのは、Timna、iAPX432、台湾製互換チップ、i860、i960、Merced、Am29000、K8、MC88000などなど。オブジェクト指向プロセサとも言われたiAPX432が取り上げたり、英InmosのTransputerに触れているところはさすがである。黒歴史、失敗作という定義からは微妙かもしれないが、個人的にはx86系では米TransmetaのCrusoeやVMTのチップ、NECのデータフロープロセサImPP、米FairchildのClipper、Javaチップなどの消息も知りたかった。
評者が現場にいたころのチップが数多く取り上げられており、「そんなこともあったなぁ」と懐かしさいっぱいの気分になった。多くのマイクロプロセサが入り乱れ、アーキテクチャを熱く語っていた時代を思い出させてくれた。
|
| |
100のモノが語る世界の歴史2~帝国の興亡~
ニール・マクレガー、東郷えりか・訳、p.325、\2205 |
2012.7.20 |
|
 |
大英博物館の所蔵品に歴史を語らせるシリーズの2冊目。本書の対象は紀元前300年から1500年まで。想像をたくましくして太古の人類を描いた第1巻ほどのインパクトはないが、ロゼッタストーンやアレクサンダー大王の金貨といった有名どころが登場するので、それなりに楽しめる。所蔵品の芸術性も第1巻に比べて高くなっているので、本来なら大判で楽しめる方よかった。オリンピックにあわせて夏休みに英国に行く予定があり、大英博物館に寄るなら予習で読むのは悪くない。
第2巻は支配者、宗教、シルクロードといった切り口で所蔵品の数々を紹介する。帝国の支配者として登場するのはアレクサンダー大王のほか、アショカ王、アクグストゥスといった面々。支配者たちが権力を誇示し、異なる民族や文明を服従させるために使った品々を取り上げる。嗜好品や贅沢品、娯楽、宗教興隆を示す所蔵品の物語は興味深い。例えばキリスト最古の肖像の一つが発見されたのが教会ではなく、イギリスの大邸宅の床だったというのはちょっとした驚きである。具象的な像を描き始めたのが、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教でほぼ同時だったというのは人間の営みの不可思議さを感じさせてくれる。
|
| |
障害者の経済学
中島隆信、東洋経済新報社、p.248、¥1680 |
2012.7.13 |
|
 |
先日書評した「刑務所の経済学」の筆者が、「第49回 2006年度 日経・経済図書文化賞」を受賞した出世作。この著者には「相撲の経済学」「お寺の経済学」とついつい誘われるタイトルをつけた本が多い。なかなかのマーケティング巧者である。本書には経済学というタイトルがついているものの、実際には障害者福祉の制度設計や社会の在り方の話がメインになっている。どのようにすれば障害者福祉予算を有効に使えるか、社会は障害者とどのように付き合っていけばいいのかを論じる。
筆者自身が障害者の親ということもあって、微妙な領域にまで踏み込んで議論を進めている。子供を自立させることをためらう親、設備は立派だがニーズにこたえきれていない施設、社会とのギャップが大きい養護学校、使いづらい運賃割引制度など、障害者福祉のさまざまな矛盾を指摘する。しかも親、行政、養護学校、施設のあいだで利害が対立し、問題は複雑の度を増す。障害者の情報が福祉関係者のなかでしか流通しないので、社会全般に障害者福祉に関する理解が進まないことも課題の一つである。示唆に富む指摘にあふれた書である。
|
| |
オリンパス症候群~自壊する「日本型」株式会社~
チームFACTA、平凡社、p.288、\1680 |
2012.7.11 |
|
 |
オリンパス事件をスクープした月刊誌FACTAの発行人・阿部重夫を中心にしたジャーナリストと経済学者が、日本社会に巣食う問題点に切り込んだ書。20年前に端を発したオリンパスの不正が、長年にわたって露見しなかった理由を切れ味よく暴いている。阿部のジャーナリストとしての矜持が前面に出た書である。ちなみに本書の執筆に参加したのは阿部のほか、ジャーナリストの磯山友幸と松浦肇、埋蔵金で知られる嘉悦大学教授・高橋洋一というメンツ。阿部、磯山、松浦が日本経済新聞証券部出身ということもあって、古巣に対する見方はきわめて厳しい。
本書は、20年を超える日本経済不振の元凶を、企業、官庁、監査法人、銀行、証券、メディアの間のもたれ合い、共犯関係に見る。株の持ち合いの問題、監査法人の問題、証券取引所の問題などについて言及する。昔から言われたことを繰り返している面もあるが、オリンパスという新素材を生かし説得力を増している。なお最後に、ホリエモン(堀江貴文)の獄中からの寄稿掲載する。ライブドアが一発で上場廃止されたのに比べ、上場を維持されたオリンパスへの甘い処分に疑問を呈している。
|
| |
日本の幸福度~格差・労働・家族~
大竹文雄、白石小百合、筒井義郎、日本評論社、p.284、\3150 |
2012.7.8 |
|
 |
アンケート調査と経済学的手法によって、幸福度を定量分析した書。日本だけではなく米国の幸福度にも言及し、日米の比較はなかなか興味深い内容となっている。多くは直感と合致するが、「へ~」と意外感のある分析も含まれ、堅目の学術書にしては楽く読める。特に結婚に関する幸福度の男女差は、男性には身につまされる内容かもしれない。ちなみに筆者によると、「日本の幸福の経済学に関する初めての書」らしい。学者っぽく難解な文章で取っ付きにくい章もあるが、そうした部分は読み飛ばしても大勢に影響はない。この手の話に興味があれば読んで損のない本である。
本書は年齢、所得、労働、格差、結婚、性差、子供、地域といった多彩な切り口で幸福度を論じる。例えば、年齢と幸福度はU字型の関係になるという。若年層の幸福度は高いが、40歳前後に最低になり、その後は年齢が高くなるにつれて幸福度は増す。働き盛りで最も忙しく、社会的にも家庭的にも責任が重くなり、同時に自らの行く末が見えてくる時期の幸福度が下がるのは、何となく分かる気がする。
所得が向上しても幸福度はそれに見合っては高くならない「幸福のパラドックス」についての考察も興味深い。絶対所得の向上の約半分は、そもそも幸福度を高める効果はない。さらに1年後には、残り半分の12%、つまり当初の所得増加の6%しか幸福度の向上に寄与しないという。ちなみに米国の調査では、絶対所得の増加の実に3分の2は幸福度を高めない。残りの3分の1の60%は2年後のために慣れのために残っていない。つまり2年後には所得増加の13%しか幸福度を高めない。
このほか女性の方が幸福。格差拡大は幸福度を引き下げる事実はない。むしろ所得格差を認識している人ほど幸福度は高い。女性にとって就労は幸福度は下げるが、家事・育児は幸福度を上げる。夫の家事労働参加は妻の幸福度を高める。興味深い話が満載の書である。
|
| |
ビジネスマンのための「行動観察」入門
松波晴人、講談社現代新書p.272、\798 |
2012.7.4 |
|
 |
人間の行動をつぶさに観察して、行動の裏に隠されている潜在ニーズや課題、ノウハウを見出す「行動観察」を紹介した新書。行動観察をマーケティングや店舗設計、人材育成、工場の生産性向上などに役立てた事例が実に興味深い。類書が出版されていないか、ついアマゾンで漁ってしまった。筆者は大阪ガス行動観察研究所の所長で、米国留学中に行動観察に触れ、日本に持ち帰った。それにしても大阪ガスにこうした研究所があるのは、ちょっと驚きである。知的好奇心を満足させられる新書らしい新書に仕上がっている。
調査というとグループインタビューやアンケートに頼ることが多い。しかし、これらだと人間のニーズを的確に把握したり、経験で培ったノウハウを顕在化するのは難しい。社会通念(日本でいえば「空気」)に引きづられ、どうしてもバイアスがかかりがちである。スティーブ・ジョブズに「消費者に、何が欲しいかを聞いてそれを与えるだけではいけない」という名言があるのは有名だ。行動観察は、観察者が現場に立って行動を観察・分析することから、ニーズやノウハウをあぶりだす。社会心理学や環境心理学、人間工学、表情分析などを総動員して、人間の行動を科学するわけだ。
本書で筆者は、ワーキングウーマンの潜在ニーズ、オフィスの残業を減らす方法、トップ営業マンの接客法、ホテルのドアマンに学ぶ記憶術、スーパー銭湯の集客法を、行動観察によって引き出している。それぞれ「そうなのか !?」と思わせる内容で、読んで得した気分になる。
|
| |
FabLife~デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」~
田中浩也、 オライリージャパン、p.224、\2310 |
2012.7.3 |
|
 |
パーソナル・ファブリケーションの入門書。パーソナル・ファブリケーション(工業の個人化)とは何か、歴史、世界的な活動状況、日本の状況、14週にわたる講習の内容などについて解説している。初めて知った話が多く、興味深い内容にあふれている。日本で普及するかどうかは微妙だと思うが、今後のモノづくりの一つの方向性を示しているのは確か。ちなみに著者は、米MIT発祥のパーソナル・ファブリケーションを日本に導入した先駆者であるとともに、実践の場であるファブラボ運営を主導している。
パーソナル・ファブリケーションを生んだのは、パソコンとインターネット、工作機械の小型化である。これらがデスクトップ・ファブリケーションと呼ばれる環境を整えた。特に工業機械の貢献は大きい。手軽な3Dプリンタやカッティングマシン、ミリングマシンの登場が、欲しいものを手元で作るという動きにつながった。インターネットを介した情報共有と情報交換が後押しした格好である。
|
| |
なぜ、日本企業は「グローバル化」でつまずくのか~世界の先進企業に学ぶリーダー育成法~
ドミニク・テュルパン、高津尚志、日本経済新聞出版社、p.211、\1890 |
2012.7.2 |
|
 |
スイスに本拠を置くビジネススクールIMDの学長と日本代表が、日本企業の戦略を分析するとともに、今後に向けた処方箋を書いた本。ビジネススクールらしくネスレ、GE、ヴェオリアなどの事例をあげながら、日本企業に足りない部分を指摘する。強化すべきポイントはダイバーシティ(多様化)とグローバル化、イノベーションの三つ。画期的な打開策を披露しているわけではないが、豊富な事例もあって説得力はさすがである。ちなみに日本企業では花王や住友商事、JTを成功例として取り上げている。
それにしてもIMDが公表している世界競争力ランキングにおける日本の凋落ぶりは目を覆うばかり。1989年~1992年は1位だったものが、2011年は59国中26位。時代の波に乗り遅れた格好だ。長期戦略がないうえに、もはや競争優位につながらない高品質へのこだわりが足を引っ張り、モノしか見ずエコシステムの構築を疎かにしたツケを払わされているというのが著者の分析である。生産現場以外におけるマネジメントの失敗だと断じる。「モノづくりへのこだわり」という言葉が「よいモノを作っていれば売れる」という考えにつながりやすく、マーケティングやブランディング軽視につながりかねない点に警鐘を鳴らす。
興味深いのは幹部教育の必要性を繰り返し述べている点。現在の幹部層は先進7カ国(G7)時代のマインドセットしか持ち合わせず、G20の世界観に対応できていない。そもそもインターネット以前の世代である。企業は若手の研修や教育には熱心だが、彼らが幹部になるにはまだ間がある。喫緊の課題は幹部の教育だと指摘する。ちなみに筆者が挙げるグローバル・マインドセットは、認知管理力と関係構築力、自己管理力である。
|
| |
|
|

|
2012年6月 |
あなたは未来、あなたは可能性
吉田和正、日経BP社、p.175、\980 |
2012.6.28 |
|
 |
インテルの吉田社長の書。タイトルから推察できるように10代の若者向けである。「英語は必要か」「世の中はどうなるか」「どんな仕事がいいか」といった疑問に答えるとともに、吉田社長が面識のある著名人との対談を収録している。ちなみに吉田社長には取材先としてお世話になったし、本書の出版元は評者が勤める会社、担当者は同僚である。それを前提にこの書評を読んでもらいたい。EISの読者の多くは、年齢的に対象外かもしれないが・・・
対談に登場するのは、歌手の郷ひろみ、横綱・白鵬、ファッション・デザイナの渋谷ザニー、ロボットスーツ開発者の山海・筑波大学教授と、ちょっと意外な面々である。渋谷ザニーの名前は寡聞にしてしらなかった。担当者によると、選択したのは吉田社長自身だという。
出色なのは郷ひろみとの対談である。対談やインタビュー慣れしている面はあるが、華やかなイメージとは別の面を引き出しているのは事実。ストイックな考え方に「ほぅ」と少し驚く。他の三つの対談も悪くない。ただし郷ひろみのインパクトが大きすぎ、影が薄くなった面は否めない。
|
| |
ヒューマン~なぜヒトは人間になれたのか~
NHKスペシャル取材班、角川書店、p.423、\1600 |
2012.6.27 |
|
 |
「人間とは何か」を探ったNHK特集を単行本化した書。心の進化、道具、農耕、お金と大きく四つの切り口で人間の進化を追っている。構想からTV放映まで12年を費やしたプロジェクトである。考古学はもちろん、心理学や遺伝子学、脳科学、経済学の最新の知見をカバーした取材量はさすがNHK。シミュレーション、実験、DNA解析など、先端技術を活用した知見を紹介する。壮大なテーマによく応えている。本書だけでも読み応え十分満足だが、どのように映像化されたのかやはり気になる。TV番組を見なかったことが悔やまれる。400ページを超える書なので、まとまった休暇がとれたときに読むのがいいだろう。
四つの切り口はいずれも興味深いが、特に知的好奇心を刺激するのが「心」の話だ。現代人に至るホモサピエンスに分化してから20万年。人間らしさのポイントは、仲間を思いやる心や分かち合う心というのが本書の見解である。チンパンジーは仲間を助けることはできるが、助け合うことはできない。積極的に、ときには先回りして助け合うところに人間らしさを本書は見る。協力が突然変異や自然淘汰と並ぶ、第3の進化の柱とみなす研究成果を紹介する。突然変異や自然淘汰だけでは、30億年前の細菌から、今の世界に至る理由が説明できないという。
人類は協力する心をもったおかげで生き延びた。キッカケは7万4000年前に起こったインドネシアのトバ火山の大噴火。寒冷化が進み人類は生存の危機に立たされた。ホモサピエンスは生誕の地アフリカから脱出せざるを得なくなったが、そのなかで協力することを学んだ者たちだけが生き残ったというストーリーである。
道具の話も刺激的だ。現代人につながるのは、2回目の出アフリカで生き残ったホモサピエンスである。1回目は、屈強なネアンデルタール人の滅ぼされた。2回目の出アフリカを行ったホモサピエンスが、ネアンデルタール人を打ち負かした背景にあったのが道具である。見てきたような話でワクワクする。
|
| |
医者は現場でどう考えるか
ジェローム・グループマン、美沢惠子・訳、p.311、¥2940 |
2012.6.22 |
|
 |
「なぜ医者は診断を間違えるのか」「誤診しない医者の特徴は何か」について、ハーバード大学医学部教授が論じた書。興味深い話が満載である。3年で5人の医者を渡り歩いて痛みの原因を突き止めた自らの体験も含め、事例が豊富である。こんな病気があるのか、医者はこれほど間違えるのか、といった驚きにあふれている。X線写真の読影精度がこれほど低いというのはちょっと驚きである。帯にあるように医学生や若い医師向けだが、誤診を防ぐために患者や家族ができることについても言及しており、多くの人にお奨めできる書である。
誤診しない一つのポイントは、患者をしっかり見ること。患者の物語を予断を持つことなく聞き、他の医者の診断に引きずられないことが肝要だと説く。アルゴリズム化したディシジョン・ツリー(フローチャート)に従い診断することは、医者の思考を制約することにつながると警鐘を鳴らす。誤診しないポイントは医者が自ら考えること。数字やIT機器に頼って、受動的に診断することは危険だと指摘する。
誤診の原因は医者の技術の問題よりも、感情や心理的な影響にあることを本書は明らかにする。例えば最初に下された診断にこだわったり、自らの診断を支持するデータに注目し否定するデータを軽視してしまう傾向にある。患者に対してネガティブな感情があると医者の目が曇り、誤診につながるという。
このほか製薬会社や医療機器メーカーなどの医療産業が診断に与える影響についても言及する。経済的な動機によって、自然な加齢による体調の変化が、立派な疾患に化けてしまう状況を危惧している。
|
| |
「ガード下」の誕生~鉄道と都市の近代史から
小林一郎、祥伝社新書、p.232、\819 |
2012.6.19 |
|
 |
鉄道高架の下に広がる空間「ガード下」を訪ね歩いた書。ガード下がどのように誕生し発展したのか。法律(権利関係)はどうなっているのか、住所表記はあるのか、などのエピソードを満載する。系統だった調査ではないのでガード下の網羅性については少々疑問が残るが、興味深い話が次から次へと登場するのは確か。素直に楽しめばいい本だろう。なぜか大阪の美章園や神戸・元町のガード下など、評者にとって思い出深い場所を多く取り上げている。つい肩入れしたくなる。
建築関係の仕事に携わっている筆者なので、意匠や構造に関する解説が本書の売り物の一つ。プロの指摘は「さすが」と思わせる。日ごろ使っている駅の知られざる“見所”を教えてくれる。通勤に使われている駅があれば、駅の外に出て観察されてはどうだろう。例えば首都圏では、有楽町、秋葉原、上野~御徒町、浅草橋、両国、日暮里のガード下が登場する。
ちなみにガード下というと、まず思い浮かべるのは「飲み屋」だろう。評者だと、有楽町の風景が頭に浮かぶ。しかし本書を読むと、ホテルやブティック、アトリエ、神社、住宅、保育園など、さまざまな施設がガード下に入っていることがわかる。ガード下のホテルだと振動が気になるところだが、免振技術が進む気にならないレベルにあるという。ちなみに、このホテル。ディズニーランドのある舞浜駅に存在する。
|
| |
Think Simple~アップルを生みだす熱狂的哲学~
ケン・シーガル、高橋則明・、NHK出版、p.320、¥1680 |
推薦! 2012.6.14 |
|
 |
評者の本棚でジョブズ本を含むアップル本がどんどん増殖している。いまやIBM本やマイクロソフト本と肩を並べる。ジョブズ死後もアップルの勢いは止まっていないので、間もなく抜き去るのは確実だ。本書はそうしたアップル本のなかでもベスト3に入る。“Simple”というJobsの行動哲学にアップル成功の秘密を見いだし、多くのケーススタディを盛り込んだビジネス書である。アップルやジョブズに興味を持つ方にお薦めしたい。
筆者は「Think Different」キャンペーンに参画し、iMacを命名した広告会社のディレクター。Jobsとは付き合いは10年以上に及ぶ。Apple追放からNeXT設立、Apple復帰まで、Jobsをつぶさに見続けてきた人物だけに、興味深い逸話にあふれている。インテルやデルの広告キャンペーンにも携わった経験をもつ筆者は、アップルとこの2社のビジネスの違いを具体事例を挙げて論じており、説得力十分である。
アップルが信じる「シンプル」という行動哲学は、言うのは易いが、行う(行い続ける)のは難しい。強烈な信念がないと維持できない。会社組織では、つい複雑さの誘惑に負けてしまう。当初はシンプルでエッジがたったアイデアも、会議を繰り返し、会社の階層を上るにつれて、角が取れると同時に複雑さの衣をまとう。結局、可もなく不可もなくの平凡なアイデアになってしまう。
筆者はシンプルであり続けるためのポイントを10個挙げ、それぞれに1章を割く。具体的には、第1章 容赦なく伝える(Think Brutal)、第2章 少人数で取り組む(Think Small)、第3章 ミニマルに徹する(Think Minimal)、第4章 動かし続 ける(Think Motion)、第5章 イメージを利用する(Think Iconic)、第6章 フレーズを決める(Think Phrasal)、第7章 カジュアルに話し合う(Think Casual)、第8章 人間を中心にする(Think Human)、第9章 不可能を疑う(Think Skeptic)、第10章 戦いを挑む(Think War)である。
|
| |
別海から来た女~木嶋佳苗 悪魔祓いの百日裁判~
佐野眞一、講談社、p.290、¥1575 |
2012.6.12 |
|
 |
3件の殺人を行ったとして、2012年4月に死刑判決をうけた木嶋佳苗を追ったノンフィクション。佐野眞一の事件モノといえば「東電OL」だが、この事件も勝る劣らず特異だ。佐野はいつものように周辺を徹底的に洗いながら、目撃証言も自供もない事件の背景を奥行きをもたせて明らかにしていく。もっとも、木嶋の人格描写が妙に目立ち過ぎているところが少し気になる。佐野の筆を微妙に狂わすほど異常な人格なのだろう。平成の事件史に残る話なので、全容を知っておくのも悪くない。新聞の社会面を熱心に読んでこなかった方にお薦めの書である。
佐野は木嶋事件を、怨念も流血もなく殺意の沸点が異様に低い、いまという時代でしか生まれなかった犯罪と言い切る。確かにインターネットの出会い系サイトで中高年の独身と知り合い、結婚をえさにお金を貢がせる。カネを巻き上げたあとは、睡眠薬で眠らせ、練炭自殺に見せかけ殺すといった手口は今風なのかもしれない。
ちなみにタイトルの「別海」とは木嶋の出身地。佐野は北海道別海町に足を運び、名家に育った木嶋の人格がどのように形成されたかを親戚や同級生の取材で浮き彫りにしている。このあたりは相変わらず見事な手際である。
|
| |
グーグル化の見えざる代償~ウェブ・書籍・知識・記憶の変容~
インプレス選書、シヴァ・ヴァイディアナサン、久保儀明・訳、p.320、¥2100 |
2012.6.11 |
|
 |
情報や地図、画像、書籍の検索など、グーグルのサービスの利便性に慣れ親しんだ結果、我々が「失った」あるいは「失おうとしている」ものを多角的に論じた書。ヒステリックに警鐘を鳴らすのではなく、グーグル化が進行する世界について、是は是、非は非として冷静に考察しており好感が持てる。バージニア大学教授の筆者は、グーグル化の社会的および文化的な危険性を指摘し、テクノロジーへの盲信と崇拝を捨てるように提言する。少し立ち止まって、グーグルへの過度の依存を考えることの大切さを気づかせてくれる書である。
筆者の危機感の原点は、我々がグーグルとテクノロジーを過度に当てにし、信じ過ぎているところにある。グーグルの若さと経験の乏しさ、テクノロジー原理主義にもとづく傲慢さに懸念を示す。我々は、“Don't Be Evil”の社是を信じ切った結果、深く考えることなく、文化と知的資源のデジタル化と配信、さらにはプライバシーをグーグルに委ねてしまった。
しかしグーグルは神ではない。利益を追い求める企業である。自らの評判を管理する権利を譲り渡すなど、むやみに信頼するのは危険性をはらむ。実際、グーグルというレンズを通して眺めた世界は歪んで屈折していると、筆者は具体例を挙げて指摘する。例えば宗教、ユダヤ人、神といった争いのある項目は、国・地域によって検索結果が異なるように操作されている。国境をめぐって紛争中の場合も、当事国によって国境線の表示を変えているという。
|
| |
100のモノが語る世界の歴史 1 文明の誕生
ニール・マクレガー、東郷えりか・訳、筑摩選書、p.285、¥1995 |
2012.6.6 |
|
 |
大英博物館が250年にわたって収集したモノから100点を厳選し、それらに世界史を語らせるという企画。歴史好きには堪らない内容である。数点の写真と10ページほどの文章の組み合わせも絶妙で、テンポよく読み進むことができる。歴史好きでなくても十分楽しめるので、多くの方にお奨めである。
元々は2010年に放送された英国BBCのラジオ番組。さすがBBCである。3巻シリーズの第1巻は、200万年前から紀元前300年までが対象。記録がろくに残っていない時代なので、筆者は想像をたくましくして歴史をよみがえらせている。一つの出来事を証明するモノよりも、多くの物語を語る所蔵品を優先的に選んだという方針が功を奏し、いずれの所蔵品もなかなか雄弁である。
本書は、大英博物館らしくミイラから始まる。エジプトで出土した木製のミイラ棺をまず紹介する。色彩鮮やかな美しい写真で度肝を抜かれるだろう。その後も見所が多い。例えば、フランスで出土したマンモスの牙を使った「泳ぐトナカイ」の彫刻。氷河期の人間が、こうした彫刻を彫っていたことを想像するだけで楽しい。そもそもマンモスの牙製の彫刻というところに素直に驚かされる。ホンジュラスで出土した「トウモロコシの神の像」、北ウェールズの「黄金のケープ」、エジプトの「ラムセス2世像」、スーダンの「タハルコのスフィンクス」など、本書に登場する文物の造形の美しさは、いずれも尋常ではない。
古代文字の所蔵品も興味深い。絵文字や楔形文字を刻んだ粘土版は立派な美術品である。例えば、ビールと官僚制度の誕生について書かれた5000年前の書字版。現存する最古の文字(絵文字)が掘られているが、不思議な雰囲気を漂わせている。イラク北部で出土した粘土版には、何とノアの方舟に類似した洪水の物語が書き込まれている。しかも推定年代は、聖書で現存する最古のものよりも400年はさかのぼる。
|
| |
刑務所の経済学
中島隆信、PHP研究所、p.256、\1470 |
2012.6.4 |
|
 |
タイトルにつられて購入した書。中身は経済学の範囲を超え、けっこう面白い。買って正解だった。筆者は犯罪者が罪を償うためにかかる経費と社会的損得を天秤にかけて論じる。老人ホームか障害者施設かと見まがう刑務所の実態を明らかにするなど、読みどころの多い書である。元代議士・山本譲司の「獄窓記」と併せて読むといいかもしれない。
本書は事例が具体的で、ぐっと引きつけられる。例えば300円の万引きが1カ月の拘置期間ののち、懲役6カ月の判決を受けて出所した場合。この間に、国選弁護士費用や裁判費用、拘置所の収容費用、刑務所の収容費用など計130万円の税金が投入される。あるいは受刑者の収容費用は年間300万円。300万円を投じて犯罪者を社会的に隔離し無力化することが、コスト的に見合うかどうかを考察する。
本書は、終身刑の経済学的な是非や厳罰化の抑止効果など興味深い視点を提供している。日本ではマスコミの影響で、実際の治安と体感治安のギャップが大きい。終身刑議論の背景には、こうした体感治安の悪化があると著者は見る。しかし終身刑の受刑者が高齢になり犯罪能力が低下した場合にも、刑務所に収容して無力化することが、本当に社会的や財政的にも妥当なのか疑問を呈する。
|
| |
スタートアップ!~シリコンバレー流 成功する自己実現の秘訣~
リード・ホフマン、ベン・カスノーカ、有賀裕子・訳、日経BP社、p.304、¥1680 |
2012.6.1 |
|
 |
読むと元気が出る書。「心配の多くは杞憂に終わる。案ずるより産むが易し。まず行動を起こせ」が全体を通してのメッセージである。セレンディビティ(偶然の幸運)は、動き回っているときにやってくるからだ。筆者はビジネスパーソン向けSNS「LinkedIn」の共同創業者。自らやシリコンバレーの起業家たちの事例に基づいた成功の秘訣を伝授する。起業家たちの逸話が適度に散りばめられているので楽しく読める。気分転換にお奨め書である。
米国西海岸のビジネス作法が色濃く出ており、日本とは状況が違うという声が聞こえてきそうだが、読後の印象は悪くない。例えば、リスクは人生の一部という考え方は共感が持てる。人間は本質的にリスクを避けるようにできている、しかしリスクは、自分が思うほど大きくないと筆者は説く。起業家だけではなく、多くの方に役立つ情報が詰まっている。ここまでポジティブだと天晴れという気持ちになれるだろう。
このほか「自らの人生を永遠のベータ版と位置づけよ」と筆者は語る。正式版に向けて、前進あるのみとはっぱをかける。ビジネスパーソンとしてのアイデンティティは生来備わっているものではなく、行動を起こし、経験を積むなかで生まれてくると説く。このとき、ビジョンと資産(能力)、市場ニーズのバランスをとることが重要だと筆者は指摘する。行動を起こすときに筆者が勧めるのが「ABZプランニング」。まずAプランから始める。不調な場合はBプランに切り替える。AもBもダメなときに緊急避難として駆け込むのがZプランである。最悪を想定して準備し、楽観的に行動することが肝要だと説く。
|
| |
|
|

|
2012年5月 |
真実~新聞が警察に跪いた日~
高田昌幸、柏書房、p.285、\1955 |
2012.5.30 |
|
 |
北海道新聞と北海道警察が争った名誉毀損裁判における裏交渉の実態を明らかにしたノンフィクション。筆者は北海道新聞の元報道本部次長。裁判の一因となった「裏金報道」や「泳がせ捜査失敗報道」を手がけた元記者である。取材や裁判資料などをもとに警察と新聞社の行状を暴いている。日本社会の在り方の一端を知ることができる貴重な1冊である。読んで損はないだろう。ちなみに裁判は決着がついており、北海道新聞が敗訴している。
両者が対立した発端は、北海道新聞が2003年から2005年にかけて行った「北海道警察の裏金問題キャンペーン」。捜査協力者と費用をでっち上げ、そのお金を警察幹部が私的に流用していた事件である。当初は否定していた警察だが、幹部の内部告発などがあり、最終的に裏金作りを認めざるを得なくなった。このキャンペーンで北海道新聞は新聞協会賞、日本ジャーナリスト会議大賞、菊池寛賞を受賞したが、同時に警察の恨みも買ったのである。
両者の関係をさらに悪化させたのが「泳がせ捜査失敗報道」。北海道警察が覚せい剤130kg、大麻2tの摘発にしくじったという大スキャンダルである。北海道県警は記事を真っ向から否定。北海道新聞を実質的に出入り禁止にし、警察ネタを北海道新聞に流さなくなった。干上がった新聞は、幹部が原告(北海道警察の元幹部)が30回以上の秘密会談をもち、お詫び社告を出すとともに、出来レース裁判をもちかかる。何とも情けない状態に陥る。サブタイトルにあるように、「新聞が警察に跪いた」格好である。
本書は最後に「泳がせ捜査失敗報道」に関する新証言を紹介している。にわかには信じがたい爆弾証言だが、これは読んでのお楽しみである。
|
| |
高橋是清と井上準之助~インフレか、デフレか~
鈴木隆、文春新書、p.255、\872 |
2012.5.27 |
|
 |
現在の日本経済と経済政策を、昭和初期と比べながら描いたノンフィクション。主人公は、日銀総裁と大蔵大臣を歴任した高橋是清と井上準之助。2人はもともとは上司と部下の関係にあり、昭和初期に活躍した大物政治家・エコノミストである。インフレ財政(国債発行)の高橋とデフレ政策(緊縮財政)の井上、経済政策の方向性は真逆だ。しかし信ずるところを突き進み、いずれも暗殺される。著者は、政治家の姿勢に対する私見を随所に交えながら筆を進める。味わいのあるノンフィクションに仕上がっている。
高橋と井上は、金融恐慌や関東大震災が日本を襲った時代に財政を指揮した。しかも軍部が台頭・暴走し、大戦の足音が迫っている状況である。生命も脅かされ、実際に井上は右翼の血盟団に、高橋は2.26事件で青年将校に暗殺された。こうした難しい時代に舵取りを任された2人は、それぞれ金解禁とリフレーション政策という劇薬で日本経済の立て直しを図った。
井上の金解禁は環境の悪さもあって日本経済を疲弊させた。一方、高橋のリフレ政策によって日本は世界に先駆けて不況から脱出した。「ケインズよりも早く世界大恐慌からの脱出策を編み出した」という高橋への評価を筆者は紹介する。
|
| |
フェア・ゲーム
ヴァレリー・プレイム・ウィルソン、高山祥子・訳、ブックマン社、p.287、\1800 |
2012.5.24 |
|
 |
筆者のヴァレリー・プレイム・ウィルソンはCIAの元諜報員。夫は元駐ガボン大使である。いずれも体制側の人間だが、夫のイラクの大量破壊兵器製造を否定する寄稿をキッカケに、夫婦はブッシュ政権から目の敵にされる。妻はCIA諜報員であることをリークされ、夫とともにマスコミの標的となる。ホワイトハウスが仕掛けた工作の数々や、政権の片棒をかつぐ一部マスコミの実態を本書は暴露する。米国の一流紙や著名ジャーナリストがこんなことをするのかと少々驚く。なんとも凄まじい話の連続である。映画のような実話という表現がピッタリ。本書は実際、映画『フェア・ゲーム』のネタ本となっている。カタカタの人名を頭に入れるのは一苦労だが、暇つぶしに読むのには悪くない1冊である。
CIAの機密(この場合は諜報員の実名)を暴露するのは犯罪である。そのためブッシュ政権の陰謀は結局、法廷の場で明らかにされてしまう。本書を読むと、ブッシュ政権のレベルの低さを改めて感じてしまう。本書が衝撃的なのは、CIAの検閲が入った“黒塗り”の箇所がいくつも登場すること。さほど機密と関係なさそうな部分なのだが、諜報員の足跡を消すための措置なのだろう。それにしても実に生々しい。
|
| |
続・日本の歴史をよみなおす
網野善彦、ちくまプリマーブックス、p.204、¥1260 |
2012.5.22 |
|
 |
従来の日本史観を覆す網野史観を展開する歴史学者・網野善彦。前作「日本の歴史をよみなおす」が実に興味深い内容だったので続編も購入。本書も期待を裏切らない好著である。常識として考えてきたことが、事実と異なっているという指摘は新鮮である。
続編で取り上げるのは、農民を中心に置いた日本史観の問題点。具体的には、「日本の中世や江戸時代は本当に農業社会だったのか」である。筆者によると、江戸時代や中世は商業・金融が有効に機能した社会で、非農民はけっして少数派ではなかったという。また商業や金融の担い手として女性や僧侶が果たした役割についても史料を基に指摘する。
確かに中世や江戸時代というと、民衆のほとんどを農民が占めていたようなイメージを持ちがちだ。これは、歴史家が「百姓=農民」と思い込んで史料を読んだために生まれた誤解だと筆者は指摘する。畳み掛けるように「水のみ百姓=土地を持たない貧しい農民」の誤りを取り上げる。水のみ百姓は廻船業などを営み豊かだったため、農業を手がける必要はなかったというのが筆者の主張である。
|
| |
予測できた危機をなぜ防げなかったのか?~組織・リーダーが克服すべき3つの障壁~
マックス・H・ベイザーマン、マイケル・D・ワトキンス、奥村哲史・訳、東洋経済新報社、p.336、¥2940 |
2012.5.18 |
|
 |
「危機を予見していたのに、どうして大惨事を防げなかったのか」「予測できた危機を防止するための方策」についてハーバード・ビジネススクールの2人の教授が論じた書。失敗の傾向と対策について説いており、優れたリーダー論である。米国の書籍らしく具体的なケーススタディが豊富で、説得力をもった論考が本書の魅力となっている。2段組みで300ページ以上の大著なうえに、翻訳が堅いのでスイスイ読めるとは言えないが、時間をかけ我慢して読んでも損のない1冊である。
ケーススタディとして取り上げるのは9.11やエンロン事件、環境問題、航空会社のマイレージ、先進国の年金と医療など。いずれも問題の存在を指摘されながら、大惨事を引き起こしてしまった(あるいは、引き起こそうとしている)。リーダーたちは、心理的な要因、組織的な要因、政治的な要因によって、有効な手が打てなかったというのが著者の見立てである。人間の愚かさがよく分かる。いまなら福島原発が格好の事例になっただろう。
本書を読んで強く感じるのは政治の問題が日米(広く言えば民主主義国家)で共通しているところ。圧力団体(ロビー活動)や政治献金などが、どれだけ危機対応を歪めてきたかを本書を明らかにする。業界団体寄りの政治は、いずこも同じようだ。「失敗の傾向と対策」のうち、対策の部分は紙幅の関係で若干食い足りないが、1冊の書籍になりそうな内容なだけに仕方がないだろう。
|
| |
なぜデザインが必要なのか~世界を変えるイノベーションの最前線~
エレン・ラプトン、カーラ・マカーティ、マチルダ・マケイド、シンシア・スミス、北村陽子・訳、英治出版、p.208、\2520 |
2012.5.13 |
|
 |
世界が抱える問題をデザインを通して解決する事例の数々を紹介した書。2010年にニューヨークで開催された国際デザイン展「Why Design Now?」の出品物138点を収録しており、デザインの重要さや楽しさを堪能できる。実用に供されているデザインもあれば、実験的な試みも取り上げており興味深く読める。大きな写真と適度な文章で構成されており、休日にリラックスしながら写真を眺めるだけでも満足できる1冊である。
本書は8分野に分けて先進的・実験的なデザインを紹介している。エネルギー(電力や照明)、移動性(鉄道や自動車などの乗物)、コミュニティ(主に建築物)、素材(紙や石、布など)、豊かさ(貧困や難民問題への対応)、健康(身体支援や乳幼児対策など)、コミュニケーション(インフォグラフィックスやアクセシビリティの向上など)、シンプリシティ(素材やデザインの簡素化など)である。
日本人の作品も少なくない。「使い捨てでも美しく」を身上にする紙食器や三宅一生のアースカラー採集プロジェクト、ホンダのボディウェート・サポートアシスタント(脚、腰、膝、くるぶしにかかる重さと負担を軽減する装置)など素敵な事例が多い。ちなみのIT関連ではiPhone、Kindle、OLPC(One Laptop Per Children)プロジェクト、Twitterなどを取り上げている。
|
| |
昭和天皇伝
伊藤之雄、文藝春秋、p.588、¥2300 |
推薦! 2012.5.9 |
|
 |
昭和天皇の人生を史料に基づき丹念に追った書。評者のような世代は、新聞やテレビ、雑誌などで戦後の昭和天皇の動向をリアルタイムで知るとともに、戦前と戦中については多くの書物から知識を得ている。本書を読むと、そんな知識がいかに浅薄なものだったかを思い知らされる。昭和天皇に対するイメージが大きく変わる1冊である。
本書には、佐野眞一の評伝の匹敵する凄みがある。ただし佐野の作品にはノンフィクション作家らしいエンタテインメント性があるが、本書は学者らしい綿密さと冷徹さ、自信に溢れている。600ページ近くの大著だが、ワクワクしながら読み進むことができる。ちょっと時間がとれる休暇や海外出張のお供にお薦めの1冊である。
読み応えがあるのは戦前から戦中の部分だ。指導者としての経験に乏しい天皇即位直後の迷い、戦争へと暴走する軍部や政治家との駆け引きにおける苦悩と失敗、経験を積んで円熟したリーダーとして下した終戦の決断など、筆者は時には厳しいことばを使いながら昭和天皇の姿を活写する。昭和天皇がどのようにリーダーとして成長していったのかを、史料や文献を詳細に読み込みながら明らかにしていく。表面的に歴史を追うのではなく、昭和天皇の内面に踏み込んで成長過程を辿っている。戦争に対する道義的な責任を感じ、自らを律した戦後の姿も興味深い。
知られざる私生活について触れているところも本書の特徴の一つ。母である貞明皇太后との関係、妻・良子皇后や皇室と美智子妃との確執、女官問題など実に生々しい。
|
| |
インサイド・アップル
アダム・ラシンスキー、依田卓巳・訳、早川書房、p.280、¥1680 |
2012.5.2 |
|
 |
知られざる米Appleの組織と幹部の実際を明らかにしたノンフィクション。筆者は米Fortune誌記者で、この書評でも取り上げたKindle版「Inside Apple」も執筆した。本書は、「Inside Apple」の中身を深耕するとともに、ジョブス死後のAppleについても言及する。秘密主義のApple社の内部システムを知る上で価値のある情報が詰まっており、本棚に並べて損のない1冊である。
社内情報の漏洩を極度に恐れるApple社らしく、取材源は元幹部や匿名希望の社員が大半を占める。本書の主役ジョブスやティム・クック(現CEO)へのインタビューさえも行っていない。ビジネス書としての要件を満たさないし実名報道の迫力に欠けるが、数十人の現・元Apple社員の証言は読み応え十分である。
本書が取り上げる話題は多岐にわたっている。経営陣の人物評、意思決定のプロセス、幹部教育プログラム(初めて聞くApple大学)、待遇など興味深い話題が並ぶ。ジョブスについては決定版の評伝が出ているので、もはや得るところは少ない。しかし、ジョブズ以後のAppleを支える面々の人物評は悪くない。特に現CEOであるクック、デザイン部隊を率いるジョナサン・アイブ、iOS担当で次期CEOの呼び声高いスコット・フォーストールの情報は貴重だろう。
|
| |
|
|

|
2012年4月 |
日本の歴史をよみなおす
網野善彦、ちくまプリマーブックス、p.237、\1260 |
2012.4.30 |
|
 |
従来の農耕民中心の日本史観に疑問を呈し、漂泊民の視点から日本史を描く網野史観が色濃く出た啓蒙書。南北朝(14世紀)の前と後で、日本は大きく変わったという史観は興味深い。15世紀以降の社会の在り方は、現在の我々にも理解可能だが、13世紀以前は我々の常識では及びもつかない異質な世界だったと論じる。転換期にある現代の日本を考える上で、後醍醐天皇の出現によって日本が大きく変化した14世紀に思いを馳せるのも悪くないというのが筆者の主張である。この書評で取り上げた「中国化する日本」と通底する。ちょっと変わった日本史観に興味がある方に向く書である。
本書は、文字、貨幣と商業・金融、畏怖と賤視、女性、天皇と「日本」の国号といった論点から14世紀の日本を論じる。特に絵巻物に描かれた人物を注意深く観察し、当時の庶民、特に漂泊民の生活や風俗を生き生きと再現するところに本書の真骨頂がある。
|
| |
うつ病の常識はほんとうか
冨高辰一郎、日本評論社、p.195、\1680 |
2012.4.26 |
|
 |
タイトルからは「うつ病」にまつわる誤解を解く書のように思えるが、内容はちょっと違う。筆者が力を入れているのは、うつ病よりも自殺の話。日本人の自殺は正規化すればけっして増えていないという主張に、全体の3分の1を割いている。タイトルに引かれて購入すると後悔するかもしれない。ちなみに筆者はパナソニック東京健康管理センター予防医療部メンタルヘルス科東京担当部長を務める産業医である。
日本の自殺の増加=ストレスと見なされることが多いが、実際は異なっている。日本の人口構成、つまり自殺する可能性の高い年齢層の増加に原因がある。正規化(本書では標準化)すれば、70年代や80年代から大きく変化していないことを筆者は明らかにする。報道の問題にも触れている。自殺の統計や専門家のコメントをメディアが報じるだけで、自殺が増える傾向にあるという。
残り3分の2で、筆者はうつ病にまつわる常識に対し疑問を呈している。例えば、うつ病受診者が増えているのはストレスの増加でよりも、啓発活動によって早期受診が世の中に浸透したことが寄与していると主張する。特定の生活傾向の人だけがうつ病になりやすいと強調するのには無理があると断じる。
|
| |
サムライと愚か者~暗闘オリンパス事件~
山口義正、講談社、p.226、\1470 |
推薦! 2012.4.24 |
|
 |
オリンパスの粉飾決算(損失隠し)を暴いた日経新聞証券部記者出身の経済ジャーナリストが、月刊誌「ファクタ」でのスクープまでの経緯、スクープ後の動きを詳細に語った書。スクープをものしたジャーナリストの緊張感が伝わり、読み応え十分である。日本のジャーナリズムの問題点と在るべき姿を知ることができる良書である。取材源の秘匿のため手を加えた形跡もあるが、それを補う価値と力強さが本書からは感じられる。名門企業のスキャンダルを忘れないためにも是非とも読んでいただきたい。
評者はファクタ読者なのでスクープ記事をリアルタイムで読んでいるし、阿部重夫・発行人のオリンパスに対する刺激的なブログも目にしている。しかし、その裏側での動きは知る由もない。本書を読むと、その一部始終を知ることができる。友人からの内部告発の情報提供、阿部との出会い、ウッドフォードにオリンパス問題を伝えることになった偶然、ウッドフォードとの仲介役をはたす怪僧の登場など、まさに天網恢々疎にして漏らさずである。ウッドフォードの言葉「日本人はなぜサムライとイディオット(愚か者)がこうも極端に分かれてしまうのか」は耳に痛い。
|
| |
帝国ホテルの流儀
犬丸一郎、集英社新書、p.176、\735 |
2012.4.23 |
|
 |
映画「JM」でキアヌ・リーブスは、アドリブでこう語ったという。「シャツを洗濯に出したい。できれば帝国ホテルのランドリーに」と。ここまで持ち上げられたサービスの原点を、父親と二代にわたって帝国ホテルの社長を務めた著者が洒脱な筆致で披露している。期待せずに読み始めたら想像以上に面白く、得した気分にさせられた。ルームサービスの達人やランドリーの達人の話などエピソード中心の内容なので、休日の暇つぶしにぴったりである。
本書で筆者は、「キメ細かさとさりげなさのバランスを重視する」といった「もてなし」術、国内初のオンラインシステムの導入、フランク・ロイド・ライトが設計したライト館の取り壊し決断、戦後の海外留学第1号に息子を送り出した父親の帝王学などを紹介している。帝国ホテルが日本で初めてバイキングを導入するまでの逸話などトリビアが満載である。交友録では、藤原義江、白洲次郎、小佐野賢治(帝国ホテルの株を買い占め取締役に就任)などが登場する。なかでも白洲次郎のかっこよさは格別である。
|
| |
こうして世界は誤解する~ジャーナリズムの現場で私が考えたこと~
ヨリス・ライエンダイク、田口俊樹・高山真由美・訳、英治出版、p.288、¥2310 |
2012.4.20 |
|
 |
1998年から2003年に中東特派員として活躍したオランダ人ジャーナリストによる報道現場の実態報告。西欧における中東報道が、どのように作られているかを詳細にレポートする。最も影響力のある国際ジャーナリスト40人」にも選ばれた筆者が、報道現場の裏側を率直に語った良書である。メディア・リテラシを高めたい方にお薦めしたい。
締切まで時間がなく、中東の事情に疎い多くの特派員(アラブ語も分からない)は現地の助手や通訳を頼り、そして現地メディアの記事を参考にすることになる。結果として、同じ情報源のネタをもとにした記事が出来上がる。こうした事情に付け込み、至れり尽くせりの対応によって巧妙かつ周到にメディアを操る米国やイスラエルの広報機関の実態も本書は明らかにしている。
特派員の在任中に9.11やイラク戦争を経験した筆者は、独裁政権下でまともな取材ができないだけではなく、信頼できる世論調査が存在しない状況で、アラブ諸国の民意を伝えることに苦慮する。写真や映像にうつった“怒る”民衆の姿は、政府が動員をかけたやらせに過ぎない。カメラやビデオのフレームから外れたところには、普通の生活を営む多くの民衆がいることを、アラブ語が話せ中東で長く生活する筆者は熟知している。
しかし、取材依頼元の求めるのはステレオタイプのアラブ像。本当のことを書いても“ニュース性”に乏く、結局、予定調和的なニュースが流れることになる。こうした状況に疑問をもった筆者は、「ニュースにならない真実」の数々を本書で明らかにしている。
|
| |
文化と外交~パブリック・ディプロマシーの時代~
渡辺靖、中公新書、p.204、¥819 |
2012.4.13 |
|
 |
政府要人同士による外交ではなく、相手国の世論に直接働きかけて所望の結果を得る「パブリック・ディプロマシー」の歴史や事例、課題を紹介した書。欧米や中国、韓国に比べ、日本のパブリック・ディプロマシーは出遅れており、戦略がないと警鐘を鳴らす。冒頭でバヌアツに戦略的に食い込んで存在感を高めている中国の事例を取り上げ危機感を煽っている。
もともとは反米機運の盛り上がりに対処するために米国がとった外交戦略がパブリック・ディプロマシーだった。対外広報や人物交流、国際放送などの手段を使って、文化や政治的な理想、政策の魅力をグローバルに訴え、米国のイメージ向上を図った。本書は米国のほか、国家ブランド委員会を立ち上げた韓国、自国語の習得をグローバルに支援するフランス学院や孔子学院といった施策を具体的に取り上げる。知らない話が多く、知的好奇心が満たされる。
日本のパブリック・ディプロマシーは惨憺たる状況ではないが、スケールが小さく、制度的に多くの課題を抱えていると述べる。「好感度を高める」「日本の国家ブランドを確立する」といった漠然とした目標が先行し、そもそも何のために好感度やブランドを高めるのか、どの地域のどの分野のどの層に働きかけるのかといった戦略的なフォーカスが甘い場合が多いと断じる。ジョゼフ・ナイは国の魅力によって望む結果を得る能力を「ソフトパワー」と称したが、筆者は自らを批判できる器の大きさや自省力、あるいは透明性や対話力から成る「メタ・ソフトパワー」の必要性を説いている。メタ・ソフトパワーの観点からは、福島原発を巡る日本の対応は最悪だったといえるだろう。
|
| |
中国化する日本~日中「文明の衝突」一千年史~
與那覇潤、文藝春秋、p.320、\1575 |
2012.4.11 |
|
 |
日本の歴史を中国化と江戸時代化という観点から再定義した書。「中国化する日本」というタイトルだけではなく、中身もかなり強烈である。本書で語られる歴史観は、教科書と大きく異なる。教科書の誤った記述で日本人の歴史観は偏ってしまったと筆者は筆鋒鋭く批判する。この偏りを正し、日本史のストーリーを描き直すことが本書の目的だと語る。筆者の歴史観への評価は分かれるところだろうが、刺激的な主張なのは間違いない。多様な歴史観に触れることができる1冊である。
タイトルの「中国化」とは、日本が欧米と中国の仕組みに追いつくという意味である。世界で初めて「近世」に到達したのが宗朝の中国。宗朝は、経済や社会を徹底的に自由化する代わりに、政治の秩序は一極支配によって維持した。この仕組みが、中国はもちろん、日本以外の先進国で現在に至るまで続いているという。
筆者が中国化と対比しているのが、江戸時代化という歴史観。日本の戦国時代以降の仕組みは、土建行政、国民国家(地域で結束して生きる社会を指す。商売や宗教のネットワークを使ってグローバルに連携する近世の中国とは真逆の社会)、象徴天皇、無思想性・無宗教性に特徴がある。これを江戸時代化と表現する。日本でも平家の時代に宗朝の制度の導入を試みたり、明治時代に中国化が進んだりしたが、結局は「江戸時代」の状態に引き戻されて今日に至っていると筆者は主張する。しかし長い江戸時代もさすがに限界がきて、中国化に向けて動き始めたというのが筆者の見立てである。
|
| |
勾留百二十日~特捜部長はなぜ逮捕されたか~
大坪弘道、文藝春秋、p.308、¥1470 |
2012.4.7 |
|
 |
大阪地検特捜部の捜査資料改ざん・隠蔽事件で、犯人隠避罪に問われて逮捕・勾留された元特捜部長・大坪弘道の手記。120日に及ぶ独房生活中に去来したものを正直に綴っている。拘禁される辛さや厳しさについての記述は体験者ならではの内容である。著者の人生観や世界観は勾留生活によって明らかに変化している。「人間が大きくなるには、大病をするか、浪人するか、刑務所に入るかだ」という言葉を聞いたことがあるが、本書を読むとそうかもしれないと思わされる。
筆者は、逮捕(勾留)する側から逮捕(勾留)される側へと180度変わった立場になったときに、どのように感じ、どのように考え、どのように受け入れていったかをつまびらかにする。自らが逮捕・勾留を指揮した厚生省・村木厚子局長の気持ちが、逆の立場になって初めて分かったと正直に述べている。検察庁への思いは複雑である。筆者は折り紙付きの仕事人間。それだけに、部長だった著者と元副部長にフロッピー・ディスク改竄の罪を押し付けてマスコミの攻勢をかわし、組織防衛に走る最高検察庁のやり口に強く反発する。可愛さ余って憎さ百倍といった気持ちが本書を読むとストレートに伝わってくる。
自己弁護と繰り返しの多い文章が少々気になるが、「被告になった特捜部長」による稀有な体験記なので読んで損はない。住宅ローンをはじめとするカネの工面を心配する記述が頻繁に出てくるが、勾留された人間の正直な反応なのだろう。ちなみに著者にはこの3月30日に懲役1年6月、執行猶予3年判決が大阪地裁で下されている。
|
| |
知性誕生~石器から宇宙船までを生み出した驚異のシステムの起源~
ジョン・ダンカン著、田淵健太・訳、早川書房、p.332、¥2310 |
2012.4.4 |
|
 |
人間の知性がどのようにして生まれているのか、脳の働きとどのように関係しているのかを、ケンブリッジ大学の脳科学者が解説した書。人間の行動や思考、知能の基本原理を、最新の実験心理学、脳科学、神経生物学、さらには人工知能研究からの知見に基づき論じている。
興味深いのが「地頭力」に言及したところ。頭のよい人は、さまざな問題を適切に処理する能力を備えているという。人間には「全体的な頭の良さ」があり、一つのことが上手にできる人は、他のことにも秀でる傾向がある。どのような作業をするときにも働く知能は「一般因子」と名付けられ、「全体的な頭の良さ」と関係する。筆者は、この一般因子が前頭葉の働きと密接に関係することを発見する。このあたりの展開は、なかなか刺激的である。
興味深い内容を含んだ書だが、問題もある。何度も読み返さないと意味が読み取れない個所が出てくる。原文に問題があるのかもしれないが、翻訳者と編集者も商品性を高める努力が必要だろう。読むことに精力を使うせいか、せっかくの中身を楽しめない。少し残念である。
|
| |
|
|

|
2012年3月 |
さいごの色街 飛田
井上理津子、筑摩書房、p.302、¥2100 |
2012.3.30 |
|
 |
売春防止法が施行されてから50年以上たった今も、昔の色街の風情を残す数少ない場所が大阪の飛田である。表立っての活動ができないだけに、部外者や取材を拒否する土地柄といえる。実際、写真の撮影も基本的に御法度という。本書は、その飛田に食い込み12年にわたって取材したジャーナリストの手によるノンフィクション。同業者として気になる表現もあるが、内容の豊かさがそれを補っている。
人は隠されれば隠されるほど知りたくなるものである。飛田の歴史や人生模様もその一つかもしれない。筆者は文字通りの体当たりの取材で、自らの取材欲と読者に期待に応えている。アッパレである。知らなかったことを知ることができるという意味で、読み応えのあるノンフィクションに仕上がっている。
筆者は、利用者、経営者、従業者のそれぞれに取材し、多角的な視点から過去と現在の飛田を描き出す。それぞれが背負っているものを、突撃取材で一つひとつ明らかにしているが、妙にユーモラスな場面も多く、一級のエンタテインメントとなっている。
|
| |
7つの危険な兆候~企業はこうして壊れていく~
ポール・キャロル、チュンカ・ムイ、谷川漣・訳、海と月社、p.308、\1890 |
2012.3.27 |
|
 |
過去25年における750件の失敗事例を検証し、企業はどのように失敗するか、どうすれば破綻を回避できるかを論じた書。失敗を引き起こすのはタイミングや運、事業遂行のプロセスではなく、戦略のまずさによるというのが筆者の結論である。豊富な事例を使った説得力のある書き口は読み手を飽きさせない。コダックやIBM、モトローラなど、ケーススタディとして取り上げる企業も悪くない。企業の失敗を扱ったビジネス書には名著が少なくないが、本書はいいレベルに達している。企業の経営者だけではなく、プロジェクトをマネージする(首尾よく成功に導く)立場にある方にお薦めである。
避けられたはずの失敗には繰り返し現れるパターンがあるという。具体的には、(1)シナジーという幻想に惑わされる、(2)金融工学の虜になる、(3)業界をまとめ一人勝ちを夢見る、(4)現実の変化を都合よく解釈する、(5)隣接市場に間違ったチャンスを見いだす、(6)新テクノロジーを求める、である。本書の前半では、この七つの罠それぞれについて1章を割き、失敗事例を挙げるとともに、どういった落とし穴が隠れていたのかを明らかにする。
後半は事業の成功率を高めるための知恵を授ける。「人はなぜ悪い戦略を選ぶのか」「企業が戦略ミスをおかす理由」といった疑問に答え、成功を導く秘訣を紹介する。本書から感じるのは人間の愚かさである。自惚れや虚栄が、賢明な人の判断を鈍らせ狂わせる。残念なことにミスから学ぶことができないのが人間である。筆者は「計画を立てたり意思決定をするとき、人間は不合理になる」と語る。人間とは興味深い存在である。
|
| |
メディアと日本人~変わりゆく日常~
橋元良明、岩波新書、p.224、¥798 |
2012.3.23 |
|
 |
1995年~2010年までの「日本人の情報行動調査」に基づき、日本人が新聞・ラジオ・テレビ・インターネット・書籍といったメディアとどのように関わってきたか、生活がどのように変化したかを論じた書。テレビ離れや書籍離れは本当か、メディアは子供に悪影響を与えるのか、といった観点からも議論を展開する。ページ数に限りがある新書なので深みはないが、メディアの誕生と普及、現状などをざっと知るうえで役立つ。
本書の特徴は、データに基づいてメディアに関する思い込みを覆しているところだろう。例えば読書離れ。出版不況で書籍の販売額は減少しているものの、読書離れと騒がれるほどには読書時間は減少していないことを本書は明らかにする。筆者は、インターネットの影響を比較的受けていないメディアとして書籍を挙げる。これは新聞とは対照的である。新聞を読む時間は、1995年と2010年を比べた場合、30代で24.5分から8.9分、40代で32.2分から14.4分と激減している。
仕事に役立つメディアのランキングも興味深い。2000年は書籍>新聞>テレビ>雑誌>ラジオの順。これが2010年には、インターネット>書籍>テレビ>新聞>雑誌>ラジオと変化する。インターネットがトップというのもインパクトがあるが、新聞がテレビに抜かれているのは考えさせられる。インターネットのアクセスがPCか携帯かで、行動パターンが大きく異なるという指摘も面白い。PCネット・ユーザーは社交性がなく、携帯ネット・ユーザーは社交的傾向が強いという。政治的関心があり政治を難解と感じていないのがPCネット・ユーザーで、政治的関心がないのが携帯ネット・ユーザーというデータも本書は紹介する。
|
| |
僕は君たちに武器を配りたい
瀧本哲史、講談社、p.296、\1890 |
2012.3.21 |
|
 |
京都大学客員准教授が、社会人として生き残るための知恵を20代の若者に授けた書。どのような企業や業界に気をつけるべきか、どういった人材になるべきかを論じている。筆者は、マッキンゼーでのエレクトロニクス業界向けコンサルタントを経て、現在はエンゼル投資家として活動。コンサルタントらしい整理整頓された書き口と投資家経験に基づいた社会観が本書の売りである。変化の激しい高度資本主義社会のなかで生き残るには、状況に応じて臨機応変に戦術を変えるゲリラ戦を展開すべきだとアジる。切り口が明確で読みやすい書だが、ビジネス書によく目を通すベテラン社会人からすれば目新しい内容は多くない。
筆者は、学生に人気のあるスキル「英語」「ITリテラシー」「簿記」を学ぶことに意味はないと主張する。必要なのはスペシャリティ。オンリーワンの存在にならないとコモディティ化するだけで、結局は賃下げの渦に巻き込まれると警告する。資本主義社会のなかで安い値段でこき使われずに、主体的に稼ぐ人間として六つのタイプを挙げる。トレーダー、エキスパート、マーケター、イノベーター、リーダー、インベスターである。ただし、右から左へとモノを動かすトレーダーと、変化の激しい資本主義社会におけるエキスパートは価値がなくなると予測する。
本書で目につくのはメディア批判。「メディアの情報をそのまま信用するな」「記事を鵜呑みにすることは、投資家としてもっともやってはいけない」「まったく金融が分からない奴が書いている」など、強烈なパンチを繰り出している。
|
| |
限界集落の真実~過疎の村は消えるか?~
山下祐介、ちくま新書、p.285、¥924 |
2012.3.16 |
|
 |
限界集落と聞くと、高齢化が進み、いずれ消滅していく過疎地域といった印象を多くの方が持つのではないか。本書はこうした定説を、地域社会学者の著者が現地取材をもとに否定した書。ここでいう限界集落とは、65歳以上の高齢者が人口の半数以上を占め、独居老人世帯が増加したために社会的共同生活の維持が困難になっている地域を指す。この定義に合致した限界集落は存在するものの、高齢化が理由で消滅した地域は皆無であることを筆者は明らかにする。
筆者が歩いた限界集落は全国に散らばる。本書でも、青森県、秋田県、岩手県、新潟県、京都府、島根県、高知県、鹿児島県を取り上げ、その実態を紹介する。共通しているのは、高齢化が進んでいるものの「ここに生きる」意志と努力の強さ。そう簡単に集落は消滅しないことを筆者は確信する。政府は2007年に191の集落が消滅したことを明らかにしたが、その理由はダム建設による移転や自然災害などによるもの。高齢化が理由ではない。同時に「限界集落=悲惨」と危機を煽るマスコミの取り上げ方を厳しく批判する。そもそも限界集落は、2007年の参議院選挙絡みでマスコミによって作られたものと断じる。
問題は、ここに生きる意志と努力が強い昭和一桁生まれ世代が去ったあと。親を気遣い近隣に住む息子世代を集落に引き戻し世代交代を行わないと、村落の消滅が現実化する。筆者が勧めるのが「集落点検」。限界集落外に住んでいる家族に、地域の良さを再確認させる試みである。キッカケさえあれば、家族は戻ると強調する。示唆に富む提言にあふれた書である。
|
| |
アイスマン~史上最大のサイバー犯罪はいかに行なわれたか~
ケビン・ポールセン、島村浩子・訳、祥伝社、p.311、\1680 |
2012.3.14 |
|
 |
「アイスマン」と呼ばれた悪玉ハッカーを追ったノンフィクション。アイスマン(本名はマックス・バトラー)は、小売店のサーバーなどに侵入して200万件にのぼるクレジットカード情報を盗み出し、懲役13年の刑を受けた。本書は、FBIの捜査に協力する犯罪者情報提供者(善玉ハッカー)だったアイスマンが、クラッキングを繰り返す犯罪者になり、ついには逮捕されるまでの軌跡を克明に追っている。著者はハッキング行為で有罪判決を受けたことがあるジャーナリストなので、犯行の手口に関する記述はかなり詳細。インターネットの裏側でどのような世界が展開されているのかを知ることができる1冊である。
本書は、クレジットカード情報を売買する闇市場の実態を克明に描く。アイスマンは「カーダースマーケット・コム」を運営し、盗み出した個人情報を販売。売り上げは1日に1000ドルに達した。クレジットカード詐欺師は、この情報をプラスチックカードに書き込み、本物と見まがう偽装を凝らす。キャッシャーと呼ぶ女性の手先がクレジットカードを使って買い物をし、ネットオークションで売りさばく。被害総額は8600万ドルに達するという。
最大の見所は、アイスマンとFBIの駆け引きだろう。FBIの捜査官が偽の肩書きでアイスマンを騙し、徐々に追いつめていくところは読み応えがある。善玉ハッカーだったアイスマンが、自らの技術に酔い、犯罪に手を染めていくまでの過程も興味深い。
|
| |
国家対巨大銀行~金融の肥大化による新たな危機~
サイモン・ジョンソン、ジェームズ・クワック、村井章子・訳、ダイヤモンド社、p.320、\1890 |
2012.3.10 |
|
 |
リーマンショックで顕在化した巨大銀行の「大きすぎてつぶせない」問題。本書は、現MITスローン校教授の経済学者が、その問題の根源をウォール街とワシントン(政府と官僚機構)の癒着に求めた書である。過去200年の金融の不祥事と危機の歴史、米国の政策を踏まえ、金融危機の原因と再発防止策を論じる。翻訳が優れていることもあり、堅い内容にしては意外にスイスイ読める。警世の書としてお薦めの1冊である。
巨大銀行が弱体化したリーマンショックのときこそ金融改革の好機だったのに、米国政府は結局、「白地小切手」を渡してしまう。いざとなったら政府はきっと大手金融機関を救うという漠然とした期待が正式な政策になったと本書は断じる。金融業界は焼け太りし、モラルハザードを生む病巣が除かれないまま残った結果、数年後にはもっと深刻でもっと大規模な危機が訪れると著者は予測する。しかも今度ばかりは市民の強い反発によって、もはや政府は金融業界を救済できない可能性を示唆しています。
では今回の金融危機に際して、政府はどういった政策をとるべきだったか。実質的に破綻していた巨大銀行を公的管理下に置き、資産を健全化し、正常に機能できるようになってから、可能なら民間に売却すべきだったと筆者は主張する。これがモラルハザードを防ぎ、公正な政策だったと断じる。最終的に筆者が思い描くのは、巨大銀行の分割と金融規制改革である。金融機関の資産に、GDPの4%以下といった上限を設けるべきだと主張する。
|
| |
メルトダウン~ドキュメント福島第一原発事故~
大鹿靖明、講談社、p.370、¥1680 |
2012.3.6 |
|
 |
2011年3月11日午後2時46分。分単位まで頭に入っている東日本大地震から1年。いまだ多くの傷跡を残している。なかでも最大のものは福島原発事故だろう。廃炉などの後始末も重要だが、あのとき何が起こったかの検証は不可欠である。政府が設置した複数の会議で議事録が存在しないなど論外。本書はAERAの名物記者が100人以上の関係者への取材をもとに、「あのとき」を追ったノンフィクション。エンターテインメント性の強さが気になるが、ジャーナリストとしての腕は一級品である。あのときを知る上でお薦めの1冊だ。
本書は福島原発、首相官邸、霞ヶ関、東京電力などの現場で何が起こったかを、ジャーナリストらしい批判精神旺盛な視点で追っている。想定外の事態に遭遇したときに、日本のエリートたちがどのような行動をとったのかを知る意味で貴重な記録である。水素爆発が起こったときに頭を抱えた原子力安全委員会の班目委員長。責任官庁にもかかわらず、その意識が乏しく国民の安全に思いが至らず、果ては権益保全に全精力を傾注する経産省。被害者意識ばかりが前面に出て、欺瞞、怠慢、傲慢の東京電力。筆者は、想定を超える事態に無力だった学校秀才たちの姿を筆鋒鋭く描く。
筆者の怒りが文章の端々から伝わってくる書だが、気がかりなのはサービス精神旺盛な筆者の書き口。つい筆者の価値観が刷り込まれてしまう。民間の有識者が立ち上げた福島原発事故独立検証委員会(民間事故調)の調査報告書が3月11日に出版されるので読み比べたい。
|
| |
Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation
Steven Johnson、Riverhead Trade、p.336、$16 |
2012.3.2 |
|
 |
発明やイノベーションのアイデアがどういった状況・環境から生まれたかを探った書。ダーウインの進化論、グーテンベルク、複式簿記といった話題から、Google、YouTube、Appleの最近の話まで、本書のカバー範囲はきわめて広い。かつては発明から製品化までに10年、普及までさらに10年という「10/10の法則」が成り立った。しかし現在は、「1/1の法則」にまで技術の進歩は加速している。こうしたなか、どのような環境がイノベーションを生むのに適しているかを本書は説く。Time誌やWired誌、New York Times紙、Wall Street Journal紙などに寄稿している手練のジャーナリストらしく、縦横無尽に論じている。ページ数は実質240ページと米国の書籍としては短いが、なかなか読み応えがある。イノベーションや発明を育む環境に興味をもつ方にお薦めの書である。
筆者は歴史を振り返ることで、発明やイノベーションを生む環境に七つのパターンを見いだしている。特に重視するのが「オープン」と「ネットワーク」。発明やイノベーションが孤立した環境で生まれることは少ない。異なる分野の研究者や発明者が気軽に接触でき、濃厚な情報交換と相互の触発を日常的に行える環境が不可欠だと説く。ある分野で枯れた技術が、別の分野のイノベーションにつながるといった連環が重要である。都会こそイノベーティブというのが筆者の主張。規模が10倍なら17倍イノベーティブ、規模が50倍なら130倍イノベーティブという指摘は興味深い。
筆者はインターネットを、イノベーションを育むうえで最適な環境と評価する。オープンなネットワークで、しかもインタラクティブ。異文化間の交流も自由自在である。ブラウズやネットサーフィンは、紙をはじめとする古いメディアとの関わり方よりも、ずっとイノベーションを触発する行為だと主張する。SNが悪い環境ほど、イノベーティブという考え方もユニーク。ノイズのない環境から生まれる発想は予定調和に終わる。世の中をひっくり返すような、突き抜けるようなイノベーションは生まれない。
|
| |
|
|

|
2012年2月 |
隠語の民俗学~差別とアイデンティティ~
礫川全次、河出書房新社、p.190、¥1890 |
2012.2.25 |
|
 |
隠語のルーツや隠された意味などを探った書。ずいぶん風変わりな書である。筆者によると、隠語の研究は進んでおらず、学説や定説がほとんど形成されていないという。それだけに隠語の形成過程や含意などを解明するときに、想像をたくましくすることができる。考古学の楽しさに通じるところがありそうだ。少し風変わりだが、言葉に興味をお持ち方に向く書である。
ここでいう隠語は、「社会集団の集団内部の秘密を保持するために、その集団内部だけにしか通じないことを意図して人為的に作られた言葉」と定義される。本書は特に、犯罪者などの反社会的集団や漂泊放浪の芸能民に焦点を当てる。閉鎖性の強い集団のなかで隠語は独特の発展を遂げた。隠語を交わすことで誇りとアイデンティティを共有したというのが筆者の見立てである。
ちなみに評者のような専門誌の記者にとって、技術者集団の隠語は非常に重要である。記事のなかに隠語を効果的に使えば、読者に文意が伝わりやすくなる。技術者が日常的に交わしている隠語を使うことで、読者にとって記事がぐっと身近になる効果も見込める。そもそも取材の際に、隠語を使いこなせれば取材の中身はぐっと濃くなることは間違いない。
|
| |
サムスンの真実
金勇・著、藤田俊一・監修、金智子・訳、バジリコ、p.384、¥1890 |
2012.2.24 |
|
 |
不振をかこつ日本の電機産業を尻目に、好調を維持するサムスン電子。本書はそのサムスン電子の暗部を元幹部が告発した書である。にわかには信じられない違法行為の数々をえぐりだしている。筆者は、韓国の元特捜検事でサムスン幹部を経て現在は弁護士。サムスン・グループや韓国社会に興味をもっている方に一読をお薦めする。ちなみに本書は2010年に韓国で出版され、韓国内で大きな反響を呼んだ。その衝撃は米国メディアでも取り上げられ、評者は日本語訳の出版を心待ちにしていた(英訳でもよかったが、Amazon.comで調べても英語版は出ていないようだ)。
サムスンの暗部と言えば裏金問題である。裏金を巡って起こされた裁判の責任をとって会長の李健熙が辞任したことはよく知られている。結局、李健熙は平昌オリンピック招致のために特別恩赦を受け、2010年3月に会長に復帰したことも日本の新聞で報じられた。しかし本書によると、裏金問題はサムスンの暗部のごく一部。サムスンと政界・官界・司法界に横たわる問題は実に根深く、広い範囲に及んでいることが本書を読むとよく分かる。
筆者が指摘する問題点は三つ。第1は組織的な裏金づくりと脱税。第2はサムスングループの経営権継承問題を巡る違法行為と裁判での証拠操作。第3は政界、官界、法曹界(裁判所や検察を巻き込んでいる)、マスコミに対する違法ロビー活動の数々。にわかには信じがたい違法・脱法行為を本書は具体的に取り上げる。李承晩から現在の李明博にいたるまで、いかにサムスン・グループが代々の政権に影響力を行使してきたかを本書は紹介する。それにしても不正の裏側に、創業者の李秉?の三男・李健熙からその長男である李在鎔への経営移譲があるというのはずいぶん生臭い。
|
| |
理系のためのクラウド知的生産術
堀正岳、ブルーバックス、p.200、¥861 |
2012.2.20 |
|
 |
海洋研究開発機構の研究者が説く現代版「知的生産の技術」。理系研究者向けにクラウド環境の使いこなし術を紹介する。一応「理系」が想定読者だが、文系でも役立つ内容を多く盛り込んでいる。もっとも「知的生産の技術」(梅棹忠夫著、岩波新書)は、評者の高校入学時に課題図書と指定されるほどの名著でロングセラーだったが、クラウド技術の進歩が速く本書の賞味期間かそうだ。
メモの残し方、同僚とのコラボレーションの仕方、プロジェクト管理法、時間の有効活用術、アイデアの育て方、どこでもオフィスの環境構築について、筆者が実践している仕事術を披露する。本書が扱うのはDropbox、Gmail、Google Docs、Google Calendar、Evernoteなど、評者も愛用しているツールの数々。すでに知っている内容が多いが、「ほう」と感心するような利用法も紹介されており意外に役立ったというのが率直な感想である。
|
| |
幸福の研究~ハーバード元学長が教える幸福な社会~
デレック・ボック著、土屋直樹・訳、茶野努・訳、宮川修子・訳、東洋経済新報社、p.324、¥2730 |
推薦! 2012.2.17 |
|
 |
ハーバード大学の学長を20年間務めた世界的法学者が、「幸福」と「国民を幸福にする政治」について論じた書。幸福に関する俗説の間違いを、最新の研究成果をもとに正すとともに、政治やマスメディアの問題を明確に描き出している。国王夫妻が昨年来日したブータンは、発展を測る尺度として幸福指数(GNH:Gross National Happiness)を1972年に採用した国として知られる。本書は、このGNHを高めるための方策の数々を提言している。ほとんどは米国を対象にした提言だが、日本にも役立ちそうなものが数多く含まれており、お薦めの1冊である。
本書の問題意識は、「世界一のGDPを誇る米国の幸福度が、なぜ先進国で平均以下なのか」にある(ちなみに日本はさらに下)。筆者はまず、結婚、教育、医療、福祉、失業、所得などと幸福の関係について論じる。経済的成功や年齢と幸福度の相関はさほど高くない。睡眠障害の幸福度に与える影響は所得や教育、就業状態に比べてはるかに大きい。お金持ちになることを重要な目標とする人は他の目標をもつ人に比べ幸福でない傾向がある。こうした最近の幸福研究の知見を数多く紹介する。
人々は勤労や善行が報われる公正な世界に住んでいると知っているときに(信じているときに)、大きな満足を感じるという指摘は含蓄に富む。実際、米国人は機会均等(アメリカンドリーム)を信じていた結果、ほとんどの人々がいつの時代でも幸福だったという。この指摘は、昨年末にウォールストリートで起こったデモを考えたときに示唆的である。
興味深いのは政治・行政の質に対する信頼と信用が国民の幸福に大きく貢献する点。筆者は、政府の施策に対する尊敬を高める取り組みの重要性を指摘する。現在のように政府に対する国民の信頼と信用が地に落ちてしまっているときには、なおさら重要度を増してると断じる。ここで問題となるのがメディアの報道だ。政策や制度といった複雑な問題よりも、スキャンダルや政党間の争い、政府内部での権力闘争といった耳目を集める話題の報道に安易に流されていると指摘する。少々耳が痛い。
このほか幸福度を尺度とした場合に、政府が採るべき政策も提言する。結婚と家族関係の強化、活動的レジャーの促進、失業による衝撃の緩和、国民皆保険の実現、退職後の安定した生活の保障、保育と幼児教育の改善、精神疾患や睡眠障害、慢性痛の効果的な治療、広範な目標に合わせた教育などである。こうした政策を優先すれば、所得の再配分、富裕者の退職貯蓄の助成といった政策よりも、国民の負担が少なく、幸福の増進にずっと有益だと論じる。
|
| |
新自由主義の復権~日本経済はなぜ停滞しているのか~
中公新書、八代尚宏、p.254、¥840 |
2012.2.11 |
|
 |
小泉構造改革と同一視され、日本では評判が芳しくない「新自由主義」の本質について論じた書。新自由主義と小泉構造改革にまつわる数々の誤解を解くとともに、日本経済復活と震災復興への処方箋を提示している。非論理的な日本の経済政策、トンネルから抜け出せない日本経済、せっかくのチャンスだった小泉構造改革をムダにした政治に対する筆者の苛立ちが伝わってくる。同感である。明確でロジカルな論旨は好感がもてるが、新自由主義の思想と政策を論じるには新書のページ数はあまりに少ない。読後に空腹感が残る1冊である。
新自由主義とは、市場での競争を重視し、それを妨げる企業の行動を禁止することで市場の機能を最大限生かす思想である。新自由主義において政府は、企業や個人のインセンティブを、経済全体の利益に沿う方向に向ける役割を担っていると強調する。例えば非効率な事業者を守るのではなく、円滑な退出のための手段を通して市場経済を円滑に機能させることに政府の役割はある。
本書が取り上げる範囲は広い。前半では、政治経済だけではなく、日本史(平清盛や織田信長が登場する)や小泉構造改革の視点から新自由主義を論じる。後半は日本政府の政策提言である。社会保障改革、労働市場改革、産業政策、震災復興、TPPを俎上にあげる。紙幅は少ないが、強い説得力をもって持論を展開する。例えば小泉構造改革の問題点は、目指した方向が誤ったいたことではなく、それが不十分・不徹底だったことだと断じる。タクシーの参入規制緩和では、価格統制が残ったために市場原理が正しく機能しなかったと見る。タクシーの台数が増えたにもかかわらず、市場原理に反した価格統制が残ったために市場が縮小し、運転手の所得の減少を招いたという。
|
| |
リトル・ピープルの時代
宇野常寛、幻冬舎、p.509、¥2310 |
2012.2.8 |
|
 |
高度成長期から現在至るまでの日本社会の変容を、村上春樹の小説、人気テレビ番組などを絡めながら解き明かした書。筆者は34歳と新進気鋭の評論家。切り口が鋭く、現在のネット社会を的確にとらえている。ただし文章は小難しい。評者は、「難しいことを難解な文章で表現する」この手の本が正直なところ得意ではない。難しいことを分かりやすい文章で書いてこそ価値があると思うのだが、そう考えない学者や評論家は少なくない。本書も評者が不得手な部類に属している。ただし本書の中身は濃いので、読むのに一苦労するが、それだけの価値はあるだろう。
筆者が取り上げるのは、村上春樹が『1Q84』で描いた「ビッグブラザーの壊死」と「リトルピープルの台頭」という論点。国家という単一のビッグブラザーが仕切る社会は、遠い昔に消滅した。国家よりも貨幣(経済)と情報のネットワークが上位の存在として君臨するようになった。ビッグブラザーから解放された子供たちは、大きな敵を失って迷走し、その寄る辺としてオウム真理教などに向かった。この時代をモチーフにして成功した作家が村上春樹というのが著者の見立てである。
ビッグブラザーに代わって台頭したのが、小さな父「リトルピープル」だ。無数の小さな存在が無限に連鎖し、その連鎖が社会を構成する。結果として、歴史や国家のような大きな物語で自らの人生を意味づけることが難しくなる。等身大の生活における人間関係のなかで承認を得るしか、自らを位置づける方法がなくなった。こうした状況は、誰もが主役(情報発信元)となり得るインターネットの世界をうまく言い当てている。
「ビッグブラザーの壊死」「リトルピープルの台頭」を論じるために筆者が取り上げた話題は、ガメラ、ウルトラマン、仮面ライダー、エヴァンゲリオン、AKB48、ニコニコ動画、初音ミクなど新旧織り交ぜ多種多様。それぞれが人気を博した(博している)理由を、時代背景を解き明かしながら論じる。本書の立て付けと構想力は大きく、魅力的な文化論に仕上がっているで。ただし後半で論じる仮想現実から拡張現実への移行は、少々説得力に欠け消化不良の感がある。興味深いテーマだけに次回作が楽しみである。
|
| |
スピーチの奥義
寺澤芳男、光文社新書、p.211、¥777 |
2012.2.2 |
|
 |
最近、日本経済新聞「私の履歴書」に登場した寺澤芳男が、スピーチのノウハウを開陳した書。画期的な内容が含まれているわけではないが、実践的なのは確か。特に英語でのスピーチに関するノウハウは貴重。海外でスピーチする機会がある方は一読して損はない。野村証券副社長、MIGA長官、参議院議員、経済企画庁長官の経歴はだてではない。
スピーチに緊張はつきもの。筆者は緊張を和らげ、肩の力を抜く秘訣を伝授する。ポイントは開き直ること。自分の話など受けなくて当たり前、伝えたいことを情熱にまかせて突っ走って語るのが肝要だという。「スピーチの出来は長さとテーマの数に反比例する」はなかなかの名言。テーマは二つ以内に絞れとの指摘は的確である。このほかジョーク活用法、視線の置き所、PowerPointの問題点、タブー集など実践的な内容が盛りだくさんである。
筆者が考えるスピーチの名手たちのエピソードも悪くない。登場するのはジョブズ(有名なスタンフォード大での卒業スピーチ)、盛田昭夫、細川護熙、オバマ、クリントンなどの名スピーチを紹介する。
|
| |
FUKUSHIMAレポート~原発事故の本質~
FUKUSHIMAプロジェクト委員会、日経BPコンサルティング、p.500、¥945 |
2012.2.1 |
|
 |
福島第一原子力発電所の事故を第三者の立場から調査・分析し、知見を後世に伝えるために昨年4月に発足したFUKUSHIMAプロジェクト。その成果をまとめた書である。このプロジェクト、仕組みがなかなかユニーク。特定組織の意向に影響されたり、経済原理に左右されることを避けるために、活動資金の一部と書籍発行の全額を寄付で賄っているのだ。この発行形態のためなのか、論旨が明確で切れ味のよい報告書に仕上がっている。500ページもある分厚い書だが、文章がこなれていて読みやすい。玉石混淆の原発関連書籍のなか、データをきっちり押さえた本書は一読の価値がある。なお本書の関係者に、評者の元上司や元同僚、知人が含まれている。書評にバイアスがかかっている可能性がある点は了解していただきたい。
本書は七つの視点から原発事故を分析する。「メルトダウンを防げなかった本当の理由」と題する第1章はかなり衝撃的。公開されたデータをもとに、福島原発1号機~3号機のメルトダウンは100%確実に防げたと断じる。1号機~3号機には交流電源が喪失しても動く自然冷却システムが用意されていた。これが稼働し8~70時間のあいだ3基の原子炉は制御可能であり、「全交流電源が喪失し、ただちに原子炉は制御不能になった」というのは嘘だと断定する。この期間に海水を注入せず、メルトダウンを起こした東京電力の経営責任は大きいと結論づける。
日本の原子力行政には核兵器製造力を保持する目的があったとする第3章も読み応えがある。技術的にも経済的にも核兵器を製造する能力を保つために、政府はあの手この手で原子力発電所を優遇した。国の手厚い援助を期待できる原子力損害賠償法、低利で資金を調達できる仕組み、資産価値が大きな発電所をもつほど利潤が大きくなる総括原価方式、原発のコストは安いという神話などで、原子力発電の建設を支えた。
個人的に興味深かったのは、第5章の「風評被害を考える」。福島原発事故が海外でどのように報じられたかを分析する。面白いのは欧米の新聞の紙面比較である。直感的にはUSA TodayやThe Daily Mailといった中級紙の方が、New York TimesやWall Street Journal、Wasihngton Postといった高級紙よりも扇情的と思われる。しかし調査結果は逆。New York TimesとWasihngton Postは否定的で、誇張した記事や誤報が多かった。高級紙でもWall Street Journalは、否定的だが誤報や誇張は少なかったという。ぜひとも理由を知りたいところだ。
|
| |
|
|

|
2012年1月 |
「僕のお父さんは東電の社員です」
森達也著、毎日小学生新聞編、現代書館、p.224、¥1470 |
2012.1.29 |
|
 |
東日本大震災が起こって3週間ほどたったころ、小学6年生の「ゆうだい君(仮名)」が毎日小学生新聞に投書を寄せた。「突然ですが、僕のお父さんは東電の社員です」ではじまる投書である。内容は毎日小学生新聞の1面に掲載されたジャーナリスト北村龍行(元毎日新聞論説委員)の寄稿に対する反論。北村は原発事故と東京電力の責任について言及した。ゆうだい君は、東電だけが悪いのか、東電にすべての責任を電力を必要とする現代社会に問題はないのか、など率直な疑問を北村に投げかける。「読んでみて、無責任だ、と思いました」という素直な書き口に、プロの書き手はついたじろいでしまうだろう。
ゆうだい君の投書ををキッカケに、毎日小学生新聞で「ゆうだい君の手紙」特集が始まる。本書におさめられたのは、この特集に掲載された小学生から大人までの投書。未曾有の国家の危機に、多くの人がどのように向き合っているのかが分かる貴重な記録である。
本書に取り上げられている投書の文章はお世辞にも優れているとはいえない。しかし素直な文章からは、いずれも原発問題に真摯に向き合っていることが伝わってくる。プロの書き手はどうしても構えてしまい、本書に取り上げられている文章には迫力負けしてしまう。物書きとして大人として、いろいろ考えさせられた書である。
|
| |
あんぽん~孫正義伝~
佐野眞一、小学館、p.399、¥1680 |
推薦! 2012.1.27 |
|
 |
二つの意味で、凄まじい迫力の本である。一つは孫正義の人生の迫力。本書が紹介する在日、差別、幼少期の貧困などは、この手の書に多い予定調和的な美談を簡単に打ち砕く。もう一つは、ノンフィクション作家としての佐野眞一の驚くべき力量。筆者はあとがきで、「人を描く場合、その人物が絶対に見ることができない背中や内臓から描く」と述べているが、本書でその真骨頂を見せてくれる。
孫正義の好き嫌いは別にして読んで損はない。ベストセラーになったスティーブ・ジョブズの評伝に勝るとも劣らない出来である。多くの方にお薦めしたい。ちなみに本書は週刊ポストの連載に大幅加筆したものなので、ご存知の方も多いかもしれない。タイトルの「あんぽん」は、孫が1990年に帰化するまでの名前「安本正義」からついた渾名である。
筆者は本書を執筆した目的を、叩かれても叩かれてもへこたれない「孫のいかがわしさの根源を探ること」と前書きで語っている。そのために父方・母方の親類全員にインタビューするとともに、韓国にまで足を延ばし徹底的に取材する。常軌を逸した行動と愛情がないまぜになった「底光りする家系」とはすごい表現である。特に孫に強い影響を及ぼした父親・安本三憲へのインタビューは秀抜。強烈な人柄をものの見事に描き出している。
本書は魂を揺さぶるエピソードを数多く紹介する。冒頭に出てくる幼少期の極貧もその一つ。ウンコ臭い水があふれる掘建て小屋のなかで、膝まで水までつかりながら必至に勉強する孫の姿を描く。孫のど根性の原点がここにあると佐野は語る。
|
| |
文明を変えた植物たち~コロンブスが遺した種子~
酒井伸雄、NHKブックス、p.272、¥1155 |
2012.1.24 |
|
 |
コロンブスの航海がキッカケになって、新大陸原生の植物が欧州に渡った。その植物が、欧州の政治や社会、産業、文化を与えたインパクトを紹介した書。4回にわたるコロンブスの航海が、新しい文明の幕開けに貢献したというのが筆者の見立てである。取り上げるのは、ジャガイモ、ゴム、カカオ、トウガラシ、タバコ、トウモロコシの六つ。毎日欠かさず口にするものではないが、ないとそれなりに困る食材である。肩の凝らない内容で、一気に読んでしまった。ちなみに筆者は明治製菓の研究所長を経て子会社社長を務め、現在の肩書きは食文化史家。
トップバッターは、アンデス高地由来のジャガイモ。エネルギー源として欧州の食卓に上がるようになったことで飢餓の恐怖から欧州の人間を救った植物として取り上げる。飢餓から解放された結果、人口が急増し、国力の増強につながった。キリスト教文明による世界支配の原動力になったとする。さらに余ったジャガイモは家畜の飼料となり、1年を通して新鮮な肉が食べる食文化を生んだ。
カカオやタバコの逸話は実に興味深く、歴史って面白いと感じさせてくれる。まずカカオ。カカオは当初飲み物として扱われた。当時の欧州は、水質が悪く、子どもも含め多くの人間はアルコール系の飲料でのどを潤していたという。1日中、ほろ酔い気分だった訳だ。それがチョコレート、茶、コーヒーの普及によって、アルコールを昼から摂る習慣は廃れた。これが労働者の質を向上させ、産業革命の進展を欧州の近代化につながった。
いまや万病のもと扱いのタバコだが、かつてはペストの予防薬だったという話は興味深い。タバコ屋は1軒もペストにかからないという噂がたち、喫煙は最も優れた予防薬としての地位を確立した。子ども吸うことを強いられたという。へ~である。
|
| |
日本経済・今度こそオオカミはやってくる
冨山和彦、竹中平蔵、PHP研究所、p.224、¥1470 |
2012.1.20 |
|
 |
竹中平蔵と冨山和彦が、日本の経済政策と産業政策について語り合った書。理論派と実践派を組み合わせた企画は編集者のファインプレーだろう。竹中はいわずと知れた小泉改革の司令塔。冨山は経営コンサルタントだが、産業再生機構設立にかかわりCOOを務めたあと、バス会社などの経営に参加した。改革派の書だけに中身は自ずと知れるが、期待を裏切らない。日本経済の没落を予想する一方で、復活への処方箋も描いている。
2人は、現在の経済政策と産業政策に悲観的な見方を示す。日本人の思考パターンは1960年代から変わっておらず、時代に取り残されていると手厳しい。悪いことに、東日本大震災と原発事故が重なった。安全神話の崩壊、製造業のサプライチェーンの寸断、電力供給に対する不安、さらに高い税金、円高など、マイナスの要因は数え上げたらキリがない。マイナス成長下の増税論議にも苦言を呈している。
こうした状況を作り出したのは、問題先送りに終始し、抜本的な対策を打とうとしない政財界だけではない。科学的で冷静な議論を避け、情緒的でステレオタイプの議論を好むマスコミや評論家にも責任の一端があると断罪する。しかし日本にはびこる責任回避システムは限界に近付いており、このままでは大空洞化時代が幕を開けると警鐘をならす。工場の海外移転はさほど顕在化していないが、それは企業が本気になっている証拠だと分析する。
現状には厳しいが、将来には意外なほど楽観的である。「現在は明治維新以来の絶好のチャンス」「危機の時代が大局観を生む」「30代はすごいリアリスト」「リーダーは忘れたころにやってくる」など、将来に期待を寄せる。東京への期待も興味深い。日本復活の前提と考えているのが、東京のもっている潜在力を伸ばしていくこと。イノベーションは都市のダイナミズムから生まれ、それができるのは東京だと論じる。
|
| |
ウェブ×ソーシャル×アメリカ~<全球時代>の構想力~
池田純一、講談社現代新書、p.320、\840 |
2012.1.18 |
|
 |
ウェブやパソコンの誕生と発展を米国文化の視点から分析した書。AppleやGoogle、Facebookが米国で誕生した思想的・社会的背景を、幅広い視野から解き明かす。新書らしい知的興奮を与えてくれる良書である。類書にない構想力の大きさが本書の特徴の一つ。情報技術やウェブの技術史については多くの書物が扱っており、評者もかなりの何冊を読んだ。しかし本書はそれらとは一線を画している。
本書は技術と文化、社会を網羅的かつ統一的に扱い、斬新な切り口から新たな視点を提供する。登場人物もイノベータの面々にはじまり、学者、評論家、編集者と幅広い。Facebookのマーク・ザッカーバーグ、Appleのスティーブ・ジョブズ、経営学者のマイケル・ポーター、サイバネティクスのノーバート・ウィーナー、認知科学のドナルド・ノーマンが1冊の書籍に登場するだけでも、ちょっと驚きである。それぞれの人物の位置づけを明確にしており、頭の整理に役立つ。もっともザッカーバーグの行動パターンは、古代ローマである詩人ウェルギリウスの叙事詩『アエネーイス』の影響を受けているといった論理展開は、評者のレベルでは壮大すぎてついていけない。
興味深いのは、米国のカタログ誌「Whole Earth Catalog(WEC)」に関する記述である。WECはジョブズがスタンフォード大学の卒業式のスピーチで使った“Stay Hungry,Stay Folish”の出所元。1968年~1972年にかけて定期的に出版され、当時のカウンターカルチャー(ヒッピーやドラッグに代表される)に強い影響を与えた。しかし、WECがジョブズに多大な影響を与えたからといって、パソコンやウェブを生んだのはカウンターカルチャーではないと論じる。一方で筆者は、WECが与える「全球という視座」に注目する。全球という視座につながる宇宙開発が、パソコンやIT、ウェブなど全ての出発点になったと結論付ける。
|
| |
横浜事件・再審裁判とは何だったのか~権力犯罪・虚構の解明に挑んだ24年~
大川隆司、橋本進、佐藤博史、高文研、p.239、\1575 |
2012.1.14 |
|
 |
冤罪を晴らすために24年間わたって再審裁判を闘った弁護士たちの奮戦記である。こう書くと、血湧き肉踊るようなノンフィクションを期待するが、本書はきわめて地味。担当弁護士やジャーナリストが、冤罪の経緯と構造を淡々と論じている。しかし現在の裁判にも通じるところが多く、示唆に富む良書である。万人向けではないが、読んで損はない。
本書が扱うのは、戦時下の1942年~1945年にかけて神奈川県警察部特別高等課(特高)が90人を検挙した冤罪事件。共産主義活動と日本共産党再建活動という特高警察の筋書き通りの調書を書くため、拷問による自白が強要された。有罪判決を覆すための再審裁判は1986年~2010年の24年間、4次にわたって続けられ、最終的に実質無罪である免訴を勝ち取った。横浜事件は特高警察と治安維持法を裁いた唯一の歴史的裁判と言われる。
|
| |
「お手本の国」のウソ
田口理穂ほか、新潮新書、p.238、\777 |
2012.1.11 |
|
 |
隣の芝生は本当に青いのか。「巷間伝わる他国の美点は正しいのか」「本当にお手本になるのか」を、現地に在住しているジャーナリストが論じた書。「ドイツは戦争責任問題を整理した」「フランスは少子化問題を解決した」「子どもの学習法なら『フィンランドメソッド』」「イギリスの二大政党制は機能している」「アメリカでは国民参加の裁判が当たり前」「ニュージーランドは政界有数の自然保護大国」フランスは少子化問題を乗り越えた」といった、ステレオタイプ的な常識について実態を紹介する。現地在住のジャーナリストの個人的見解の域を出ないところもあるが、各国の一面をとらえているのは確かで一読をお薦めする。
|
| |
ナチを欺いた死体~英国の奇策・ミンスミート作戦の真実~
ベン・マッキンタイアー著、小林朋則・訳、中央公論新社、p.469、¥2625 |
2012.1.9 |
|
 |
とてもノンフィクションとは思えない、奇妙きてれつな第2次世界大戦時の話。実に面白い。連合軍がシチリア島への進攻を企てたときに、上陸ポイントについてドイツ軍に偽情報をつかませて作戦を成功させた「ミンスミート作戦」の舞台裏を詳細に描いている。「現実は小説よりも奇なり」を地で行ったようなストーリーで、400ページを超える大著だが気にならない。充実した写真も見所の一つである。
ミンスミート作戦に関しては、立案したモンタギュー自身によるベストセラー「実在しなかった男」(映画化もされている)があるが、筆者によると内容には英国政府の検閲が入っており、必ずしも史実に忠実とはいえないという。本書は、機密解除になった公文書とインタビューをもとに、第2次世界大戦の行方を左右したミンスミート作戦を詳述する。
ミンスミート作戦とは、英国情報部がドイツ軍を欺くために立てた奇策。一般人の死体を高級将校に仕立て、あたかも極秘文書運搬時に航空機事故で溺死したように見せかけてスペインの浜辺に漂着させる。ドイツ軍に信じさせるために英国情報部があれこれ手を打つ。いずれも芝居がかっていて(映画のようで)楽しい。
|
| |
|
|

|
2011年12月 |
ザ・ラストバンカー~西川善文回顧録~
西川善文、講談社、p.322、\1680 |
2011.12.27 |
|
 |
住友銀行(現・三井住友銀行)元頭取で、日本郵政の初代社長を務めた筆者が、激動のバンカー人生を振り返った書。取り上げるのは、住友銀行の天皇と呼ばれた磯田一郎との確執、安宅産業処理、平和相銀・イトマン事件、バブル崩壊にともなう不良債権問題、郵政民営化など。それぞれが日本の金融史において一大トピックとなった事件だが、当事者だった筆者が生々しく振り返る。自己弁護の部分がないとは思わないが、一級の回顧録なのは間違いない。
山場の一つは、磯田一郎をめぐる裏話だ。「向こう傷を恐れない」経営スタイルで知られ、有能な銀行家として名をはせた磯田だが、ヤミの勢力に食い物にされたイトマンに深く関与し失脚した。長女かわいさのあげくビジネスマンとしての道を踏み外した磯田の弱さを明らかにする一方で、「悪人ではなかった」と人物を評価する。
銀行再編の裏話も興味深い。住友銀行は、さくら銀行(太陽神戸銀行と三井銀行が合併して誕生)と合併することになるが、著者と旧さくら銀行の岡田明重頭取との親交が縁となったことを明らかにする。東京三菱銀行ではなく、なぜ三井系のさくら銀行を選んだかの理由についても明らかにする。合併話に比べ不良債権問題は、「不良債権と寝た男」と評された筆者にしてはイマイチ迫力に欠ける。関係者への遠慮なのだろうか。
経済合理性とかけ離れた非論理的な政治に翻弄され続けた日本郵政社長時代については、愚痴っぽい話がぐっと多くなる。特に鳩山邦夫・総務大臣との確執について詳細に振り返る。「かんぽの宿」「東京中央郵便局再開発計画」で両者は対立したが、本書を読むと何ともばかばかしい話である。
|
| |
ホームレス博士~派遣村・ブラック企業化する大学院~
水月昭道、光文社新書、p.214、\777 |
2011.12.21 |
|
 |
人間環境学博士で、立命館大の研究員と同志社大非常勤講師を務めている筆者が、大学院と大学院卒業生の窮状を切々と訴えた書。博士号を取得しても就職できない状況や、非常勤講師という低賃金で不安定な雇用形態、東大卒の博士の就職率が約40%など、本当なのだろうかと思うような話が次から次へと登場する。こうした悲惨な状況を招いた国の文教政策を痛烈に批判している。筆者の主張がすべて正しいとは思えないが、日本の大学と文教政策の一面を知ることができる新書である。
いやはや大学院は、凄いことになっている。評者の大学時代にもオーバードクターの問題はあったが、桁違いに悲惨になっている。そもそもの元凶は、需要と供給の関係を無視した国の大学院重点化政策にあるというのが筆者の主張。20年前に7万人だった大学院(修士+博士)の定員が、大学院重点化政策が始まった1991年には10万人、そして現在は26万人に急増。超高学歴の博士を増産したものの、就職先は限られる。とりあえずの非常勤講師は平均的に週に9コマを担当するが、その年収は320万円。週2コマとなると年収は70万円と100万円に満たない。しかも昇給なし、雇用保険なしと辛い。
こうした状況を筆者は「国家の詐欺」と断じる。少子化によって経営が苦しくなっている大学と天下り先のポストを確保したい文科省の利害が一致した結果とみる。減少する大学生を大学院生の増加で補う訳だ。
|
| |
日本の企業統治~その再設計と競争力の回復に向けて~
宮島英昭・編著、東洋経済新報社、p.384、\5040 |
2011.12.19 |
|
 |
バブル崩壊に伴う銀行危機(1997年)から2008年のリーマンショックを経て現在に至るまでを対象に、日本における企業統治の変遷を追った書。経産省系の経済産業研究所の研究成果をまとめている。社外取締役、執行役員制度、株式の持ち合い、海外機関投資家の増加、雇用システムの変化、親子上場といった切り口から日本企業のガバナンスと組織を論じる。内容にさほど意外性はないが、なんとなく感じていることをデータで裏付けているところが本書の真骨頂である。
ただし評価基準は主に経営パフォーマンスなので、オリンパスや大王製紙の事件が世間を騒がせているいま、不祥事や違法行為防止の観点を期待すると裏切られる。内容が堅いうえに400ページ近くあるので、読破するのはそこそこ大変。それぞれの章は独立性が高いので、興味のあるところをつまみ食いして読み進むのがお勧めである。
現在の日本企業の統治形態は、関係性を重視した旧来日本型と、市場性に重きを置く米国型のハイブリット構造をとるというのが筆者の見立て。日本企業における外部および内部ガバナンスの変化、企業統治と企業構造(取締役制度や人事制度)との関係、企業統治の企業行動(研究開発投資や雇用)への影響などについて分析する。
執行役員制度が企業のパフォーマンス向上につながることはない、取締役会の縮小が利益率の向上と正の相関があるといった指摘や、外国人投資家や機関投資家の株式保有が近視眼的な企業行動につながる証拠はないという指摘は、本書の中では意外性があり興味深い。ちなみに本書では数字が並んだ表が頻出するが、読み飛ばして結論を急いで読んでも支障はない。
|
| |
鷹匠の技とこころ~鷹狩文化と諏訪流放鷹術~
大塚紀子、白水社、p.216、\2310 |
2011.12.15 |
|
 |
世界的には5000年以上、日本でも1650年以上の歴史を持つ放鷹・鷹狩。日本では徳川家康の時代に大きく発展した。鷹狩に際して、人鷹一体となって狩りを遂行するのが鷹匠である。本書は、早稲田大学の卒業研究をキッカケに鷹匠に興味を持ち、ついには諏訪流鷹匠になった女性の書。
鷹匠とは何か、放鷹のテクニックと道具、鷹狩の歴史と現在、鷹の気性と個性、海外の鷹狩などについて綴っている。門外不出の口伝・秘伝を文書化しており興味深い。特に、鷹の調教や体調管理法などに言及する放鷹術の章は秀抜。鷹狩文化の伝承に対する筆者の想いがひしひしと伝わってくる魅力的な書である。
東京・浜離宮で正月に行われる「放鷹実演」の話で本書は始まる。汐留の電通ビルの屋上からハヤブサを放ち、急降下する姿を見物人に見せるというもの。こうした行事が東京のど真ん中で行われていたとは、寡聞にして知らなかった。ただし鷹狩自体は1972年以降は禁止されており、その技術の伝承が途切れることに筆者は危機感を募らせる。
人と鷹が一体になるための数々のテクニックは奥が深い。人鷹一体の鷹に仕立てるための手順、狩りに向けた鷹の体調管理、鷹の体調の見分け方など、へ~と驚くような話が並ぶ。華麗な放鷹術に「羽合(あわせ)」がある。鷹に加速をつけるために、拳の上にのった鷹を獲物に向けて投げるように押し出す動作である。連続写真が掲載されているが、これがカッコイイ。電子書籍なら動画を組み込みたくなるところだ。
|
| |
ThinkPadはこうして生まれた
内藤在正、幻冬舎、p.201、¥1575 |
2011.12.10 |
|
 |
期待はずれに終わった書。いまやMac派に戻った評者だが、かつては長期間にわたってThinkPad愛好者だった。家族にも勧めていた結果、3台のThinkPadが家で稼働していた時代もあった。「トラックポイント」は、ノート・パソコンのポインティング・デバイスの最高傑作だと今でも考えている。そのThinkPadの父と呼ばれる内藤在正が綴った書とあって、設計哲学や開発秘話が語られるのだと期待して読んだ。興味深い記述もあるのだが、書き込み不足で心に響くものが少ない。散見される誤字も含め、編集者の力量の問題だろう。悪い題材ではなかっただけに残念である。
ThinkPadが誕生したのは1992年。米IBMがパソコン事業を中国Lenovoに売却したあとも、1年間に1200万台が出荷されているという。キーボードやポインティング・デバイスといった入力部の操作性、堅牢性といった面で、ビジネス・パーソンに支持されているのだろう。Let'sNoteに席巻されるまで、ThinkPad Xシリーズが記者の定番パソコンだった時代がけっこう長かった。最近では、レノボNECホールディングスの米沢事業場にThinkPadの製造拠点を移すという話(当該記事)も出ている。
本書はThinkPadが生まれるまでの経緯、ThinkPadの設計思想や開発秘話、内藤自身の技術者および管理者としての哲学、大和研究所の思い出、LenovoやNECレノボ・グループについて総花的に語っている。ThinkPadについて論じている前半部はともかく、LenovoやNECレノボ・グループなそ社内に向けたような書きぶりになっている後半は、読んでいてイマイチしっくりこない。
|
| |
福島 嘘と真実~東日本放射線衛生調査からの報告~
医療科学社、高田純、p.108、¥1260 |
2011.12.8 |
|
 |
世界の核災害調査を手掛けた札幌医科大学教授(専門は放射線防護学)が、福島原発事故の影響を受けている地域の環境と健康を実地調査した書。結論は、福島の放射線は心配なレベルではなく、健康被害はないというもの。著者がこれまで調べた中国やロシアの核災害地と比べて、はるかに安全と強調する。問題は、政府の根拠が不透明な対応とそれに振り回される行政にあると指摘。全体で108ページの小冊子だが、数多くの現場を踏んだ人間のもつ力強さを感じさせられる。原発問題は、専門家と素人が入り乱れたり、エセ専門家が登場したりと混乱状態だが、本書は一読の価値がある。日本の書籍で軽視されがちな索引が充実しているのも見逃せない。後々役立ちそうだ。
筆者は、ガンマ線スペクトル・メーターやアルファ・ベータ・カウンターなどの計測器を携え、2011年4月に札幌から福島経由、東京までの「東日本放射線衛生調査の旅」を敢行した。旅の途中では、屋外における放射線の計測を行うほか、避難者の甲状腺線量検査などを実施。いずれも問題のないレベルであることを確認している。
筆者が憤るのは二つ。一つは、国際原子力事象評価尺度で「レベル7」とチェルノブイリ事故と同等と評価した問題。レベル7の根拠となる放出放射能の算出方法を明記した検証可能な報告書が開示されていない点を問題視する。もう一つは、計画的避難の根拠となる年間線量の算出方法。住民に個人線量計を装着することもなく、屋外線量率を一定値にして年間時間数をかけたため、科学的にみて過大な数字になったと指摘。被災者を苦しめる杜撰な算出法で容認できないと避難する。
|
| |
利他学
小田亮、新潮選書、p.255、¥1260 |
2011.12.7 |
|
 |
人はなぜ赤の他人を助ける、もっといえば自分が相手よりも損をするような利他的な行動をするのだろうか。その根源的な理由を、人間行動進化学を中心に生物学、心理学、経済学、哲学の研究成果をもとに探った書。なぜ人間は利他的なのか、何が利他的行動を起こさせるのか、なぜ利他的行動が維持されるのか、利他性はどこから来たのか、利他性はどこに行くのかといった切り口で持論を展開する。知的好奇心を満足させられる書である。
興味深いのは利他性の原因をさぐる実験である。たとえば「人の目」の効果。1000円を分配する実験で「目」の絵を飾っておくと、他人への分配額が増える。「目」の写真を置いたカフェテリアでは、トレイが片付けられる割合が増え、テーブルがきれいになる。これは利他的な行動によって自分の評判がよくなり、回りまわって自らの利益になるという仕組みが進化の過程で出来上がったという。東京都内では、歌舞伎の隈どりをした目を描いた「東京都防犯ステッカー」を張ったクルマが走っているが、人間行動進化学的に意味があるわけだ。
人間は利他的主義者を外見から見分けることができるという実験結果も面白い。高利他的主義者は低利他的主義者よりも積極的で、心が広く、責任感があるように見え、感じよく、親しみやすく、親切であり、外向的であるという印象をもたれるという。よいところだらけである。では、どういう外見が利他的主義者につながるのだろうか。筆者は、額にしわがよる頻度やうなずきの頻度が多く、ほほ笑みの左右対称性が高いほど利他的に見えるという実験結果を紹介している。ほほ笑みの回数が多いのも好印象につながる。
|
| |
江戸のしきたり~面白すぎる博学知識~
歴史の謎を探る会、KAWADE夢文庫、p.221、¥540 |
2011.12.5 |
|
 |
この手の蘊蓄本は当たり外れが大きい。あまりにも下世話だったり、内容が薄かったりしてガッカリすることが少なくない。本書の評価は可もなく不可もなくといったところ。一つのエピソードに2ページ前後を割き、テンポよく江戸時代の風習や風俗を紹介している。紹介するには、しきたり、近所つきあい、身だしなみ、遊びのマナー、恋愛と結婚、年中行事、商売、武士の作法、刑罰である。深さこそ足りないが、エピソードの選択の仕方が優れており飽きさせない。江戸時代の豊かさを感じることができる1冊に仕上がっている。暇つぶしに読むのには悪くない書である。
|
| |
世界一のトイレ~ウォシュレット開発物語~
林良祐、朝日新書、p.192、¥756 |
推薦! 2011.12.2 |
|
 |
1980年に登場したウォシュレットは世紀の発明である。外出先のトイレで、ウォシュレットがあればついホッとするのは評者だけではあるまい。本書はウォシュレットだけではなく、暖房便座、防臭装置、汚れない便器、節水装置など数々の日本発の技術が生まれるまでの試行錯誤を開発者であるTOTOウォシュレットテクノ社長が綴った書。日本的なキメ細かさと創意工夫が随所に出ているし、技術の奥深さがよく分かり興味深い。技術者の方々にお薦めしたい良書である。ちなみに日本家庭におけるウォシュレット普及率は実に70%超。すごい。
評者は、上前淳一郎が週刊文春に連載していた「読むクスリ」でウォシュレットの開発秘話を読んでから、この発明がずっと気になっていた。「読むクスリ」では、ウォシュレットのノズルの最適な角度を知るために、嫌がる社員を動員した話が紹介されていた。そのほかにも逸話があるはずと、本書の登場を10年以上も待ちわびていたのだ。
ウォシュレットが普及するまでの苦闘の歴史は読み応えがある。人間が飲料する水を直接便器につなぐことに対する水道局の拒否反応。感電を恐れることが普及の障害になった訴訟大国・米国の事情など、パイオニアのTOTO技術者の苦労がわかる。トイレにコンセントが入り、便器が電気製品になったったことが画期的だったという筆者の指摘は目から鱗である。
本書を読んで感心したのは、ウォシュレットの洗浄水に隠された秘密である。おしり洗浄機能「ワンダーウェーブ洗浄」では、しっかりと当たる強い吐水と、水をセーブする弱い吐水を1秒間に70回以上繰り返しお尻に当て、2倍の洗浄力を得ている。何気なく使っているウォシュレットにこんな技術が使われているのには正直驚く。女性ならではの意見がウォシュレットの技術革新に生かされているという逸話も興味深い。
|
| |
|
|

|
2011年11月 |
「方言コスプレ」の時代~ニセ関西弁から龍馬語まで~
田中ゆかり、岩波書店、p.280、\2940 |
2011.11.30 |
|
 |
方言に対する日本人の価値観の変遷を各種の意識調査、テレビ番組や文学作品の分析などから追った書。表題の「方言コスプレ」とは、大阪人でもないのに吉本芸人のように大阪弁で突っ込んだり、高知出身者でもないのにドラマの坂本龍馬のような言葉を使ったり、TPOに応じて方言を使い分ける「言葉のコスチューム・プレイ(コスプレ)」現象を指す。筆者によると比較的若い年齢層を中心に、親密な間柄やくだけた場面で定着しつつある表現という。日本人の方言に対する意識がこの40年ほどで劇的に変わったことがよく分かる書である。
評者のような世代だと、話し言葉といえば標準語というイメージがある。生まれ育った地域の方言(評者の場合は生まれ故郷の大阪弁だったり、育った金沢弁だったりする)は使っているものの、頭のどこかに標準語の呪縛が存在する。筆者は「近代から戦後にかけての標準語の登場と強制」と書いているが、当たらずとも遠からずである。しかし方言に対する日本人の姿勢は徐々に変わっていく。1980年代になると方言コンプレックスが問題にならなくなり、逆に方言がプレステージ化することを筆者は新聞記事や投書から明らかにする。
同時に方言は特定のイメージと結びつく。大阪弁なら「おもしろい」「怖い」「かっこいい」、沖縄弁は「あたたかい」、東京弁は「つまらない」「冷たい」、広島弁は「男らしい」「怖い」、福岡弁は「怖い」などだ。このステレオタイプのイメージが会話相手と共有されることによって、方言のコスプレ化が可能になっていく。このあたりの論理展開はなかなか読ませる。興味深いのは、NHKドラマ(特に大河ドラマ)を分析することで日本社会の方言に対する変化を論じる部分。NHKドラマが試行錯誤しながら方言を扱ってきたことを、筆者は丹念な調査で明らかにする。かつては標準語だった坂本龍馬が、ついには土佐弁を喋るようになっていく。丹念な分析に裏付けられたこの部分を読むだけでも価値がある。
|
| |
Steve Jobs、Walter Isaacson
Simon & Schuster、p.656、$35.00 |
推薦! 2011.11.28 |
|
 |
iPhone 4S発表の翌日10月5日に逝去したスティーブ・ジョブズの評伝。600ページを超える大著で、読み終えるまでにほぼ1カ月かかってしまったが、それだけの価値は十分だ。本書が出版されたのは、当初の予定から1カ月前倒しの10月25日。日米でほぼ同時発売というのも驚きである。原著をあえて読んだのは、日本語版では21章「Family Man」が削られているから。家庭人としてのジョブズを扱った章で、削られた理由はよく分からない。日本語版にはもう一つ問題がある。ジョブズは自らの評伝の装丁にこだわり、やり直しを命じたという。原著はジョブズの要求に沿っているが、日本語版は無視している。
本書がジョブズ本の決定版であるのは間違いない。ジョブズの人生の表面(長所)と裏面(欠点)を微に入り細を穿って描いている。ジョブズが複雑な性格で、どれほど“嫌な奴”なのかは本書を読めばよく分かる。JobsやAppleに関してはJim Carltonの「Apple」やJeffrey Younの「iCon」など優れたノンフィクションがあるが、内容の充実度では本書に一歩譲る。IT業界やパソコン業界の裏側で繰り広げられていた逸話が満載なので、この業界に関心のある方々にお薦めである。Isaacsonという手だれの伝記作家の目を通してだが、ジョブズの強烈なメッセージがビシビシ伝わってくる。一読の価値がある。ただし何せ長いので、まとまった時間がとれる正月休みなどで読んでほしい。
ジョブズの人生を一貫するものは、デザインへのこだわりと、シンプルさの追求である。誰も見ない製品の裏側にまで完璧を期すなど、その徹底ぶりはすさまじい。凡人にはとうてい真似できそうにない。ジョブズの完璧主義が、Macintosh、iMac、iPhone、iPad、iTunes、Apple Storeなどの成功を生んだ経緯を本書は丹念に追っている。ジョブズの行動の背景にある仏教や禅への傾倒も興味深い。
Apple、NeXT、Pixarといったビジネスでの成功物語と並んで、本書で特筆すべきなのはプライベートな面にかなり突っ込んでいる点。妻や娘との関係はもちろんだが、ガンとの闘いについても多くのページを割いている。死の床にあるジョブズをゲイツが見舞った話や、近所に住む米グーグルの創設者ラリー・ペイジとの交流はちょっと感動的である。人生の最後におけるジョブズの姿を知るだけでも本書を読む価値はある。
|
| |
ゲームが変わった~ポストものづくりの競争をどう勝ち抜くか~
中村吉明、東洋経済新報社、p.272、¥1890 |
2011.11.4 |
|
 |
世界市場における競争条件が変わったにもかかわらず、日本企業は対応できていない。では、どうすれば活路が見出せるのか、どうすれば持続的な成長を成し遂げられるのかを経済産業省の官僚が説いた書。正直なところ得るところは少ない。日本の官僚はこの程度なのかという思いを強くする。この手の「日本復活の処方箋」を読み見慣れた方には、新たな発見は多くない。特にIT関連の詳しい方は失望するかもしれない。出てくる事例がいまどきアップルやアマゾン、グーグル、シスコでは言い古されており魅力に乏しい。
筆者はIT業界のほか、水ビジネスと鉄道ビジネスの現状に二つの章を割いて触れる。この部分はお薦めである。評者にとっても土地勘のない分野だけに興味深く読むことができた。
|
| |
|
|

|
2011年10月 |
かぜの科学~もっとも身近な病の生態~
ジェニファー・アッカーマン著、鍛原多惠子・訳、早川書房、p.351、\2205 |
2011.10.25 |
|
 |
身近な病気「カゼ」について、微に入り細を穿って解説した書。サイエンスライターである著者が、カゼとは何か、かかったらどうしたらいいのか、かからないための工夫、カゼ薬や民間療法の効果について、最新の研究や研究者への取材を交え紹介する。すごい驚きがある内容ではないが、知的好奇心をそこそこ満足させられる。アポロ7号の乗組員全員が身体検査のあと6時間後に発症し散々なフライトだったなど、カゼにまつわるエピソードの数々は興味深い。睡眠時間やストレス、性格と発症との関係を明らかにするなど全体に肩の凝らない内容なので、ヒマつぶしに読むのに向いている。
現代は「カゼの黄金時代」らしい。とりわけ保育施設や学校は病原菌の巣。「第一次世界大戦時の塹壕以来、病原体がこれほど効率的に共有されている場所は現代の保育施設以外にない」という専門家の言葉を本書は取り上げる。秀抜なのは、チキンスープなど民間療法や、免疫力が下がると風邪にかかるという俗説についての解説とエピソードの数々である。ビタミンCの摂取やニンニクを食べることの効果の有無についても、本書は紹介する。
カゼの身体機能に与える影響は興味深い。カゼをひいても肺機能や運動能力は損なわれない。ただし記憶する速度は落ちたり、情報を分析・処理する能力に影響を与えるという。カゼは200種類以上の異なったウイルスによって引き起こされ、アデノウイルスのように脂肪細胞の形成速度に影響を与え、肥満の原因となるものさえ存在する。ちなみに、カゼに限らず伝染性疾患の蔓延を予防するもっとも有効な方法は「手洗い」であり、カゼはウイルスであり細菌ではないので、抗菌石けんや洗浄剤はカゼの予防には効かないことを本書は紹介している。
|
| |
勲章~知られざる素顔~
栗原俊雄、岩波新書、p.224、\756 |
2011.10.19 |
|
 |
勲章について、制度創設の経緯や歴史、制度の中身、人選の方法、製造現場、売買の実態などについて詳説した書。新聞に叙勲の記事が出ていても読み飛ばしていたが、毎年春と秋に約4000人が勲章を授与されているという。そんなに多いとは、ちょっと驚きである。勲章制度には法律の裏付けがないとか、文化勲章と文化功労者との関係など知らないことが満載である。蘊蓄好きの方にお薦めの1冊である。
勲章制度の誕生をめぐる裏話は興味深い。時は140年ほど前のパリ万博。薩摩藩は独立国として国際社会に認められるために「薩摩琉球国勲章」をフランス政府高官に進呈した。これが日本の勲章制度の始まりと言われる。幕府側でも「葵勲章」を作ったが、倒幕とともに幻となったという。
このほか本書では、戦前と戦後における勲章制度をめぐる動き、選考の過程、受勲者や拒否者の素顔、叙勲するための涙ぐましい運動、勲章の製造現場、売買の実態、勲章を身につけるときのドレスコードなどを紹介する。
|
| |
独自性の発見~消費者の心をつかむ唯一の方法~
ジャック・トラウト著、スティーブ・リヴキン著、、吉田利子・訳、海と月社、p.312、¥1890 |
2011.10.17 |
|
 |
メインタイトルからはハッキリ分からないが、モノがあふれる時代に企業が生き残るためのマーケティング法を説いた書。実は原題「Differentiate or Die」が内容をよく表している。失敗とは言えないが、邦題には一考の余地があったと思う。差別化は企業が常に努力しなければならない最も重要な戦略だと、筆者は強調する。そして、他社との差別化で効果がある「真の独自性」を実現する方法を豊富な事例を駆使しながら紹介する。具体例が多いのでマーケティングに興味のある方にお薦めである。
とにかく著者は自信満々である。あのマイケル・ポーターに対して、「独自のポジショニングの必要性について語るが、どうすればよいのか助言してくれない。戦略的継続性とか戦略的ポジショニングの深化、トレードオフの最小化などについて語るが、これでは差がつかない」と断じる。広告会社も「広告会社が重視するのはアートであり、科学的姿勢ではない。それでは差はつかない」と切って捨てる。
筆者が推すのは「USP(Unique Selling Proposition)」。USPの要諦は三つ。第1は、広告を見る人に「この商品を買ったら、こういう利益がありますよ」と知らせること。第2は、消費者への提案は競争相手が出さないか、出せないものであること。第3は消費者の気持ちを動かせる力があること。いずれも当たり前のことだが、実現できている例は多くない。少ない成功例と多くの失敗例を筆者は次々に取り上げ、ポイントを手際よく解説する。
筆者が強調するのは「科学的・論理的であるべき」という点。マーケティングの世界で論理的な議論に出会うことはめったになく、これこそが失敗する原因だと自らの経験をもとに分析している。
|
| |
民意のつくられかた
斎藤貴男、岩波書店、p.222、¥1785 |
2011.10.13 |
|
 |
原子力、オリンピック招致、事業仕分け、選挙、道路建設、捕鯨問題などを切り口に、世論はどのように形成されていったのか、民意とは何かを追った書。巨額の広告宣伝費、誘導的な世論調査、営利的な非営利団体を切り口に関係者を取材して実態に迫っている。もともとは雑誌「世界」に掲載された記事。岩波書店と斎藤貴男の組み合わせなので、読む前から方向性が分かるが、思ったほどには岩波臭さは感じなかった。ありがちな切り口だが、日本社会の裏の実態を知ることができるノンフィクションなのは確か。
時節柄、原子力問題に8章のうち冒頭2章を割き、原子力に関する世論形成の舞台裏を明らかにしている。評価したいのは、1章、2章とも福島原発事故の前に雑誌「世界」に掲載されている点。1章が2010年2月、2章が2009年12月が初出。便乗組ではなく、少なくとも斎藤の目の確かさが分かる。内容的にも、大手広告代理店のマスメディアを巻き込んだ巧妙な広報宣伝手法、教科書検定の仕組みを使った原子力教育の実態を明らかにしている部分は読み応えがある。
国策PRと題した3章も刺激的である。原子力行政以外にも、国家が広告を巧みに利用して世論を誘導していることを明らかにする。事例として挙げるのが2008年から2009年に繰り広げられた「チーム・マイナス6%」キャンペーン。京都議定書で義務づけられた二酸化炭素削減を周知徹底するための広報活動である。一見すると無関係に見えるイベントを矢継ぎ早に繰り出すことで、国策の普及啓蒙を図った過程を明らかにする。
|
| |
ひとはなぜだまされるのか
石川幹人、ブルーバックス、p.298、¥861 |
2011.10.8 |
|
 |
人間の心の動きを、生物の進化に基づいて考える「進化心理学」の入門書。進化心理学は1990年代から注目され始め、心の動きが形成された経緯を進化論に基づいて解釈する学問である。例えば、壁の汚れを幽霊だと間違える、怒りの感情を損と知りながら爆発させる、想像と現実は無関係と分かっていながら関連づけて考えたといった行動の根底に、人間の進化の過程があると考える。本書は、錯視、注意、記憶、感情、想像、信念、予測の七つの切り口から、進化心理学の考え方を紹介する。進化心理学では、人間の心は過去の狩猟時代の生活に合うようにチューニングされていると考える。現在の生活環境は、人間の心の仕組みとはズレており、それが数々の齟齬を生む。タイトルとの内容に若干のギャップはあるが、知的好奇心を満たしてくれるブルーバックスらしい書である。
例えば錯視の裏側には、草原に生きる上で適切なように調整された視覚が存在する。注意力にも人類の長い歴史が横たわる。獲物や外敵の敏捷な動きに対して瞬間的に対応するために、速い変化には注意を集中できるが、遅い変化には散漫になってしまい気づかない。記憶の仕組みも興味深い。見たままを忠実に記憶するのではなく、ロジカルな解釈とともに記憶する。また多くの事柄をバラバラに記憶するのではなく、相互に関連づけて整合的な知識として蓄える。
示唆的なのは予測の章である。人間の心は、将来の予測にあまり重きをおかないようになっているという。進化心理学的に人間は、数十年、数百年に1回しか起きないような災害に準備する姿勢は決定的に欠けている。本書執筆中の東日本大震災が起こったが、不幸にも進化心理学の理論を裏付ける結果となった。今回の教訓をどう生かすか、我々には進化心理学を超える英知を求められている。
|
| |
余震(アフターショック)~そして中間層がいなくなる~
ロバート・B・ライシュ著、雨宮寛・訳、今井章子・訳、東洋経済新報社、p.207、¥2100 |
推薦! 2011.10.6 |
|
 |
ウォール街で現在起こっているデモを予言するような内容を含んだ良書。一部の富裕層に富が偏在し、国家の経済成長を支える中間層が喪失しかねない米国の状況に警鐘を鳴らすと同時に、明快な処方箋を書いている。筆者はクリントン時代の労働長官など民主党政権の要職を歴任し、オバマ大統領のアドバイザーを務めた大学教授。この書評で前著「暴走する資本主義」(2008年)を推薦したが、本書もお薦めの1冊だ。
筆者は資本主義を、「富が集中するように仕組まれたゲーム」と位置づけ、その暴走によって富裕層と中間層の経済格差は拡大し続けると論じる。富裕層がどんどん経済力(上位10%が国民総収入の50%)を手に入れても、米国経済を浮揚させる力にはならない。中間層に十分な購買力がなければ需要は拡大しないからだ。米国経済は縮小するばかりで、リーマンショックからの回復は覚束ない。リーマンショックの“余震”は続き、中間層の所得は増えず経済力はどんどん落ち込む。その結果、不平不満が蔓延し、社会は不安定になると結論づける。
筆者は1920年代の大恐慌と2000年代のリーマンショックを比較して、前者は新たな経済秩序を生み出したが、後者は何も生み出していないと断じる。政府は多額の資金を投入し経済破綻を防いだが、格差拡大という社会問題の解決を先送りにしてしまった。政府は大恐慌の教訓を学んでおらず、危機の火種は残ったままというが筆者の判断である。
筆者は中間層への配分を厚くすることが需要を喚起し、経済再生のポイントになると1947年~1975年の大繁栄時代の分析をもとに強調する。筆者は富の再配分について、即効性のある方法として「負の所得税」「所得補助」「税控除」といった方策を提案する。
|
| |
江戸の歴史は大正時代にねじ曲げられた~サムライと庶民365日の真実~
講談社プラスアルファ新書、古川愛哲、p.192、\840 |
2011.10.4 |
|
 |
タイトルと内容が異なっている書。タイトルの引かれて購入すると、評者のように期待はずれに終わるかもしれない。江戸時代についての蘊蓄話が本書の中心である。時代劇の時代考証はめちゃくちゃといった話が次々に登場する。エンタテイメントとしては悪くないが、知的好奇心を満たされる度合いは低く、少々食い足りない。
そもそも、「江戸の歴史は大正時代にねじ曲げられた」という話がどこに出ていたのだろうかと読み返すと、冒頭に登場する。要するに、大正時代に始まった「チャンバラ」に描かれた江戸時代は間違いだらけという話である。タイトルにもかかわらず、何とも印象に残らない。
|
| |
死のテレビ実験~人はそこまで服従するのか~
クリストフ・ニック著、ミシェル・エルチャニノフ著、高野優・訳、河出書房新社、p.309、¥2100 |
2011.10.3 |
|
 |
テレビ番組を模して2009年に行われた心理学実験(服従実験)の詳細を紹介した書。人間が権威に弱いことと、テレビの影響力の大きさを示すショッキングな内容である。筆者はテレビ番組の制作者とジャーナリスト。刺激に飢え、どんどんヒートアップするテレビ番組に危機感を募らせ、この実験を企画した。人々はテレビを無条件に信頼しており、信者に絶対的な権威を持つカルト宗教のようなものだと、筆者は警鐘を鳴らす。その手口は、感情に訴えることで視聴者を煽動しており、独裁者とそっくりだと断じる。
実験はクイズ番組の体裁をとり、出題者(一般人)は回答者(俳優)が間違えるたびに、回答者に与える電気ショックの電圧(最大460V)を高めていくというもの。高電圧に苦しむ回答者の声を聞きながらも、電気ショックを与え続けるように司会者から命令されたときに、人はどれくらいの割合で権威に服従し残酷な行為に走るかを調べた。有名なミルグラムの服従実験(通称「アイヒマン実験」)を架空のクイズ番組に応用し、テレビのもつ権威性を確かめる目的で行われた。
結果は衝撃的。81%の出題者が最後までクイズを続け、最終的には表面上460Vもの電気ショックを回答者に与えたのだ。科学者の権威に対する服従を調べたミルグラムの実験の結果が62.5%だったので、単純に数字を比べるとテレビの権威が科学者を上回ったことになる。
日本のテレビの低俗化は酷いが、本書が紹介する欧州の状況も似たようなもの。露出度と露悪度は欧州が先をいくかもしれない。筆者が服従実験と実験をもとにしたドキュメンタリー番組を思い立ったのは、「このままでは、いずれ殺人を見せる番組が登場しかねない」という危機感が背景にある。テレビ番組によって、テレビ番組を批判するためだったという。
本書は服従実験について、なぜ人々は良心に背く行動をとったのか、途中で服従をやめた人々の状況はどうだったのかについて、社会心理学的な分析を加える。前者は、自発的に参加してという意識から生まれる義務感、部分的な細かい作業に集中する、相手が悪いと考える、といった行動をとることで良心を抑える。後者は、仲間を作る連帯によって服従から逃れることができたと分析する。
|
| |
|
|

|
2011年9月 |
アカデミック・キャピタリズムを超えて~アメリカの大学と科学研究の現在~
上山隆大、NTT出版、p.385、¥3360 |
2011.9.28 |
|
 |
米国の大学と市場経済とのかかわりを、歴史的な経緯や最近の事件・判決、米国社会の特性を踏まえて論じた書。情報技術やバイオ・テクノロジーの分野でイノベーションを生み続ける米大学と産業界の関係を知るうえで役立つ。研究の特許化をはじめとする大学における市場経済の浸透、大学そのものの商業化(ショッピングセンターやホテル、病院、出版社の経営)などについて、ベイエリアの状況を中心に議論を展開する。日本の大学や研究開発の在り方を考えるときに、貴重な情報を与えてくれる1冊である。
研究は、特定の科学者の閉じられた真理探究の活動であってはならないという規範が米国社会に存在すると著者は指摘する。研究者は、一般の人々に対して何らの金銭的利益や精神的利益、幸福にもたらさなければならない。一方で基礎研究は、応用研究を経てイノベーション、産業の発展、豊かな社会へとつながっていく(いわゆる「リニアモデル」)。だから大学の研究への政府や企業の投資は正当化される。こうしたメンタリティが社会には組み込まれており、米国の“地頭”の強さにつながっている。
あまり語られることのない研究費還流の仕組み、遺伝子情報や研究ツールの特許化、研究者における利益相反(出資企業の利益と公共の利益の対立)など、本書には興味深い実例が並ぶ。例えばスタンフォード大学における研究費還流の仕組みはこうなっている。自然科学系研究者は政府から巨額の資金援助を受けているが、大学は50%の共通費を徴収する。この資金を研究費の乏しい人文・社会科学に配布している。メジャーリーグの「ぜいたく税(luxury tax)」同様、米国らしい合理的な考え方だ。有名なスタンフォード・ショッピングセンタの設立経緯についても触れている。
|
| |
日本中枢の崩壊
古賀茂明、講談社、p.386、¥1680 |
2011.9.15 |
|
 |
現役官僚が民主党政権の国家公務員制度改革などを批判したことで話題を呼んだ、古賀茂明のベストセラー。雑誌論文や国会証言などで政権批判を行ったため経済産業省大臣官房付という閑職に追いやられた。その後も現役官僚の肩書きで政権批判を続けていたが、9月22日付で辞表を提出したようだ。本書は“現役官僚”が徹底的に政権を批判している点で見るべきところはあるものの、内容自体は他の民主党政権批判や官僚批判と大きく異なってる訳ではない。政官界の問題について頭を整理するときに役立つといったところが、本書の評価として妥当なところだろう。
筆者が力点を入れて論じるのが国家公務員制度改革。自民党政権時に渡辺喜美・行政改革担当大臣がどのように改正させたか、成立までの紆余曲折、成立後の官僚の抵抗などを詳述している。自民党への失望が大きかっただけに、民主党にいる政権交代に筆者は期待する。期待はすぐに失望に変わる。期待が高かっただけ、その反動は大きかったといえる。
さすがに現役官僚だけに、官僚機構についての記述は詳細だ。天下りの仕組み、官僚が駆使する騙しのテクニック、大企業との癒着など、自らの体験を踏まえ紹介する。
|
| |
調査報道がジャーナリズムを変える
田島泰彦、原寿雄、山本博、花伝社、p.243、¥1785 |
2011.9.15 |
|
 |
政府や官庁、企業の発表を唯々諾々として受け入れ伝える「発表報道」が蔓延するマスメディアに警鐘を鳴した書。10人の筆者がそれぞれの経験を基に、発表報道と対極をなす「調査報道」の重要性を説く。ここでいう調査報道とは、ジャーナリストやマスメディアが独自に取材、調査して読者に伝える手法を指す。日本での金字塔は立花隆「田中角栄研究~その金脈と人脈」だし、米国ではボブ・ウッドワードとカール・バーンスタインがニクソン大統領を辞任に追い込んだウォーターゲート報道が有名である。
本書の前半「調査報道の実際」では、桶川ストーカー事件、足利事件、リクルート事件、日米政府間の核密約、北海道警察の裏金づくりといった調査報道の過程を当事者がたどっている。休刊した写真週刊誌FOCUSの元記者(現在は日本テレビ)や共同通信記者、北海道新聞記者、フリージャーナリストが当時を振り返っており、現場の香りがぷんぷんする。彼らの述懐を読むと、調査報道が成功するまでの道のりは決して平坦ではないことがよく分かる。取材対象の抵抗、同業者の妨害、社内の反対、取材の行き詰まりなど、多くの困難にぶち当たる。挫けそうになる現場を勇気づける場面は読み応え十分である。
後半「調査報道の可能性とジャーナリズム」は、大学教授の論考が中心になっている。ウィキリークスやYouTubeの台頭、名誉毀損訴訟の頻発と賠償金の高騰、個人情報に対する保護意識の高まりなど、マスメディアがおかれた環境の激変をどのように判断すべきか、さらにどのように対処すべきかについて論じる。あまりに変化が劇的で、ウィキリークスに対する評価などまだ定まらない点が多いが、マスメディアで禄を食んでいる評者のような人間の頭の整理に役立つ内容を含んでいる。
|
| |
ユニコード戦記~文字符号の国際標準化バトル~
小林龍生、東京電機大学出版局、p.290、¥2700
|
2011.9.14 |
|
 |
文字コードの国際標準化の舞台裏を綴った書。ジャストシステムから派遣された日本人技術者の視点から、ユニコードとISO/IEC 10646における、漢字標準化作業の詳細を描いている。日本と欧米の標準化に対する考え方の違い、日本国内における標準化推進派と反対派の確執などの人間模様を話の中心に据える。ただし文字コードや情報技術の専門知識がないと読みづらい個所もあり、必ずしも一般向けとはいえない。
ジャストシステムの浮川専務(当時)から辞令を受け、著者が国際標準化作業の現場に放り込まれたのは1995年のこと。パックス・アメリカーナ的な情報技術楽観主義の論理がまかり通る標準委員会のなかで、英語が不自由なまま悪戦苦闘する様子を本書は活写している。苦しい状況のなかで、出身企業(ジャスト以外は外資系)が異なる日本人委員が連帯しながら欧米委員と対峙していく様子は興味深い。
国内における標準化作業も一筋縄ではいかない。もともとJIS漢字は「情報交換用符号化文字集合」として作られており、文学作品を想定しない。そのため「日本文化の根幹たるべき漢字の使用が工業規格ごときに左右されるとは何事か」とJIS批判・ユニコード批判の矢面に立たされる。筆者は「ヒステリックで声高な抽象的非難ではなく、具体的な形で提示してほしい」「国際整合性を無視できない」と考えたものの、文字コードの素人相手に説得は難しかったと嘆く。
本筋と異なるが、国際標準化作業にかかる経費や英語上達法の話は興味深い。経費は出張旅費が中心だが、社員を送り出す企業の負担は相当なものである。英語が苦手だった著者は、最後には部会の議長に就任できるまでスキルを高めたが、それまでの道のりを付録部分で詳述している。まさに英語漬けで、やはり上達に近道はなさそうだ。
|
| |
エネルギー論争の盲点~天然ガスと分散化が日本を救う~
NHK出版新書、石井彰、p.224、¥777
|
2011.9.12 |
|
 |
著者が天然ガスに長年かかわってきた人物という点を差し引いても、エネルギー問題を考える上での貴重な情報が多く盛り込まれた良書。原発派 対 反原発派(再生可能エネルギー派)という構図で“0”か“1”かの不毛な議論に陥りがちな日本のエネルギー論争の問題点を鋭く突いている。部分最適ではなく、全体最適の視点を提供する。
筆者の舌鋒は鋭い。原発容認派も再生可能エネルギー推進派も、都合の悪い事実には目を背けて、自分たちのつごうによいように主張を組み立てていると切って捨てる。同時に、安易な技術楽観論と技術革新期待論を拠り所にしていると批判する。勉強不足のマスメディアが議論の迷走に拍車をかけているという指摘は耳が痛い。
本書の特徴の一つは、エネルギー問題を文明史・人類史的、さらには生物学的・物理学的な視点から論じるところ。第1章と第2章を割いて、ユニークな視点から持論を展開している。新書なのでページ数の成約があるので語り尽くしているとは言いづらいが、名著「銃・病原菌・鉄」を彷彿させる内容である。刺激的だし頭を整理するうえで役に立つ。
筆者が推すエネルギー源は天然ガスである。天然ガスは、同じ熱量でCO2排出量が石油よりも30%、石炭よりも50%少ない。シェールガスの採掘が可能になって埋蔵量は飛躍的に拡大。現在の生産量なら400年以上は維持でき、石油よりも豊富という。さらに米国が世界最大の天然ガス生産国になったことで、地政学的な懸念は少なくなる。筆者が考える全体最適のエネルギー政策はこうなる。天然ガスを活用したコジェネレーションと分散化を進め、太陽光発電と風力発電などの再生可能エネルギーと組み合わせる。再生可能エネルギーではコスト面を考えて風力発電を優先すべきと主張する。
|
| |
清貧と復興~土光敏夫100の言葉~
出町譲、文藝春秋、p.288、¥1400
|
2011.9.8 |
|
 |
石川島播磨重工と東芝で社長を務め、経団連会長や第2臨調会長を歴任した土光敏夫の箴言・至言をまとめた書。100件の発言と背景説明で構成している。キリのいい100にこだわったせいで、後半部が息切れ気味なのは少し残念。短く・鋭くで十分に著者の思いは伝わったように思う。
土光の発言からは、人間としての気骨と迫力、自信が、言葉に乗り移っている感じがする。没後20年あまりになるが、言葉はまったく色あせていない。日本の政治・経済・社会に対する危機意識は強く、いまなお通用する警鐘が並ぶ。しかも実行を伴っていたところが、土光の真価だろう。本書を読むと、この20年間、われわれは何をやってきたのだろうとの思いを強くする。
城山三郎は土光を「一瞬一瞬にすべてを賭ける、という生き方の迫力。それが八十年も積もり積もると、極上の特別天然記念物でも見る思いがする」と称したという。多くの経済人を見てきた城山にこう言わしめる人間力はちょっと凄いが、本書を読むと理由が分かる。ここ数年、筋が通らない、腰が据わらない、言いっ放し、見識を疑うといった場面に散々出会ってきただけに、本書は一服の清涼剤である。
|
| |
The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators
Jeff Dyer、Hal Gregersen、Clayton M. Christensen、Harvard Business School Pr、p.304、$29.95
|
2011.9.7 |
|
 |
「イノベーションのジレンマ」で知られるClayton M. Christensenなど3人の大学教授の手によるビジネス書。8年間の調査研究の成果という。本書の主題は「イノベーションはどうやって生まれたのか」「我々は、どうすればイノベーションを生み出せるのか」で、破壊的イノベーションを生む秘訣を事例に基づき論じる。画期的な議論を展開している感じはしないが、米国のビジネス書らしく、多くの事例や調査で裏付けをとっており読み応えはある。ただし、そのうちに翻訳が出ると思われるので、慌てて原書を読む必要性は感じない。
筆者によるとイノベーティブな起業家は、一見関連がなさそうな事柄のあいだに関係性を見つける能力に長ける。その関係性からイノベーティブな製品やサービスを生み出すという。このほか、違和感がイノベーションのスタート、イノベーションには人材の多様性が不可欠、イノベータの能力はT型(特定分野における深い専門知識と幅広い興味)など、興味深い指摘が多い。ちなみに、生まれつきの才能がなければイノベータになれない訳ではなく、努力すれば身に付く。誰でも五つのスキルを磨けば破壊的イノベーションを生むことが可能と論じる(ビジネス的に成功するとは無関係だが…)。
ここでいう五つのスキルとは、Associating(関連づけ)、Questioning(探究心)、Observing(観察眼)、Networking(人的ネットーワーク)、Experimenting(実行力)である。これらのスキルの鍛え方について、それぞれ1章を割いて詳述する。特に印象に残ったのはQuestioningとExperimenting。前者ではブレストならぬQuestionStormingの重要さ、後者では自ら手を動かすかどうかがイノベータと非イノベータの差だと説いている。
興味深いのはイノベーション企業ランキング。過去の実績だけではなく、将来的にイノベーティブな企業かどうかを評価するための指標を筆者らは作成した。正しいかどうかは歴史が判断することになるが、1位はSalesforce.com、2位はIntuitive Surgical、3位はAmazon.com、4位Celgene、5位Apple。Googleは6位である。ちなみに過去の実績に基づくBusinessWeek誌のイノベーション企業ランキング(1位Apple、2位Google、3位Microsoft、4位トヨタ、5位GE)である。
|
| |
五感で学べ~ある農業学校の過酷で濃密な365日~
川上康介、オレンジページ、p.195、¥1500
|
2011.9.1 |
|
 |
タキイ種苗が1947年に設立した農業学校「タキイ研究農場付属園芸専門学校」の体験入学記。40代のノンフィクションライターが18~24歳の若者に交じって1年にわたって学校生活を送り、ユニークな教育と寮生たちの成長を追っている。「タネのタキイ」で知られるタキイ種苗が運営している学校が存在していること自体に驚くと同時に、農業という自然を相手にする仕事の奥深さと人格形成に与える影響を感じさせてくれる書である。
学生の出身校はさまざま。高校からの進学者が大勢を占めるが、農学部以外からの大卒者も多く含まれており、農業のエリート養成校という位置づけも的外れではなさそうだ。全般に筆者の強い思い入れが感じられ、少し引いてしまう場面もあるが、素直に感動するのも悪くない。何よりも登場する学生たちが若者らしくていいし、彼らに対する記述に筆者の愛情が感じられる。
|
| |
|
|

|
2011年8月 |
フォールト・ラインズ~「大断層」が金融危機を再び招く~
ラグラム・ラジャン著、伏見威蕃・訳、月沢李歌子・訳、新潮社、p.318、¥1995
|
2011.8.30 |
|
 |
リーマンショックの原因を分析した書籍として、欧米で高い評価を得ているビジネス書。帯にはBusiness Books of the Year 2010を受賞したとなっている。確かに高い視点から米国および世界経済を俯瞰し、過去の歴史を踏まえながら、なぜ金融危機が起こったかを丁寧に論じている。得るところの多いビジネス書である。
筆者であるラグラム・ラジャンは、金融危機を2005年に予言したとされる米シカゴ大学経営大学院教授。「米国でいま最も注目を集める経済学者」といわれる。本書にはジャスミン革命を予言するような記述もあり、いま乗っている経済学者というのは間違いなさそうだ。議論が多岐にわたり頭の整理がつきづらいところもあるが、一読の価値はある。
筆者は金融危機を引き起こした原因が、フォールト・ラインズ(断層線)にあると指摘する。ここでいう断層線は、富裕層と貧困層、輸出国と輸入国、先進国と新興国といったギャップを指す。このギャップのあいだに蓄積したエネルギーが拡大し均衡を失い破断した結果、経済危機が生じたと分析する。例えば米国の富裕層と貧困層のギャップは政治的な圧力を生み、住宅ローン拡大を促す政策を政府にとらせた。サブプライムローンといった粗悪な金融商品に対する監視が行き届かなくなり、金融危機の原因の一つになったと結論づける。
本書の特徴は複雑に絡み合う世界の政治、経済、社会システムを解きほぐし、金融危機の原因に迫っているところにある。第1に挙げるのは、前述の米国の経済政策。拡大した米国消費を、日独中といった輸出国が支え、輸出国と輸入国のあいだの依存関係が強まるとともに貿易不均衡は拡大を続けた。米国の消費が限界を超えて変調をきたすと、その影響は米国だけではなく世界にも及んだ。世界通貨危機となり負の連鎖が始まったのだ。
断層線は現在も存在し、今後も金融危機は必定である。筆者は後半部で、金融危機を周期的に起こさないための処方箋を書く。米国における金融改革だけではなく、教育や医療、セーフティネットの拡充などについて論じている。このなかでは失業対策(セーフティネット)に比較的多くの部分を割いているのが特徴的である。金融改革に際しては、「いかなる民間金融機関も政府の保護を受けてはならない」という主張も印象的である。
|
| |
生物学的文明論
本川達雄、新潮新書、p.248、¥777
|
2011.8.25 |
|
 |
生物学は評者が好む分野の一つ。多くの書籍を読んでいるが、そのなかで特に印象に残っている2冊がある。「試験管のなかの生命~細胞研究入門~」と「ゾウの時間 ネズミの時間~サイズの生物学~」だ。いずれも生命や生物の不思議や魅力を巧みに紹介している。本書は後者の筆者・本川達雄 東工大教授による現代文明論。生物学の視点から現代文明や技術、科学に批判を加えている。
筆者の主張は、環境問題、資源・エネルギー問題、高齢化社会といった問題を数学・物理学的発想から解決しようとするから袋小路に入ってしまうというもの。生物学者の視点からは別の解決策が見えると論じる。まず取り上げるのはサンゴ礁。サンゴ礁における共生や資源リサイクルを引き合いに、質よりも量を追う現代技術や科学の限界を指摘。普遍性を重視し多様性を軽視する科学的発想にも苦言を呈する。歴史を持つ独特なものは、それだけで価値があるとすべきというのが筆者の主張だ。
本書の後半は、「ゾウの時間 ネズミの時間」の著者の真骨頂というべき内容が続く。ゾウの時間はゆっくり、ネズミの時間はせわしなく進む。エネルギー消費量に比例して時間が速くなるのだ。例えばネズミは単位時間あたり、ゾウよりも30倍のエネルギーを消費するので、30倍の速度で時間は進む。筆者はこれを現代社会に当てはめる。現代社会の時間は、エネルギーを使って(じゃんじゃん石油を燃やして)いるから、人間が生物として持つ時間よりも速くなっている。そのために、地球温暖化や資源エネルギーの枯渇が起こった。時間を少しゆっくりにして、社会の時間が体の時間とかけ離れないようにすれば、自動的に温暖化もエネルギー問題も解決する、と筆者は論じる。ちょっと風変わりだが、傾聴すべき内容を含んだ新書である。
|
| |
ロボット兵士の戦争
P・W・シンガー著、小林由香利・訳、日本放送出版協会、p.720、¥3570
|
推薦! 2011.8.23 |
|
 |
軍用ロボットの過去・現在・未来を詳細に追ったノンフィクション。ロボットだけではなく、無人航空機や非致死性兵器などの最新兵器や研究開発に関するエピソードや事例が満載である。1991年の湾岸戦争は空爆の様子をリアルタイムで映し出し、戦争のイメージを大きく変えた。シュワルツコフ将軍が「ハイテク戦争」と呼び、「コンピュータがなければ、あれだけのことをやり遂げることはできなかった」と言われた戦争である。それから20年。筆者は、変貌を遂げつつある戦争の実態とそこから生じる問題に迫っている。700ページを超える大著で読み終えるのは大変だが、それだけの価値がある。
筆者は国防総省、国務省、CIAなどの顧問も務める米ブルッキングス研究所の研究員。この書評で以前取り上げた「戦争請負会社」の著者でもある。2008年の大統領選ではオバマ陣営の国防戦略を取りまとめたという。米政府の政策に影響を与える人物だけに内容に説得力があるし、将来についての見通しは示唆的である。ロボットに興味を持つ方だけではなく、多くの技術者に読んでもらいたい。
本書は、戦争のスタイルがこれまでと根本から違っていることを明らかにする。中核は情報技術(IT)とネットワーク技術、ロボット技術、そしてAI(人工知能)である。その結果、兵士は戦場に赴くことなく、敵に攻撃を加える。
例えば無人攻撃機のパイロットの1日はこうだ。朝、米国の自宅で目覚め、米国内のオフィス(基地)に出勤する。オフィスの自席に座り、午前中はアフガニスタンのテロ組織の拠点を攻撃、午後にはイラクを偵察、夕方には自宅に帰って家族と食事、といった具合だ。ゲームと紙一重の世界がそこにはある。本書のタイトルになっている人型ロボットが歩兵の代わりに使われ始めるのは2025年ころ。米国では、150人の兵士と2000台のロボットから成る分遣隊も計画されているという。
本書は、戦争がIT化することの危険性について言及する。これまで政治家は、武力を最後の選択とみなしてきた。しかし無人システムを使うと犠牲者が減るように見えるため、選択肢としての武力行使の順位が上がりかねない。すなわち戦争の可能性が高まってしまう。このほかロボット化とIT化は、軍隊の指揮系統や政治家・軍人の倫理観に影響を与えると指摘する。とにかく読みどころの多い1冊である。
|
| |
百姓たちの江戸時代
渡辺尚志、ちくまプリマー新書、p.175、¥798
|
2011.8.16 |
|
 |
江戸時代の人口の80%を占めていた農民(本書では百姓と呼んでいる)。その暮らしぶりを紹介した書。記述は淡々としていて面白みに欠けるが、衣食住や労働、育児、医療、教養、遊び、文化などについて浅く・広く論じている。物足りない部分は文末に掲げた参考文献を漁ればいいとといった割り切りを感じさせる。
本書を読むと江戸文化の豊かさと、評者のもつ江戸時代のイメージが時代劇に強く影響を受けていることを認識させられる。農民といえば年貢の取り立てに苦しみ、衣食住は貧しいとつい思ってしまう。しかし本書が紹介する農民の生活はずいぶん豊かである(比較的豊かな層に焦点を当てていることも影響している)。例えば「衣」。意外に衣装持ちだったり、絹の羽二重を持っていたりする。「食」にしても、婚礼の祝い膳に使われた食材の豊かさは驚きである。
江戸後期は晩婚化(もちろん現代に比べるとずっと若い)と少子化が進んでいたというのも意外。18~19世紀の平均初婚年齢は男が25~27歳、女が18から24歳と現代に比べれば若いが、17世紀に比べて男が2歳、女が3歳ほど上昇したという。晩婚化の影響もあって子どもの数は2~3人程度。少なく生んで、手間ひまかけて育てるのが普通だった。口減らしの対象から脱し、子宝という考え方も生まれた。何とも江戸時代への興味が増す書である。
|
| |
チェルノブイリの森~事故後20年の自然誌~
メアリー・マイシオ著、中尾ゆかり・訳、日本放送出版協会、p.381、¥2310
|
2011.8.11 |
|
 |
チェルノブイリ原子力発電所で事故が起こったのは1986年4月26日。今から25年前である。本書は、原発事故が生態系にどのような影響を与えたのかを追ったルポルタージュ。ウクライナ系米国人ジャーナリストが現地に赴き、チェルノブイリだけではなくベラルーシやロシアなど周辺地域にも足を運んで実態をレポートしている。危険地域に暮らす庶民の生活にも迫っており、目線の低いルポらしいルポに仕上がっている。冗長な感じを受ける個所もあるが、放射線や放射性物質が20年ほどのスパンで生態系にどのような影響を与えるのかを知るうえで貴重な記録である。福島原発の事故に注目が集まるなか、読んで損はない1冊といえる。原著は2005年に出版されており、チェルノブイリの現状とは異なっている可能性もある。
この書評では2008年に「人類が消えた世界」を紹介した。チェルノブイリとその周辺は人間の立ち入りが厳しく制限され、まさに“人類が消えた世界”である。生態系の再生能力を試す場となっており、事故後の変化は興味深い。では、事故から約20年後に訪れた筆者の目に、チェルノブイリはどう見えたのか。筆者はこう書いている。「ヨーロッパ最大の自然の聖域として息を吹き返し、野生の生物で満ちていた」と。人類が去った後に生まれたのは動植物の楽園で、筆者は行く先々で希少種や絶滅危惧種と出会っている。
放射線による生物への影響と聞くと、奇形や巨大生物といった連想がわく。しかしチェルノブイリに関しては、遺伝子にキズがついている生物は認められるが、外見でそれと分かる事例は少ないという。本書を読んでも、チェルノブイリ原子力発電所から10km圏内にある枯れた松林「赤い森」の話が印象に残るくらいである。
深刻なのは、やはり原発である。爆発した4号炉はコンクリートで固められ、「石棺」と呼ばれる建造物になっている。ところが応急措置で建てられたためにガタがきており、事故から20年あまりたち老朽化も進んでいる。地震によって崩壊する可能性もあると指摘する(チェルノブイリは活断層の上に建っているらしい)。石棺を覆う可動型シェルターを作る計画もあるようだが、建設が始まったという話は聞かない。チェルノブイリ原発という重荷は、今後も長く人類にのしかかり続ける。
|
| |
感染症と文明~共生への道~
山本太郎、岩波新書、p.224、¥756
|
2011.8.5 |
|
 |
ペストや天然痘といった感染症が、古代以来の人類にどういった影響を与えたかを論じた書。文明が感染症の流行の土台となるとともに、感染症の存在によって文明が守られ、拡大を支えたこと、感染症の存在が社会の在り方に影響を与えたことを明らかにする。スケール感では昨年読んだ「銃・病原菌・鉄」に譲るが、対象を絞った分だけ感染症の内容は充実している。面白みは少ないが、新書らしい新書に仕上がっている。
本書を読むとペストの威力と影響がよく分かる。ペストの起源は中国にあり、それが絹の道を通してユーロッパに達する。その結果、ユーロッパの人口は600年の間に3300万人から1800万人の激減するといった衝撃を人類に与えた。ペストによる人口激減が賃金の上昇を生み、農民の都市への流入につながり荘園制の崩壊を加速した。最終的には封建制度の解体につながる。
本書はペスト以外に、マラリア、新型インフルエンザ、エボナ熱、エイズ、天然痘といった感染症について、流行の歴史と人類に与えた影響を論じている。
|
| |
大泥棒~「忍びの弥三郎日記」に賊たちの技と人生を読む~
清永賢二、東洋経済新報社、p.444、¥2520
|
2011.8.3 |
|
 |
一種の奇書である。筆者は犯罪行動生態学の書と位置づける。伝説の大泥棒「忍びの弥三郎(のびのやさぶろう)」が服役中に書き記した6冊の日記をもとに、元警察庁の犯罪研究者だった筆者が防犯の要諦を解説している。犯罪者の心理に焦点を当て、犯罪予防のポイントを説く。家屋への侵入の実演や泥棒の目の動きを追った写真など、シカケを有効に使っており説得力に富む。なかには泥棒が建てた、泥棒に入られないための安心・安全住宅というものもある。ちなみに忍びの弥三郎の「忍び(のび)」とは、刑事や犯罪者が使う隠語。家人が就寝時に屋内に侵入し金品を盗むことを指す。
本書の成り立ちは複雑である。刑務所の検閲を前提にした日記なので、ストレートに手口は書かれていない。そこで、これまた稀代の泥棒「猿の義ちゃん(ましらのぎちゃん)」の助けを借りて日記を解読したのが本書である。的確な指摘が多いので、悪用されることを恐れて核心部分は伏せ字になっている。本当に知りたい部分が読めないのは大減点だが、それでもなお興味深い内容にあふれている。
本書は導入部分で犯罪および犯罪者に関する一般論や研究成果を紹介したあと、忍びの弥三郎の実像に触れる。その後、日記にそって「探る」「獲る」「退散する」について紹介する。なかには、子どもを犯罪者にしない13か条、泥棒の目のつけどころ、犬と猫はどちらが防犯に役立つかといった項目もある。
|
| |
|
|

|
2011年7月 |
どがんね~古賀常次郎詳伝~
佐保圭、日経BPコンサルティング、p.224、¥1260
|
2011.7.31 |
|
 |
古賀常次郎といっても、ほとんどの方はご存じないだろう。評者も同じだったが、ひょんなことから会社の会議で古賀の話題が出てさっそく購入。「こんな快男児が佐賀県にいるのだ」と驚かされた。どちらかと言えば若い方々、特に小中学校の生徒に読んでもらいたい内容である。224ページの本だが、とても字が大きいので2時間もあれば読み通せる。
古賀をどのように紹介するのが適切なのかは難しい。筆者は発明家、実業家、篤志家と枕詞を付けているが、そのいずれにも該当する。ともかく不思議な魅力をもった人物である。
幼少期の家庭環境は恵まれず、読み書きもろくにできなかった。鑑別所送りになったりもしている。中卒で働きながら金型の技術を身につける。この経験が、「振動しても緩まない平ネジ」の発明につながる。日本だけではなく欧米でも特許を取得。NASAがロケットに使ったといった伝説も伝わる。佐賀県の長者番付の常連になるなど事業家としても成功しているが、業務内容は特許と無関係のビル管理業。篤志家としても佐賀県では有名。夏休みに読むと、一服の清涼感を与えてくれる書である。
|
| |
ウォール・ストリート・ジャーナル陥落の内幕
サラ・エリソン著、土方奈美・訳、プレジデント社、¥2100、p.440
|
2011.7.22 |
|
 |
米ウォール・ストリート・ジャーナル紙が、ルパート・マードックの手にどうして落ちたのか(買収されたのか)を克明に追ったノンフィクション。副題の「なぜ世界屈指の高級紙はメディア王マードックに身売りしたのか」が、本書の内容をよく表している。今や盗聴事件の渦中にいるマードックだが買収においては手だれ。大株主である創業家・バンクロフト家を分断し内紛を起こさせるなど、百戦錬磨の手口がよく分かる。ちなみに筆者はウォール・ストリート・ジャーナルの元記者。記者側の視点から、経済紙から大衆紙への紙面の変化を批判的に描いている。
否定的なイメージの強いマードックだが、本書を読むと別の側面も感じる。インターネットの興隆に伴う広告収入と販売収入の減少によって、新聞業界は苦境に陥っている。それでも買収の手を緩めないマードックのメディアへの情熱は凄い。ウォール・ストリート・ジャーナル買収でも、株価に70%近いプレミアムを上乗せした。いったい何がマードックの背中を押しているのか知りたいところだ。権力欲なのか政治的な野心なのか。
本書は、ウォール・ストリート・ジャーナルの編集がどのようになされてきたのか、紙面(特に1面)の作り方のコンセプト、編集局の人間模様といった側面からも楽しめる。マードックの経営手法や、手に入れた新聞や放送局の編集にどのように干渉してきたかの説明も興味深い。一般向けの書ではないが、マスメディアに興味を持つ方にお薦めである。
|
| |
トラブルなう
久田将義、ミリオン出版、p.207、¥1050
|
2011.7.24 |
|
 |
雑誌の編集者を務める筆者が遭遇したトラブルの数々を紹介した書。恫喝や脅迫、恐喝、拉致といった体験を面白おかしく綴っている。多くの事例を紹介しているぶん、個々のエピソードに対する書き込みは不足気味。物足りなさを感じるが、内容が内容だけに仕方がない面もある。詳しく書くと、さらなるクレームの呼び水になりかねない。評者の商売柄、文章が粗いのも気になる。同様の書に「ヤクザが店にやってきた―暴力団と闘い続け」が有名だが、面白さと役立ち度は一歩ゆずる。
筆者は大学卒業後、ダークサイドJapan、週刊朝日や選択、別冊ラジオライフなどの編集を経て、現在は「実話ナックルズ」の発行人である。寡聞にして実話ナックルズは知らないが、コンビニに置いてあるらしい。創刊10年を超えているので、そこそこ固定ファンをつかんでいるのだろう。ちなみに本書のカバーでは、実話ナックルズをアウトロー雑誌と称している。
本書は、筆者が体験したクレームの数々を、アウトロー(ヤクザ、右翼、ギャング)編、政治家編、文化人・ライター編に分類して紹介する。それぞれに業種(?)の特徴が出ていて興味深い。特に文化人・ライター編は実名で当該人物が登場している。同業者ということもあって容赦がない。「ほう」と驚くような話も出てくる。
本書は個人的な体験談を紹介しているが、クレーム対処のノウハウ本としての価値もそこそこありそうだ。最後に休刊中の「噂の真相」の岡留・元編集長との対談を収録する。これがなかなか面白い。
|
| |
東電帝国~その失敗の本質~
志村嘉一郎、文春新書、p.232、¥798
|
2011.7.22 |
|
 |
本書の帯には、「最も知る記者がついに書いた、超エリート集団のカネと人脈」とある。だったら「もっと前に東京電力の実態を書いてくれていたら」と突っ込みを入れたくなる。東日本大震災の前に上梓されていたら、筆者の評価と本書の価値はぐんと高まっただろう。東電に関する情報が溢れるなか、本書は馬群に埋もれた感がある。もっとも東日本大震災前に出版されていても、在庫の山を築いた可能性が高かったのも事実だが…
筆者は朝日新聞で経済部記者として電力、石油、電機などを担当。朝日新聞退社後に東電の影響下にある電力中央研究所の研究顧問に就いている。ただし東電関連のマンション建設の反対運動に関係したため、他のマスコミ出身者の契約が延長されたにもかかわらず、筆者は雇い止めになったという。自慢話にも言い訳にも聞こえる話である。
暴露的な話題を期待して本書を読むと失望するだろう。筆致は抑えられ、どちらというと淡々と東電の歴史と現状を紹介する。もちろん、豊富な資金力を生かして政治家や役所、マスコミを操り、寄付講座や寄付金で学界を動かしてきた実態に触れているし、官僚主義がはびこり驕り高ぶったところに原発事故の原因を見ているが、いずれも今となっては目新しさに欠ける。むしろ、木川田一隆や平岩外四といった歴代社長の逸話、電力の鬼と呼ばれた松永安左衛門との関係、福島県に原発が置かれた経緯、原発の新聞広告を巡るエピソードなどをバランスよく取り上げているところに本書の特徴がある。今の時期に一歩後ろに下がり落ち着いて、東京電力とはどんな会社かを考えたい方に向いている。
|
| |
日本の電機産業はこうやって蘇る
若林秀樹、洋泉社、p.308、¥1575
|
2011.7.20 |
|
 |
証券アナリストとして電機業界を20年あまり見続け、現在はヘッジファンドの社長を務める筆者が描く電機産業の未来像。アナリストらしい視点で電機産業を俯瞰している。全体としてよくまとまっているが、議論の展開が少し雑駁なのが気になる。個人的な体験に基づいて将来像を語っているところが散見される。もう少し裏付けをしっかりした方が読者の安心感と信頼感は増しただろう。この書評で、筆者の前著「日本の電機産業に未来はあるのか」についてこう書いた。「電機業界に詳しくない方が読んで全体像を把握するには役立つ。逆に、少しでも業界を知っている方々には、刮目すべき議論が少なく退屈かもしれない」と。この指摘は今回も通用する。
出版直前に、東日本大震災が起こったのも本書にとっては不幸だった。奥付を見ると本書の発行日は4月5日。震災の影響を反映する時間的な余裕はなかったのだろう。前書きや後書きでぎりぎり触れることも可能だったかもしれないが、そうすると景況感や原子力発電に関する記述と辻褄が合わなくなる。本文に手を入れるとなると、オオゴトになってしまう。こうなると、タイミングが悪かったとしかいえない。
これまた前回と同じだが、校正の甘さとITやIT業界についての知識不足も気になるところだ。中国の大学は精華大学ではなく清華大学だし、通信機器(ルーター)で名前を挙げるならルーセントではなくシスコシステムズだろう。精華大学は京都の大学である。ルーセントは合併によってアルカテル・ルーセントに社名が変わっている。もう少し細部に気を配るべきだ。
|
| |
Making the World Work Better:The Ideas That Shaped a Century and a Company
Kevin Maney、Steve Hamm、Jeffrey O'Brien、IBM Press、p.350、$29.99
|
2011.7.14 |
|
 |
米IBMの創業100周年を記念して出版された書。社長兼会長兼CEOのSamuel Palmisanoが力のこもった序文を書いている。USA TodayやBusinessWeek、Wired出身の3人のジャーナリストを使い、IBMの歴史を技術、経営、社会貢献といった視点から描く。成功だけは失敗についても触れている点で単なる社史と一線を画そうとする努力が伺えるが、しょせん社史の一種。サービス精神と批判精神の発揮には自ずと限界がある。とりわけ「IBMは素晴らしい」といったトーンの第3部は退屈である。評者のような IT 業界に関連する職業の人間はともかく、万人にお薦めの書とはいえない。
本書は3部構成になっている。第1部は技術、第2部は経営、第3部は社会貢献について触れる。個人的に読み応えがあったのは、センシング、メモリ、プロセシング、ロジック、コネクティング、アーキテクチャを取り上げた第1部。ページ数が限られているので深みはないが、コンピュータと周辺機器の開発にまつわるエピソードを発明者への取材を交えて紹介する。ノーベル賞受賞者が続々登場するし、System/360、パンチカード、ハードディスク、磁気テープ、Fortranの開発物語は実に興味深い。
第1部の著者Kevin Manleyが力を込めて書くのはスーパーコンピュータの話である。スーパーコンピュータ「Watson」が、クイズ番組「Jeopardy!」のチャンピオンとの対決し、勝利を収めた話に多くのページを割く。「DeepQA」と呼ぶ技術を使うWatsonに、チェスに特化したDeepBlueに比べて高い評価を与える。実際、DeepQAはコールセンターでの応用を考えているようだ。
第2部ではIBMの経営の先進性を紹介する。社史であることを割り引く必要はあるが、女性雇用をはじめとする多様性や月給制の導入など、いろいろ勉強になる。IBM を破綻のふちから救ったGerstner はここで登場する。
ちなみに本書はペーパーバック版は家で、Kindle版は通勤電車で読んだが、前者がお薦めである。レイアウトが凝っていて、興味深い写真がメリハリをつけて掲載されている。こうした楽しみがKindle版では残念ながら味わえない。ここらが、いまのデジタル出版の限界だろう。
|
| |
赤ちゃんの科学~ヒトはどのように生まれてくるのか~
マーク・スローン、早川直子・訳、日本放送出版協会、p.424、¥2310
|
2011.7.6 |
|
 |
30年近く出産現場に立ち会ってきた小児科医が紹介する「赤ちゃんの神秘」。どこかの書評が取り上げていたので購入したが、400ページを超える大著なのでツンドク状態が続いていた。何となく目障りなので読み始める。筆者は赤ちゃんだけではなく、人間という生物の不思議にも言及する。読み出すと、なかなか面白い。肩の凝らない内容なので暇つぶしに向く。ただし、400ページ超なので集中力を持続するのが大変かもしれない。
本書が扱う話題は多岐にわたる。帝王切開が一般的な出産法になるまでの歴史、陣痛を抑えるための数々の試み、分娩室に信頼できる人が付き添うことの大切さ、男性に起こる「つわり」の不思議、分娩にまつわる風習、新生児の五感(視力、聴力、味覚、嗅覚、触覚)などなど。
とりわけ、帝王切開に初めて成功した医師の経歴は、生涯を男性で通した女性というのは驚きだ。あのナイチンゲールもかかわったという。クイズに出てきそうな逸話で興味深い。赤ちゃんの味覚も、聞けば当たり前の話だが、「ほう」とつい感心してしまう。人間は羊水の匂いを長期間記憶しており、母親の好みや文化に根ざした食べ物を受け継いでいくという(羊水には、母親が食べたものの匂いがすぐに反映するらしい)。最大の見せ場は、誕生から2~3分のあいだに起こる変化と、生まれたばかりの赤ちゃんを母親のお腹の上に乗せたときの行動。後者は感動的だ。
|
| |
津波と原発
佐野眞一、講談社、p.258、¥1575
|
2011.7.4 |
|
 |
東日本大震災の被災地を歩き、惨状を目の当たりにしたノンフィクション作家・佐野眞一の驚きと怒りがひしひしと伝わってくるルポルタージュ。特に怒りが凄まじい。本書はルポの基本である現場を歩くことの重要さを改めて教えてくれる。佐野はこう言う。「被災者はあまりにも激甚な災害に言葉を失った。その沈黙を伝えるには“大文字”の論評ではなく、ディテールを丹念に積み上げて“小文字”で語るノンフィクションしかない」と。こうした思いにかられて、手術後の身体にもかかわらず現場に向かう。
筆者の怒りは、新聞やテレビといった大メディアに向けられる。“お上”の言うことを書くだけで、本当の現場を報じない。テレビが垂れ流す他人事のような津波映像や、新聞の紋切り型の美談報道に知的怠慢を感じ取る。大メディアは、空疎で重みも深みもない言葉をまき散らすだけと手厳しい。筆者は被災した人びとを丹念に描く。対象は、親交のあった新宿のオカマバーのママだったり、漁協の組合長や定置網の帝王と呼ばれる漁師、日本共産党の元文化部長などだ。それぞれが吐く言葉は重く胸に響く。
後半は、逮捕覚悟で立ち入り禁止地域に入ったルポに始まり、日本の原子力発電や福島原発の原点に迫る。東電OL殺人事件に見る東京電力の体質、正力松太郎・読売新聞と原子力発電、福島原発と堤康次郎の関係など、縦横無尽に議論を展開し読み応え十分である。
|
| |
|
|

|
2011年6月 |
江戸の卵は1個400円!~モノの値段で知る江戸の暮らし~
丸田勲、光文社新書、p.203、¥777
|
2011.6.30 |
|
 |
町人文化が花開いた文化・文政年間(1804~1829年)の物価を、円換算して紹介する書。江戸っ子や武士の暮らしぶりが垣間見えて楽しい。取り上げるのは、表題の卵のほか、大岡越前守の年収、不倫の慰謝料、家賃、医療費、化粧品など。ちなみに一両は12万8000円と換算している。肩の凝らない内容なので、夏休みなどの休暇のおともにお薦めの書である。
最初に紹介するのは庶民の生活。番頭の年収は256万~384万円とそこそこだが、豪商となると年収1280万~2560万円とかなりの高給取り。大工は職人のなかでは高給取りで年収は317万円ほど。長屋の家賃は年24万円なので、年収に占める家賃の割合は7.6%。現代に比べると家賃負担は比較的軽い。一方で食費にはお金がかかっており、エンゲル係数は46%と現代の23%に比べると高い。将軍の小遣いにも言及する。12代将軍の家慶が19億2000万円。大富豪の紀伊国屋門左衛門が築いた資産は1280億円と弾き出す。
|
| |
ウォールストリート・ジャーナル式図解表現のルール
ドナ・ウォン著、村井瑞枝・訳、かんき出版、p.160、¥1680
|
2011.6.27 |
|
 |
米ウォール・ストリート・ジャーナルのグラフィック・エディタを務める筆者が伝授するグラフや図、表の作り方。記者時代にさんざん図表を作った評者だが、的確な指摘が多く、なかなか役立つ。経験から何気なく実行していた作図法や作表法が、理論だって裏付けられた感じである。顧客へのプレゼンテーションや社内資料の達人になりたい方にお薦めする。
本書が推薦する図表作りの要諦は六つ。数字は分かりやすい表現(絶対値か変化率か)を使う、むやみにフォントの数を増やさない、色は使い過ぎず伝達のためにだけ使用する、ひと目で分かる工夫をする、データに応じて適切なグラフを選ぶ、図表はシンプルが一番。図や表には情報を詰め込みたくなるが(苦労してかき集めた場合は特に)、筆者は厳に戒める。
全編にわたって豊富な具体例を掲載しており、読者の理解を容易にしている。本書のレイアウトが妙にスカスカなのは、空白の重要さを筆者が訴えているのだろう。
|
| |
破壊する創造者~ウイルスがヒトを進化させた~
フランク・ライアン著、夏目大・訳、早川書房、p.448、¥2625
|
2011.6.26 |
|
 |
生物の進化をもたらした要因は、突然変異以外にも存在することを説いた書。副題にもあるようにウイルスが生物(動物・植物・昆虫・・・)の進化に重要な役割を果たしたというのが主張の一つだが、本書の幅はもっと広い。へ~っと驚くような話が満載である。特に進化生物学の最新動向は十分に刺激的で、知的好奇心を大いに満たされる。ただし、学術的に細かいレベルにまで言及しており、素人には付いていけない部分もあるのも事実。そうした部分は読み飛ばしても大きな障害とはならない。どんどん読み進めばよい。
最大の読みどころは、ウイルスと宿主(生物)との共生の部分である。攻撃的で宿主を滅ぼす一方で、生き残った宿主とは歩調をあわせながら、ともに進化する。HIVなどのウイルスが、死にいたる病気を引き起こすと同時に、進化に大きく関与する可能性を本書は示唆する。ウイルスそのもの、ウイルスの遺伝子、ウイルスの派生品が、ヒトゲノムの進化に大きな影響を与えていると主張する。
後半では進化の推進力についての最新の研究成果を紹介する。共生、突然変異、自然選択、エピジェネティクスを取り上げる。特に力を入れて解説しているのがエピジェネティクス。後天的な作用によって遺伝子が制御される仕組みで、DNA配列そのものが変わらなくても生物に変化をもたらす。環境からのシグナルによってエピジェネティクスな変異が誘発され、それが遺伝する。進化生物学で最もホットな話題の一つという。頭の片隅に置いても損はない専門用語といえそうだ。
|
| |
想像するちから~チンパンジーが教えてくれた人間の心~
松沢哲郎、岩波書店、p.240、¥1995
|
2011.6.21 |
|
 |
30年以上もチンパンジーを研究してきた、京都大学霊長類研究所所長の筆者が「人間とは何か」「心とは何か」を論じた書。チンパンジーを一人二人、彼・彼女と呼ぶ筆者の愛情が伝わる感動的な書き出しに始まり、興味深い話題が盛りだくさんである。チンパンジーと人間のゲノムの違いはたった1.2%。人間に最も近いチンパンジーを深く知ることで、教育や親子関係、社会の進化の起源を探るというのが本書の主旨だが、成功している。
筆者は「人間とは何か」に答えを用意している。共に育てる「共有」こそが人間の子育てであり、共有こそが人間の親子関係だと断言する。そして本書は、「高い高い」をしたり、わざわざ赤ちゃんを身体から引き離して顔と顔を見つめ合うチンパンジーの子育てを写真を交えて紹介する。ちょっと感動的である。
筆者は人間を人間たらしめる特性を、「親子が生まれながらにして離れていて、赤ちゃんが仰向けで安定していられる」ところに見る。この姿勢が、見つめ合う、微笑み合うという視覚的なコミュニケーションを支える。さらに、声でやり取りするという音声聴覚的なコミュニケーションを支え、発語につながったという。直立歩行で手が自由になり道具を使い始め、それが脳を増大させて、人間の知性が生まれたという“定説”を真っ向から否定する。刺激的な論理展開である。
|
| |
突然、僕は殺人犯にされた~ネット中傷被害を受けた10年間~
スマイリーキクチ、竹書房、p.284、¥1365
|
2011.6.17 |
|
 |
足立区で起こった殺人事件の犯人とインターネットで名指しされた、お笑い芸人・スマイリーキクチが誹謗中傷と戦った10年間を綴った書。現在ではネットにおける誹謗中傷や脅迫に対する摘発はかなり進んでおり、新聞でも取り上げられたりするが、著者への中傷が始まった1999年といえば警察や弁護士に専門家がわずかしか存在しなかった時代。本書の詳細な記録は実に貴重である。現在でも通じる部分もあり、読んで損はないだろう。
それにしても、司法のインターネット・リテラシーは10年前にこれほど低かったとは少々驚きである。本書が詳述する警察・弁護士・検察とのやり取りは全くトンチンカンで、18人の書類送検で終わるまで事件解決に10年を要したのも納得できる。ちなみに巻末には「ネット中傷被害に遭った場合の対処マニュアル」と題して、筆者の経験に基づいたアドバイスを掲載する。
|
| |
国家と政治~危機の時代の指導者像~
NHK出版新書、田勢康弘、p.240、¥819
|
2011.6.16 |
|
 |
日経新聞の元政治記者で現在は政治評論家の田勢康弘が、四国新聞に連載した政治コラムを加筆・再構成した書。連載は2007年から始まったようだが、本書では2009年の民主党への政権交替前後から東日本大震災後までを中心にカバーする。東日本大震災後の政治の惨状を見ていると、政権交替時のマスメディアや社会の高揚は何だったのかという思いにさせられる。
本書は危機の時代に即応した政治の在り方や望まれる政治家像、日本外交の欠点、政治の迷走の一因となっている世論調査をはじめとした政治ジャーナリズムの問題などを論じる。多くの政治家と政局を見続けてきたベテラン・ジャーナリストの筆らしく、ストーリーには説得力がある。言葉は慎重に選んでいるものの語り口は実に厳しい。
本書を読んで感じるのは、日本の政治と政治家はずっと権力争奪ゲームに明け暮れ、迷走を続けているということ。本書は、カバーしている時期が政権交替後なので民主党の鳩山由紀夫、小沢一郎、菅直人に焦点を当て批判しているが、自民党も五十歩百歩。筆者もこうした状況に危機感を募らせ警鐘を鳴らす。もっとも政治に対するメディアの論調も十年一日の状態に感じる。いつも同じように嘆くだけで、さほど変化を感じられない。虚しさを感じるのは評者だけではあるまい。田勢ほどのベテラン・ジャーナリストでも、政権交替時に民主党の問題点に厳しく切り込めなかったのは不思議である。
|
| |
Idea Man: A Memoir by the Cofounder of Microsoft
Paul Allen、Portfolio Hardcover、p.368、$27.95
|
2011.6.13 |
|
 |
米Microsoft共同創始者であるPaul Allneの自伝。Bill Gatesとの出会いと決別、Microsoftを30歳で退社した後の人生を綴っている。300ページを超える本だが、英語は平易で読みやすい。前半はMicrosoftとGatesに絡む数々の裏話が披露されており、評者のようなIT業界関係者には興味深い。特にGatesに対する人物評には、シアトルの私立学校時代からの親友らしい指摘が随所にみられる。この部分を読むだけでも価値がある。Microsoftを離れた後の話が続く後半部は、米国の大富豪の生活を垣間見ることができる面白さはあるが、多くの方にとっては退屈かもしれない。
読み応えがあるのは、Microsoft設立前後の話とMicrosoftを離れるときにGatesに送った決別の手紙。前者では、マイクロプロセサやパソコンの登場に伴う当時の熱気が伝わってくる。Gatesとピザとかじりながら、「ビジネスがうまくいけば、プログラマを35人は雇える」と語り合った話など、貴重なエピソードが盛りだくさんである。一方後者からは、MicrosoftとGatesに対するAllenの思いがひしひしと伝わってくる。現在のMicrosoftに対する視線は厳しい。図体が大きい普通の会社になっており、大企業病にかかり、官僚主義がはびこっていると断じる。4分の1は不要といった幹部の発言も紹介する。
ちなみにタイトルである「Idea Man」はAllenを指す。本書の描くGatesは、優秀なプログラマという側面はあるものの、高校時代からFortune500企業に興味をもつなど経営に関心をもつ徹底的な現実主義者である。技術の将来性を見通す能力はさほど高くない。Allenがコンピュータ端末で新聞を読む時代、全ての人がネットワークでつながる時代、すべての机と家庭にコンピュータが置かれる時代を夢想したのに対し、Gatesはコスト面から即座に否定する場面が本書では描かれている。Allenの母親はGatesを「スリルを楽しむアドレナリン・ジャンキーで、崖っぷちギリギリを歩くEdge Walker」と評したという。お金に対する姿勢も、根っからの技術者であるAllenとは異なり厳しい。報酬をめぐっては常にAllenが譲歩したことを本書は明らかにする。
Microsoft退社後の人生はすさまじい。バスケットやアメリカンフットボースのプロチームのオーナーを務めたり、SF博物館の設立、民間宇宙飛行機スペースシップワン(SpaceShipOne)への出資、地球外生命の発見を目的とした非営利組織SETI協会への寄付など、休む間のなく人生を楽しんでいる。巨万の富をもっているだけに投資意欲は旺盛だが、アップダウンも激しい。AOLへの投資で大もうけしたかと思えば、CATV会社チャーター・コミュニケーションズで失敗といった具合だ。しかし、こんな話が150ページほども続くと、さすがに飽きてしまう。
|
| |
Inside Apple~From Steve Jobs down to the janitor: How America's most successful - and most secretive - big company really works~[Kindle Edition]
Adam Lashinsky、Fortune、505Kバイト、$2.99
|
2011.6.5 |
|
 |
購入したKindle端末を使って、初めて読んだ電子書籍。Amazonの販売では「電子書籍>紙の書籍」になった今としては、遅ればせながらのKindle体験である。パソコン、iPhone、Kindleと端末を渡り歩きながら読み終えた。意外にスムーズに読めたのは驚きだった。食わず嫌いだったと少々反省した。時間がちょっと空いたときに、iPhoneで読み進むことができるのは評者のような本好きには嬉しい。ちなみに本書はKindle版だけで、紙のバージョンは存在しない。ページ数ではなく、505Kバイトとメモリ容量で分量を表すのは電子書籍らしい。
本書は雑誌Fortuneの記事を電子書籍化した、コンパクトにまとまったApple論である。大企業となったAppleがベンチャーのような急成長を続けられるのは何故か、次から次へとヒット商品を生み出す秘訣はどこにあるのか、Appleの意思決定はどのようになされるのか、ポストJobsのAppleはどうなるのか、といった疑問に雑誌的な視点とエピソードを交え答えている。当然のことだが、Jobsに関する記述は多い。ただし、本人へのインタビューは掲載されていない。
分量が少なく物足りなさも感じるが、雑誌記事がベースということを考えると致し方ない面がある。退職したエグゼクティブのコメントを多く載せており、Appleの内実を垣間みることができるのが本書の楽しみの一つである。トップ100ミーティングという幹部を養成する仕組みの存在は興味深い。Appleという企業に興味ある方に向くし、英語が平易なのでKindle初心者にもお薦めである。
|
| |
津波災害~減災社会を築く~
岩波新書、河田惠昭、p.224、\756
|
2011.6.2 |
|
 |
東日本大震災前の2010年12月に発行された書。2010年2月27日に起こったチリ沖地震津波がキッカケになって執筆したという。このときに日本では168万人を対象に避難指示・避難勧告が出されたが、実際に避難した人はたった3.8%。津波防災や減災など災害研究の第一人者である筆者は、こうした状況に危機感を覚え本書を執筆したという。
本書では、津波研究の現状、津波のメカニズム、津波への対策などに言及する。日本だけではなく海外の事例も取り上げる。津波対策は説得力があり、筆者が勧める対策を打っていれば、東日本大震災の被害を少しは小さくできただろうとつい考えてしまう。岩手県田老町、釜石市、大船渡市など、今回被災した地域も例に挙げているだけに、この思いを強くする。
筆者が声を大にして主張するには「避難すれば助かる」というもの。そのために津波に関する知識の絶対量を増やすことが不可欠。こうした思いで、津波に関する誤解、本当の恐ろしさ、忘れられた教訓、メカニズム、津波情報の活用法、津波対策などに言及する。ハード的な対策だけ被害を抑えられるわけではなく、ソフト対策を加えて減災を実現すべきと主張。東日本大震災の知見を踏まえると正鵠を射ている。津波に関する情報を本書は過不足なく提供しており、筆者の目的は達成されている。いまの時期、お薦めの書である。
|
| |
|
|

|
2011年5月 |
マーケティングを学ぶ
石井淳蔵、ちくま新書、p.318、\945
|
2011.5.30 |
|
 |
実に分かりやすく「マーケティングとは何か」を説いた入門書。供給過剰な市場環境のなかで品質は過剰になる。しかも企業間の技術力の差は小さい。必然的に企業の収益力は低下する。こうした状況で重要性を増すのが、「売れるものを作る」マーケティングというのが筆者の主張だ。マーケティングに長けた企業の取り組みを具体的に解説しており、論理展開は説得力がある。いまだに、マーケティング=販促といった考えが残るなか、マーケティングとは何かを再確認するうえで好適の書である。
筆者が重視するのが「マーケティング・マネジメント」。企業が消費者に向けて行う活動であるマーケティングを統一的に管理(マネージ)する経営手法を指す。ここで重要になるのが、自分の意志を市場に反映できるようにデザインすること。本書は「市場のデザイン」を四つの視点から論じている。生活者・顧客志向の戦略づくり、戦略に合わせた組織づくり、市場接点のマネジメント、組織の情報リテラシの確立である。
事例をつまみ読みするだけでも本書は十分楽しめる。例えば企業では、女性視点から事業を拡大したアート引越センター、小さな池の大きい魚をめざしレッツノートを開発したパナソニック、緑茶市場を席巻する伊藤園など。商品ではキットカットやファブリーズ、ドラフトワンなどを取り上げている。身近な話が多いので、ふむふむと読み進むことができる。
|
| |
完全なる証明~100万ドルを拒否した天才数学者~
マーシャ・ガッセン著、青木薫・訳、文芸春秋、p.322、¥1750
|
2011.5.27 |
|
 |
数学における七大難問の一つだった「ポアンカレ予想」を2002年に証明した数学者グリゴーリー・ペレルマンを扱ったノンフィクション。キレのよい、第一級の評伝である。数学的な話がほんの少し出てくるが、読み飛ばしても問題ない。翻訳はよく読みやすい。ちょっとした休暇に読むのに向く、肩の凝らない良書である。
ペレルマンは、数学のノーベル賞といわれるフィールズ賞を拒否しただけではなく、「ポアンカレ予想」の証明にかかっていた懸賞金100万ドルの受け取りまで拒んだ。一時マスコミを賑わせたのは今でも記憶している。その後は数学界だけではなく、世間からも距離を置いてロシアで過ごしている。本書は「ポアンカレ予想」証明前後のペレルマンの行動や心の動きを明らかにする。権威が通用しないペレルマンへの対応に右往左往する数学界のドタバタぶりも興味深い。
天才数学者を生んだ旧ソ連の教育システムについて、詳細に言及しているところも本書の特徴である。著者は、ペレルマンと同時代に旧ソ連で数学のエリート教育を受けているだけに、記述に深みがある。このほか、旧ソ連におけるユダヤ人差別の実態、数学界における巧妙争いや裏の部分、怪しげな中国人数学者の動きなど、読みどころの多いノンフィクションといえる。
|
| |
ビジョナリー・カンパニー3~衰退の五段階~
ジェームズ・C・コリンズ著、山岡洋・訳、日経BP社、p.316、¥2310
|
推薦! 2011.5.24 |
|
 |
ベストセラー「ビジョナリー・カンパニー」の第3弾。興隆をきわめ、偉大とされた企業が衰退する過程を明らかにする。これまでの2冊と同様、周到な調査とあざやかな切り口で多くの企業を俎上に上げ分析する。衰退の歩みを逆転させるための指針も示している。明確な論理展開はさすがだし、警句にあふれている。多くの方に読んでほしい、教えられるところの多い良書である。惜しむらくは、日本企業への言及がほとんどないところである。
企業は五つの段階を経て衰退する。第一段階は「成功から生まれる傲慢」、第二段階は「規律なき拡大路線」、第三段階は「リスクと問題の否認」、第四段階は「一発逆転策の追及」、第五段階は「屈服と凡庸な企業への転落か消滅」。本書が取り上げるのは、「ビジョナリー・カンパニー1と2」で言及した60社のうち衰退へと向かったHP、メルク、モトローラ、ラバーメイド、スコット・ペーパー、ゼニスなどの11社。アナログ携帯電話の雄だったモトローラのデジタル携帯電話での衰退、DSPで復活したTI、IBMを復活させたガースナーとHPを衰退させたフィオリーナの対比など、評者がリアルタイムでウォッチしていた企業の話が数多く盛り込まれており、つい引き込まれる。
ちなみに筆者はIBMやディズニーなどを例に挙げ、第五段階から回復することはできないが、第四段階の深みに落ち込んでも復活できると論じる。また100年という期間で見た場合、すべての企業が必ず消滅するという証拠は存在しないと断じている。全体では300ページを超えるが、後ろの100ページは付録や注釈、参考文献が占める。本体は200ページほど。翻訳もこなれているのでサクサク読める。少し時間を割けば、土日で読み終えることができるだろう。
|
| |
組織の思考が止まるとき~「法令遵守」から「ルールの創造」へ~
郷原信郎、毎日新聞社、p.288、¥1575
|
2011.5.22 |
|
 |
特捜OBで現在は名城大学コンプライアンス研究センター長を務める著者が、企業コンプライアンスの在るべき姿を論じた書。。郵便不正事件における証拠改ざんをはじめとする検察の不祥事、社会保険庁の年金不正処理事件、テレビにおけるねつ造事件、原発における不正隠蔽など様々な事例を挙げ、組織や企業はどのように対処すべきだったかを説く。理科系出身の法律家という経歴のためなのか文章が硬く読みづらいが、主張はきわめて明確。数々の不祥事を振り返り、企業経営や組織マネジメントに生かせる内容である。
元特捜検事だっただけに、特に検察庁批判は鋭い。八百長事件に揺れる大相撲の世界になぞらえ、内輪の論理に終始し、外部の動きや空気が読めない検察の現状を舌鋒鋭く批判する。このあたりは読み応え十分である。
著者はコンプライアンスを、「単純に法令を順守することではなく、社会からの要請に適応すること」と定義する。形式的な法令順守が日本社会に歪みと弊害をもたらしていると断じる。隠すことよりも、不正の存在を言い出せる仕組み(ルール)を構築することが大切というのが著者の主張である。そもそも守れない実態と乖離した規則や規定を改め、問題の本質を理解した新たなルールを創造することを勧める。このあたりは組織マネジメントに活用可能だろう。
|
| |
後藤新平~外交とヴィジョン~
北岡伸一、中公新書、p.252、¥798
|
2011.5.17 |
|
 |
関東大震災後の東京復興を東京市長としてリードし、このところ取り上げられることの多い後藤新平の評伝。ただし東京復興物語を期待して読むと失望するかもしれない。本書は「唯一の国民外交家」と称された外交指導者の側面に焦点を当て、むしろ政治家としては落第点を与えているからだ。本書の特徴は、台湾総督府の民政長官や初代満鉄総裁として壮大なビジョンは描けるが、言動は矛盾と飛躍に満ち、しかも演説べたという後藤の複雑な人間像に迫っているところ。東京復興について知りたい向きには別の書籍を読まれることをお勧めする。
後藤が成果を挙げるのは、課題の存在が誰の目にも明らかなときというのが著者の見立て。通常の組織を率いたときには、平凡な結果に終わることが少なくなかったという。では後藤はどのような哲学で課題を解決していったのか。その要諦は、「統治は生物学の原理、すなわち慣習の重視によって行われなければならない」というもの。台湾統治が成功した最大の秘訣は「生物学の原則」と筆者は見る。
満州経営の基本に置いた「文装的武備」の思想も興味深い。鉄道を中心として合理的経営を進め、農業や牧畜を振興し大量の移民を実現する方が、大兵力を駐屯させるよりも、軍事的な効果が見込めるという思想。軍事輸送に転用可能な鉄道や、遊撃軍となりうる移民は潜在的な軍備となるからだ。筆者は、持ち前の豊かな想像力と台湾での経験に加え、満州での大規模な計画によって、たぐい稀な都市建設者としての後藤が生まれたと見る。
|
| |
In The Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes Our Lives
Steven Levy、p.432、$26
|
2011.5.13 |
|
 |
創設時から直近の話題まで、詳細にGoogleの急成長の足跡を追ったノンフィクション。この書評でも、「The Google Story」「The Google Story」「The Search」といったGoogle本を取り上げたが、ミクロの視点でGoogleに迫っており、内容の濃さでは本書が抜きん出ている。何より驚くのは、筆者の密着取材。ほとんどインサイダーといえるレベルである。2人の創業者(Larry Page、Sergey Brin)、Eric Schmidtはもちろん、数多くのキーパーソンが登場し、節目におけるGoogle社内の状況を活写する。
ちなみに筆者は元Newsweek、現Wired誌の記者。ビジネス的な視点やジャーナリスティックな視点を本書に期待すると失望するが、Googleの歴史を淡々と振り返ってみたい方にお薦めの1冊である。ただし400ページを超え、しかもフォントが小さいので、読み終えるまでには想像以上の時間がかかるのは要注意。
本書を読むと、「Googleが普通の大きな会社になりつつある」ことを痛感する。影響力が弱く周囲の警戒心も薄かった創世記の活気や自由奔放な行動が、図体が大きくなり、行く先々で軋轢を生むようになると、活気はどんどん薄れ、行動は制約されてくる。例えば中国進出での中国政府との交渉、プライバシー問題や書籍のスキャンにおける反発などだ。特に中国政府との駆け引きは時系列で詳細に紹介しており特筆ものである。このほか初代のAndroid Phone「Nexus One」における、「良い製品ならサポートがなくても売れる」というGoogleの考え方と、一般世間のギャップも興味深い。本書は、こうした問題の一つひとつについて、Google社内の動きを丹念に追っていて読み応え十分である。
|
| |
人は放射線になぜ弱いか~少しの放射線は心配無用~
近藤宗平、ブルーバックス、¥1029、p.282
|
2011.5.5 |
|
 |
タイトルと中身のギャップが気になるが、著者の主張は副題「少しの放射線は心配無用」である。国連科学委員会と国際放射線防護委員会がお墨付きをあたえた「放射線は微量でも毒」「放射線は微量でも厳密に管理する」という勧告に対して、動物を使った実験や被爆調査の結果をもとに徹底的に反論を加える。国際機関の勧告は20世紀最大の科学スキャンダルと筆者は言い切る。図表を駆使した主張は納得性が高い。1985年初版で本書は1998年の第3版。福島原発事故を受けて3月に増刷をかけたもの。デマに惑わされず、正しく放射線を怖がるには必読の書だろう。ただし文章としてはまとまりに欠け、表現も独特で少々読みづらい。編集者の手をもう少し加えるべきだろう。
本書は、原爆被爆で遺伝的な影響が出る、放射能汚染で幼児に白血病が増える、放射線は少量でも危険など、いくつもの通説を否定する。こうした通説に対して、少量の放射線を浴びても被爆による傷は身体から完全に排除されると、生命科学の研究から反論する。人体の神秘を見るようで興味深い。
|
| |
|
|

|
2011年4月 |
ユニクロ帝国の光と影
横田増生、文藝春秋、p.384、\1500
|
2011.4.26 |
|
 |
ユニクロの実像を描いたノンフィクション。柳井正社長へのインタビューや社員、OBだけではなく、生産を担う中国の工場、競合するスペインZARAなど、ユニクロ関係者を丹念に取材している。心に響くものは多くないが資料的価値は十分である。上出来のビジネス書といえる。ユニクロという企業や柳井正という経営者に興味のある方にお薦めの1冊である。
商品のコンセプトは分かりやすいが、ユニクロの経営には不透明な部分が数多く存在する。社長だった玉塚元一だけではなく執行役員はなぜ次々と辞めるのか、中国の協力工場をなぜ秘密にするのか、柳井はなぜ社長に返り咲いたのか、グローバルに見たときの実力はどのレベルか、将来は前途洋々なのか。さらに柳内正とはどういった人間なのか。こうした疑問に、本書は一つひとつ答えていく。
興味深いのは、鉄の統率といわれるユニクロの企業文化。カリスマ経営者にありがちな話だが、役員からアルバイトまで、柳井の経営哲学が浸透している様子を本書は活写する。筆者はユニクロの経営をかなり批判的に見て取材を展開したようだが、結果的に本書はユニクロ経営の優れた面を浮き彫りにしている。「成功の秘訣は、当たり前のことを徹底的に実践すること」。こんなことを教えてくれる1冊である。
|
| |
数学的思考の技術~不確実な世界を見通すヒント~
小島寛之、ベスト新書、p.256、\840
|
2011.4.18 |
|
 |
東大数学科出身の経済学者が書いた思考術。世の中の事象を抽象化してとらえる秘訣(思考法)を書いているのかと想像して購入したが、ちょっと違った。主に、経済学で数学はどのように活用されているかを数式を用いずに説いている。新書らしく「給料が上がらない理由」「デフレ不況への処方箋」「村上春樹の小説と数学的思考」といった身近な話題を取り上げ読者の関心を引こという努力は買える。もっとも、評者には得るものが少なかった1冊である。
|
| |
グローバルプレイヤーとしての日本
北岡伸一、NTT出版、p.338、\2415
|
2011.4.15 |
|
 |
国連の次席大使を務めた東大教授による政治・外交・安全保障論。日本がグローバルに果たすべき役割を明確に説く。他国、特に中国や韓国に対する歯に衣着せぬ評価が実に新鮮。職業外交官ではない良さが出ている。筆者の実体験に基づく国連を舞台にした各国の駆け引きを知ることができるのも本書の特徴だ。刺激的な外交論を展開する本書は、多くの方にお薦めできる1冊である。
日本を取り巻く状況は厳しい。経済成長は鈍化し、GDPは中国に抜かれた。人口減少は日本経済と社会をじわり蝕む。こうしたなか筆者は、経済だけではなく総合的な力を発揮し、米国やアジア以外にも目を向けたグローバルプレーヤーになることで、世界に影響力を行使できると論じる。能力は十分あるにもかかわらず、PKOやODAなどで世界に貢献しようとしない日本外交を「鎖国状態」と評し不快感を露にする。
本書は、2005年に刊行が始まったNTT出版「日本の<現代>シリーズ」の第1巻。評者も期待して待っていたのだが、著者が国連次席大使に就いたなどの影響で大幅に出版が遅れた。本書は国連での経験などが盛り込まれており、待っただけの価値があったと言えそうだ。
|
| |
パーソナルプロジェクトマネジメント
冨永章、パーソナルPM研究会、日経BP社、p.208、¥1785
|
2011.4.5 |
|
 |
初めに断っておく。筆者の冨永章氏は評者の取材先である。日本IBMの専務、日本のプロジェクトマネジメント学会の重鎮として、日経コンピュータ編集長時代にお世話になった。そもそも本書は、編集者から「現代の奇書」という推薦文とともに献本してもらった。したがって、この書評にはバイアスがかかっているかもしれない。そう思って読んでいただきたい。
本書は、システム開発やエンジニアリングといった企業活動の世界で成果を挙げているプロジェクトマネジメント(PM)の手法を、個人の生活(オンとオフ)に適用するための入門書である。ダイエットや禁煙、受験と言った身近かな事例にPMを適用した事例を紹介する。著者自らの経験談も紹介しており興味深い。
確かに実生活にPMを適用することは成功の近道だろう。しかし、PMの方法論に沿うように自分を律することが凡人に難しいのも事実だ。結局は、成功するかどうかは個人の心根の強さということになる。やはり成功に至る道は険しい。
|
| |
凋落~木村剛と大島健伸~
高橋篤史、東洋経済新報社、p.286、¥1890
|
2011.4.9 |
|
 |
破綻した日本振興銀行の木村剛とSFCG(旧商工ファンド)の大島健伸を扱ったノンフィクション。かなり対照的な2人の人生とともに、振興銀とSFCGの設立から崩壊までを追っている。直前に読んだ「世紀の空売り」が妙にカラっとした明るいタッチで金融事件を扱っているのに対し、本書はジメジメとした“陰”の雰囲気が漂う。いかにも日本の金融事件といった感がする。
大島のバックグラウンドを考えると、蓄財に励んだ点やSFCG破綻時の資産隠しといった行動は納得できるところがある。不思議なのは木村の歩んだ道だ。竹中平蔵のブレーンや金融庁の顧問を務め一世を風靡した木村の姿と、経営破綻し日本初のペイオフが発動された日本振興銀行末期のドタバタ劇は、あまりにギャップが大きすぎる。蓄財でも保身でも、名誉欲でもないだろう。挫折らしい挫折もないエリートが、なぜ破滅の道を辿ったのか。いったい何なんだろう。本書がこの疑問に答えているとは言いがたい。いまいち読後感が悪い。
|
| |
世紀の空売り~世界経済の破綻に懸けた男たち~
マイケル・ルイス、東江一紀・訳、文藝春秋、p.304、p.1890
|
2011.4.5 |
|
 |
「ライヤーズ・ポーカー」「マネー・ボール」などの著者があるノンフィクション作家のマイケル・ルイスが、リーマンショックを生んだ米国金融業界の裏側を追った書。米ソロモンブラザーズ出身で金融ノンフィクション「ライヤーズ・ポーカー」でデビューした著者だけに、手慣れた感じでウォルストリートの人間模様を克明に描いている。それにしても、マイケル・ルイスの著書は当たり外れが少なく面白い。
本書が描くのは、サブプライムローンの証券化、格付け、保険といった仕組みで信用を自己増殖していた米国の金融システムであり、そのシステムが崩壊することに賭けて大もうけした相場師たちの動きである。バブルに加担した金融業界と米国政府の無知ぶりも凄まじい。
それにしても、人間とは愚かで、バブルとは不思議なものだ。客観的に判断すれば破綻必至にもかかわらず、いったん動き出した暴走は誰も止められない。数字や格付けの“まやかし”に気づかず、あるいは気づかない振りをしてバブルは拡大する。バブルは結局破裂するが、さんざん投資家を食い物した投資銀行は「Too Big To Fail」で生き残る。バブルに煽った張本人たちは表舞台からは姿を消すものの、しこたま儲け、すでに大金を手にしている。
エンターテイメント性が高く楽しく読める書なので、連休や新幹線のなかの暇つぶしに最適である。
|
| |
|
|

|
2011年3月 |
認知症と長寿社会~笑顔のままで~
信濃毎日新聞取材班、講談社現代新書、p.272、¥798
|
2011.3.31 |
|
 |
読売新聞の名物記者だった故・黒田清の言葉「報道とは伝えることやない、訴えることだ」が頭をよぎる書である。本書は医療関連のルポルタージュで定評のある信濃毎日新聞が、長寿社会の実情を足を使って取材したもの。2010年1月3日から6月29日にかけての連載が基になっている。
先日推薦マークをつけた『「社会的入院」の研究』が統計データや研究資料を駆使してロジカルに長寿社会の問題点を指摘していたのに対し、本書は感情に強く訴えるところに特徴がある。日本の医療制度が生んだ社会的入院だが、家族の苦しい事情を聞くとむげに断れない病院関係者のコメントなどを読むと、理論と現実のギャップを感じさせられる。
本書が扱うのは、介護する家族、認知症の老人を受け入れる介護施設や社会、認知治療の受け皿となっている精神科の病棟、認知症治療の研究と臨床の最前線、高齢化した地域など。現場に足を運び、当事者への取材を重ねながら認知症と長寿社会の抱える課題と解決策を探る。現場を丹念に取材した力強さがある良書である。
|
| |
トレードオフ~上質をとるか、手軽をとるか~
ケビン・メイニー著、有賀裕子・訳、プレジデント社、p.275、¥1800
|
2011.3.28 |
|
 |
製品やサービスを成功を導く秘訣を、多くの事例を示しながら論じた書。筆者はUSA Todayのテクノロジー欄を20年担当したジャーナリスト。エレクトロニクスやIT関連企業の取材から得た結論は、製品やサービスが成功する秘訣は「上質さ」と「手軽さ」のいずれかを選択すること。どっちつかずや、二兎を追う姿勢はいけない。画期的な内容の書ではないが、米General Magicや米AppleのNewtonといった昔懐かしい事例が多く登場し楽しめる。
筆者の言う上質さは、最高のユーザー・エクスペリエンス(経験)とオーラ、個性によってもたらされる。NFLやライブ演奏、ハーバード大学、Jobsが戻ったあとのAppleの製品群などは上質の部類に属する。一方の手軽さは、入手しやすさと安さがポイントとなる。手軽さの代表格として、筆者はiTunesやサウスウエスト航空、ウォルマートを挙げる。一方で上質さと手軽さの両立をねらうことは、不毛地帯に足を踏み入れることを意味する。経営戦略として選択すべきではないと断じる。二兎を追う戦略で危機に瀕した事例として取り上げているのが、筆者の古巣・新聞業界、低価格帯の製品で市場拡大を図ったコーチやティファニーである。
本書で気になるのは装丁。カバーや帯には『ビジョナリー・カンパニー』の著者ジム・コリンズの名前がデカデカと踊る。まるでコリンズが著者のようだが、実は序文を書いているだけ。これは少々酷い。どうしてこんなことになっているのか、内容が悪くないだけに残念だ。
|
| |
フェイスブック~若き天才の野望(5億人をつなぐソーシャルネットワークはこう生まれた)~
デビッド・カークパトリック著、滑川海彦・訳、高橋信夫・訳、日経BP社、p.544、¥1890
|
2011.3.24 |
|
 |
日本でもジワリと存在感を見せ始めたFacebook。本書は、そのFacebookを立ち上げたマーク・ザッカーバーグの評伝である。現在進行形で拡大中のFacebookの生い立ちやこれまでの成長過程を知る上でも役立つし、ベンチャーキャピタルの生態、米Googleや米Microsoft、米Yahooとの駆け引きなども興味深い。ザッカーバーグはマスコミのインタビューを受けることの少ないだけに、その実像を垣間みることができる貴重な1冊となっている。500ページと少々大部だが、つい引き込まれる内容なのと翻訳がいいので一気に読める。Google、Twitter、Facebookなど、次から次へと成長企業を生み出す米国社会の仕組みに興味のある方にお薦めである。
|
| |
「つながり」を突き止めろ~入門!ネットワーク・サイエンス~
安田雪、光文社新書、p.254、\798
|
2011.3.10 |
|
 |
人と人との「つながり」を科学的に分析する学問「ネットワーク・サイエンス」を紹介した書。イラクのフセインを探し出した、写真に写った人物をもとに人間関係を追っていく探索手法など、本書で取り上げている事例はなかなか興味深い。ネットワーク分析の哲学を著者はこう説明する。人間の行為や嗜好、信条を決定するのは、「誰とともに過ごしたか」「誰に囲まれているか」「誰に影響を受けたか」「誰に影響を与えようとしているか」など、その人を取り囲むネットワークだと。ネットワーク・サイエンスを平易に説いた書である。
|
| |
「社会的入院」の研究~高齢者医療最大の病理にいかに対処すべきか~
印南一路、東洋経済新報社、p.404、¥3780
|
推薦! 2011.3.9 |
|
 |
日本の高齢者医療制度が生み出した「社会的入院」。その現状と問題点、対策を論じた書。ここで言う社会的入院とは、医療行為が不要な状態にもかかわらず家族や医療機関の意向で高齢者が入院状態を続けることを指す。本書は社会的入院を生み出すメカニズムを解き明かし、日本の医療制度の問題点を論じる。介護が必要な高齢者を抱える人間の胸に、ズシンと響く良書である。
筆者は、病院が病人を作る日本の医療制度を厳しく批判する。日本の病院の安静第一主義によって、心身の機能が低下する「廃用症候群」が生み出され、高齢者を寝たきり状態にしてしまう。治療のために入院した病院での社会的入院によって、人生の最後が台なしになってしまう。
日本の医療制度の病巣は低密度医療にあると筆者は指摘する。一般病床が過剰で、病床あたりの医師数や看護師数が少ない。医療の密度は稀薄にならざるを得ない。低密度の医療しか提供できないから、手のかからない患者を漫然と入院させた方が病院経営上プラスになる。低密度医療は一般病床で始まり、療養病床に引き継がれる。しかも要介護度に基づく支払い制度のせいど、介護施設に寝たきりと認知症の患者があふれることになる。
筆者は返す刀で、病院志向の根強い日本社会にも切り込む。患者にも家族にも、病院にいれば安心という病院信仰がある。これに介護力不足と介護忌避、介護保険制度の不十分さが加わり、不適切な社会的入院を生み出す。ちなみに社会的入院が解消すれば1兆5000億円の医療費が低減されると、筆者は試算している。
|
| |
日本の教育格差
橘木俊詔、岩波書店、p.256、\840
|
2011.3.4 |
|
 |
この書評でも扱った「日本の経済格差」「家計から見る日本経済」の著者が、教育を切り口に格差問題を論じた書。教育の格差の実態や要因、それがもたらす問題について丁寧に持論を展開する。中卒、高卒、短大卒、大卒といった卒業段階での差、名門校と非名門校の差、私立と公立の差、専攻学科による差が、人生にどういった結果をもたらすのかを詳細に論じる。
データを駆使して社会を論じる手口はこれまでと同じ。手慣れたテーマを、お得意の手法で料理しているので安心して読み進むことができる。ただし悪い本ではないのだが、内容は想定の範囲内におさまる。教育格差に対してボンヤリと抱いていたイメージを確認できるメリットはあるが、ハッとするような驚きや読むことの楽しさは期待しない方が良い。
著者の主張の一つは、所得格差が広がるなかで、教育の機会の不平等化が進んでいるというもの。質の高い教育を受けると就職に有利で、高所得の可能性が高まる。その結果、子どもの教育にお金をかけられ、子どもが受けられる教育レベルは高くなる。こうして格差社会が固定化が進行する。筆者は日本の教育行政の貧困さをやり玉に挙げているが、同意できるところが多い。
|
| |
もういちど読む山川日本史
五味文彦、鳥海靖、 山川出版社、p.254、¥1575
|
2011.3.2 |
|
 |
社会人向けに再編集した高校の教科書。ベースは「日本の歴史 改訂版」。一時ベストセラーになった書を、ようやく読むことができた。中身は教科書なので基本的には淡々と話は進み、さして面白みはない。興味深いのは、昔習った史実が、その後の研究で覆っているところ。本書では学会における新たな定説を注釈として挿入している。聖徳太子、和同開珎、吉田兼好、安藤広重などの話は、へえ~と感心しながら楽しく読み進める。
|
| |
|
|

|
2011年2月 |
競争の作法~いかに働き、投資するか~
齊藤誠、ちくま新書、\777、p.233
|
2011.2.25 |
|
 |
日本経済に関する多くの勘違いを指摘し、日本経済が再生し「日本人が本当の意味での豊かさ」を得るためのヒントを与えてくれる書。けんか腰の語り口はなかなか強烈である。ジャーナリズムや論壇で派手に立ち回りたわけたことを言っているエコノミストや経済評論家を、「ただのバカ」だと一刀両断で斬り捨てる。「2010年度エコノミストが選ぶ経済図書ベスト1」に選ばれたのも分かる。目から鱗の指摘が多いお薦めの1冊である。
2002年から2007年にかけて日本は「戦後最長の景気回復」を果たした。しかし給与水準は上がらず、多くの人は生活が向上した実感をもつことはなかった。実はこの時期に日本経済は脆弱性を抱え、リーマンショックが起こらなくても経済崩壊の危機に瀕していた。その理由はどこにあるのか、経済成長がなぜ幸福に結びつかないのか、といった疑問に本書は明快に答える。
いまの日本に必要なのは、適正な市場原理の活用だと筆者は論じる。日本社会は多数の安堵のために市場原理から逸脱した。そのために労働の現場や金融の現場、教育の現場で多くの人々の能力がどうしようもなく低下し、規律が目も当てられないほど劣化した。日本社会はいま、市場原理に基づく働き方と投資の見直しが求められていると筆者は説く。
ちなみに御用学者やお調子者の評論家だけではなく、「経済危機を煽りたい政治的な勢力の言いなりになっている」と、マスコミにも辛口である。定見もなく、現実を見ようとせず、数字を読み取り自分で考えることをしない輩として厳しく批判する。耳が痛い。
|
| |
電子本をバカにするなかれ~書物史の第三の革命~
津野海太郎、国書刊行会、p.290、¥1890
|
2011.2.24 |
|
 |
雑誌「本とコンピュータ」を手掛けていた編集者・津野梅太郎の電子書籍論。この分野の先駆者らしい見識の高さと紙の書籍への愛情が随所に出ている。特に最初の1/3は書き下ろしで、いい味が出ている。例えば「世界全体がデジタル化され、インターネットになったとしても、本は殺せない。出版業は何度でも殺せるだろうが…」と論じる。ふむふむ。そうかもそれない。残り2/3は「本とコンピュータ」を中心とした既存記事の再録。妙に肩に力が入った書き口でイマイチの感がある。
津野は本書で、電子書籍を5000年の書物史のなかで位置づける。現在の微分的な騒動はいずれ落ち着き、書籍は電子と紙の双方で生き続けると説く。紙の書籍は、「一つひとつの色、一つひとつの肌ざわり、香り、味がみんな意味をもつ」個別性や多様性を多く担保できるメディアだと位置づける。一方の電子書籍は、最初こそビックリするが、どれも同じ味しかしないから必ず飽きる。疲れた者は紙の書籍に向かうとする。本が二つのかたち、二つの仕組み、二つの方向に分かれて、それぞれの道をたどり始めると説く。もちろん電子書籍で満足する向きも多いので、紙の書籍の衰退は避けられないのだが…
|
| |
人口減少時代の大都市経済~価値転換への選択~
松谷明彦、東洋経済新報社、p.293、\1800
|
2011.2.22 |
|
 |
大蔵省出身の大学教授による経済論。人口の減少が日本経済にどのような影響を与えるかを統計データを駆使しながら、断定調で歯切れよく論じる。人口減少によって日本では大都市の方が地方よりも大きなダメージを受ける、人口が減少している状況下の増税は愚の骨頂と断じる。高齢化社会における年金の在り方などについて持論を展開する。人口減少という1点から切り込む視野の狭さと処方箋に驚きがない点が気になるものの、日本の人口動態を知り、その社会的影響を概観するうえで役立つ1冊である。
筆者は、日本の大都市が取り組むべき課題を四つ挙げる。一つは国際化。大都市経済の閉鎖性が製品の国際競争力の低下につながっている。国際分業せよと説く。第2はビジネスモデルの転換。大都市経済は、輸入技術と低賃金労働を基盤とした薄利多売のビジネスモデルをいまだに使い続けているが、もはや限界。専門性を高め、製品やサービスを高く売る工夫をしなければ生き残れないと論じる。第3は、増税一辺倒の財政政策からの転換。人口減少下では、支出を削減しない限り、際限のない増税が必要になる。第4は人生の再設計である。生涯収入が確実に減るなか、お金をかけない生き方が不可欠になると説く。
|
| |
What Technology Wants
Kevin Kelly、Viking Adult、p.416、$27.95
|
2011.2.18 |
|
 |
技術の切り口で生物・生命、社会、都市の進化を論じた技術哲学論。技術、生物、都市の進化を統一的にとらえ、すべてに共通する法則を探る。恐竜の話から映画「アバター」、爆弾犯ユナボナー、アーミッシュ、小説「1984」の世界までストーリー展開は縦横無尽。スコープは実に壮大で読み応え十分である。問題は少々難解なところ。語彙不足を痛感させられる。400ページを超える大部で持ち運びに不便なところも難点である。
Wired創刊に参加し、ニューヨーク・タイムズやウォールストリート・ジャーナルに寄稿する筆者の主張は、煎じ詰めると技術の進歩は必然的に起こるというもの。進化の方向性は決まっており、ブレークスルーはけっして突然変異ではない。ブレークスルーを生む環境は徐々に整い、最後の一押しのところまで熟す。だから、原子爆弾の理論が6カ所で同時に発見されたように、多くのブレークスルーは同時多発的に生じる。
壮大な技術論だが、技術に対する著者の見方はさして新しくない。曰く、技術は進歩すると見えなくなる、進歩の定石は組み合わせること、制約こそが技術を進歩させるドラーバ、効用が大きい技術ほど弊害も多い、技術は汎用で生まれ専用へと深化する、などである。
|
| |
合理的市場という神話 ~リスク、報酬、幻想をめぐるウォール街の歴史~
ジャスティン・フォックス著、遠藤真美・訳、東洋経済新報社、p.508、¥3360
|
2011.2.6 |
|
 |
ジャーナリストの手による経済学興亡の歴史。株式市場の効率性や合理性、株式市場の興隆と崩壊、経済理論の誕生と凋落を丹念に追っている。「科学を市場に応用すべきだ」という思想に始まり、「市場は情報を完璧かつ合理的に処理し、資本を効率的に配分する」「市場のリスクは計測可能で、完全に管理できる(リスクを完全になくせる)」といった理論がどのようにして生まれ、崩壊していったかを論じる。最近流行の実験経済学や行動経済学にも言及する。
本書は、経済学者や投資家ごとに章を分け、学説と時代背景を絡めながら紹介する。評者のような素人が市場経済をめぐる時代の流れをざっと知るには最適な書に仕上がっている。翻訳もこなれているので読みやすい。ただし、総勢20人を取り上げているので、個々の経済学者や投資家の記述には物足りなさを感じるところもある。
本書を読んで感じるのは、米国の経済学者の活躍ぶりとその影響力。日本における経済学者の影の薄さと比べ、大きな違いを感じる。株式市場の成立過程(先日取り上げた「そして窮屈な日本経済が始まった」に出ていた)、世界的および社会的な位置づけが異なるにしても、市場や政策に関する発言力における彼我の差はすさまじい。こんなところにも、日本経済が混迷する原因の一つがあるのだろう。
|
| |
|
|

|
2011年1月 |
しまった!「失敗の心理」を科学する
ジョゼフ・T・ハリナン著、栗原百代・訳)、講談社、p.300、\1575
|
2011.1.31 |
|
 |
心理学や行動経済学などに基づきながら、なぜ人間はミスを犯すのかを分析した書。事例が豊富なので読んでいて楽しいし、翻訳も悪くないのでスイスイ読める。暇つぶしに向いている。
本書は、人間の不完全さ・不可思議さを次から次へと取り上げる。レントゲン技師は画像に写った悪性腫瘍の90%を見落とす、有権者は政治家が有能かどうかを顔を見てから1秒以内に判断している、人は高校時代の成績を実際よりも良いと信じている、人は考えを変えたあとに自分は昔からずっと同じ考えだったと思い込む、などなど。人間とは自惚れの強い動物であることを改めて思い知らされる。
最後に、ミスを少なくする方法を説いている。例えば、行動した結果からフィードバックで微調整を繰り返す、自らの考えに対する反証を探し自信過剰を排除する、体験談を重視しない、睡眠は十分にとる、幸せであること、などである。
|
| |
そして窮屈な日本経済が始まった
鈴木隆、かんき出版、p.320、¥1890
|
2011.1.26 |
|
 |
日本に自由経済が定着しない理由と日本経済不振の原因を明治時代に求めた書。明治の元勲たちの活躍を追うと同時に、それが現在の日本経済にどのような影響を及ぼしているかを説いている。歴史書と経済書の特徴を併せ持つ不思議な魅力をもつ書である。日本経済の混迷を明治時代に引き戻す際に牽強付会的な部分もあるが、全体に著者の視野の広さを感じさせる。
明治の元勲たちの人間模様は、抜擢、左遷、下積み、裏切り、謀略、官民癒着、学閥・藩閥など実に人間臭い。彼らが政治家と資本家の癒着、政治と日本銀行の微妙な間合い、東大閥の跋扈など日本独特の状況を生み出し、それが日本経済不振につながっているというのが著者の見立てである。政治と大企業の癒着は明治時代以来続いている伝統であり、カネに関する限り政治家は無知で、ソロバン高い経営者に丸め込まれていると、筆者の舌鋒は鋭い。
本書が扱う元勲は西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允、伊藤博文、大隈重信、伊藤博文、井上馨、松方正義ら多士済々だが、中心となるのは大隈と松方だ。この2人の対立を中心に話は進む。大隈たちは英米型の経済を目指したが、遅咲きの松方が中心となったプロシア派が影響力を強め、大企業優先の経済システムに作りかえられてしまう。筆者は松方らが「日本経済の基本を歪めた」と説き、日本は明るい夢を失い、儒教やプロシア絶対主義の亡霊に取り憑かれたと主張する。そして、これらの亡霊を取り除き、窮屈な日本経済を自由で伸び伸びした体制に変えなければならないとする。
|
| |
ストーリーとしての競争戦略~優れた戦略の条件~
東洋経済新報社、楠木建、p.518、\2940
|
推薦! 2011.1.21 |
|
 |
本書の主題は「成功する経営戦略には、思わず人に伝えたくなるような生き生きとしたストーリーがある」「一見不合理な戦略が競争優位を生む」「個々には合理的な経営戦略が、合体すると合成の誤謬を生み失敗につながる」。500ページを超える紙幅を使い数々の事例を挙げながら、こうした持論を展開する。書き口が軽妙なので、あまり大部という感じがしない。読むのに時間がかかるが、お薦めの経営書である。
著者の主張のポイントは、シンセシス(総合)の重要性を説いているところ。経営戦略は個別戦略ではなく、全体として評価しなければならないとならないと主張する。本来なら動画であるはずの経営戦略が、無味乾燥な静止画の羅列になっているとうのが著者の見立てである。戦略をつくる仕事が「項目ごとのアクションリスト作り」にすり替わっていると、わけ知り顔のコンサルタントが作るバズワードだらけのPowerPointのスライドに踊らされる愚を鋭くつく。
取り上げている事例はなかなか魅力的。マブチモーター、ガリバーインターナショナル、アマゾン、サウスウエスト航空、スターバックスなどを、ストーリーという切り口でうまく料理している。刺激的な指摘にあふれた良書である。
|
| |
無縁社会~“無縁死”三万二千人の衝撃~
NHK「無縁社会プロジェクト」取材班、文藝春秋 、p.272、¥1400
|
2011.1.14 |
|
 |
身元が分からない死亡者は、身長体重、推定年齢、死亡時の状況などの情報とともに「行旅死亡人」として官報に記載される。その数は1年に1万人ほど。身元が分かっても親族から引き取りを拒否され、行政によって公費で火葬・埋葬される人数を合わせると3万2000人に達する。こうした無縁死を扱い話題を呼んだNHKスペシャル(2010年1月放送)にも基づいたノンフィクション。内容は重く読んでいて辛いが、今の世代が正面から向かい合うべき内容であり、多くの方に読んでほしい良書である。
急増する無縁死を生んだ社会的背景、無縁死を前提にしたビジネスや社会システムに迫るとともに、孤独死に至るまでの経緯や人間関係を詳細に追う。日本社会で進行する病を、時間をかけた丹念な取材で明らかにしている。無縁死までの人生をたどると、ほとんどが普通の生活を営んでいた人々だったことをNHKの取材班は明らかにする。
家族の絆の希薄化、生涯未婚の急増、社縁の切れ目が縁の切れ目など、無縁死につながる要因は多い。親族は存在しても「迷惑をかけたくない」といった心情から、自ら無縁を選択するケースも少なくない。ちょっとしたキッカケや行き違いが無縁死につながっていく。誰にでも起こりうる話であり、それだけに恐ろしい。
|
| |
GIGAZINE 未来への暴言
山崎恵人、朝日新聞出版、p.264、¥1575
|
2011.1.12 |
|
 |
ニュースサイト「GIGAZINE」編集長の山崎恵人が描くインターネットの未来予想図。ネットメディアの最先端を見ている著者ならではの見解が多く盛り込まれており、役に立つ。賛否が分かれそうな装丁で手に取るのを躊躇するかもしれないが、中身は真面目。インターネット・メディアの今後に興味のある方にお薦めの1冊である。
本書の話題は多岐にわたる。専門バカとオタクの違い(GIGAZINEは、興味を持つジャンルを広めようとするオタク・メディア)、YouTubeはこそ真の破壊的ビジネスモデル(著作権は崩壊する)、今後のインターネットを支えるのはパトロンモデル(無料なものに対価を払う)、インターネット時代の学校教育(コピペで済ませられる問題を出す方が悪い)、紙の出版物は必ず絶滅する、超少額決済システムを握ったところが最終的な勝者に、などなど。評者とは見解を異にする項目もあるが、現場経験に裏付けられており説得力がある。
|
| |
リスクに背を向ける日本人
山岸俊男、メアリー・C・ブリントン、講談社現代新書、p.272、¥798
|
2011.1.8 |
|
 |
『安心社会から信頼社会へ』『日本の「安心」はなぜ、消えたのか』などの著書で知られる社会心理学者の山岸俊男が、旧知のハーバード大学教授と行った対談をまとめた書。アメリカ社会よりも日本社会の方がリスクが高い、リスクを避ける傾向は日本人が先進国のなかでずば抜けて高い、など日本社会が抱える問題について議論を繰り広げている。全体に読み応えのある書に仕上がっている。
労働市場、女性雇用、出生率、教育、コミュニケーション能力など両者の議論は多岐にわたる。とりわけ労働市場についての指摘や、日米における信頼感の違いについての議論は示唆に富む。対談だけに冗長な部分も散見されるが、議論がす~っと腑に落ちるところがいい。
|
| |
権力の館を歩く
御厨貴、毎日新聞社、p.368、¥2625
|
2011.1.5 |
|
 |
歴代の首相や有力政治家の邸宅・別荘、政府や政党の建物を訪ね歩いた書。吉田茂の大磯・別荘、鳩山一郎の音羽御殿、佐藤栄作の鎌倉別邸、田中角栄の目黒御殿、小沢一郎の深沢邸、首相官邸、国会議事堂、最高裁判所、自民党本部などの建物を、数々のエピソードを盛り込みながら紹介する。佐藤栄作と田中角栄、福田赳夫など、政治家の建物に対する姿勢と政治活動との対比がなかなか興味深い。
新聞連載の単行本化とあって、一つひとつの建築物に関する書き込みが足りない。政党や政府機関の建築物の説明はそこそこ詳しいが、政治家の“館”についての記述は建物自体の魅力への言及が少なく、建築好きの評者には物足りなさが残る。セキュリティ上の問題があり内部の写真や配置図などは出せないのだろうが、建築物をメインに据えた書だけに残念である。
ちなみに筆者の御厨貴は政治家のオーラルヒストリーで知られる。この書評でも「渡邉恒雄回顧録」などを紹介した。その御厨が、建築への造詣が深いということを本書で初めて知った。
|
| |
|
|


|
横田英史(yokota@nikkeibp.co.jp)
|
1956年大阪生まれ。1980年京都大学工学部電気工学科卒。1982年京都大学工学研究科修了。
川崎重工業技術開発本部でのエンジニア経験を経て、1986年日経マグロウヒル(現日経BP社)に入社。
日経エレクトロニクス記者、同副編集長、BizIT(現IT Pro)編集長を経て、2001年11月日経コンピュータ編集長に就任。
2003年3月発行人を兼務。2004年11月、日経バイト発行人兼編集長。
記者時代の専門分野は、コンピュータ・アーキテクチャ、コンピュータ・ハードウエア、OS、ハードディスク装置、組み込み制御、知的財産権、環境問題など。
|
|
|
|