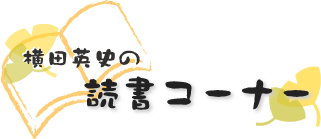| 今度Sun MicrosystemsのCEOに就任するJonathan
Schwartzが自身のブログで「Recommended Reading」と書いていた本。さっそく原書を購入。よくあることだが、読まないうちに翻訳が出てしまった。Schwartzはこう書いていた。「It's
a quick read, quite good.Once you've read that, this is interesting
reading, too」。確かに読みやすい上に、なかなか興味深い本である。本の帯にはティッピング・ポイントの著者の「これは世界観を180度ひっくり返すような本だ」というコメントはあるが、これはちょっと言いすぎ・・・。
本書は要するに、一般人の考えを集めた結果には集団の知恵が反映する。したがってその判断は、正しいことが多いというもの。Googleの検索技術が事例の一つである。ここで重要なのは多様性。多様性こそが正しい結果を生む源泉となっている。筆者は集団が賢明な判断を下す条件として、「多様性」「独立性」「分散性」を挙げる。インターネットの時代の空気にマッチした本といえる。
本書の背景にあるのは、ベスト・エフォートという考え方だろう。道を極めるのではなく、ほどほどで切り上げて、後は多くのユーザーの要望を吸い上げてニーズに応えていく手法。これこそが、最適な道にたどり着く早道で“今的”というわけだ。道を究めることに重点を置く日本的な手法とはかなり異なる(だからITの時代になって、米国のスピードに歯が立たなくなった)。
著者はこうも指摘する。「システムの成功は、どれが敗者かをはっきりさせて速やかに淘汰する能力にかかっている。大量の敗者を輩出できる能力の有無がシステムの成功の鍵を握る」と。まさに米国システムである。
本書が強調するもう一つの視点は、違うスキルを持った人が数人加わることで、集団のパフォーマンスは向上するというもの。組織に新しいメンバーを入れることは、その人に経験も能力も欠けていても、より優れた集団を生み出す力になる。古参のメンバー全員が知っていることと、新しいメンバーが知っているわずかなことが重複しないことが重要だというわけだ。例として取り上げるのがNASA。さまざまな職業を経由した人間の集まりだったアポロ計画のチームの方が、現在のNASAよりもうまくトラブルに対応できる理由を多様性に求める。巷間言われるように、会社が大きくなり著名大学の出身者が集まり始めると落ち目になるというのと、根は同じなのかもしれない。 |