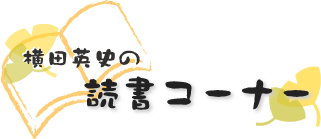|
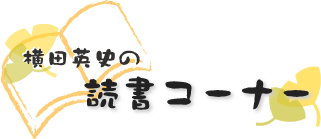 |
|
|
|

|
| 2005年12月
|
| 容疑者Xの献身
東野圭吾、文芸春秋、\1600、p.352 |
2005.12.30 |
|
 |
| 2005年に出たミステリー関連書のなかで際立って高い評価を得ている1冊ということもあり、冬休みに入って読み始めた。今年の『このミステリーがすごい!』でも1位に輝いている。それも納得の出来である。ただしその高評価に引きづられて大きな期待を抱いて読むと、ひょっとしたらガッカリするかもしれない。それは本書が悪いからではなく、書評での持ち上げ方が少々大げさという点に原因がある。
予断をはさむことなく読めば、実によくできたミステリーで十分に楽しめる。主人公は大学助教授の湯川。東野の小説では「探偵ガリレオ」や「予知夢」にも登場している。本書は湯川助教授シリーズの第3作となる。シリーズ最高の出来だろう。伏線の張り方は秀抜だし、最後の謎解きも意外性に富んでいる。ただし登場人物の設定に少し無理があるような気もするが・・・。 |
| |
| きずなをつなぐメディア〜ネット時代の社会関係資本〜
宮田加久子、NTT出版、\2800、p.221 |
2005.12.25 |
|
 |
| このところ沈黙を守っていた感があった社会心理学者の宮田・明治学院大学教授の近著。かなり前に「電子メディア社会:新しいコミュニケーション環境の社会心理」(1993年)を読んだが、けっこう鋭い指摘があったように記憶する。本書は主にパソコンによるインターネット・アクセス、パソコンと携帯電話による電子メールに焦点を当て、これらが人間関係の形成にどのような影響を与えるかを論じている。すごく目新しいい知見が語られているわけではないが、メディア論としてはよくまとまっている。調査もそこそこ行われていて、仮説をしっかり検証しているところにも特徴がある。
タイトルや帯に「社会関係資本」という用語が使われているが、それほど一般的な言葉なのだろうか。ちょっと疑問である。あまりキャッチな言葉になっていない気がする。ここでいう社会関係資本とは、個人に協調行動を起こさせる社会構造や制度を意味する。この社会会計資本には、大きく二つの型があるとする。一つは、ある属性(所得や職業、性別)をもつ人間が集まって構成されたネットワークが、インターネットをブリッジとしてつながっていく「橋渡し型」。もう一つがある属性(所得や職業、性別)をもつ人間が集まって構成されたネットワークである「結集型社会関係資本」である。このうち前者の重要性と「その社会関係資本の形成や活用に適しているインターネットの存在」を指摘するのが本書のねらいである。学者にありがちな、こねくり回した表現ではなく、あくまでプレーンな書き口には好感がもてる。 |
| |
| ソフトウエア企業の競争戦略
マイケル A,クスマノ、サイコム・インターナショナル監訳、ダイヤモンド社、\2400、p.445 |
2005.12.22 |
|
 |
| 「マイクロソフト・シークレット」のクスマノMIT教授の新作。ずっとツン読状態で気になっていた1冊である。日経バイトの休刊処理も終わり、心理的に余裕が出てきたこともあり挑戦。何せ450ページ近くもある本なので、読み始めるにもそれなりの決心がいる(持ち運びも重いし・・・)。
米国の学者の本らしく、くどいほど事例(ケーススタディ)が出てくる。クスマノ教授はかつて「日本のソフトウェア戦略」という本を出したこともあり、日本のソフトウェア産業も事例に出しながらバランスよく論を進める。このあたりの視野の広さが本書の特徴だろう。組み込みソフトウェアに対する指摘も含め、日本のソフトウェア産業の問題点も正鵠を射ている。そして、よくあるプログラマの偉人伝や逸話集ではなく、ソフトウェアをビジネスの視点でとらえているところが高く評価できる。このほかベンチャーの経営に関して、自らも経営に関与した経験に基づき多くの提案を行っているところが、類書と大きく異なっている。 |
| |
| 日本の<現代>9:グローバルスタンダードと国家戦略
坂村健、NTT出版、\2300、p.272 |
2005.12.10 |
|
 |
| タイトルにある「グローバルスタンダードと国家戦略」を論じるには打ってつけの著者だろう。TRONからRFIDへと重心の置き所は昔とは変わっている部分はあるが、著者が求心力をもってスタンダード作りを牽引したのは間違いないところである。かつてのBTRONをめぐる日米の争いは、いまだに多くのところにトラウマとなって残っている(少なくとも記者の頭には強烈に刻まれている)。ユニークなのは、本書のところどころに顔を見せるマスコミ批判。いずれも的を射ている指摘だが、TRON騒動の影響が出ているようにも感じられる。
著者選定は問題ないが、中身はかなりRFID寄り。現在進行中の話なので今感は確かにあるが、「RFIDとは」「RFIDの細部」が前面に出てしまい、本筋の「グローバルスタンダードと国家戦略」が脇役になった感があるのは残念である。現在進行中だけに、あまり生々しいことを書けないのも減点要素である。妙に評論家的なのも少々気になる。本書の価値を高めているのは、最終章「新時代のグローバルスタンダード」だ。インターネット時代を的確にとらえた視点はなかなかクールである。ただし書きなれていない部分が多いのか、文章にこなれていない部分が残っている。一部、校正が甘くなっているところも少々気になる。 |
| |
| スティーブ・ジョブズ〜偶像復活〜
ジェフリー・S・ヤング、ウイリアム・L・サイモン、井口耕二訳、東洋経済新報社、\2200、p.527 |
推薦!
2005.12.3 |
|
 |
| 原書を購入したのに翻訳が出てしまった本。なぜか東洋経済が出版元である。すでに色々なところで書評に取り上げられているが、とにかく抜群に面白い。そして、昔のAppleを知る人にとっては実に楽しい本だろう。NeXT
ComputerやGeneral Magicなどなど、半ば忘れかけてる懐かしい名前が続々と出てくる。
本書が扱うのは、Apple Computer立ち上げからApple追放、ピクサーの大成功、最後にiPodにおける大成功までだが、中心はAppleを追われてから大成功をおさめるまである。ちなみに、失格CEOだと思っていたギル・アメリオが大きな功績をAppleに残していたというのは、本書で始めて知った事実である。
本書に登場するジョブズは、実に嫌な奴に描かれている。ひところ話題になったように、Apple社から出版差し止めを求められたのも納得である。ジョブズに対する筆者の思いは実に微妙だ。感動的なプロローグを読むと、筆者は本質的には熱狂的なファンのようにも感じられる。しかし本書のほとんどは、嫌な奴としてジョブズを描いている。「自分勝手で短期、粗暴にして狭量」と、愛憎半ばしているのか表現はかなりきつい。ちくりちくりとジョブズを批判する(ジョブズがやたらと泣くのも面白い)が、それでも成し遂げたことの偉大さには頭を下げざるを得ない。まさに大いなる矛盾の人である。その矛盾の人のジョブズを余すところなく描いたのが本書である。 |
| |
|
|

|
| 2005年11月
|
| <育てる経営>の戦略:ポスト成果主義への道
高橋伸夫、講談社、\1500、p.210 |
2005.11.30
|
|
 |
| 話題を呼んだ「虚妄の成果主義」(2004年)の続編。成果主義が企業から活力と勤労意欲、忠誠心を奪ったと、問題点を徹底的に叩いている。前著とのダブリ感が気になるが、時間がたち熟成されただけに叩き方は迫力満点である。
前半と後半で大きく内容が異なっている。前半は具体例を挙げて、「小器用」「小ざかしい」「お調子者」といった種族が跋扈する成果主義の病根を抉り出す。「成果主義はみな失敗する」「客観評価の虚妄」「貧困な発想」「人的資源は買えない」といったフレーズが次から次へと飛び出す。
後半は学術的な内容になる。学者の著作らしく、訓詁学的な話が展開する。若干、退屈である。中村修二氏の「青色発光ダイオード裁判」の話が登場するが、正直言って「なぜ?」といった感じが強い。ちなみに著者は、中村氏への特許使用料が減額されたのは妥当との立場をとっている。 |
| |
| 宗教常識の嘘
島田裕巳、朝日新聞社、\1200、p.198 |
2005.11.27
|
|
 |
| 帯には「目からウロコ!世の中の宗教常識はこんなに間違っていた」とある。30件の宗教常識を挙げ、それぞれに反論を加える。「仏教は世界の三大宗教にあらず」「キリスト教徒もアッラーを信仰している」「人間は苦しいときに神を頼まない」などが並ぶ。最初は興味深く読んだが、だんだんと退屈してくる。ただし、最後の「パウロはイエスのことは知らなかった」はなかなか興味深い。 |
| |
| The Google Story:Inside
the Hottest Business,Media and Technology Success
of Our Time
David Vise, Mark Malseed、Delacorte Press、$26、p.326 |
推薦!2005.11.25
|
|
 |
| このところ気になるIT企業といえば、真っ先に挙げられるのが米Google。インターネットの記事やブログでも、Googleというとつい読んでしまう。Google本は「The
Search」に次いで2冊目だが、こちらの方が読ませる内容になっている。「The Search」はビジネス書の色合いがあるので真面目に読む必要があるが、こっちは肩の凝らない読み物に仕上がっている。明るい面ばかりが取り上げられているところが少々気になるが、現時点では致し方ない面もある。
創設者のSergey BrinとLarry Page、従業員、出資者など、米Google社をめぐる人物のエピソードが満載の書である。中国Google責任者(MSからの転職者)が語る「youth+freedom+transparency+new
model+the general public's benefit+belief in trust=The Miracle
of Google」と語る同社の企業文化や従業員の生態をあますところなく伝えている。SergeyとPageの米スタンフォード大学の恩師の2人に対する評価もなかなか面白い。「求む!イノベーティブなシェフ」といった求人広告を従業員が45人のときに出した企業文化など実に興味深い(ちなみにイノベーティブなシェフは、後にExecutive
Chefになった)。
「The Search」と併せて読むことをお薦めする。英語は平易なので、正月休みに読むのも悪くない。 |
| |
| 坂の上の雲(7)
司馬遼太郎、文芸春秋、\590、p.367 |
2005.11.22
|
|
 |
| ついにラス前になった「坂の上の雲」。風呂につかりながら読む本だったので、夏のシャワー期間中は完全に中断。結局、8月以来の書評となった。あまりに長い中断で、第7巻の最初の方は実はよく覚えていない。
第7巻は前半が陸軍の奉天会戦、後半がバルチック艦隊の動静という構成になっている。どう考えても劣勢の日本が日露戦争に勝利した背景にある、ロシアの指揮官の判断ミスとロシアの専制君主制の問題が敗因として克明に描かれている。平時には優秀そうに見える指揮官が戦場では無能をさらけ出す様子が、司馬らしい筆致で描かれる。陸軍にしても海軍にしても、指揮官に人を得ない場合の軍隊の弱さ・脆さが伝わってくる。明治時代の日本外交の有り様、庶民の感覚といったサイドストーリも読ませる。さて第8巻は日本海海戦。楽しみである。 |
| |
| ブログ〜世界を変える個人メディア
ダン・ギルモア、平和博訳、朝日新聞社、\2100、p.417 |
2005.11.16
|
|
 |
| いま話題の書。いろいろな雑誌・新聞の書評に取り上げられているし、著者のダン・ギルモアのインタビューも見かける。新聞記者からブログへと活躍の場を移したジャーナリストであるギルモアは、同業者として気になる存在といったところだろうか。
本書は、ブログのインパクトをジャーナリズム(メディア)の観点から紹介している。メディアとしてのブログ、既存メディア(多くの問題が列挙されており耳が痛い)とブログの関係といった最新の状況をざっと知る上で役立つ。技術に対する米国人らしい楽観にあふれており、米国のブログがおかれた最新の空気をよく伝えている。
同じブログといっても、実は読み応えの面で日米で大きく違っている。押しなべて、米国の有名人(例えば俳優やスポーツ選手)は哲学や思想が語れるが、日本の方はせいぜいエピソード(もっと悲惨な例は多い)程度。こうした傾向が、ブログにも反映されている気がする(もちろん、日本にも驚くほど充実したブログが存在するが・・・)。ちなみに、数年前にランディ・ジョンソン(当時はマリナーズ?)が日本の報道番組のインタビューで、含蓄深い応答をしていたのを見て大いに驚いた記憶がある。俳優にしても、アクターズ・スタジオ・インタビューを見ると彼我の差には驚かされる。このあたりは、別途、研究してもらいたいものだ。 |
| |
| 働く過剰〜大人のための若者読本
玄田有史、NTT出版、\2300、p.288 |
2005.11.10
|
|
 |
| NTT出版が始めた『日本の<現代>シリーズ』の一冊。筆者は、「ニート」や「仕事の中の曖昧な不安」といった著書で知られる玄田有史。最近ちょっと気になる論客である。本書は、副題に「大人のための若者読本」とあるように、大人の視点からは窺い知れない若者の置かれた状況や常識のウソを解説している。
筆者は、即戦力指向や過重労働が若者にプレッシャをかけ、働くことを必要以上に難しく見せているとしている。評者も含め、就労している大人たちがそんなに立派で“即戦力”で“個性的”だったとは到底考えられない。つまり無い物ねだりといえる。その無い物ねだりが若者を追い詰めておるとしたら、あまりに愚かだろう。電機メーカーの人事の格言「人事のやることは必ず間違っている。だからその間違いを最小限にするための日々の努力を忘れてはならない」が紹介されているが、こうした真っ当な感覚がいつの間にか麻痺したことが現在の日本の不幸を生んでいるといえそうだ。
ニートはいまや社会問題化している。ニートには二つの種類があると筆者は語る。一つは、学校を中退・卒業後に円滑に就業へ移行できなかった、まったく働いたことがないニート。もう一つは、過去に働いた経験をもちながら、就業がうまくいかず働くことに自信を失ったり、心身の健康を損なって働くことができなくなったニートである。そしてニートに関する常識にはウソがあると、筆者は調査データで暴いている。つまり、ニートが裕福な家庭に育ち、親のすねをかじっているというウソである。いまやニートは、貧困な再生産につながっていると分析する。
玄田が「あとがき」に書いていることに、本書の本質がある。どうして若者にとって、働くことや生きることが、何故これほど難儀で複雑になったのか。仕事にせよ、生活にせよ、もっとシンプルだったはずだ。尤もである。そして、こう断言する。働くための必要なのは「ちゃんといい加減に生きる」ことだと。 |
| |
| 下流社会〜新たな階層集団の出現
三浦展、光文社、\780、p.284 |
2005.11.7
|
|
 |
| ベストセラーになっている本。マーケッタである筆者らしい、ネーミングの勝利である。筆者があとがきで書いているように、かなり乱暴な内容である(書き口も、なぜかときどき乱暴になっている)。「下流社会」化の論拠として筆者が挙げているデータはサンプル数が少なく、統計的な有意性に乏しい。タイトルにも「?}がついていたりして、マーケッタの直感に基づいた、あくまで仮説・推論である。ただし、その直感は鋭い。直感自体が読者の琴線(問題意識)や不安感に触れてベストセラーになったのだろう。
筆者の主張は実は見も蓋も無い。「はじめに」にはこう書いている。「下流」とは、単に所得が低いということではない。コミュニケーション能力、生活能力、働く意欲、学ぶ意欲、消費意欲、つまり人生への意欲が低いと断じる。その結果として、所得が上がらず、未婚の確率も高い。だらだら歩き、だらだら生きているものも少なくない。
評価が分かれそうな本だが、文章はこなれているのでどんどん読み進める。ちょっと時間があるなら読んでみるのも悪くない。 |
| |
| ブルー・オーシャン戦略〜競争のない世界を創造する
W・チャン・キム、レネ・モボルニュ、有賀裕子訳、ランダムハウス講談社、p.294、\1900 |
2005.11.3
|
|
 |
| いろいろなところで引用されている、いま話題のビジネス本である。要は、競合他社が多く、差別化やコスト低減、値下げ、ブランディングに心を砕き消耗戦に陥る「レッド・オーシャン」のビジネスから抜け出し、前途洋洋たる「ブルー・オーシャン」を見つけなさいということである。ブルー・オーシャンとは、買い手や自社にとって価値を大幅に高め、競争のない未知の市場空間である。したがってライバルを打ち負かす必要はなく、競争自体が無意味になるとしている。
ブルー・オーシャンを見出した企業をピックアップし、どこがブルー・オーシャンなのかを分かりやすく解説している。図を効果的に利用していることもあり、読みやすく説得力に富んでいる。もちろん言うはやすし、行なうは難しである。誰もがブルー・オーシャンに発見できる訳ではないし、本書を読んだからといってビジネスで成功する訳ではないし、そもそもブルー・オーシャンを発見したとされる企業にしても、ブルーオーシャン理論を意識していた訳ではない。ただ、目先のことにとらわれて、当たり前のことを当たり前にできないビジネス環境にあっては、ある種の“気づき”を与えてくれる本といえる。 |
| |
|
|

|
| 2005年10月
|
| 戦略の本質〜戦史に学ぶ逆転のリーダーシップ
野中郁次郎、戸部良一、ほか、日本経済新聞、p.375、\2200 |
2005.10.31
|
|
 |
| 名著(だと思う)「失敗の本質〜日本軍の組織論的研究」の続編である。「失敗の本質」の主題は、どうして日本軍の敗北は避けられなかったかを探る出すところにあった。続編と位置づけられる本書は、「勝利を導き出す戦略に共通性はあるのか」を主題に置いている。とりわけ、圧倒的な不利な状況からの逆転を題材に、勝つための戦略をあぶりだそうとしてる。日露戦争以降の日本に適切な事例が存在しないこともあり、取り上げられているのはいずれも、海外の戦史である。いずれもよく知られた戦争だが、具体的には「毛沢東の包囲討伐戦」「ヒトラーとの戦いであるバトル・オブ・ブリテン」「スターリングラードの戦い」「朝鮮戦争」「第四次中東戦争」「ベトナム戦争」である。
切れ味という意味では前作が上回っている。心象風景的な親近感で前作に及ばないところがある。本書は史料を丹念に読み込んで戦略を導き出しているが、冷静な分析だけに、逆に今一歩、どすんと胸にこたえるような迫力に欠けるのかもしれない。 |
| |
| The Search:How Google and Its Rivals Rewrote the Rules of Business and Transformed Pur Culture
John Battelle、Portfolio、p.311、$25.95 |
2005.10.25
|
|
 |
| BusinessWeekの書評欄で見て購入した本。今まさに旬のIT企業である米Google社を扱っている。同社を扱うビジネス書としては最初の本のようが気がするが、正直なところ断言する自信はない。ちなみに11月にも別のGoogle本が発行されると知り、さっそく予約してしまった。日本ではインターネットに絡めば、どう考えても技術的でない会社もIT企業と分類しているが、Googleは正真正銘のIT企業といえよう。流行の言葉を使えばWeb2.0企業の代表格である。それにしても、技術指向の強い、このユニークな会社は実に興味深い。
著者はWired立ち上げにかかわりIT業界に精通しており、Google以前と以後の変化を怜悧に描いている。Googleに関する知られざるエピソードもあり、なかなか読ませる内容になっている。インターネット・ビジネスや検索ビジネスを俯瞰的にとらえようとする努力は買える。検索ビジネスの今後も、律儀にきっちり押さえている(米国人らしい底抜けの楽観主義がよく出ている)。
ただ、周辺状況をきっちりと押さえているだけに、逆に話が広がりすぎている傾向が否めない。Google成功までのインターネット業界の状況やWeb検索事情を理解するには最適だが、もう少しGoogleに焦点を絞ってくれた方が評者のニーズには合う。単行本のため仕方がないが、Googleの最新のトピックが抜けているのもちょっと惜しい。Googleの目指す世界がもう少しはっきり見える本が望まれるところだ。もっとも放っておいても、Google本は続々と登場するだろうが・・・。 |
| |
| 731
青木富貴子、新潮社、p.391、\1700 |
2005.10.10
|
|
 |
| 石井四郎率いる細菌戦部隊「731」を追ったノンフィクション。731部隊に属していた医者たちや関係者、石井の生まれ故郷・千葉、東京の自宅周りを丹念に取材している。本書の最大の売り物は、石井四郎の直筆のメモ(本の表紙になっている大学ノート)に基づいているという点。この石井のメモというのが新発見の資料という。全体にすごくワクワクするという内容ではないが、ずしんと響いてくるといった感じのノンフィクションである。
731部隊というと、戦争時に行った人体実験や細菌研究が主に取り上げられる。確かに731は、森村誠一の「悪魔の飽食シリーズ」で取り上げられ、一時期大いに騒がれた。しかし本書にとって、人体実験や細菌研究は二の次、三の次である。なぜ石井をはじめとした731部隊の関係者が戦犯に問われなかったが本書の主題だ。「GHQはなぜ石井と取引をしたのか」「米国はその取引で何を入手したのか」を解き明かすのが目的である。ニューヨーク在住のジャーナリストである青木は、「国」のためにご都合主義に走る米国の姿勢を批判的にとらえている。 |
| |
| ヴェニスの商人の資本論
岩井克人、ちくま学芸文庫、p.317、\950 |
2005.10.6
|
|
 |
| 最近ひいきにしている経済学者・岩井克人が30代で書いた単行本の文庫本。専門的な学術論文の範疇におさまらない文章を集めたと、著者はあとがきで書いているが、そういは言うもののかなり専門的である(ちなみに、週刊ポストや中央公論、日経新聞、毎日新聞などに、1980年代前半に掲載された文章が含まれている)。
最近の岩井は、「会社はだれのものか」「会社はこれからどうなるのか」といった著作で、肩の力が抜けた経済学者といった雰囲気を作っている。本書はその岩井が若いときに書いたこともあり、目いっぱい肩に力が入っている感じである。身近な事柄から経済を解き明かそうという姿勢は今も昔も変わっていないが、本書の書き口がやはり硬い。専門知識がないと読み進むのはかなり骨である。もちろん評者の経済学に関する知識のなさが、最大の問題なのだが・・・ |
| |
|
|

|
| 2005年9月
|
| メディアの支配者(下)
中川一徳、講談社、p.390、\1800 |
2005.9.29
|
|
 |
| 権謀術数。フジサンケイグループの暗闘を描いた後編。頭のよい人間たちが全精力を傾けた権力闘争を、あますところなく描いている。当事者を含め、とにかく、当事者へのインタビューも含めてよく調べている。十分に時間をかけて書かれたノンフィクションというのが伝わる(真偽のほどは、もちろん不明だが)。ただ上下2巻はさすがに長い。読むほうが少々バテてくる。 |
| |
| インターネットは「僕ら」を幸せにしたか?
〜情報化がもたらした「リスクヘッジ社会」の行方〜
森健、アスペクト、\1600、p.340 |
2005.9.18
|
|
 |
| インターネットや情報技術の負の側面を扱った書。驚くような事実があるわけではないが、よくまとまっている。筆者自身がインターネットを活用してジャーナリスト活動を行っていることもあり、利便性は認めつつ、問題点を指摘するといった形式をとっている。バランスのよさが本書の特徴といえる。
取り上げるのはブログやソーシャル・ネットワーク、電子メール、検索エンジン(Google)、ICタグ、街角に設置された監視カメラ、生体認証など。特にインターネット関連に多くのページを割いている。例えばインターネットにおけるパーソナライゼーションやエージェント技術の進展に、「思考の一極集中」といった表現で懸念を示す。フィルタリングした情報がインターネット・ユーザーの視野狭窄を招き、自分の関心のない分野への無関心と非寛容を生むと主張する。こうした傾向が進むと、相互理解ができないグループが乱立し、不安定な社会が生まれる危険性を指摘し、偏った情報による判断の危うさに懸念を示す。雑誌の“雑”の部分の重要さを改めて感じさせられる内容である。 |
| |
| メディアの支配者(上)
中川一徳、講談社、\1800、p.365 |
2005.9.18
|
|
 |
| 講談社ノンフィクション賞や新潮ドキュメント賞を受賞し、今年のノンフィクション関連の書籍で突出した評価を受けている本。上下2巻とボリューム的にも、内容的にもなかなか読み応えがある。本の帯には10年あまりの取材とあるが、納得の出来である。本書の対象はフジサンケイ・グループ。特に鹿内信隆という人物、さらには鹿内家を軸に描いている。ライブドアとフジテレビの攻防は記憶に新しいところだが、その一因を作ったのが資本の上ではフジテレビの親会社となっているニッポン放送の存在。そして、この構造を作った鹿内信隆と本書は位置づける。
上巻ではまず、鹿内信隆の後継者であるフジサンケイ・グループ議長の鹿内宏明の解任劇を克明に追っている。ドロドロの人事抗争であり、迫真のドラマとなっている。その後は、鹿内信隆がフジサンケイ・グループの総帥に登り詰めるまでの足跡を追う。この部分は、戦前から戦中、戦後の経済界の裏面史といった趣がある。すでに見聞きしているエピソードもあるが、へ〜っといった内容がいくつも出ており興味深い。ちなみに司馬遼太郎が意外なところで登場し、これまた意外な役割を演じている。 |
| |
| ジャーナリズムの条件4:ジャーナリスムの可能性
野中章弘編、岩波書店、\2500、p.234 |
2005.9.2
|
|
 |
| ジャーナリズムのあり方を問うシリーズの最終巻。既存のマスメディアの内部と外部から、現状の問題点を指摘するとともに、新しい動きをオムニバス方式で紹介する。全体は大きく三つに分かれる。「マスメディアの再生」「市民型未来系ジャーナリズム」「ジャーナリスト教育」である。
ジャーナリズムの内部に評者としては、多少の違和感とともに共感を感じる本である。インターネットが発達した状況におけるジャーナリズムの難しさ、インターネットに依存するジャーナリストの危うさを説く編者・野中の指摘には、考えさせられるところが多い。 |
| |
|
|

|
| 2005年8月
|
| 病院で死なないという選択〜在宅・ホスピスを選んだ家族たち
中山あゆみ、集英社新書、\660、p.236 |
2005.8.31
|
|
 |
| 末期がん患者で、死に場所を自宅に選んだ患者と家族のノンフィクション。かつてベストセラーになった「病院で死ぬということ」(山崎章郎著)の在宅版である。
ジャーナリストの筆者が、患者と家族、医療関係者の姿を丹念に追っている。ちょっと患者や家族が美化されているかなといった気持ちもするが、人間というものは気高く凄いものだと改めて感じさせられる。感動の物語も多い。この本を読むときには注意事項がある。確実に涙する個所がいくつもあるので、下手に通勤電車では読まないこと。とにかくこの本を読むと、最後は家族に看取られて家で死にたいと痛切に思う。 |
| |
| Revolution in The Valley〜The Insanely Great Story of How The Mac Was Made
Andy Hertzfeld、Oreilly & Associates 、$24.95、p.291 |
2005.8.28
|
|
 |
| Macのシステム・ソフトの開発者として知られるAndy
Hertzfeldが書いた「Macintosh開発物語」。Macintoshの開発プロジェクトが始まった1979年8月から、John
SculleyによってSteve JobsがMacプロジェクトから追われた1985年5月31日までをカバーする。Macのオリジナル設計チームである7人を軸に話は展開する。ハードウエアの中心人物であるSteve
Wozniakが、はしがきを書いているように「お金のためではなく、何か偉大なことを行っていることに意気を感じた者たちの物語」である。。
とにかく実に面白い。当時のスナップ写真やプロトタイプの写真が大量に収録されていて、それを見るだけでも楽しい。特にBill
AtkinsonがMacのユーザー・インタフェースの開発過程を丹念に撮影したポラロイド写真は貴重な資料だろう。手組みのMacintoshのボードなど、時代を感じさせる。それにMacintosh開発チームの面々の写真は、みんな実にいい顔をしている。
もちろん価値は写真だけではない。開発者自らが執筆していることもあり、知られざるエピソードが満載である。本書執筆にあたり、HertzfeldがWebを使って当時の逸話を募集したこともあり、当時のシリコンバレーの若々しい息遣いが伝わってくる。もの作りの楽しさや苦しさが感じられるのと同時に、徐々に大企業病に侵され官僚的になっていくAppleへの違和感や居心地の悪さも正直に綴っている。もの作りではなく、管理が仕事になっていくAppleに対するHertzfeldの感情は複雑である。HyperCardの開発者として知られるBill
Atkinsonの栄光と挫折も、ありがちな話。技術的に突出した業績をあげているにもかかわらず、成果をマネジャ層に横取りされてしまう。その結末もAppleらしい。そのほかAppleとMicrosoftとの関係も面白い。Windowsのユーザー・インタフェースをめぐるGatesとJobsの直接対決など、ぐっと引き込まれる内容である。 |
| |
| 震度0
横山秀夫、朝日新聞社、p.410、\1800 |
2005.8.16
|
|
 |
| 警察小説の第一人者といえる横山秀夫の最新作。なかなか読ませる内容だが、横山の代表作になり得るかどうかはちょっと疑問。ちょっと長すぎて、中盤がダレ気味になる。締めの部分もちょっと凝りすぎかなという気がする。
舞台設定は阪神淡路大震災当日のN県警察本部。腐臭の漂う警察組織の問題、失踪した警務課長をめぐる人間関係が小説の主題である。帯には「錯綜する思惑と利害、保身と野心」といった文言が並ぶが、ほぼ正確に内容を言い表している。 |
| |
| 坂の上の雲(6)
司馬遼太郎、文芸春秋、p.375、\590 |
2005.8.13
|
|
 |
| 第6巻は、大きな戦いがなくちょっと盛り上がりに欠ける。日本海戦に向けて航海を続けるバルチック艦隊、旅順の戦いを終えた乃木将軍といった話が出てくる程度。本書の主人公である秋山好古・真之兄弟が出てくる部分もすごく少ない。ただ、司馬遼太郎が大山巌とともに高く評価している児玉源太郎がもらした「東京は座敷で戦争をしている」「東京は座敷で人事をしている」というコメントは、どこかの映画に出てきたセリフが思い出されてちょっと面白い。 |
| |
| 会社はだれのものか
岩井克人、平凡社、p.183、\1400 |
2005.8.11
|
|
 |
| 2004年に「会社はこれからどうなるのか」という本を書評したが、その続編に当たる書(帯のもそう書いてある)。ライブドア-フジテレビのニッポン放送株をめぐる攻防を見て、出版を思い立ったと著者自身が述べている。会社とは株主のものなのか、従業員のものなのか・・・・。答えはいずれも否というのが筆者の考えである。前作で「資本主義とは何か、会社とは何か」をわかりやすく説いているが、その応用例として、ライブドア-フジテレビの争いを取り上げる。実に明確な論理構成で、米国型の株主資本主義の発展と限界を指摘するところは前作と同じである。
本書で筆者は、これからの会社で重要になってくるのは、お金ではなく人間。個人よりもチームと説く。技術にしても、何にしても、それが差別化要因である期間はどんどん短くなっている。企業の最終兵器は、結局はヒトということになる。ヒトだけがアイデアや構想といった「無」から、製品ひいてはお金という「有」のものを生み出せると持論を展開する。
本書の秀抜なのは、後半部の対談のところ(急いで出版したために、書き下ろしの部分が短くならざるを得なかった)。富士ゼロックスの小林陽太郎、技術持ち株会社の原丈人、コピーライターの糸井重里という選も面白いし、中身も実に濃い。評者は本を読むときに付箋紙をそこらじゅうに付けるし、アンダーラインもバンバンひく(したがって古本として売れる気がしない)。本書は、後半部が付箋紙であふれている。秀抜なのは、デフタ・グループという技術持ち株会社の会長である原丈人との対談である。実に米国的な会社を運営している原が、MBA経営者(そういた経営者をトップの座につけた会社)の限界と愚を徹底的に叩いているのは面白い。数字にしか興味がなく、数字だけに命をかけるようなやり方の愚かさと時代遅れさを、傾いた会社の具体的な例を挙げて指摘する。 |
| |
| バブルの物語〜暴落の前に天才がいる
ジョン・K・ガルブレイス、ダイヤモンド社、p.173、\1400 |
2005.8.9
|
|
 |
| ぜひ読みたかった本。オランダにおけるチューリップ投機にはじまり、日本のバブルにいたる「バブル」の歴史を扱っている。歴史といっても、堅苦しい内容ではなく、深い知識に裏打ちされた洒脱(翻訳の力に負うところが大きい)なエッセイに近い内容となっている。警句にあふれ、読み応えがある。投機の踊らされて大損をしたニュートンの話や、投機家たちに口実を与えたシュンペーターといった評価も目新しく勉強になる。ただし絶版になっているので、古本屋で入手する必要がある。筆者はAmazonの古本サイトで購入。便利な時代になったものだ。古本といっても十分に美しい。 |
| |
| 戦略不全の論理:慢性的な低収益の病からどう抜け出すか
三品和広、東洋経済新報社、p.308、\2600 |
推薦!2005.8.5
|
|
 |
| 間違いなく良書である。日本の企業が慢性的な低収益にあえぐ理由を戦略の不在に求める。「戦略とは何か」「日米の違いはどこにあるのか」「戦略に必要な要素は何か」「戦略的経営者を生む企業のキャリア形成はいかなるものか」といった視点から考察した書。理論先行ではなく、具体例を示しながら説得力のある持論を展開する。
日本の企業では「戦略」を安易に使いすぎで、逆に戦略不在を証明し、言葉の空洞化を招いているという著者の指摘はなかなか手厳しい。戦略とは事後に浮かび上がってくるもので、事前に鎮座するものでないという指摘もユニークである。戦略とは個々の着手を意味のある形でつなげる全体構想だが、構想自体は時代観や大局観から形成されるもので、最初から言葉としてそこにあるものではないという訳だ。
経営における戦略に必要なのは、「非合理性」「非可分性」「非可逆性」と筆者は分析する。非合理性とは、情理や常理を否定して、競合他社とは微妙に異なるスタンスをとることにつながる。最初は「ばかな」と思われることが、最後は「なるほど」と納得させることが戦略の要諦としている。非可分性とは全体の一体性を意味する。デルやサウスウエスト、ウオルマートといった企業の事業システムは、各事業が高い相互関連性によって支えられるため、仕組み自体は周囲からは丸見えでも真似できない。最後の非可逆性では、後戻りできない選択に縛り付けるコミットメントが経営者に求められるとしている。
最後に日本企業の慢性的な無為無策の背景には、キャリア・システムの根本的な欠陥があると指摘する。日本のキャリア・システムでは、「非合理性」「非可分性」「非可逆性」が求められる戦略を遂行する経営者は生まれないとしている。 |
| |
|
|

|
| 2005年7月
|
| プライバシー・ゼロ:社員監視時代
小林雅一、光文社、p.259、\952 |
2005.7.27
|
|
 |
| 光文社のペーパーバックスは、売れるネタを魅力的なタイトルで出版するシリーズである。本書も「社員監視時代」という刺激的なタイトルで、セキュリティ問題に関する現状を紹介している。どこかの書店の売れ行きで、トップ10に入っていたのを目にしたことがある。そこそこ売れているのだろう。
新聞や雑誌で報じられた話をざっと“おさらい”する上では有用な本。逆に言えば、ノンフィクションとしての目新しさや驚きは多くない。この点は、ネタが悪くないだけに少し残念である。そのなかで、関西情報・産業活性化センターの木村修二氏(情報漏えいを引き起こした宇治市役所の担当者)へのインタビュー、名簿業者であるイアラ代表取締役の雨宮和人氏のインタビューは、いずれも本音が出ていてなかなか面白い。この二つのインタビューには一読の価値がある。 |
| |
| The Secret Man〜The Story of Watergate's Deep Throat
Bob Woodward、Carl Bernstein、Simon&Schuster、p.249、$23 |
2005.7.25
|
|
 |
| ウォーターゲート事件を暴いた立役者、ボブ・ウッドワードとカール・バーンスタイン。このうちウッドワードの情報源となったのが、政府高官のディープスロートである。この6月に、ディープスロート本人が名乗り出て大騒ぎとなったのは記憶に新しいところである。おかげでウォーターゲート事件を扱った本やDVDが売れたりした(評者も、DVD「大統領の陰謀」を手に入れた)。
本書は、本人による突然の告白を受けて緊急出版された本。いかにも緊急出版といった感じで、精緻なインタビューが売り物のウッドワードの他書に比べると、ちょっと物足りない。活字も大きく、何とか1冊の本にしたという感じである。「なぜフェルトがディープスロートになったのか」という最大の疑問については、残念ながら答えていない。来年にもフェルトの自伝が公開されるので、そのときに明らかになるのかもしれないが・・・。
本書はウッドワードが、ディープスロートであるFBI副長官のマーク・フェルトとの偶然の出会い、ウォーターゲート事件との関わり、引退したフェルトとの再会などを綴っている。ワクワク、ドキドキといった感じではなく、淡々とした筆致である。最近問題となっている取材源の秘匿といった意味で、ウッドワードはフェルトが死ぬまで取材源を公開するつもりはなかったという。それにしても、ワシントンポストの6人がディープスロートの正体を知りながら、30年あまりも秘匿し続けた点は驚くべきことである。また最近認知症が進んでいるフェルトの体調を考えて、ウッドワード自身が死後の公開に向けた手を打っていたことを本書で明らかにしている。
ちなみにフェルト自身がかつて回顧録を発表していたり(そのなかで、自分はディープスロートでないことを明言している)、米国にはディープスロート・ハンターとして取材源探しをしているジャーナリストがいたりと、いままで知らなかったような情報も、本書にはつまっている。 |
| |
| 運命の法則〜「幸運の女神」と付き合うための15章
天外伺朗、飛鳥新社、p.182、\1400 |
2005.7.21
|
|
 |
| CD、ワークステーションNEWS、AIBOと数々の開発を手がけた、ソニーの土井利忠氏の本。取材の事前資料として読んだが、なかなか面白い。技術者やマネジャとしての著作も行っている土井氏だが、「あの世」「超能力」といった話題を取り上げた著書がこのところ目立っている。実際、著書は精神世界といったジャンルに分類され、書店に並んでいることが多い。本書は、ビジネス書と哲学書/精神世界の間に位置する本である。
本書で土井氏が痛烈に批判するのが、日本企業が導入に走った「成果主義」。日本の組織が伝統的にもっていた「おおらかな愚者を演出するリーダー」が死に絶え、「小ざかしい小モノ」の世界に企業が堕しつつあると指摘する。個々の人間が心の奥底で満足感を感じ仕事をする内発的報酬ではなく、他人による評価・統制で仕事をする外発的報酬に依存する人事制度の愚かしさと危険性を指摘する。マネジャは低次元の干渉に血道をあげ、企業には不明瞭な雰囲気が漂う。当然活力は低下する。独特の腐臭が漂うとまで表現している。
本書でも触れているが、高橋伸夫氏の著作に相通じるところが多い。仕事を楽しい遊びとして進めてきた土井氏にとって、仕事が不愉快になるような現状は我慢ならないというのがよく分かる本である。 |
| |
| ヒューマン・インフォマティクス〜触れる・伝える・究める
デジタル生活情報術、長尾真監修、工作舎、p.353、\2800 |
2005.7.20
|
|
 |
| 長尾真、金出武雄、木戸出正継、三宅なほみ、辻井潤一、所真理雄などなど、おなじみの研究者の名前がずらりと並ぶ書。これらの研究者に工作舎の編集者が取材して書き起こし、長尾氏が監修している。未来を見据えた場合、ITが人間の生活に幸福感・満足感・充足感を与えるには、どうすればいいのかという問いに対する答えを探し求めた書といえる。ITと人間はどのように関わるべきか、ITは人間の生活にどのように貢献していけばいいのかを、三つの視点から扱っている。
三つの視点とは、【触れる】ITは人間の所作や声から何を学べるか、【伝える】ITは、時間や空間を越えて人間の生活にどのように貢献できるか、【究める】人間世界の情報をどのように蓄えれば人の英知を共有できるか、コンピュータと人間はどうすれば理解しあえるか、である。図や写真を多く挿入し、肩のこらない形で最新の研究を紹介している点は評価できる。 |
| |
| 「うつ」を治す
大野裕、PHP新書、p.211、\660 |
2005.7.18
|
|
 |
| ヘルパーの仕事をしているカミさんの書棚から取り出して読み出した本。3連休にはちょうどよい分量と内容。多くのところで問題となっている「うつ病」について、実に分かりやすく解説している。テレビのCMでも言っているように、1週間以上も、眠れなくなったり、食欲が落ちると要注意という。自分や周囲を冷静に見るうえで役に立つ情報が満載である。「心のカゼ」とも呼ばれるうつ病だが、軽視は禁物。注意事項や自己診断チャートや対策、薬物治療、ボケとうつの関係など丁寧に解説している。何かと役に立ちそうな本である。 |
| |
| 坂の上の雲(5)
司馬遼太郎、文芸春秋、p.411、\590 |
2005.7.3
|
|
 |
| 日露戦争が大きな山を迎えた。「203高地の攻防」が5巻の中心である。乃木希典と児玉源太郎の明治の武人らしい駆け引きなど、読みどころ満載である。司馬遼太郎は、203高地での愚行を日本人の特性にまで敷衍している。すなわち、日本人は戦略や戦術の型ができると、あたかも宗教家の教義のように絶対の原理としてしまうというというもの。いわゆる専門家の保守性と官僚体質も指摘する。専門家というものが、必ず「できない」と言う種族だというのが司馬の見立てだ。この保守性を打ち破るところから、203高地の攻略の突破口を見出したのが、児玉源太郎である。なかなか示唆に富む1冊である。さて次なる山は日本海海戦である。 |
| |
|
|

|
| 2005年6月
|
| 小説:盛田学校(下)
江波戸哲夫、プレジデント社、p.467、\1524 |
2005.6.30
|
|
 |
| 盛田昭夫を中心に描いたソニー本の下巻。下巻はトリニトロンの話に始まり、VTR(ベータ対VHS)、ウォークマン、そして盛田の死までを扱う。ベンチャーのレベルを脱し、大企業になったソニーと盛田の苦悩を描いている。次期CEOになるストリンガー氏をして、「ソニーはものづくりではなく、マネジメントが本業になってしまった」(ニューズウィークからの引用)と言わしめる原因が垣間見える構成になっている。ソニー本は数多くあるが、小説には小説の味わいがある。心象風景を自由に描けるのも悪くはない。お馴染みの話が多いが、盛田の政治活動に関しては知らなかった逸話もあり楽しめる。ただタイトルに「学校」とある割には、学校らしさがない気がする。登場人物が多すぎて、やや散漫になったためだろう。 |
| |
| ジャーナリズムの条件(3)メディアの権力性
佐野眞一、大塚将司、川崎泰資ほか、岩波書店、p.233、\2500 |
2005.6.24
|
|
 |
| 既存ジャーナリズムへの批判精神にあふれたシリーズ企画「ジャーナリズムの条件」の第3巻。本書では、立法・行政・司法をチェックする「第4の権力」ならぬ、3大権力と並ぶ「4番目の権力」となっているのではないかという危機感と批判的精神をもつ執筆陣が、思いのたけを述べている。ただし、ページ数がかなり限られているため、ちょっと物足りない部分もある。執筆陣には、大塚将司(日経)、川崎泰資(NHK)、吉岡忍、溝口敦、安田純平といったおなじみの面々が名を連ねている。巨大メディアに対する危機感、公権力とメディアとの危ういバランス、フリー・ジャーナリストの闘いといった内容である。
大学時代に福田恒存をはじめとるする新聞批判が盛んな時期があったが、本質的な部分は四半世紀を経てもあまり変わっていないなぁというのが読後感である(悪いというわけではない。そのイナーシャの大きさに驚くだけである)。いずれにせよ、岩波らしいといえば、岩波らしい内容に仕上がっている。秀抜なのは佐野眞一の総論だ。この部分だけでも、十分に読む価値がある本だろう。出来合いの「大文字」言葉に頼らず、ひたすら「小文字」で書き続けることがジャーナリズムの使命という佐野の考え方には、深く共感する部分がある。メディアとしてのインターネットに関する部分に中途半端なところもあるが、この分野に興味をもつ人には最適な書である。
|
| |
| 小児救急〜「悲しみの家族たち」の物語
鈴木敦秋、講談社、p.285、\1700 |
2005.6.21
|
|
 |
| 確か朝日新聞の書評を読んで購入した本。読売新聞の記者の手による、激務だが報われない小児医療の在り方に焦点を当てたルポルタージュである。取り上げるのは、理不尽な過重労働の末に命を絶った小児科医、病院をたらい回しにされ死に至った7カ月児、救急病院での誤診と引継ぎミスによって亡くなった5歳児。小さな子どもをなくした親の話は実に辛い。いずれも、この国の小児科医療における矛盾を強く感じさせる話である。とりわけ最後の誤診というか無責任極まりない当直医の話は、新聞で読んだ記憶があるが、こうしてまとめて読むと、その悪質さがよく分かる。
実は、本書の特徴はルポルタージュの部分ではない。最終章で取り上げた三つの家族と、日本小児科学会の理事との討論の場を設けたところが、通常とは異なる。批判だけに終わらることなく、明日につなげようとする意欲は買える。子どもを亡くした親が発する意外な提案には少し驚かされる。 |
| |
| ルパンの消息
横山秀夫、光文社、\876、p.331 |
2005.6.18
|
|
 |
| いまや超売れっ子ミステリー作家の横山秀夫の処女作。今はなき、サントリー・ミステリー大賞の佳作を15年前に受賞した作品である。なぜか出版されずにフロッピー・ディスクのなかに埋もれていたという。新たに改稿作業をした後、この5月に出版された。けっこう宣伝していたので、知っている方も多いかもしれない。
2段組みで331ページもある大作だが、横山秀夫の作品らしく一気に読ませる。殺人事件の設定は、昔読んだエラリー・クイーンを思わせるものがある。高校で起こった殺人事件に三億円事件を絡ませるのは少々やりすぎの感はあるが、エンタテインメントとして十分に楽しめる。人間ドックの待ち時間に読む本として購入したが、判断は間違っていなかった。 |
| |
| ドラッカー選書<3>現代の経営(上)
P.F.ドラッカー、ダイヤモンド社、p.293、\1553 |
2005.6.15
|
|
 |
| 珠玉の言葉が満載のドラッカー本。原書を読むのに時間がかかり、ドラッカー本の「再読プロジェクト」がしばらく中断していた。ようやく再開にこぎつけた。本書も期待を裏切らない、十分な満足感が得られる本である。
ドラッカーの主張は、いずれもごく当たり前のことばかり。例えば企業の永続性に関する考え方。企業の存続を犠牲にして目前の利益を挙げることの虚しさを指摘する。それまで築いてきた資金や資産、信用を食い潰しているに過ぎず、愚かで無責任なマネジメントと切り捨てる。そして事業のマネジメントは、官僚的、管理的、政策立案的なものであってはならないとする。では優れたマネジメント(経営管理者)はどうやって生まれるのか。それは企業の文化によるというのがドラッガーの主張だ。組織の卑しい文化からは卑しい経営管理者しか生まない。面白いのはマネジメントの思い上がりを戒めている点。所詮マネジメントは企業の一部を担うのに過ぎない。ソニーの新CEOであるストリンガー氏が、「いつのまにかマネジメントが仕事になってしまった」と、ニューズウィークのインタビューに答えて、こう問題点を指摘したのと相通じるところがある。
ちなみにドラッカーには、「予算を守ることはバカでもできる。しかし守るだけの価値のある予算を作れるひとは少ない」という警句があるが、本書に、GMの事業部長の言葉として収録されている。 |
| |
| 小説:盛田昭夫学校(上)
江波戸哲夫、プレジデント社、\1524、p.418 |
2005.6.16
|
|
 |
| 仕事柄、企業関係の書籍が本棚にけっこう並んでいる。現時点で最も多いのはMicrosoft、次にIBMだ。ずっとIBMが1位だったが、いつの間にか逆転した。日本ではソニーがこれまでダントツだったが、このところトヨタの猛追を受けている。本書は、追われる立場のソニーの歴史を小説仕立てで扱った本。ジャーナリスティックではないので、ホンワカしている。緊張感が薄いので好き嫌いの分かれるところだが、出来自体はけっして悪くない。大宅壮一とソニーとの関わりや、ソニーの商標をめぐる菓子メーカーとの裁判の話は、初めて聞くような気がする(正直、自信はまったくないが・・・)。
いずれにせよソニー本(ホンダ本も同じだが)の多くは、技術者らしい夢が前面に出てくるので(日本にとって古きよき時代と、ソニーの成長は軌を一にしている)、読後感が良い。ニューヨーク・タイムスの東京特派員が、「失われた10年で日本人が失ったのはお金ではなく、夢だ」といった言葉の意味を改めて考えされられる本である。書名通り、盛田を中心にした人物群像を描きながらソニーの歴史をたどっている。
上下2巻だが、上巻では井深大と盛田昭夫の出会いから、トランジスタ・ラジオの発売、カラーテレビの開発、米国進出といった内容。有名な設立趣旨書の話がほとんで出てこないのは、ビジネス書とは一線を画してるという著者のこだわりかもしれない。 |
| |
| 13日間〜キューバ危機回顧録
ロバート・ケネディ、毎日新聞社外信部訳、中央公論社、p.194、\705 |
2005.6.10
|
|
 |
| こんな本が存在することをまったく知らなかった。ケネディ政権時代に起こったキューバ危機を、当事者であるロバート・ケネディ司法長官がつづった回顧録。回顧録自体は110ページほどなのですぐに読める。回想録のあとの記録文書は、お好きにどうぞといった感じである。
回想録の部分は、航空写真によるキューバのミサイル基地の発覚から、ミサイル撤去をフルシチョフが決断するまでの13日間を振り返ったもの。米国とソ連の首脳部の駆け引きや、ホワイトハウスを凍らせた突発事故など、緊張感あふれる本である。著者の兄であるJ.F.ケネディ大統領の様子が随所に書き込まれている。米国の政権内でどのようなやり取りが繰り広げられ、どのような論拠のもとで、どう決断したのかを当事者の目で語られている。当事者だから語れない部分(脚色された部分)もあるだろうが、それにしてもすごい史料である。本書が最も優れているのは、米国の意思決定プロセスや危機管理のあり方が、よく分かる点だろう。そこにはケネディ時代の米国の理想主義がよく出ている。もちろん、一方でベトナム戦争もあるが・・・(ベトナム戦争に関しては、優れたロバート・マクナマラの回想録が別途存在するが、積読状態になっている)。いずれにせよ軍部とケネディ政権とのやりとりは、イラク戦争と対比させると、いろいろと考えさせられる内容である。
本書の成り立ちも数奇だ。もともとはニューヨークタイムズが日曜版のためにロバート・ケネディに執筆を依頼したことが発端だが、分量が多くなりすぎたことや、大統領選の選挙運動との兼ね合いで公表されなかった。雑誌の誌面に掲載されたのは、ロバート・ケネディが暗殺されてから4カ月後だった。日本版は単行本が1968年に発売されているが、文庫本は9.11直後の2001年11月25日に出版され、舛添要一があとがきを書いている。 |
| |
| 定刻発車〜日本の鉄道はなぜ世界で最も正確なのか?
三戸祐子、新潮社、p.404、\590 |
推薦!2005.6.3
|
|
 |
| JR西日本の事件を契機に急に売れ始めた本。インターネット書店でも売り切れが続発し、評者の発注も一度はキャンセルされた。なかなか入手できなかったが、最近は平積みになっている。もともとは2001年に交通新聞社が出版した本である(文庫本は事故後の5月1日付発行)。寡聞にして知らなかったのだが、フジタ未来経営賞(書籍の部)や交通図書賞を受賞している。それも頷ける十分に内容である。文章もこなれているし、お奨めだ。
定刻発車の仕組みが克明に解明されていて、実に面白い。副題になっている「日本の鉄道はなぜ世界で最も正確なのか」を、鉄道会社だけではなく、日本の社会史にまで範囲を広げながら究明する。日本の鉄道に関する驚くべき事実が次から次へと出てくる。
定刻発車には、乗務員やメンテナンス作業員の努力・技量、鉄道を支える情報システムをはじめとする最新技術だけではなく、乗客の協力(しつけ)が大きな役割を果たしていると、筆者は指摘する。東北新幹線が東京駅を乗り込むときになされた発想の転換など、驚かされる。もちろん今回の事件に関しても、示唆に富む指摘がいくつか含まれており、「何かおかしい」「そこまでやらなけらばいけないのか」「鉄道会社はいつまで続けられるのだろうか」「重要なのはゆとり」といった指摘が出ており、考えさせられる内容である。ちなみに、あとがきでは、新幹線の96.2%、在来線の90.3%が、「1分違わず」正確に発着しているという、2003年度のJR東日本のデータを紹介している。1列車あたりの遅れは、新幹線が平均0.3分、在来線が同0.8分だ。 |
| |
|
|

|
| 2005年5月
|
| Dark Hero of the Information Age〜In Search of Nobert Wiener The Father of Cybernetics
Flo Conway and Jim Siegelmen、Basic Books、p.423、$27.5 |
2005.5.31
|
|
 |
| 大学時代に制御工学を学び、生体工学関係の卒業論文を書いた評者にとって、「サイバネティクス(Cybernetics)」とはなつかしい言葉だ。確か、岩波書店から本が出ていたと記憶する。このサイバネティクスの理論を打ちたてのが、本書の主人公ノバート・ウイナーである。情報技術の理論的な基礎を築いた数学者、情報理論の父(これまた有名なシャノンもいるが・・・)といった評価も可能だろう。デジタル・コンピュータの概念を打ち立てたことも、本書は紹介している。
本書はノバート・ウイナーの人生を克明に追っている。十代で博士号を取得するなど、子どもの頃のウイナーはまさに神童。18カ月の赤ん坊が2日間教えられただけでアルファベットを覚え、砂に文字書き始めたといった逸話も紹介する。しかし父母との確執など、けっして恵まれた幼少時代とはいえなかったのも事実。天才ゆえの悩みも多かった。学者になってもなかなか認められない。特に米国での評価が低く、失意の日々を送る。サイバネティクスで認められてからも、人生は平坦ではない。妻との関係で悩んだり、フォンノイマンとの反目、娘の病気、そして本人も精神に変調をきたす。そして奇行。大変な人生である。
戦争や冷戦もウイナーの人生に暗い影を落とす。戦争のときはレーダーの研究で米国に貢献したウイナーだが、次第に反戦の姿勢を明確にして、政府と対立していく。アカ狩りにも遭遇し、ソビエトとの関係を疑われる。最後はCIAの尾行がつけられる始末だ。そして、スウェーデンでの突然の死。まさに波乱万丈の人生である。しかし、あまりに長く、本が分厚い。 |
| |
| 知の科学:コミュニケーションロボット〜人と関わるロボットを開発するための技術
石黒浩、宮下敬宏、神田崇行著、人工知能学会編集、オーム社、p.201、\330 |
2005.5.22
|
|
 |
| 言葉やしぐさによって、人間と人間らしい交流を図る「コミュニケーション・ロボット」の入門書である。人工知能に関する学術的な最前線を紹介する「知の科学」シリーズの1冊。大学で工学部の教育を受けた人を対象と書かれているが、さほど難しいという感じはしない。コミュニケーション・ロボットは、特定の目的に使う「産業用ロボット」と明確に区分されるロボット。著者は「ロボットはメディア」という言い方で、その特徴を表現している。
本書は開発方法論に始まり、センサー技術、制御技術、性能評価の仕方をざっと紹介する。よくまとまっているが、ページ数の都合もあり駆け足の記述が目立つ。ただし目次を工夫したり、かなり充実した参考文献や参考書籍を掲載するなど、ページ数の少なさを補っている。写真が多いのも評価できる。コミュニケーション・ロボットの“性能”を、心理学的・認知科学的なアプローチで評価する方法に多くの紙面を割いているのが興味深い。
著者が特に注目して欲しい技術や手がけている開発事例は、囲みの体裁で本文中に挿入しメリハリをつけているが、少々多すぎる。肝心の本文をズタズタに切り裂いてしまい、読みづらくなっている。囲み自体は興味深いだけにちょっと残念である。 |
| |
| 鈴木敏文の「本当のようなウソを見抜く」〜セブン-イレブン式脱非常識の仕事術
勝見明、プレジデント社、p.245、\1238 |
2005.5.15
|
|
 |
| 著者が雑誌プレジデントでのインタビューをベースに再構成した本。ヨーカ堂とセブンを率いる鈴木敏文の人気は絶大である。講演会には会場からあふれるほどの人が集まる。凄いの一語である。実は、氏をよく知る人は「喋ることはいつも同じ」と語るが、同時に「軸が全くブレない」と評価する。そこがまたウケている理由だろう。本書にもその「軸がブレない」感じがよく出ている。現場感覚に優れたコメントが多いだけに、多くのビジネスパーソンの琴線に触れる。これまでのビジネス書では、松下幸之助や本田宗一郎の特集を組めば確実に売れるといわれていた。ソニーの井深大や盛田昭夫も同様だが、いずれもメーカーの経営者。鈴木が脚光を浴びるところが、今風と言えそうだ。いずれにせよ気づきの多い本。すごく読みやすいので、一読を薦める。 |
| |
|
坂の上の雲(4)
司馬遼太郎、文春文庫、p.414、\590 |
2005.5.14
|
|
 |
| 日露戦争がいよいよ佳境に入ってきた。全8巻なので、半分を読み終えたことになる。話題の中心は、当然、乃木希典が率いる陸軍と東郷平八郎が率いる海軍である。いずれも、戦闘自体は教科書にも出ているし、結果は多くの日本人は知っているだろう(もっともお寒い教育状況を考えると、もはや安心はできないが・・・)。司馬史観という側面はあるものの、教科書の日本史では感じることのできない歴史の面白さを堪能できる。203高地や日本海戦の結果だけでは、知りえない話が満載されていて実に楽しい。
陸軍の旅順要塞への攻撃は、指導者があまりにも無能な結果として、本書では物笑いになっている。ただし、全軍の総大将とは懐が深く泰然とすべきという感覚があり、乃木への評価はけっして低くない。読むも無残なのは、参謀・伊地知への評価。同様に陸軍への見方も厳しい。具体的には、部内人事に血道をあげ、書類好きの陸軍の体質を挙げる。その象徴ともいうべき山県有朋の評価は惨憺たるもの。その権力好きで、人事いじりに情熱を傾けるケチな姿は、傾国の張本人として怨嗟の対象である。ちなみに大山巌や児島源太郎といった面々は、“人物”として扱っている。悪貨が良貨を駆逐するといった具合で、山県・伊地知的な流れが昭和へのつながっていくというのが、司馬の史観といえそうだ。
一方の海軍は、山本権兵衛の指揮の下で無能者を退け、闘う組織への変身させたとして評価は高い。山本権兵衛がここまで持ち上げられると、大昔に読んだ江藤淳の「海は甦る」を再読したくなってしまう。ただし、東郷率いる海軍の闘い方は、意外なほどほめられるものではない。実に多くの失敗を繰り返している。ロシア海軍の失策(こちらも、多分に人の問題だった)の助けられて、結果オーライで勝ってしまった過程も、本書では克明に追っている。 |
| |
| 折れたレール〜イギリス国鉄 民営化の失敗〜
クリス・ウルマー(著)、坂本憲一(訳)、ウェッジ、p.396、\2400 |
2005.5.12
|
|
 |
| 民営化後に脱線事故などが多発した英国の鉄道を扱ったノンフィクション。なぜ民営化後に大きな鉄道事故が起こったかを、しっかりした裏づけ調査を基に論じる。経済面、ビジネス面、政治との不幸な関係といった、さまざまな切り口からしっかり分析し、書き込んでいる。そのため少々冗長かなといった感じで、最後のほうは読むのに疲れてくる。エンタテインメント性は薄いが、ノンフィクションとしてはなかなかの出来である。3年ほど前に出たときに購入したが、ツン状態が続いていた。今回の尼崎列車脱線事故があったこともあり、本棚から取り出した。
英国は国鉄を民営化するときに、大きく四つの会社に分けた。インフラ整備会社、保守・更新請負会社、旅客輸送会社、貨物輸送会社である。インフラ部分と運用部分を分離したわけだ。もう一つ大きな問題は研究関連の部門を抱えなかったこと。技術的に正しい選択や措置が打てなくなったために、常に「安全サイド」といった過剰反応ともいえる配慮がなされ、事故が起こったときなど混乱に輪をかけたし、経営も傾けた。このほか示唆的な記述もある。大きな列車事故を起こした旅客輸送会社(レールトラック社という)が、5分の運行遅れのパーセンテージを記録するシステムを導入し、それによって評価する成果主義の導入した点や、列車制御のATPを導入しなかった点だ。
日本と英国の事情の違いはあるが、なかなか読ませる本である。サッチャー、メージャー、ブレアと、おなじみの政治家も多数登場する。ちなみにサブタイトルに「民営化の失敗」とあるが、先日TVで報道された内容をみると、民営化後の鉄道事故を教訓にして、英国の鉄道は面目を一新したようである。したがって本書の現在的な表題は、「英国の国鉄民営化の教訓」ということになろう。
ちなみに鉄道事故を扱った書籍には「なぜ起こる鉄道事故」がある。この書評でも2002年に扱っている、なかなかよくできた本である。このほか列車関連で気になっているのが「定刻発車」という文庫本。あるインターネット書店に24時間以内に発送とあったので、さっそく発注をかけたが、注文が殺到したためかキャンセルになってしまった。残念。 |
| |
| 世間のウソ
日垣隆、新潮社、p.206、\680 |
2005.5.6
|
|
 |
| 辛らつな書き口で、世の中の“妙ちくりんなこと”を真っ向から斬りまくるジャーナリスト日垣隆。最近はとんと読まなくなった週刊エコノミストだが、同誌の巻頭をかざる「巻闘言」は大好きなコラムだった。本書は、付和雷同しない日垣の特徴が存分に出ている新書本である。1時間もあれば読み終えることができるので、電車のお供に向く。
内容は、期待を裏切らず世間のウソを斬りまくっている。テーマは、「民事不介入の原則」「鳥インフルエンザ」「裁判員制度」「幼児虐待」「宝くじ」などなど多彩である。とりわけ警察の「民事不介入の原則」など、多くの人が信じているのではないだろうか。実は何の根拠もないらしい。
多くの場合、日垣の苛立ちの矛先はマスコミに向けられる。メディア・ウイルスのごとく(日垣は狼少年報道と呼ぶ)、根拠の薄い事柄があたかも事実のようになって伝染、拡大再生産されていく。これを日垣は、一点突破全面展開と呼んでいる。さらに、“専門家”の思惑を持った発言が混乱に輪をかける。マスコミで働くものにとって自戒すべき記述が多い本。もちろん、日垣自身の発言も検証すべきなのは言うまでもない。 |
| |
| 看守眼
横山秀夫、新潮社、p.281、\1700 |
2005.5.1
|
|
 |
| 横山秀夫の短編を三つ集めた本。警察小説を得意とする横山らしい短編集である。カミさんが古本屋で見つけてきた本で、新刊ではない。すごく面白いという訳ではないが、まずまずの出来。連休中に読むには最適といえる。表題の看守眼は、刑事になる夢を奪われ定年まで留置所の看守として勤め上げた警官の話。いつものようにどんでん返しがあり、楽しめる。警察もののほか、新聞記者としての体験をもとにした新聞ものも収録されている。こっちの話はちょっと身につまされる部分がある。殺人に巻き込まれることはないだろうが・・・。 |
| |
| 日本はなぜ敗れるのか〜敗因21カ条〜
山本七平、角川書店、p.313、\781 |
推薦!2005.4.30
|
|
 |
| 抜群に面白い本である。本の帯には、トヨタ自動車の奥田碩が「ぜひ読むように」と幹部に薦めたとある。納得できる。本書は小松真一の「虜人日記」という戦争体験を綴った書をベースに、山本七平が縦横無尽に日本人論を展開する体裁をとっている。戦争時の体験はえてして誇張されたり、自己弁護の傾向があるというのが山本の見解だが、その山本が「虜人日記」を選んだのは、何の遠慮も思惑も介在し得ない環境で書かれたリアルタイムの“日記”だから。誇張する必要もないし、自己弁護の必要のない環境で書かれたことを評価する。
日本人論は山本の得意技だが、本書はまさに見事の一言。本書のエッセンスを知りたいのなら、冒頭にある「敗因21カ条」あるいは裏表紙の説明書きがすべてを言い尽くしている。本書は日本人の行動を、「小市民的価値観を絶対とする典型的な小市民的態度」と規定する。身に覚えのある手厳しい指摘が次から次へと出てくる。「ものまねの限界」といった指摘もその一つ。日本人は本質を理解せず、みずから創作しないために「作り直す」ことができないし、その自信もない。結果、さまざまなものを“権威”として崇め奉ることになり、「本家よりも厳しくすれば大丈夫」といった思考に陥る。前後の見境なしに、情緒的にどんどん引きずられ、機械的な拡大再生産を繰り返す。その極限で一挙に崩壊する。そして最後に一言。「やるだけのことはやった。思い残すことはない」といった羽目になる。
本書を読んで頭に浮かぶのが、「マネジメント」と「管理」の違い。マネジメントは管理と訳されることが多いが、実は両者はかなり意味合いが異なる(評者が付き合うプロジェクトマネジメントの専門家の方々は、必ずこの点を指摘する)。マネジメントは「首尾よく行うこと」、一方の管理は「統制すること」、似て非である。本質を理解しようとしない、物まね好きには、統制(管理)がよく似合うということかもしれない。 |
| |
|
|

|
| 2005年4月
|
| まかり通る〜電力の鬼・松永安左ェ門〜
小島直記、東洋経済新報社、p.690、\2500 |
2005.4.28
|
|
 |
| 就寝前と休日の朝にちょこちょこ読んでいたために、読み終わるのに恐ろしく長い時間がかかった。読み始めたのがいつだったのかを忘れしまったほどだ。なにせ690ページもあるので、通勤に持ち歩くにはまったく適さない。家で読みざるを得ない代物である。
本書は作家の小島直記が得意とする人物評伝。手馴れた感じの仕上がりだ。本書では戦前・戦中・戦後の電力業界を引っ張った松永安左ェ門を扱っている。この人物、確かにユニークな経歴と強烈なキャラクタの持ち主で、いかにも明治の人物である。「電線を地下に埋めてしまえ」と語るなど、先見性も備えている。破天荒、天衣無縫といった趣がある人物だが、小島の筆致はあくまで冷静である。こうした筆致は、好き嫌いの分かれるところだろう。松永が電力王になるまでの経緯もかなり変わっている(正確には、この部分が本書の大部分を占めている)。いかにも明治から昭和にかけての立志伝である。この手の評伝が好きな人にはお奨めの本といえる。福沢諭吉や福沢桃介、小林一三、益田孝といった登場人物も、松永の人生に彩をそえている。
ただ、何といっても690ページで2段組は少々長い。小島の筆も淡々としているので、わくわくして一気に読み進むといった本ではない。終わりのほうの筆が妙に乱れていると感じるのは筆者だけだろうか。 |
| |
| ジャーナリズムの条件2:報道不信の構造
徳山喜雄責任編集、岩波書店、p.221、\2500 |
2005.4.27
|
|
 |
| 報道被害、マスコミと政官界との癒着(記者クラブ制度の問題)、経済事件報道、ワイドショー的報道(田中真紀子と小泉純一郎が槍玉にあがっている)、戦争報道(イラク戦争や自己責任騒動)といった問題を、ジャーナリストの視点から見直した書。本来なら市井の側につくはずのジャーナリズムが市民から指弾されている現状に危機感をもって、その原因と解決策を探っている。新聞、雑誌、テレビの現場からのメッセージを集めた、なかなかの力作である。執筆陣には、蟹瀬誠一、山田厚史、歳川隆雄、須田慎一郎、小谷真生子、玉木明といった名前が並ぶ。当たり前といえば当たり前だが、小谷真生子の筆力のなさが際立っている。ビジュアルのない文章だけだと、観念が先走った平板さが妙に目立つ。テレビの人だけに、こうした面子が並ぶとちょっと気の毒である。
本書の冒頭にある徳山喜雄(責任編集者)の「公共性の倫理」は出色の出来である。よく主張がまとまっており、この章を読むだけでも価値がある(一般の人にとって、2500円に見合うかといえば疑問だが・・・)。最近のジャーナリズムの危機を、情報機器の発展、記者の質の低下(志の低下)、人材の流動性といったところに原因を見ている。マスコミ側の脇の甘さも指摘する。いずれも、なかなか説得力のある視点である。徳山の部分以外にも、実名報道、少年事件の扱い、死体の写真の掲載に関する判断基準など、この商売をやっていると参考になる話が数多く出ている。 |
| |
| On intelligence
Jeff Hawkins,Sandra Blakeslee、Times Books、p.261、$25 |
2005.4.23
|
|
 |
| 脳科学とコンピュータ・サイエンスを扱った書。筆者は携帯情報端末としては定番であり、評者もかつて持っていたPalm生みの親、現在もpalmOneのCTOである。このシリコンバレーの成功者が、学生時代から興味を持っており、インテル入社後は通信教育で勉強し、Palmで成功を収めた後に研究所まで作ってしまった脳科学について、新しい知見と持論を自信満々に書いている。米国のコンピュータ・サイエンスの懐の深さを感じさせる。専門用語も入っているので、ちょっと読みづらい面もある。最近の原書の傾向だが、本書も英語で一生懸命読んでいるうちに翻訳本が出てしまった(ランダムハウス刊)・・・・。ただし翻訳本には存在しないオマケが原書にはついている。参考文献と著者の理論を検証するための仮説である。
本書から感じるのは、技術者らしい楽観と米国人らしい起業家精神である。筆者は、これまでの人工知能のアプローチは根本的に間違っていたと主張する。いくらプロセッサの性能が高まり、メモリーの容量が増えても、いまの理論の延長では人間の知能や理解のレベルには、到底達しないと語る。一方、大脳新皮質の「記憶」と「予測」の機能に関する理論を現在の技術で展開すれば、人間を超える能力をもつマシンを実現できるという、これまた楽観的な理論を展開する。ここまでくると、マシンが人間を支配するといった懸念が頭をかすめるが、技術の向上が生活の向上につながると主張している。
本書の主題は脳科学だが、Palmに組み込んだ手書き認識「グラフィティ」に関する開発方針など、ユニークな思考法が各所にちりばめられている。いずれにせよ、知的好奇心を満たしてくれる本である。 |
| |
| 人材は「不良社員」からさがせ〜画期的プロジェクトの奥義〜
天外伺朗、講談社ブルーバックス、\580、p.202 |
2005.4.22
|
|
 |
| 1988年初版ととても古い本で、もはや絶版である。天外伺朗氏と会うときの参考文献として読んだもの。本書の中核は、ソニーが開発した32ビット・ワークステーション「NEWS(ニューズ)」の開発物語。当時、格段に低価格で、BSD版のUNIXを搭載したマシンは、きわめてエポック・メイキングな存在だったことを記憶している方も、少なくないのではないだろうか。ただNEWSはしばらく快進撃を続けたものの、さほど長続きはしなかったのは残念である。NEWS開発メンバーのその後を追う企画も個人的にはとても興味がある。
本書はNEWSだけでなく、CDや最近ならロボットといった斬新な開発を数々手がけた天外伺朗が、技術者として、またマネージャとしての心得を綴っている。同時に大企業病に罹った(もの作りではなく、マネジメントが仕事になってしまった)ソニーの病巣を鋭く突いている。20年近く前の本だが、ちっとも古さを感じさせないユニークな本である。いまや超能力や“あの世”についての著述で有名な天外氏だが、こういったマネージャ論もなかなかいい。もっとも、どれだけ警鐘を鳴らしても日本企業には暖簾に腕押しで、上を見てしか仕事をしない“いい子ちゃん社員”を排出している状況に、マネージャ論を展開することに嫌気がさしているのかもしれないが・・・・。 |
| |
| 国家の罠〜外務省のラスプーチンと呼ばれて〜
佐藤優、新潮社、\1600、p.398 |
2005.4.20
|
|
 |
| 佐藤優といっても誰だか分からない。「ロシア絡みで鈴木宗男と不正を働いたと、マスコミに書き立てられた外交官」というと分かりやすいかもしれない。「背任」と「偽計業務妨害」容疑で逮捕され、東京拘置所で512日の勾留生活をおくり、第一審で懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決を受けている。ふてぶてしく見える風貌も影響されたのだろが、とにかく大悪人に仕立て上げられた当の本人が、数々の内幕を綴っている。ほとんど全ての人間が実名で出ている。拘置所での日々、鈴木宗男のこと、田中真紀子のこと、外務省の上司・同僚、検察官との交流、なにせ実名なので迫力満点である。とりわけ検察官とのやりとりは驚きの内容。ちょっと驚かされる。自己弁護と感じる記述もあるが、鈴木宗男事件の裏側を知る上で有用な書といえる。 |
| |
| 獄窓記
山本譲司、ポプラ社、p.391、\1500 |
2005.4.3
|
|
 |
| なぜか連続してポプラ社になってしまった。このところポプラ社の本を読むことが多くなった。すぐれた編集者が育ったのか、あるいは引き抜いたのだろうか。ちょっと気になる。「Good Luck」の装丁をした人の話はどこかで聞いたことがあるが・・・・
本書は、秘書給与詐取事件で実刑判決を受け服役した衆議院議員・山本譲司氏による獄中記。出版されたのは知っていたし、本屋でもよく見かけていたが、これまでさほど興味をひかれなかった。謝罪にかこつけた、自慢話あるいは再起決意の表明と勝手に思い込んでいた。福祉関係の本で中身を紹介されていたこともあり手に取った。確かに日本の福祉について考えさせられる内容になっている。刑務所に入らないと、国会議員でさえ知る術がないということ自体が大きな問題といえる。
本の帯を見ると、TBSでドラマ化とある。出演者の一人が、「こんなにも涙した本はない」とコメントを寄せているが、これは言いすぎ。ホロッとくる場面もあるが、お涙頂戴といった本ではない。むしろ淡々とそして率直に、刑務所の様子、規則、看守、受刑者たちを描写している。妙に難しい熟語を使うところは閉口するが、読みやすい文章である。堀の外からはうかがい知れない状況を知る上では、妙に大向こう受けをねらったものないだけ貴重だろう。
このほか、秘書給与詐称事件の当事者側の言い分として読んでも興味深い。意外に知らなかったり、忘れてしまっていることが多い。マスコミに対する痛烈な批判も随所に含まれている。ありがちな批判だが、耳の痛い指摘ではある。 |
| |
|
|

|
| 2005年3月
|
| 私にとってオウムとは何だったのか
早川紀代秀、川村邦光、ポプラ社、p.339、\1600 |
2005.3.30 |
|
 |
| 今年は地下鉄サリン時間から10年。当時、丸の内線を使って通勤していたが、事件当日の東京駅で聞いた、「臨時に霞が駅を通過しています」とのアナウンスが今でも思い出される。
オウム事件は実に不可思議である。なぜ教養の高い人たちが、松本千津夫(麻原彰晃)に帰依するようになったのか、容易には理解できない。おかげで書棚の1段を、オウム関係が占めるようになった。本書は、坂本弁護士殺害事件などの関与し、死刑判決(控訴中)を受け獄中にいる早川紀代秀が、自らの半生とオウムとのかかわり、そして数々の事件を率直に綴った手記。オウム関連の当事者の書いた本としては、林郁夫の「オウムと私」くらいなので、貴重な書籍といえる。書き口は実にストレートである。
早川は神戸大学農学部を卒業して鴻池組に就職し、将来を嘱望されていたもののオウムに出家した。このあたりはヨーガの教室にでも参加するような気軽さを感じさせる。その後、急速に松本千津夫への帰依を深めていたのだが、ここらの過程は本書を読んでもよく分からない。当時の状況をストレートに書いており、後から当時を振り返って分析するという形をとっていない。そのため、いまだに松本千津夫の呪縛が解けていないような印象さえ受ける。逆に呪縛が徐々に解けていく様子もよくわかる。もっとも、あまりにも単純な話で拍子抜けする。
後半は宗教学者で、早川の公判で弁護側の証人を務めた川村邦光が、早川の手記を分析する。最初の部分は無駄のようにも思えるが、意外に読ませる内容になっている。 |
| |
| 坂の上の雲(3)
司馬遼太郎、文芸春秋、p.361、\590 |
2005.3.26 |
|
 |
| 今年5月27日で日本海海戦100周年である。これに触発されて読み始めた「坂の上の雲」。風呂でゆっくり読んでいることもあって、やっと3巻目を読了。少し盛り上がってきた。日本海海戦については、何と専門のWebページまで存在する。このサイト、ちょっと面白い。世間的には認知度は低いが、地元(?)横須賀ではそれなりに盛り上がっているようだ。
第3巻では日露戦争の緒戦を扱っている。日本海海戦はまだだが、遼東半島をめぐる海戦までが対象だが、今後の展開を期待させる内容になっている。本書の主人公である秋山好古・真之兄弟や東郷平八郎、さらにはロシアの将軍たちの人物描写はさすがに魅力的である(もちろん、こうした司馬史観に好き嫌いはあるだろう)。日本軍の将軍たちは、陸軍、海軍を問わず、実に論理的で科学的な思考で戦いを進めている。「失敗の本質〜日本軍の組織的研究〜」で戸部良一氏らが分析した日本軍の有り様とは随分ちがう。ただし司馬遼太郎は、その萌芽を本書のところどころで指摘している。ここらも読みどころだろう。 |
| |
| 自閉症裁判〜レッサーパンダ帽男の「罪と罰」〜
洋泉社、p.318、\2200 |
2005.3.25 |
|
 |
| レッサーパンダ帽をかぶった男が、浅草で女子短大生を刺殺した事件を覚えている方は多いだろう。その背景と裁判を4年をかけて追った書。もう遠い記憶になってしまっている「浅草通り魔殺人事件」が、なぜノンフクションとして成立しているのか。それは加害者が自閉症(裁判では認めていない)だったからである。自閉症の加害者に対する取調べと裁判が、自閉症に対する無理解もあって、適切ではないというのが、本書の主張である。ちなみに本書は、自閉症の加害者を裁判で初めて扱ったリーディング・ケースとこの裁判を呼んでいる。
恥ずかしながら、加害者が東京の建築現場で逮捕されて以降、この事件についての記憶は筆者にはない。新聞や雑誌の記事を読んだ記憶もない。裁判がどのように進められ、何が争点になっていたのか、寡聞にして知らない。熱しやすく冷めやすい悪癖(筆者だけではないが)が出たわけだが、そういった欠けた部分を補うという意味で、本書のようなノンフクションは貴重な存在である。それにしても、加害者が自閉症だったということや、養護学校出身だったということを、どれくらいの人が知っているのだろうか。その謎解きも本書ではなされている。
自閉症の加害者への取調べがどれだけ難しいものなのか、その証拠としての正当性の問題点、そして警察や検察からの情報に頼る面が多いマスコミの報道の問題点を、本書は取り上げる。法廷における医学者同士の論戦などを読むと、専門家の中でも自閉症に対する見解が定まっていないように見える。これなども含め、貴重な情報が含まれた本といえる。勉強になる。それにしても加害者男性が育った家庭環境の悲惨さには言葉を失うし、被害者女性の家族の発言には胸が詰まる想いがする。 |
| |
| 坂の上の雲(2)
司馬遼太郎、文芸春秋、\590、p.413 |
2005.2.5 |
|
 |
| 秋山好古/真之兄弟と正岡子規を軸に明治の群像を活写する歴史小説の2冊目。2巻は日清戦争から日露戦争前までを描く。1巻は立ち上がりとあってイマイチ盛り上がらなかったが、日清戦争が出てくることもあり、2巻に入ってちょっと調子が出てきた感じだ。司馬遼太郎の歴史小説は、日本史の教科書を裏側から読む楽しさがある。歴史上の人物が語る、数々の警句も色取り添えてくれる。 |
| |
| 坂の上の雲(1)
司馬遼太郎、文芸春秋、\590、p.351 |
2005.2.1 |
|
 |
| 昨年末の週刊文春の歴史小説ランキングで、1位になったのが本書「坂の上の雲」。日露戦争で活躍する秋山好古と秋山真之の兄弟、同じ愛媛出身の俳人・正岡子規を軸に明治の群像を描く長編歴史小説で、全8巻からなる。久々の司馬遼太郎だが、正直な話、思ったよりも盛り上がらない。昔読んだときは,もう少しワクワクした記憶があるのだが・・・。8巻の長編ということが影響しているのかもしれない。1日の終わりに風呂の中で読むことにしたので、いつになったら読み終わるか分からない。1冊ずつレビューを書くのも妙だが、1冊ずつレビューを書くことにする。1冊目は、登場人物の紹介と、周辺状況の解説に終始していることもあり、少々退屈だった。 |
| |
| 戦争請負会社
P.W.シンガー著、山崎淳、NHK出版、\2500、p.485 |
2005.3.20 |
|
 |
| 2003年に読んだ「戦争広告代理店」(高木徹著、講談社)を、さらに一歩進めたような書。戦争広告代理店もインパクトに強い本だったが、本書「戦争請負会社」はそれを上回る。翻訳も悪くないので、スイスイ読める。戦争請負会社の著者はNHK社員だったと記憶するが、本書の発行元はNHK出版。何か関係があるのだろうか。ちょっと不思議。
平和ボケといわれる日本にいると、「傭兵」というのは映画に出てくるような存在。戦争で兵士が持つ法的保護を、傭兵には認めないという国際条約(ジュネーブ条約)があるのは本書で初めて知った。本書が扱う戦争請負会社は、この傭兵を派遣する民間会社を発展させた形態である。単なる傭兵の派遣だけではなく、情報システムの構築、企画立案、コンサルティングなど、戦争に絡むもろもろを請け負っている(とりわけITは民間の支援が不可欠という話には納得)。チェイニー米副大統領がトップだった米ハリバートン社の話も出てくる。ハリバートン社は、イラク戦争で何度も取り上げられているので覚えている方も多いだろう。このほか戦争請負会社を何社か詳細に紹介しているが、この部分が少々退屈な感じを与える。
いずれにせよ、戦争請負会社の実態は驚くべきものだ。冷戦の終焉で世界の秩序が崩壊し、「安全保障の空白」を生み出した。そこを民間市場が埋めた格好である。本書を読むと、国家の専任事項だった戦争というものが、いかに“民営化”されているかがよく分かる。たとえば兵器。冷戦構造の崩壊で、どっと兵器が市場に出た。鶏一羽の値段で小銃を購入できたり、最新の戦車がRVよりも安く買えたりする実態を著者は明らかにする。こうなると、軍事行動、テロ活動のもととなる兵器を政府や国際機関が支配・制御できなくなってしまう。軍事能力を増強するには時間をかけざるを得なかったものが、いまや金さえ払えば一足飛びに最新の装備をもつ軍事力を備えることも可能になった。
国家の側にも、大きな問題があると指摘する。民間企業を隠れ蓑に(議会の了承・国民の監視もなしに)、国家の意思が遂行されている事実を明らかにする。例えば人権保護がなされておらず、米国の軍事援助を受ける資格のない国が、民間企業によって軍事支援を受けるさまを紹介する。考えさせられる1冊である。 |
| |
| 考える一族〜カシオ四兄弟・先端技術の航跡〜
内橋克人、岩波書店、\900、p.271 |
2005.3.13 |
|
 |
| カシオ計算機の樫尾忠雄・俊雄・和雄・行雄の四兄弟を追ったノンフィクション。主役は発明家の俊雄だが、それをサポートして会社を盛り立てていく兄弟・両親の様子が描かれている。内橋克人氏が得意とする技術分野の評伝だが、今となっては古さを感じさせられる内容である。その昔、「匠の時代」など興味深く読んだ記憶があるが、本書は散漫な感じで、今一歩のりが悪い。もちろん読む側の問題も大きい。匠の時代を読んでいたのは、商売として物書きになる前。大きな枠組みで見れば、いまや同業。感想が厳しくなるのは仕方ない。もう少しディテールを書き込んでいれば、ぐんと面白い本になったと思うと少し残念である。
謙虚な立場で見ると、個々のエピソードは、現在では忘れ去られた事実を掘り起こすようで、なかなか興味深い。コンピュータ(計算機)の黎明期を振り返る上では非常に有用な本である。発明家の面目躍如ともいえる、樫尾俊雄の「考える」ことへの姿勢は実に興味深い。最後の部分に「ADPS(自動事務情報処理装置)」が登場するが、この発表会に出た記憶がある。摩訶不思議な機械だったが、今になると懐かしい。 |
| |
| 密約〜外務省機密漏洩事件〜
澤地久枝、中央公論社、\320、p.271 |
2005.3.10 |
|
 |
| 便利な時代になったものだ。「職業としてのジャーナリスト」を読んで読みたくなった本。Amazon.comで検索をかけると、すでに絶版。ユーズド本(中古本)で売られていると表示される。少し前まで中古本の品揃えはイマイチだったと記憶しているが、このところ充実の度を増しているようだ。出品があることが判明。元々は320円の文庫本だが、1800円の値付けがされていた。さっそく購入。この仕組みがなければ中古本の入手は簡単にあきらめていたところ。今更ながら、インターネットの凄さ・便利さに感じ入る。
本書は、日本のジャーナリズム史上の大事件になった、沖縄返還における日米密約の秘密文書漏洩(漏洩とは官側の視点だが・・・)事件を、裁判の傍聴を基に詳細に追ったもの。報道の自由や国民の知る権利という争点が、「情を通じた」という一文でもみくちゃになった事件である。本人へのこそ取材はないが、裁判の傍聴、新聞・雑誌・テレビの報道を絡めることで、周辺状況が実によく分かる仕掛けになっている。澤地久枝の駆け出しの頃の作品と合って、ちょっと力みすぎのところがあるのはご愛嬌。事件自体はさまざまな本が扱っていることもあり知っていたが、登場人物(毎日新聞の西山記者、外務省の蓮見事務官)のデテールを知ったのは本書が初めて。かなり抱いていたイメージとは異なっている。ちなみに読売新聞のナベツネこと渡辺恒雄が、意外なところで登場しており、ちょっと驚かされる。少なくとも渡辺恒雄がジャーナリストとしての矜持をもっていたことが分かる。 |
| |
| ジャーナリズムの条件(1):職業としてのジャーナリスト
筑紫哲也 責任編集、岩波書店、\2500、p.258 |
2005.3.5 |
|
 |
| 筑紫哲也、佐野真一、野中章弘、徳山喜雄が編集委員を務めるシリーズ企画「ジャーナリズムの条件」の第1弾。すでに2巻目が出ている。ジャーナリストというのは何者なのか、どういった職業なのかを説いた本。本のカバーの説明にもあるが、商業主義化(金儲け化)が著しく、ジャーナリストとしての矜持が失われた報道機関への危機感が、このシリーズ企画の背景にある。
もう一つの危機感は、(筑紫哲也が序文に書いているが)ジャーナリストという職業には資格も免許もない。極端に言うと、自ら宣言すればなれる職業である。しかも敷居はぐんと低くなっている。インターネットを使えば、「ジャーナリストをやる」ことは誰でも十分可能だ。実際、米国ではブロガーはジャーナリストか、そして取材ソースの秘匿が認められるのかが問題になっている。結局、真のジャーナリストと偽のジャーナリストは、そのアウトプット(記事)でしか測れない。本書の執筆陣は、そういう意味で優れたアウトプットを出した人たちといえる(寡聞にして知らなかった人も多い)。編集委員の価値観が反映しているのは言うまでもない。
本書は、新聞・雑誌・テレビと活躍の場を変えてきた筑紫哲也の総論のあと、ジャーナリストたちが語るスクープの裏側が続く。執筆者とテーマの選定に岩波書店の価値観が漂うが、それなりに読み応えがある。テーマは、防衛庁リスト問題や外務省機密漏洩事件、水俣病報道、週刊文春回収騒動など。リアルタイムでは見落としていたり、フォローの取材があってこそ明らかになった事実が出ているなど、なかなか勉強になる。出色なのは、石澤靖治のマスコミに対する企業買収の記事。米国の三大ネットワークに対するM&Aの経緯を描く。マスコミ側が対応を読むと、フジテレビとライブドアの騒動が二重写しになる。 |
| |
| 人は仕事で磨かれる
丹羽宇一郎、文芸春秋、\1300、p.221 |
2005.3.3 |
|
 |
| 伊藤忠商事会長の丹羽宇一郎氏が書き下ろした書。前半と自伝的な後半から成る。後半の自伝部分は、「日経新聞の私の履歴書は書くつもりはない」という意思表明だろうか。あるいは文芸春秋の担当者の対抗意識の表れだろうか。ユニークな経営者として名をはせた丹羽氏くらいになると、いずれ「私の履歴書はどうですか?」といった誘いが来るようにも感じるのは私だけだろうか。まあ、そんなものは期待しないと言いそうな人ではあるが・・・。
伊藤忠社長時代は、4000億円の不良債権を一括処理したり、社長になっても電車通勤したり、社長就任時に明言した2期6年で社長をやめたり、いろいろ話題を呼んだ。とにかく、その行動と言動が気になる社長だった。日経ビジネスにコラムを定期的に寄稿していたが、なかなか読み応えがあったこともあり、本書を早々に購入した。前半部分は丹羽氏の人生の美学がよく出ており、何を経営判断の基準にしていたかが分かる。商社というと生き馬の目を抜く、金・カネとなりがちだが、その愚かさ加減や陳腐さ、前時代性を説いている。いずれにせよ、共感の持てる美学である。後半の自伝部分は、筆者の“変人ぶり”が全開といった感じで、よく出ている。自惚れや自慢などが入り混じった不思議な自伝である。帯に清廉・異能・決断力とあるが、いずれにせよ丹羽宇一郎という一本筋の通った(しかも、頑強な筋である)、人物の美学が色濃く出た本である。 |
| |
|
|

|
| 2005年2月
|
| 親の「ぼけ」に気づいたら
斎藤正彦、文芸春秋、\750、p.259 |
2005.2.27
|
|
 |
| 「自分の物忘れのひどさに暗澹とすることもありが、やはり心配は老親がボケるのではないか」という方も多いのではないだろうか。そういう人にピッタリの本である。実にいい本である。新書なので、すぐに手軽に読めるところもいい。著者は慶友病院の副院長。痴呆性疾患について、初期の症状、医療機関の探し方、当人を受診させる説得の仕方、治療法の実際、症状の進み方、失禁や徘徊への対処法といった内容を盛り込んでいる。アルツハイマーなどの痴呆性疾患といった症状について、具体的なエピソード(実例に基づいた架空の話)を紹介しながら、実に分かりやすく説いている。早め早めの対処によって、改善することも進行を遅らせることができると説く。素人のあさはかな判断への警鐘をならした部分なども参考になる。この手の本としては出色の出来である。親の痴呆を話題にした本だが、自らのボケ具合、自らの行く末を知る上でも、打ってつけの本である。最後には情報源に関する章も設けており、役立つ。 |
| |
| 日本の優秀企業研究〜企業経営の原点
新原浩朗、日本経済新聞、\1800、p.319 |
2005.2.24
|
|
 |
| セミナー講師として登場してもらい世話になった経済産業省の新原浩朗氏の書。トヨタ、キヤノン、ソニーといった日本の優良企業が「優良」と呼ばれる本質は何なのかを分析している。特徴は、公表された資料や調査データをかき集めて「一丁あがり」とするのではなく、インタビューに基づいている点。名前を出さないことを前提に取材しているのは残念だが、足で稼いだ成果物であるのは確かである。その成果の一端が、世間的通念として考えられている優秀企業像が、実態とは異なることを明示しているところである。
著者は優秀企業の条件を六つ挙げている。(1)分からない事業をやらない、(2)自分の頭で考えて考えて考え抜くこと、(3)客観的に眺め不合理な点を見つけられること、(4)危機を持って企業のチャンスに転化すること、(5)身の丈にあった成長を図り、事業リスクを直視すること、(6)世のため、人のためという自発性の企業文化を埋め込んでいること、である。そこここに、示唆に富む指摘が数多く出てくる。実に読み応えのある書となっている。それにしても、IT系の企業が1社も登場しないには、現実として仕方がないのかもしれないが、あまりに寂しい気がする。残念。いずれしても、具体例がふんだんに出ているので、わが身/わが会社をふり返り比較してみるといいかもしれない。当然、相手は日本の優良企業なので、彼我の差にガックリくるかもしれないが・・・。 |
| |
| 希望格差社会
山田昌弘、筑摩書房、\1900、p.254 |
2005.2.22
|
|
 |
| タイトル通りの本である。玄田有史の「ニート」や橘木俊詔の「日本の経済格差」、佐藤俊樹の「不平等社会日本」といった、この書評欄で取り上げた書籍と通じるところがある。本書を一言でいえば、村上龍が「希望の国のエクソダス」で書いた有名な言葉「日本には何でもあるけど、希望だけがない」というテーマを、データに基づいて定量的に証明した書となる。論考の対象は、職業、家庭、教育である。著者が一貫して書いているのが、「自分の将来の見通しが立たないから将来について考えない、将来について考えないから見通しがますますたたなくなる。このような悪循環に若者がはまりつつある」という点である。ちなみに本書のサイブタイトルは、「『負け組』の絶望感が日本を引き裂く」。何とも救いようのないタイトルだが、本書の内容を正確に表しているといえる。悲観的に描かれる日本と対比して語られるのが、高度成長期の日本の姿である。ただ筆者は、昔を懐かしみ、変化を拒絶する動きを「ネオ・ラッダイト(機械打ちこわし)運動」と位置づけ警鐘を鳴らす。
東京学芸大教育学部の先生らしく、引用は豊富で正確。ちょっと食指の動く本の紹介もあるので役立つ。なお、日経BP社のITProの名物コラム『記者の眼』欄に「希望なき繁忙なのか」という記事を先日書いた。本書を読む前に書いた記事だったが、通底する部分が少なくない。読後ならもう少し深みのある記事にできたかもしれなかった・・・・。少々残念。
|
| |
| トヨタシステムの原点〜キーパーソンが語る起源と進化
下川浩一、藤本隆宏編著、文眞堂、\2500、p.231 |
推薦!2005.2.20
|
|
 |
| 実に面白い本である。世の中にトヨタ本は多いが、本書を併せて読むと理解が進むだろう。久々に出会った良書である。本書の特徴は、トヨタシステムを作り上げた“歴史上”の人物へのインタビューで構成したところ。終章で編著者が、「生の声」を集めることで、トヨタシステムを生成してきた過程における「混沌」と「多様性」を示そうとしたと語っているが、その意図は成功している。有名な大野耐一氏のほか、豊田英二氏ら6人がインタビューで登場する。あまりに現場に近い人のインタビューは、内容がディープすぎて分かりにくいところもあるが、エンジニアにとっては得がたい情報だろう。豊田英二氏へのインタビューはミスキャスト気味だが、押さえとして必要だということだろうか。
本書で何よりも面白いのは、いまや有り難く奉るような「トヨタシステム」が、どのような試行錯誤、失敗を経ながら完成したかがよく分かる構成になっているところ。神様ともいわれる大野耐一氏の話など、へ〜っ感心させられるところが多い。現場を見ることに大切さを改めて知らされる。かなり個性的な面々が「試行錯誤」「紆余曲折」「怪我の功名」「瓢箪から駒」「意見の不一致」といった混沌とした状態から、きわめて合理的なシステムを生成したプロセスが、口述によって描かれている。トヨタシステムを形だけを導入してもダメというのがよく分かる。。トヨタ自動車の社長である張富士夫氏の英語の技術論文という珍しいものも収録されている。ちなみに張氏は、帯に献辞を書いている。 |
| |
|
|

|
| 2005年1月
|
| 検証:日本の組織ジャーナリズム〜NHKと朝日新聞〜
川崎泰資、柴田鉄治、岩波書店、\2200、p.221 |
2005.1.29 |
|
 |
| 典型的な日本の組織ジャーナリズムとしてNHKと朝日新聞を取り上げ、OBの大学教授が批判を加えた書。NHKと朝日新聞以外のマスコミについても、創価学会のマスコミへの圧力、意に染まない結果が出ると報道されない恣意的な世論調査、意義が見えないまま暴走する地上デジタル放送といった問題に批判の矛先を向けている。いずれも手際よくまとめられているので、ジャーナリズムに関心のある人にとって読み応えがある出来栄えといえる。
出版されたのは昨年暮れ。NHKと朝日新聞が番組改変問題で対立する前である。改変問題については、政治家に関する話を抜きに本書でも取り上げている。NHKと朝日新聞が対立するいま、実にタイムリに書店に並ぶことになった。その昔(大学生の頃と記憶しているが)、福田恒存などの主導によって新聞批判が展開されたことがあった。当時の論点は「偏向」だったが、本書が問題視するのはそれ以前の問題。偏向するも何も、本来報道すべきものを避けて知る権利を無視する、ジャーナリズム精神が衰えた企業体質を指摘する。とりわけNHKに向ける目が厳しい。 |
| |
| 知能の謎〜知能発達ロボティクスの挑戦
けいはんな社会的知能発生学研究会、講談社ブルーバックス、¥1029、p.273 |
2005.1.22 |
|
 |
| ロボットを研究することによって、「人間とは何か」「知能とは何か」に迫ろうという知能発達ロボティクスの研究プロジェクトを扱った書。SF作家の瀬名秀明やロボットの研究者として有名な阪大の浅田稔などが執筆している。知能を探るのにコンピュータではなくロボットを使うのは、後者のほうが環境に積極的に関与でき、逆に環境によって変化できるから。社会的な相互作用のなかで社会性を持った知能が発達してくる過程と原理を解明するというのが、知能発達ロボティクス研究者の目的である。学習・発達するロボットを設計する上で赤ちゃんの研究から得るものが多く、逆に発達メカニズムを知る上でろぼっとを用いたモデル構築が有効だという。
学生時代にロボットと関わりのある研究室に在籍し、就職してからもロボットを身近に見ていたのでロボットは非常に気になる存在。興味深々で読み始めたが、正直言って哲学的で少々難解である。気軽に読める本ではない。 |
| |
| ドラッカー選書<2>創造する経営者
P.F.ドラッカー、ダイヤモンド社、\1650、p.329 |
2005.1.19 |
|
 |
| 体系的にドラッガーを読む第2弾。原題は「Managing
for Results」で、このままタイトルをつけるとしたら「結果を生むマネジメント」という感じだろう。当然のことながら、内容は原題に近い。むしろ日本のタイトルが頭にあると、内容とのあいだにギャップを感じることになる。よく考えると当たり前の指摘が並ぶが、ドラッカーの手にかかると何となく有り難く思えてくる。語り口は平易だし、例によって豊富な事例が挙げられている。分かりやすいうえに、説得力と警句に富む。特筆すべきは、製品の分析を扱った部分である。本書では11種類に分類し、企業が陥りやすい判断ミスを的確に突いている。身につまされる指摘も多く、自らに投影して読むといいだろう。
本書でドラッカーがとりわけ強調しているのは、「成果を早くあげること」である(タイトルと整合性がとれている)。理想企業の実現のための最善の方法を指摘する部分を読むと、米国流の経営に通底する考え方がそこには感じられる。そのほか「イノベーション」についてのドラッカー流の定義やリスクについての正しい考え方など、読みどころ満載の本である。 |
| |
| 創価学会
島田浩巳、新潮新書、\680、p.191 |
2005.1.10
|
|
 |
| 宗教学者の島田裕巳による創価学会を客観的(?)にとらえた書。政権党になっている公明党の出身母体だけに、創価学会の動向は気になるところ。本書が出版された背景にもこれがある。創価学会の歴史から体質などを、史料をもとに解き明かしている。創価学会と大論争している新潮社の新書だけに、本当に客観的だろうかという思いで読み始めた。最初のうちは、「やっぱり」といった記述もあるが、後半に行くにしたがいバランスのとれたものになっている(創価学会の人は違う思いを持つのかもしれないが・・・)。池田大作氏に対する評価などバランスがとれた記述である。週刊新潮のグループと新書のグループで、ちゃんとファイアウォールが築かれているところは、さすが大出版社である。児玉隆也や松本清張、内藤国男、田原総一郎といった面々が、池田大作氏にインタビューしていたというのは興味深い。各氏の池田氏への感想というのも、これまた面白い。ちなみに松本清張が、共産党と公明党の歴史的和解に動いた理由は、このインタビューにあるというのも興味深い。 |
| |
| 日本のもの造り哲学
藤本隆宏、日本経済新聞社、\1600、p.347 |
2005.1.5
|
|
 |
| 能力構築競争(中公新書)など、このところ話題の書を立て続けに出している、ものづくり経営研究センター長を務める東京大学大学院教授・藤本隆宏氏の本。自動車産業の分析を得意とする藤本だけに、トヨタをはじめとする自動車産業の話が中心だが、電機産業や半導体産業などにも言及している。組み込みソフトウエアの話もところどころに出てくる。日経新聞の書評欄で2004年の経済書ナンバーワンに選ばれている。確かに、選ばれただけのことはある。なかなか得るところの多い本である。藤本は「もの造り」を、「擦り合わせアーキテクチャ(インテグラル型)」と「組み合わせアーキテクチャ(モジュラー型)」に分けて考える。この分類から日本の強さ・弱さ、米国の強さ・弱さを分析する。なかなか的を射た指摘が多く、役に立つ。藤本の本をまとめて読んでみようかと、つい思ってしまう。 |
| |
|
|


|
横田英史(yokota@nikkeibp.co.jp)
|
| 1956年大阪生まれ。1980年京都大学工学部電気工学科卒。1982年京都大学工学研究科修了。
川崎重工業技術開発本部でのエンジニア経験を経て、1986年日経マグロウヒル(現日経BP社)に入社。
日経エレクトロニクス記者、同副編集長、BizIT(現IT Pro)編集長を経て、2001年11月日経コンピュータ編集長に就任。
2003年3月発行人を兼務。2004年11月、日経バイト発行人兼編集長。
記者時代の専門分野は、コンピュータ・アーキテクチャ、コンピュータ・ハードウエア、OS、ハードディスク装置、組み込み制御、知的財産権、環境問題など。
|
|
|
|