| イベント・リポート NO-15
Embedded System Conference(ESC)サンフランシスコ 2005、No-1
3月8日〜10日 at モスコーネ・センター
リポータ : EIS編集部 中村 |
|
 |
|
 |
|
| 会場となったモスコーネ・センターの入り口 |
昨年に続いて、北米における組込み業界最大のイベント、Embedded
System Conference(ESC)サンフランシスコ2005を訪問してきた。展示会場は昨年と同様、モスコーネ・センターの南ホール。昨年のESCサンフランシスコはドイツの総合電子部品展、「ELECTRONICA」の北米版、「ELECTRONICA
USA」との併設イベントであったが、今年はESCの単独開催となった。
|
|
全体的な印象
|
|
| 今年のESCはELECTRONICA USAとの併設が解消され、さらに同時期にドイツでDATEという、EDA/SoCデザイン関連のイベントが開催されていたこともあってか、出展社の数は昨年の約400社から約300社までに減少し、規模がかなり縮小された印象だった。来場者の数も主催者発表で約1万人と、日本のET2004などと比較すると半分以下。したがって、展示会場で大混雑したブースはなく、小さなブースで手持ち無沙汰にしている説明員も多く見かけられた。しかしながら、今年のESCには「Microprocessor
Summit」という、組み込み用プロセッサにフォーカスした新たなイベントが追加されたこともあって、各出展企業から印象に残る新製品の発表が数多くあった。また、定評のあるカンファレンス・プログラムも200セッション以上が実施され、このイベント自体としては今年も業界関係者に重要な役割を果たしていたようだ。 |
|
製品別で見ると、今年のESCでは、「Microprocessor
Summit」が開催された影響もあって、RTOSやLINUXなどよりも、最先端RISCプロセッサやDSP、複数のDSPとRISCを混載したマルチプロセッサ、RISC+FPGAのような複数のデバイス機能を集積化した新しいタイプのLSIの発表や展示が目立っていた。ソフトウェア開発環境でいえば、昨年までは「ちらほら」だった「Eclipse」の文字が、いたるところで見られたのも今年の特徴だった。また、米国でも日本と同じように組込みソフトウェアの品質改善、生産性向上、セキュリティ対策、設計管理手法などに対する関心が高いようで、これらのキーワードに対応したツールの展示が従来よりも増えたような気がした。アプリケーションでいえば、広い意味での「ワイヤレス」が今年のキーワードだったかもしれない。
以下、今年のESCの様子を2回に分けてリポートする。
|
|
|
もっとも大きなスペースを確保して出展した4社 |
|
|
 |
|
| 巨大な赤い壁がそびえていた
Wind River社のブース |
今年のESCサンフランシスコで会場入り口付近にもっとも大きなブースを構えていたのは、Wind River、メンター・グラフィックスのアクセラレイテッド・テクノロジー事業部、マイクロソフト、アナログ・デバイスの4社だ。これらの企業のブースは入り口から一列目に並んで配置されていた。まず、展示会場を入ってすぐに目に入ったのはWind
River社の奇抜なブースだ。今年の同社のブースは巨大な赤い色の壁に大型スクリーンを配置した構造で、その前で連日、動画を交えてVxWorks
6.0をベースにした統合開発環境などに関するプレゼンテーションを精力的に行っていた。この高い壁の赤い色は、最近同社が採用した新しいコーポレート・カラーのようだ。実は、今年のESCの出展社リストにWind
River社の名前は会期直前までなく、我々もいったんは不参加と判断していた。それだけに、同社が例年通りの規模で出展してきたことに主催者はホット胸をなでおろしたことであろう。 |
|
マイクロソフトのブースでは、Windows
CE 5.0のプレゼンテーションが行われ、Windows CEが組み込まれている機器などが展示されていた。
メンター・グラフィックスのアクセラレイテッド・テクノロジー事業部のブースでは、NuCleus RTOSを中心に各種ミドルウェア、Eclipse
v3.0に対応した統合開発環境のNuCleus EDGEの他、同社が北米支部を務めるTRON Projectの紹介も行われていた。同社のブースには、かつて同社の日本支社に勤務し、現在はアラバマの本社勤務になった吉田有里さんが、今年も元気な顔を見せていた。会期中、同社はNuCleus
EDGEによるPowerPCアーキテクチャに対するサポートなど、いくつかの重要なプレス発表も行い、今年も目立つ存在だった。
|
|
 |
|
 |
|
| マイクロソフト社のブース |
|
アクセラレイテッド・テクノロジーのブース |
|
|
 |
|
| アナログ・デバイス社のブースにあった
μClinuxによるBlackfinのサポートを
示すパネル
|
昨年に引き続いて大きなスペースで出展していたアナログ・デバセス(ADI)のブースは昨年ほどの派手さはなかったが、同社の戦略製品、Blackfin
に対するサード・パーティのベンダからの幅広いサポートを示す展示にかなりのスペースが割れていた。会期中にプレス関係者に届けられたニュースリリースには、上記のメンターグラフィックス・アクセラレータ・テクノロジー事業部やExpress
Logic社などのRTOSベンダベンダによるBlackfin に対するサポートに関する発表が多く含まれていた。Blackfinに対するサポートは、Linux陣営でも進んでいる。展示されていたパネルにはμClinuxによるサポートを示すものまであったのは、少し予想外だった。DSPとC言語、DSPとRTOS、DSPとLinux、少し前までは思い浮かばなかった関係がいまや常識化しつつあるようだ。ちなみに、昨年のアナログ・デバイセズ社のキャッチコピーは「LEADING」。今年は昨年のET2004のときと同じ「Like
never before」だった。 |
|
TI、Freescale、Cradle Technologiesから多彩な新製品の発表 |
|
アナログ・デバイスのブースを紹介したら、やはりDSP市場でNo1の地位にあるTexas
Instruments(TI)のブースにも触れなければならない。今年のTI社のブースは自社製品の展示に半分とパートナー企業のサポート製品の展示に半分が割り当てられていた。
|
|
|
|
 |
|
| TI社のサードパーティ・パビリオン |
今回のESC開催中でもっとも印象に残ったプレス発表のひとつが、TI社による65nmプロセス採用の次世代ワイヤレス・ディジタル・ベースバンド・プロセッサに関するものであった。最先端のnmプロセスをドライブしているのはRISCプロセッサやDSPではなく、FPGAだという印象を持っている人もいるかもしれないが、TIの今回の発表はこの思い込みを大きく変えさせるものでもあった。今回のTI社の発表で注目すべきことは、65nmプロセスで携帯電話の低消費電力要求に対応しているだけでなく、アナログ部の集積化も実現している点だろう。一般的にRF部などのアナログ回路は、プロセスが微細化するほど、素子間の整合やノイズ対策などで設計が困難になるといわれているからだ。この他、TI社からは、モータ制御などに使用するの内蔵PWMの分解能を大幅に向上させた新しい32ビット高速DSP、TMS320F280Xシリーズの発表も行われた。 |
|
|
一方、昨年のこのイベントには、まだ「モトローラ」の名前で出展していたFreesacle
Semiconductor社も大きなブースで出展していた。DSP市場で業界第2位の地位にある同社は、関連会社であるStarCoreの技術をベースにしたハードウェア診断機能搭載の新DSP、MSC7119
とMSC7118を発表し、PowerPCコアの通信用プロセッサ、PowerQUICCファミリでも、新たにパケット処理に最適なエンジンを搭載した新製品、PowerQUICC
Pro、MPC8360Eを発表していた。
出展ブースは確認できなかったが、過去2年間、日本のET(組み込み総合技術展)にも出展している米国のベンチャー企業、Cradle
Technologiesが、ESCに併設された「Microprocessor Summit」において複数の汎用RISCコアとDSPコアを1チップに集積したマルチ・プロセッサ・デバイスの新製品、CT3600ファミリを発表して大きな注目を集めていた。このデバイスは汎用RISCプロセッサを最大8個まで、32ビットのDSPコアを最大16個まで1チップ上に搭載し、16チャネルまでのリアルタイムMPEG-4信号を同時にエンコードすることができる。
このようないくつかの革新的なDSP搭載のマルチ・コア・プロセッサの発表と、多数のサード・ベンダによるDSPに対するサポートの表明は今年のESC
San Franciscoのハイライトのひとつだったということができる。
|
|
|
| 組込みシステムに浸透するFPGA―アクテルもARMコアのライセンスを取得 |
|
|
| FPGAは組込みシステムの分野ですでに重要な地位を占めるようになっているが、このイベントにもザイリンクスとアルテラの2大ベンダの他、ラティス・セミコンダクター、アクテル、アトメル、クイックロジックの各ベンダが揃って出展していた。FPGAはすでにロジックのみを集積した単純なデバイスから、プロセッサなどの機能を内蔵したシステム・レベルのソリューションを提供する段階に入っており、各社のブースでもソフト・コア、ハード・コアのプロセッサに対応した開発環境のデモやシステム・ソリューションを示すプレゼンテーションが盛んに行われていた。 |
|
 |
|
 |
|
| ザイリンクスのブースとプレゼンテーションの様子 |
|
|
|
| FPGAに関していえば、このイベントの開催に合わせて大きな発表がひとつあった。それは、アクテルがARMからARM7コアのライセンスを取得したというものであった。このニュースを知らされたのは、サンフランシスコに到着した月曜日の夜、ARM社がプレス関係者を招待して開催されたパーティ会場だった。この日の朝、流されたARMおよびアクテルのニュースリリースによれば、アクテルはARM7コアを「ソフトIP」としてユーザに提供するとある。ただし、「ソフトIP」といっても実際にはRTLのソース・コードで提供されるはずはなく、暗号化されたネットリリストで提供されるものと考えられる。 |
|
 |
|
| ARMとの提携を発表して注目された
アクテルのブース |
アクテルが供給するFLASHベースのFPGAには構成データを暗号化して保持できる機能があり、ARMはここに心を雨後されたのかもしれない。アクテルの担当者によれば、ARM7コアはまず最近発表された、ProASIC3/Eで使用可能になる予定だとのこと。FPGA上でARMコアが使用できるのは、ARM922Tをハード・マクロで搭載しているアルテラのExcaliburに次いで2番目となるが、アクテルが言う「ソフトIP」としてのARM7コアがハードIPの場合と比較してどのような柔軟性や利点を持つようになるのか注目したい。
|
|
| アトメルとSTマイクロが近くFPGA+RISC混載デバイスを提供 |
|
AVRマイコンの供給者としても知られるアトメル社は以前から自社のFPGAとAVRマイコンを同一チップに搭載したField
Programmable System Level Integrated Circuits (FPSLIC)と呼ばれるデバイスを提供しているが、同社はこのFPSLICをさらに進化させたFPGA搭載の「リコンフィギュラブル・プロセッサ」を開発中であることを明らかにした。同社は、ESCでチェコの国立科学アカデミー、Academy's
Institute of Information Theory and Automation (UTIA)と英国のセロクシカ社と共同でこの次世代デバイスに対応した設計ツールを開発中であることを発表した。アトメル社のブースでは開発を担当しているアトメルのブースではUTIAの担当者も説明にあたっていたが、C言語での開発が可能になるこのデバイスは今年半ばには正式発表される見込みだ。 |
|
一方、STマイクロエレクトニクス社(STM)もARM9プロセッサ、16MビットのエンベデッドDRAM、多様なペリフェラル・インタフェース、エンベデッドFPGAブロックを1チップに集積したワイヤレス基地局用コントローラ、STW21000-GreenFIELDを発表し、ESCのプレス・ルームでも大きな注目を集めていた。エンベデッドFPGAのブロックは4,000個のLUTに相当する集積度のようで、この部分はフランスのIPプロバイダ、M2000社からライセンスした。このデバイスは130nmのCMOSプロセスで製造され、量産価格が25ドルというから、既存のFPGAベンダにとっても大きな脅威になるかもしれない。ただし、STM社のブースには、このGreenFIELDに関する展示は見当たらず、ブースに立っていた説明員もこのデバイスのことを理解していなかった。ところで、STM社には、Lattice
Semiconductorの創業者だった、Rahul Sud 氏が在籍しており、スイスを拠点にしてFPGAの開発を行っているとの情報を耳にした。FPGAベンダにとってのプロセッサ、ASSPまたはプロセッサのベンダにとってのFPGAは、従来とは異質の領域の製品に相当するため、それぞれの企業での技術サポートが課題になるかもしれない。 |
|
 |
|
 |
|
| アトメル社のブースでプレゼンテーション |
|
各アプリケーションのソリューションを
示していたSTマイクロ社のブース |
|
|
半導体ベンチャーで目立ったのはStretch |
|
今年のESCに出展した半導体ベンチャー企業の中でもっとも目立ったのは、プログラマブル・ロジック部を内蔵したソフトウェア・コンフィギュラブル・プロセッサのStretch社だった。まず、同社は出展社、来場者用バッジのストラップ(英語ではLanyardという)のスポンサーになっていたし、ブースもベンチャー企業とは思えない非常に目立つ派手なものだった。同社は、このイベントで新製品、S5620を発表した。これは昨年発表した最初のデバイスS5610がMIPSアーキテクチャのシステムに最適化されていたのに対して、S5620はPowerPCアーキテクチャのシステムに対するインタフェースを内蔵している。S5620のコアとなるプロセッサはS5610と同じTensilicaのXtensaで、内部アーキテクチャはS5610と同じようにカスタム命令などの追加が可能なInstruction
Set Extension Fabric (ISEF)を内蔵したものになっている。 |
|
 |
|
| 女性が目立ったStetch社のブース |
同社はS5620ベースの開発をサポートするツール・セット、S56DVK20 Development Platformも同時に発表した。同社のブースには女性の説明員が目立っていたが、同社のマーケティング担当副社長も女性で、昨年のこの時期にザイリンクスに買収されたTricend
Microsystems社のCEOだった人と知り、少々驚いた。Stretch社はVCから得た60Mドルもの豊富な資金をバックに人材の確保も積極的に進めているようだ。
|
|
日本の半導体メーカーは? |
|
日本の半導体メーカーとしては、ルネサス、東芝、NECエレクトロニクス、富士通、シャープ、沖電気などの現地法人が出展していた。このうち、ルネサス・テクノロジと富士通の両社は展示会初日の同時刻にプレス関係者向けの説明会を開催した。小生はルネサスのプレス発表会に参加した。同社は用途別の主要なMCU市場で世界第一位のシェアを持っていることを強調すると共に16ビットのフラッシュ・マイコン、R8c/Tinyシリーズの新製品などを発表していた。これに対して、富士通の半導体部門の現地法人、富士通マイクロエレクトロニクス・アメリカ(FMA)は最新の指紋認証用モジュールや32ビットのMCU、MB9140x、FlexRay評価キットなどの新製品を発表し、同社の指紋認証技術の採用が米国で相次いでいることも発表したようだ。 |
|
 |
|
| 東芝のブース |
一方、東芝は90nmの最先端CMOSプロセスを採用したハイエンド用途向け64ビットRISCマイクロプロセッサ、TX4939XBG-400をESCで発表した。NECエレクトロニクスからはエンベデッドDRAMの発表があったものの、プロセッサに関する新しい発表はなかった。日本ですでに発表された新しいゲートアレイ、CMOS-12Mが、米国ではストラクチャードASICの新製品として発表されていたのには、ちょっとびっくりした。
|
|
インテルとAMD |
|
PC用プロセッサで激しい戦いを展開するインテルとAMDの両社もESCに揃って出展して、それぞれ目立つ存在だった。インテルのブースではIXP、IOP、PCAの各プロセッサ群が展示され、AMDのブースでは、関連会社、SpansionのFLASHメモリとメディア・プロセッサ、AlchemyとGeode中心にした展示となっていた。AMDは期間中、x86 Opteron
プロセッサの供給期間を延長し、ハイエンドの高性能組み込み機器市場のシステム設計者を支援すると発表していた。組み込み用途のX86市場でもインテルとAMDは戦うのであろうか? |
|
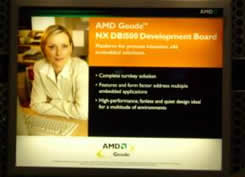 |
|
 |
|
| AMDのGeodeプロセッサを示すパネル |
|
青で統一されたインテルのブース |
|
|
以上、NO-1はデバイス・ベンダを中心にしたリポートになったが、OS、ソフトウェアベンダの様子はNO-2で紹介する。 |
|
>>
NO-2へ |
|
| |
| バックナンバー |
>> EDSF
2005 with FPGA/PLD Design Conference |
|
|
>> SEMICON
Japan 2004 |
|
|
>> ET2004 |
|
|
>> ALTERA
PLD WORLD 2004 |
|
|
>> ESEC
2004 |
|
|
>> ESC
San Francisco 2004 NO−2 |
|
|
>> ESC
San Francisco 2004 NO−1 |
|
|
>> EDSF2004,
第11回FPGA/PLDコンファレンス |
|
|
>> Semicon
Japan 2003 |